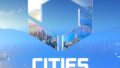2025年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故について、気になって調べた情報をまとめておきます。
- 2025年2月5日:水中ドローンで調査したところ運転席のあるキャビンらしきものを、現場から100~200m下流で発見したとの報道あり。なお男性は現時点で確認できていない。埼玉 八潮 道路陥没事故 下水道管に障害物 トラックの運転席部分か【埼玉県が相談電話窓口を開設】 | NHK | 事故
- 2025年2月4日:2個目のスロープの全体像把握のため、午前11時ごろのANN空撮映像からのキャプチャを追加。
- 2025年2月3日:本日16時ころから着手し始めたという第2のスロープを図示するキャプチャ映像を1枚追加。
- 2025年2月2日18時:ANNからの空撮映像のキャプチャを「事故の経緯」に2枚追加
- 2025年2月1日:古い情報での混乱を避けるため、更新を停止する「事故の影響について(インフラ関連)」、「その他自治体発表関連」について折りたたみました。報道各社発表や自治体発表を御覧ください。
- 今後は大きな動きがあったときに主に「事故の経緯」について更新予定です。
- 2025年1月30日:初稿
事故の瞬間
TBSが視聴者からの提供として放送していたようです。
ほんとに一瞬の間に穴が開き、一瞬の間にトラックが飲み込まれています。
落下したのは2トントラック
- ドライバーとは定期的に連絡が取れていたが、1月28日13時ごろを最後にやりとりができていないといいます。非常に心配です。
事故の経緯
- 1月28日10時前(9時50分頃):八潮市二丁目487付近の交差点(松戸草加線中央一丁目交差点)で道路が陥没し、トラック1台が転落と通報
- 穴の大きさ:直径10m、深さ5m

※交差点で陥没 下水管破損が原因か – Yahoo!ニュース 28日15時とのキャプション。南西側からの撮影と思われる。写真左下から右上の斜めの道路が県道54号松戸草加線。上に伸びるのが潮止通り、左上角がサガミ駐車場。
- 穴の大きさ:直径10m、深さ5m
- 1月29日17時?:2つ目の陥没(穴)が発生
- 穴2ヶ所目:写真右下の1つ目の穴に対して写真左上側(大きい方)。専門家によれば、落ちたトラックが下水管の穴を塞いだ状態になっていたが、トラックを引き上げたことで穴が開き、土砂がさらに流入し陥没を引き起こしたそうです。いわゆる二次災害です。

※埼玉・八潮市の陥没、下水の河川への緊急放流始まる…塩素投入済みで飲み水への影響なし : 読売新聞 南西側からの撮影と思われる。写真の角度がほぼ同じで2つ目の穴の位置と大きさがわかりやすいため引用した(後で落下する横断歩道の位置角度がほぼ同じ)。29日17時時点とのキャプション。2つある右下が1つ目の穴で、左上の大きめなのが2つ目の穴。1つ目の穴の左上の「サガミ」側に大きな穴があき、サガミの看板や電柱が飲み込まれた。1つ目の穴の右上にあるのは引き上げられたトラックの荷台部分(その後移動された)。ちなみにサガミの看板は8m前後ありそうな巨大なものです。電柱も含めてこれらが一瞬で地中に引きずり込まれました。
- 穴2ヶ所目:写真右下の1つ目の穴に対して写真左上側(大きい方)。専門家によれば、落ちたトラックが下水管の穴を塞いだ状態になっていたが、トラックを引き上げたことで穴が開き、土砂がさらに流入し陥没を引き起こしたそうです。いわゆる二次災害です。
- 1月29日23時20分:埼玉県が下水道管の上流部で汚水をくみ上げて川に流す緊急放流を開始 ※詳細後述
- 1月30日午前2時半すぎ:穴が拡大し1つに。
- 穴がつながって1つになった。当時は作業をしていなかったという。穴の直径は20mと発表されてますが、駐車場のマーキングや右上にいる人物を見るとそれ以上ありそうです。→ ANN報道によると地元消防発表で幅40m、深さ15mになっているようです。

※埼玉 八潮 道路陥没 発生から3日目 汚水の緊急放流を開始 | NHK | 埼玉県 6時40分ごろNHKヘリが撮影。撮影角度は上2つと異なり、東北東あたりからの撮影になっている。左上から中央下の道路が県道54号松戸草加線。写真右側に接続している潮止通り側の横断歩道がまるごと消えている。写真右側が「サガミ」駐車場。なお少し見えている四角いブロック状の管は雨水管(暗渠)と呼ばれるもので、今回問題の下水管ではない(下水管は直系4.75mの大きなものでもっと下にある)。
- 穴がつながって1つになった。当時は作業をしていなかったという。穴の直径は20mと発表されてますが、駐車場のマーキングや右上にいる人物を見るとそれ以上ありそうです。→ ANN報道によると地元消防発表で幅40m、深さ15mになっているようです。
- 1月30日14時ごろから:サガミ駐車場に重機を使って穴を掘る作業が進行中。
- どうもサガミ駐車場から幅およそ4メートル、長さおよそ30メートルスロープ(31日NHK報道)を作って陥没穴につなげ、重機を下に降ろして作業するのではないかとされている。※3枚目(1月30日午前2時半)の空撮写真の右側がサガミ駐車場。穴を掘り始めた位置は右端見切れた辺り。
- 【速報】埼玉・八潮市の道路陥没 重機使いスロープを作り穴内部に重機を下ろす救助活動進める方針 運転席は土砂埋まり74歳男性の安否は不明(TBS NEWS DIG Powered by JNN) – Yahoo!ニュース
- スロープ完成まで数日かかる模様:埼玉 八潮 道路陥没 転落した男性救助のためスロープ作る工事 周辺への影響は 道路崩落の瞬間も【動画】 | NHK | 埼玉県。2~3日とのこと。
- 1月31日8時過ぎの様子
- テレビ朝日のYoutubeライブ放送。空撮ヘリが31日8時頃に飛んで撮影し、Youtubeで放送された映像よりキャプチャ

※南西側から写したもの。掘削はすでにかなり掘り進んでいるようですが、二次災害をこれ以上起こさないためにも地固めをしながら掘り進むということになるのでしょうか。スロープ自体は今日31日中に出来上がる予定も、さらに崩れないように両側に土のうを積み上げて経路を確保してからの小さめの重機投入となる模様。
- テレビ朝日のYoutubeライブ放送。空撮ヘリが31日8時頃に飛んで撮影し、Youtubeで放送された映像よりキャプチャ
- 1月31日16時過ぎの様子
- テレビ朝日のYoutubeライブ放送。空撮ヘリが31日16時頃に飛んで撮影し、Youtubeで放送された映像よりキャプチャ。交差点のやや東、ほぼ南側上空から撮っている。左上がサガミ、手前の道路が県道54号線

サガミ正面側:つまり交差点南東上空から北西側に向けて撮ったもの。サガミ正面に養生用とみられる白い仮囲いシートがかかっている。左下が県道54号線、左上の白い軽トラが止まっているのが浄水場通り。

スロープは60%完成とのこと。31日は夜通し作業が続けられるそうです。スロープ完成後、重機で内部の土砂を排除し、その後作業員の手彫りで運転手を探す予定とのこと。
- テレビ朝日のYoutubeライブ放送。空撮ヘリが31日16時頃に飛んで撮影し、Youtubeで放送された映像よりキャプチャ。交差点のやや東、ほぼ南側上空から撮っている。左上がサガミ、手前の道路が県道54号線
- 2月2日18時:
- 現場では朝からずっと雨がシトシト降っていたようで、土砂崩れの危険性が高まったため、作業員による手掘りは17時ごろに見送られた模様。今は周辺の土砂をさらに固める作業をしていると思われる。ANNがまとめている最新状況ページ「【最新情報まとめ】直径40mの穴に拡大 埼玉・八潮市の道路陥没 運転手いまだに安否不明」も参照のこと。
- 同じくANNのYoutubeチャンネルから現状のわかる映像があったためキャプチャを引用します。1枚目:これが2日18時現在の現場の状況で、現場南側上空から交差点北側を向けて撮ったもの。

※すでにサガミの駐車場がどこかわからないくらいにスロープが広がっている。青いトラックが北向きに止まっている道路が「潮止通り」。画面右から中央下へ斜めに横切っているのが県道54号。 - 2枚目:やや東側上空から撮られた映像に、位置を特定するためのピンク色の線囲み2つを追加したもの。

※写真上側に四角い雨水管が見えている。これは1月30日午前2時半の写真を見ると、現場交差点の北西に接続している「浄水場通り」と県道の間あたりの真下を走っている雨水管だと思われる。写真下やや左の丸囲みは恐らく問題の下水管と思われる濁流(下記埋設管についての模式図参照)。恐らく上側が腐食して崩れて(直径4.75mの)上辺が覗いている状況なのだろうと思われる。かなり勢いよく流れている様子が伺えた。大きさの感覚が狂うが、ここで道路面から10mの深さの地下ということになると思われます。重機での作業はこの写真で言う中央より右側の段差までということになり、そこから下は作業員による手掘りになるようです。
- 2月3日:16時半
- 1本目のスロープでは重機で届かない瓦礫があるため、2本目のスロープを新たに県道54号の東側から掘ることを決定し、着手開始したとのこと。

※ANNのYoutubeLIVEの空撮映像をキャプチャし、点線を追加した。右側の県道54号線の東側(中川方面)から現場交差点に向かってピンク点線の要領でスロープを作る模様。写真左上の大半がサガミの駐車場から作ったスロープ。交差点右上側に伸びているはずの潮止通りは砂埃で判別できなくなっている。
- 1本目のスロープでは重機で届かない瓦礫があるため、2本目のスロープを新たに県道54号の東側から掘ることを決定し、着手開始したとのこと。
- 2月4日:午前11時頃
- 2個目のスロープがだいぶ掘り進んでいる。

※ANNYoutubeLIVEより南方上空からのキャプチャ。上下中央で左右に走るのが県道54号線。写真中央から右側が2個目のスロープ掘削地点。緑色の重機が掘り、それを後方(東側)の黄色の重機がトラックに積んでいる。

※2枚目はやや白飛び気味だがスロープ全体がよくわかる東方上空からの空撮映像からのキャプチャ。中央やや左を縦に走るのが県道54号線。事件交差点の東側の(県道を渡る)横断歩道がわずかに残っている。こう見ると県道54号線の横幅ほぼ一杯がスロープとなるようだ。細かな位置は不明ながら、下水道管はこの写真で上側から県道54号線地下を下ってきて(方角的には西から東向き)、この交差点で斜め右下方向の潮止通り(オレンジ色重機側)へと曲がっていく(方角的には西北西、中川方面)と思われる。画面右下の三角のゾーンは、石井木工という会社の敷地だと思われるが(写真中央下側に県道に面した生け垣が残っている)、どうも駐車場を開放して救出・復旧工事に協力しているようだ。
- 2個目のスロープがだいぶ掘り進んでいる。
- 2月5日状況
- 2個目のスロープ造成続く ※1個目のスロープについては、下水道管の上になってしまう関係上重機作業にはむかない。
- 下水道管については、その上部の(主に交差点南側の)残存道路及びその下部にくっついている平べったいボックスカルバート(旧用水路遺構という。現在未使用)が落下する危険性があることから、それを先に取り除く手順となる模様
- ただし下流から行った水中ドローン調査により、「崩落現場から下流に100メートルから200メートル付近で、運転席あるキャビンらしきものを確認」したとのことで、もしこの調査によりキャビン及び男性を発見することができれば、現場交差点での作業手順が大きく変更されるのではないかと想像できる(重機での採掘及び下水道管復旧工事への移行)※ドローン投入箇所はそこからさらに4~500m下流のマンホールとのこと。つまり現場から600mほど下流から調査開始し、400~500m上流へ遡行したところ(つまりは現場から100~200m下流)で発見したのだと思われる。
※グーグルマップをキャプチャしたものに、報道情報を元に下流100~200m範囲をピンク色点線で図示したもの。県道54号線の下を通ってきた下水道管は、この交差点で潮止通りの下を通って北東に流れていく。

- その他:NHKが、空撮映像から立体化した映像2本を公開中(埼玉 八潮 道路陥没事故 下水道管に障害物 トラックの運転席部分か【埼玉県が相談電話窓口を開設】 | NHK | 事故)
- 2月6日:
- 埼玉県が設置した復旧工法検討委員会の森田弘昭委員長(日大教授、土木工学)が取材に応じ、下水道管の復旧方法について、「補修ではなく、穴を 迂回 する形で上流600メートルと下流600メートルの2地点をつなぐ管を新設する方法を提案。民家の地下を避ける必要があり、「完成までに2、3年はかかるだろう」との見方を示した」とのこと。八潮道路陥没「復旧に2、3年」…工法検討委員長がより強力な下水の利用自粛求める : 読売新聞 ※いろいろ見てると勘違いしている人が多いので念の為に書くと、運転手の救出に2・3年かかるという話ではない。
- 2月8日状況:
- 現場交差点南側で宙吊り状態になっていたボックスカルバート(旧用水路)の撤去作業がヨを徹して行われ、8日に完了した。
埋設管について
写真や動画で何やら管がいっぱいあってわかりづらいのですが、TV局がまとめていました。※これはANNからの引用ですが、TBSなども同じ様な見た目の画像を使っていたため、埼玉県の資料が元なのかも知れません。

空撮映像などで目に付く”白っぽい四角いブロック状の管”は、ボックスカルバートという名称のブロック状の管です。上図の中央上に2本描かれているものです。プレハブ方式で、現場で組み立てて素早く暗渠や通路を構築できるもので、この交差点の場合は雨水管として使われているようです。逆に崩れるときも粉々に割れるのではなくブロック単位で崩れるため、今回目につきやすくなっています。サイズは恐らく小さい(八潮市用水)のが2m×2m、大きいほう(同幹線)が2.5×2.5mくらいだと思われます。
※東京・大阪など古くから下水が整備されてきたところでは雨水と汚水(トイレなど)を1本の管で済ませる合流式が取られていますが、この八潮市の場合には分流式だということがわかります。
なお写真でもう一つ目に付く”黄色い細い管”はガス管だと説明されており、東京ガスによれば現場付近においてはすでにガスが止められており、ガス漏れの心配はないとのことです。
一番下やや左の大きな丸い管、これが問題の下水道管で、道路面から10m地下に直径4.75mの大きな管が埋め込まれています。今回ここに穴が開いたことから周辺の土砂が吸い込まれて道路下に空間ができてしまい、あるタイミングでそれが陥没として現れトラックが吸い込まれたということになります。
上流で20%ほどポンプで吸い上げて川に緊急放流しているとは言え、下水を完全に止めることは不可能なため、次々と土砂が吸い込まれる状態にあるようです。最初はトラックが穴を塞いだ状態になっていたため止まっていたのが、トラックを引き上げたことで再び穴が開き、土砂が吸い込まれた結果2個目の穴が開いたというメカニズムになるようです。
※参考に単線の地下鉄のトンネルが直径(内径)5~7mといいますからあれを想像すればイメージしやすいでしょう。日常生活ではあまり見かけない驚くほど巨大なサイズ感です。
また雨水管も完全には止められず、(仕組みはよくわかりませんが)東京湾の汐の満干に伴っての逆流もあるようで、それが恐らく中川方面から(東から西に)逆流しているものもあるようです(雨水管は恐らく中川接続)。30日にジャバジャバと水が現場に流れ込んでいる映像が流れましたが、あれがそのようです。
トラック運転手について
74歳男性と発表されています。トラック自体は千葉県流山市の運送会社所属のようです。いわゆるユニック車と呼ばれるクレーン付きのトラックだったようです。
場所について
事故発生場所は、埼玉県八潮市二丁目487付近の交差点(松戸草加線中央一丁目交差点)。
Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/mUeBhvRUCK8Vwdp19
写真などで見える、東西に走る片側2車線(交差点では右折レーン入れて5車線)の大きな道は県道54号松戸草加線(けやき通り)、それに地図右上側に接続しているのが「潮止通り」(地図北東側接続)と地図左上側に接続しているのが「浄水場通り」(地図北西側接続)。いずれも南側接続道路はかなり細くなっている。
後述する下水道管地図によれば、下水道中央幹線は、地図西側のけやき通り地下を通って東向きに流れてきて、この交差点で東北東へと流れを変えて潮止通り地下を流れていく。
交差点の左上側(北側)が、看板の落下した「サガミ」(和食麺処サガミ 八潮店)で、現在営業休止中との案内あり。
- 和食麺処サガミ 八潮店|和食麺処サガミは和食の原点とも言える蕎麦、みそ煮込、和食を主体とした店舗を東海地区に展開
- お知らせ|和食麺処サガミは和食の原点とも言える蕎麦、みそ煮込、和食を主体とした店舗を東海地区に展開:「和食麺処サガミ八潮店の周辺道路陥没に関して、お客様、及び従業員の安全確保を最優先とし、当面の間 店舗の営業を休止させていただきます。安全が確認され次第、営業再開予定でございます。尚、現在のところ営業休止期間は未定です。」
- ※空撮ヘリ映像などを見ると、重機や関係車両などに駐車場を開放して協力している模様 → スロープ入口にするらしく、アスファルトが剥がされそこで土砂を混ぜている様子が映っていました。どうも土砂崩れを防ぐための土壌改良の準備作業をしていたようです。
「そば処やぶ」
- YoutubeLive映像などでよく映っている「そば処やぶ」というのは、県道54号松戸草加線(けやき通り)と「浄水場通り」(地図北西側接続)の間にある店舗です。現場交差点の北西側に位置しています。
- つまりこの店舗の看板が映っている場合は、現場東側の道路から撮影していることになります(その後ろに家族葬の看板も見える)。どうも交通規制の関係からか、ANNもTBS(確認してませんが恐らく全局)も地上撮影映像の場合はこの方角から撮影・中継しているようです。車の上にポールを建てた中継車がズラリと並んでいる映像もあったかと思います。※なお事故当初は北東側「潮止通り」が閉鎖されていなかったのか、「カットサロンCORE」の看板が見えている北東側からの映像も多くありました。このカットサロンは事故交差点の南西側にあります。
- ネット掲示板などでは蕎麦屋の駐車場で工事?してるという書き込みも見かけますが、30日晩に
ポリマー材?生石灰らしいで土壌改良?らしき工事をしていたのはサガミの駐車場です。もちろん蕎麦屋も営業休止中ですが、駐車スペースは4台程度でとてもここでは重機を2台も入れての土壌改良作業などはできないでしょう。
事故の影響について(更新停止)
下水道管について
埼玉県では、原因は下水道管に穴が空き、そこへ周辺の土砂が流れ込んだことから空洞が発生し、最後に道路が陥没して穴が空いたという説明をしている。
県下水道事業課によると、現場地下約10メートルにある下水道管が腐食し、破損した部分に土砂が流入。地中にできた空洞の上を車両などが通行したことで重みに耐えきれなくなり、陥没した可能性があるという。下水道管が破損した原因は、汚水から発生した硫化水素が空気に触れて硫酸になり、徐々に腐食したとみられる。
八潮市の道路陥没事故 埼玉県は「想定外」…都市部の下水道管老朽化が地方より早い理由(日刊ゲンダイDIGITAL) – Yahoo!ニュース
このフジの動画が、ちょうど陥没の過程を説明しておりわかりやすい。
報道によれば(八潮市へのインタビュー)、下水道管は地面から10m下に直径4.75mの下水道管が埋設されているといいます。
※なお同様の事故としては「博多駅前道路陥没事故」が記憶に新しいが、あれは福岡市地下鉄七隈線の延伸工事が原因ではないかとされており、今回とはやや異なります。地下鉄七隈線の延伸工事では計3件の陥没事故がおきた。
下水道管接続について
そこで八潮市の下水道平面図を確認する。
※この下水道管地図(下水道台帳)は各自治体で発表しており、「自治体名 下水道台帳」などで検索すると出てくる。
- 八潮市公共下水道平面図/八潮市 ※八潮市の場合は台帳全図のインターネット公開までは至っておらず、平面図までしか閲覧できない。残りは市役所窓口での閲覧申請。
- リンク先の「八潮市公共下水道平面図(PDF:14,095KB)」
- 閲覧時間は午前8時30分から午後5時15分までということなので、以下にスクリーンショットを掲載しておきます
下水道管地図:八潮市広域図

※事故現場は地図中央やや右付近。どうも下水管は事故現場付近で「中川流域下水道中央幹線」に集合し、地図東側方向の中川を越して、埼玉県三郷市番匠免3丁目にある「中川水循環センター」へと流れているようだ。この中川は、下流で荒川と合流して東京湾に流れ込んでいる。
下水道管地図:周辺拡大図

上述したが、下水道中央幹線(青色)は地図西側から県道54号松戸草加線(けやき通り)を通ってきて、この交差点で東北東へと流れを変えて潮止通りを流れていく。
参考)八潮市の下水道案内ページ:下水道のご案内/八潮市
下水道には、下水管、中継ポンプ場、下水処理場(中川水循環センター)という施設があります。
同様の事故は起きないのか?
ここで気になるのが、同様の道路陥没事故が他の地域で起きないのか?という点ですが、その懸念通り各地で同様の下水道処理をしており、他の地域でも(規模の大小はあれ)発生する可能性は充分あると指摘されています。
※おさらいしておくと、原因はまず下水道管に穴が空き、そこへ周辺の土砂が流れ込んだことから空洞が発生したことである。付近は集合していることや段差があることから硫酸などが発生しやすい状況にあったという指摘がされています。埼玉県八潮市で道路陥没 トラックが転落、救助続く 2日間の動き [埼玉県]:朝日新聞
つまり発生する化学物質により管のコンクリート部分などが劣化し、さらに鉄筋が劣化することで穴が開いていったのではないかと想像できます。
耐用年数の問題
そもそも下水道管は標準耐用年数50年とされており、なおかつ都市部の下水道設備はおよそ50年前前後に整備されたこともあり、すでに劣化が始まっている可能性があるという指摘があります。
上記国土交通省のページによれば、
- 令和4(2022)年度末における、全国の下水道管渠の総延長は約49万km。
- 標準耐用年数50年を経過した管渠の延長約3万km(総延長の約7%)が、10年後は約9万km(約19%)、20年後は約20万km(約40%)と今後は急速に増加
- 令和3(2023)年度末で約2,200箇所ある下水処理場でも、機械・電気設備の標準耐用年数15年を経過した施設が約2,000箇所(全体の90%)と老朽化が進行

※国土交通省サイトより
2022年時点から考えて50年前は昭和47年(1972年)なので、それ以前に布設された管が対象として赤矢印で示されている資料なのですが、グラフを見ればわかるように整備されていった時期が今後加速度的に50年目を迎えるのだということがわかります。
ただし、気をつけなければいけないのは、今回事故の起きた現場は1983年に供用開始された下水道管だということなので、43年目ということになります。50年経っていないから大丈夫というわけでは決してないのです。埼玉 八潮 道路陥没 転落した男性救助のためスロープ作る工事 周辺への影響は 道路崩落の瞬間も【動画】 | NHK | 埼玉県
※今回事故の起きた場所では、複数の下水道管が集合している箇所であること、またそのために段差もあるという硫酸などの発生しやすい箇所であることが指摘されています。
もちろん国土交通省も手をこまねいているだけではなく、ストックマネジメントという考え方に基づいて対策を練っています。
国交省による点検要請
そこで国土交通省では、全国の下水道管理者(各自治体など)に同様の箇所の緊急点検を要請したと発表しています。埼玉の道路陥没うけ下水道管理者に緊急点検要請 国交省 – 日本経済新聞
国土交通省によれば、同様の道路陥没が起きたのは2022年度で2607件だったという。
国交省によると、2022年度、下水道管が原因で発生した全国の道路陥没は2607件だった。
「そのほとんどは深さ50センチ未満の規模が小さいものです。今後、増加するかどうかは分かりませんが、道路の下には下水道はじめ、電力など生活に必要なライフラインが埋まっています。日々、パトロールをして路面の異常を確認し、特に都市部では路面の下に空洞がないか、調査を行い、事前に対策を取っています。道路が沈んでいるように見えるとか、ヒビが生じてるとか、異常に気付いた場合、道路緊急ダイヤル(#9910)に通報してください」(国交省国道・技術課担当者)
八潮市の道路陥没事故 埼玉県は「想定外」…都市部の下水道管老朽化が地方より早い理由(日刊ゲンダイDIGITAL) – Yahoo!ニュース
※引用者が下線強調を行った
LINEでも報告可能
- 報道発表資料:日本全国の道路異状の通報が LINE アプリから可能となります
~全国の道路を対象に LINE による道路緊急ダイヤル(#9910)の運用を開始します~ – 国土交通省 - 国土交通省道路緊急ダイヤル(#9910) | LINE 公式アカウント
上下水道の管轄について
参考として、上下水道は現在国土交通省で一括して管轄になっているが、それが1本化されたのは2024年4月からであり、それ以前は上水道は厚生労働省、下水道は国土交通省が所管となっていたという。
上水道の整備や管理が4月1日、厚生労働省からこれまで下水道の整備や管理を担ってきた国土交通省へ移りました。
このため、各自治体でも両者を一体として捉えて考えることが少なかったという。これも遠因の一つにはなるだろうと思われる。※コロナ感染の根本対策の一環ということ。下記引用記事は、上下水道の歴史からたどり現在の行政までを見通す非常に質の高い記事です。
公衆衛生に関する厚生労働省の機構が大幅に見直され、水道行政を国土交通省に移管させる方針が決まりました(水質に関する業務は環境省に移管)。政府は今年の通常国会で法改正し、2024年度から新体制に移行する見通しです。
これは「上水道=厚生労働省(旧厚生省)」「下水道=国土交通省(旧建設省)」に分かれていた体制の実質的な一元化を意味しており、約60年ぶりの機構改革になります。さらに言うと、水道行政が公衆衛生から社会資本整備の一つに包摂されたと解釈することも可能です。つまり、感染症対策の強化が思わぬ形で上下水道行政に飛び火し、機構改革に繋がったと言えます。
埼玉県での発表
道路陥没の恐れ、周辺は「なし」 埼玉県が調査結果を公表 八潮陥没事故(産経新聞) – Yahoo!ニュース
被害拡大防止が狙いで、調査は、破損したとみられる下水道管と同じ流域の下水道が走っている約3・5キロのうち事故現場周辺の警戒区域外の2・5キロの県道と市道を対象とした。ジオ・サーチ(東京都大田区)に依頼する形で、29日午後2時過ぎから約2時間、調査車両下部から電磁波(レーダー)を照射し、地下に空洞があれば跳ね返り状況が分かる方法で広域に調べた。深さ3メートルほどまでであれば陥没につながるような空洞があるかがわかる仕組みで、同社が収集したデータの解析を進めた。
※ただしこれ注意なのは、あくまで3mまでの深さに空洞があれば感知するという仕組みのようなので、それより地下に空洞がある場合は検知できないのではないか?という指摘する報道が、この埼玉県発表とは別にありました(埼玉 八潮 道路陥没 トラック運転手の救助活動の見通しは 穴の中で断続的に崩落続く“新たな陥没おそれも” | NHK | 事故の一番下、東京大学生産技術研究所の桑野玲子教授の指摘)。
「地下の空洞を調べるには、レーダーによる探査が行われますが、一般的には深さ2メートル程度が限界で、今回、下水道管が埋設されていた地下10メートル前後にある場合は困難だとしています。浅いところまで空洞が広がった場合でも、すぐに陥没する危険性が高まるため、間に合わない可能性があり、早期の発見は難しかったのではないかと指摘しています。また、定期的に行われているカメラや目視による下水道管の点検については、下水道管自体の劣化を調べることはできるものの、下水道管の背後に空洞があるかを予測するのは困難だったとしています。」もちろん埼玉県の調査が無駄だと言っているのではありません(できる範囲できちんと実施して一時的にでも県民の安心を得ることはとても大事)。他都道府県・基礎自治体含めて、レーダー調査で安心することは出来ない可能性がある(例え管内調査でも下水道管の外側は認識できない可能性もある)ということを考慮しておく必要があるということです。
八潮市での対応
なお八潮市でも放置していたわけではなく、該当箇所については5年前の調査で「B」判定だったということです。
県では5年に1度、管渠(地中に埋設された水路や排水管)の内部調査を行い、緊急度の高い順にAからCまでランク付けしています。今回の箇所は5年前の調査でBランクだったため、至急対応する内容ではなかった。陥没の原因にならないよう内部を点検し、維持管理をしていましたが、想定外のことが起きてしまった。これだけの規模の陥没も想定していませんでした
八潮市の道路陥没事故 埼玉県は「想定外」…都市部の下水道管老朽化が地方より早い理由(日刊ゲンダイDIGITAL) – Yahoo!ニュース
なお埼玉県知事の会見では、500m上流(西側)で「A」の地点があり、そこでは鉄筋がむき出しになっていたといいます。
この管きょについては、令和3年当時、検査したところ、Bランクでありました。これは直ちに工事等が必要な状況にはないということになります。しかしながら、令和2年、その前の年ですね、にこの地点の上流500メートルの地点で管きょ調査を行ったところ、鉄筋がむき出しになっている状況でありました。これはすなわち、Aランクの腐食度合い、つまり、事故が起こったところの500メートル上流のところでは、事故が起こったところよりも深刻な状況にあるということが、当時、判明いたしました。
地形の影響
こういう事故では地形の成り立ちも見ておく必要があります。そもそも埼玉県東部は河川流域であり湿地帯だったといいます。
埼玉県地盤沈下調査報告書によれば、以下のように書かれています。※八潮市は東端①の地域に該当する。
東部地域は中川低地と呼ばれる沖積低地である。特に東部地域の南部は軟弱地盤であり、かつ、標高が約0.6m(八潮市)と低いため、地盤沈下による影響を受けやすい。
国土地理院の土地条件図:数値地図25000(土地条件)では下図のようになっています。

中心の×位置が今回の交差点。図の大半を占めるピンク色の網掛けは「盛土地・埋立地」、黄色は「自然堤防」、橙色は「更新世段丘」を示しており、この場合、この地図のほぼ大半は湿地帯が埋め立てられた(または自然に埋まった)ものと思われる。つまり八潮市全域(周辺地域含めて)がほぼ低湿地帯だったことがわかる。ちなみに地図の北に広がる水色は「海岸平野・三角州」、地図左上隅の薄緑色は「谷底平野・氾濫平野」となっている。※凡例参照(PDF)。
※上記「国土地理院の土地条件図」をドラッグ移動すればわかるが、台地や丘陵地帯を除く大半の都市部は、この沖積平野にある。例えば東京都北区、荒川区、台東区以東。大田区や横浜市の中原区、幸区、川崎区、鶴見区。あるいは愛知県の南部、あるいは大阪市の上町台地以外など、人口の多い部分はほぼこの沖積平野にあり、特段八潮市近辺が特殊というわけではない。
ただ八潮市近辺が特殊なのは、東から荒川、中川、江戸川という3つの大河川の流域であり、さらに昔、家康の関東入部以前は利根川(古利根川)が南流して東京湾に流れていた。この古利根川が現在の八潮市付近の中川ということになる。家康により利根川東遷事業が行われた結果、現在のように利根川は鹿島灘へと注ぐように変えられたという経緯があります。
もっと太古で言えば縄文時代には縄文海進と言って平地の大半が海底だったわけですが、八潮市あたりはもちろん、さいたま市あたりまで奥東京湾と言って海底だったわけですから、推して知るべしです。※貝塚というものの位置を調べると、当時の海岸線のおおよそがわかります。
このような地形では(その縄文海進後に海岸線が引いていって川が運んできた砂が溜まった地形であることから)基本的に地下は砂地が多く、いったん土砂の流れが起こると連鎖的に土砂が流れていってしまい、陥没が起こる可能性が考えられます。実際陥没が発生し2ヶ所目の穴があきました。
その他自治体発表関連(更新停止)