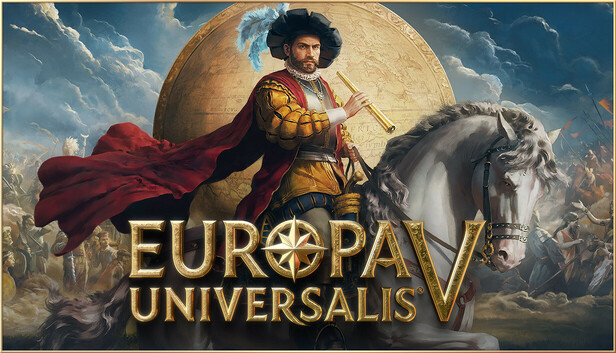2025年11月5日に発売されたEU5(Europa Universalis V)の小技やFAQなどをまとめます。
※EU5での最初のとっつきの悪さは、皮肉なことに操作の柔軟性にあります。ある特定の操作に複数のアクセス手段があったり、ある画面から別の画面への遷移が各所に仕込まれており、習熟してしまえば非常に使いやすいのですが、(左手法よろしく片っ端から抑えていこうと意気込む)初心者にとっては気づけば勝手に別のウィンドウに飛ばされてたりするため迷子になりがちです。
※ここではそういう小さな操作方法や、初期に躓きがちな情報をまとめたいと思います。特に前作EU4を未経験の人にもわかるように、できるだけ端折らずに書こうと思います。
変更履歴:
- 2026年1月2日:「生産方法の選択」を追加。翌日「建造物に助成金を出したい」「建造物を操業停止させたい」を追加
- 2026年1月1日:「実践的な建造物建築」を追加
- 2025年12月31日:「建造物メニューのフィルタについて」を追加
- 2025年12月19日:時代フォーカスの三択追加、「招集」としていた単語をベースゲームに合わせて「召集」に改めました。
- 2025年12月頃:国家変容(変態)について、探検と植民地の手順、属国の再征服CBなどを追加
- 2025年11月7日:「リリース後の動き」を「「EU5」2025年11月の動き」として切り出し
- 2025年11月6日:初稿。Mod情報まとめから切り出し
公式情報など
Europa Universalis V Player Resources | Paradox Interactive Forums
EU5初心者向けのオリエンテーション。公式Wikiなどへのリンクが整備される予定とのこと。
- EU5公式Wiki:Europa Universalis 5 Wiki ※英語
- バグレポート:Europa Universalis V: Bug Reports | Paradox Interactive Forums
※なおバグレポートはゲーム内からCtrl+F7でもスクショ撮影と同時にバグ報告ができるようになっている - クイズ:EU5 Quiz – Paradox Interactive ※10問ほどのプレイスタイルアンケート。全員にEU5ゲーム内で利用可能なモニュメントボーナス付与(これは事前メール登録でもらえていたもの)のほか、ゲーミングマウスやヘッドセット、マウスパッドなどが抽選であたる
Steam
- ニュース :: Europa Universalis V
- ワークショップ :: Europa Universalis V
- Europa Universalis V 総合掲示板 :: Steam コミュニティ
- Steam コミュニティ :: ガイド :: EU5: All Achievements Guide [WIP]
- SteamDB:Europa Universalis V Steam Charts · SteamDB
ゲーム配信プラットフォームTwitchのEU5ページ
シミュレーション・ゲーム全体
自動化(ゲームAIへの部分委任)
EU5では、自国の様々な内政・外交アクションをゲームAIに任せることを「自動化」と呼んでいる。
※初心者が自動化しておいたほうが良いかもしれない項目については、内容が重複していたため後述の「初めにやるべきこと」にまとめました。
この自動化できる項目は、収支、交易、生産方法、建造物(操業・閉鎖・助成)、階級建築物の破壊、RGO(採集建築物)、研究(技術ツリー)、法律、政府改革、内閣、議会、階級、文化の受容、宗教の教義、外交、ライバル、探索、植民地、陸軍編成、海軍編成、将軍の交代(部隊創設時の初期割当及び欠員時の自動割当)、提督の交代といった多岐に渡ります。
わかってきた時点でいつでも解除して自分で直接操作できるし、わかったとしても面倒であればそのまま任せることもできる。恐らく始めはとにかく軍隊を動かして他国に攻めることをしたいはずで、内政はとにかく細かくて影響もわかりづらく、めんどくさいので飛ばしたいのが人情だと思われる。
なお軍隊行動の自動化については、陸海軍の編成と将軍/提督の管理を行ってくれるほか、戦争中はユニットごとに指示することで包囲行動、敵殲滅行動などを対象地域で行ってくれるが、戦闘行動すべてを自動化することは出来ない。ただし属国軍の操作は完全に自動化されているので(自軍ユニットに付随行動させることもできる)、面倒なら属国を積極利用するのもあり。
自動化は、左パネルの「政府」-「内閣」や「経済」-「収支」などからも個別に設定できるが、画面左上部”~時代”の下の段にあるアイコンの並びの自動化アイコンからはその他のカテゴリーに対しての自動化設定ができる。
※左パネルでの自動化は、それぞれのタブについているギアアイコンを右クリックすれば自動化設定できる。もう一度右クリックすれば自動化オフになる。
※ただしこちらの右パネルアイコンで設定した自動化項目の自動化キャンセルは左パネルではできず、右パネルアイコンからまず解除する必要がある。
画面上部のアラートの選択
例えば子女の婚姻が出た(ている)とする。この時アラートにはホバーすると対象が複数人がいることがあり、このうち2人目の婚姻政策を進めたいとする。
こんな場合は、そのアラートを2回左クリックすれば良い。クリックするたびに対象が順番に切り替わってサイクリック動作する(それに伴って左側パネルの人物が順に切り替わる)ようになっている。
※右クリックするとアラートの非表示(取り消し)になるので注意。右下のログをオンにしておけば、そのログから辿れるものもある。
首都の移転
国家の首都を移転するには、F1政府タブを開き、君主像の上の段の「首都を移動」ボタンをクリックする。移転先を選べば若干の費用+安定度とともに移転できる。
※なおオスマンのコンスタンティーニイェ移転などは戦争で併合した時点でイベントが発生して選択できる。
注意が必要なのは「首都」条件で建っている建造物(王宮・王宮庭園など)が破壊される点。新たな首都で建築しよう。
※ちなみに「州都」というものも存在するが、これはあくまで動的に変動するものであり、州内で自国が領するロケーションのうち最大人口のロケーションへと自動的に遷移する(プレイヤーが直接制御することは出来ず、人口を増減する施策などで間接的に移動を促すことはできる)。例えば国境地帯などで同一州が複数国に分割統治されている場合には、同一州でありながら州都は複数(各国家ごとに)存在することになる。
これはEU4の州単位からEU5のロケーション単位へと地区単位を分割したものの、それを戦争でそのまま全ロケーション占領ルールとすると手間なため、便宜的に州都を定めてそこを占領すれば州内すべてを占領したものとするルールにしたために便宜的に置いているに過ぎないためである。戦争中ですら占領などで州都が入れ替わることもあるという。州都条件でしか設置できないようないものはないため気にする必要はない。
国家ランクの上げ方
国家ランクを上げるには、F1政府タブを開き、君主像の上の段の右側「新しい国家に変容」をクリックする。
ボタンがグレーアウトしていれば、そのボタンにホバーすれば条件が表示される。
- 【王国化条件】:いずれかひとつ(総人口200万人、主要宗教信仰150万人、主要文化または受容文化100万人)、威信50、従属国ではない、王国化禁止がない。
- ※つまり最低条件なら文化100万人、最悪でも総人口200万人で到達可能
- 王国のエフェクト:文化許容量+1、外交範囲+500、外交許容量・最高外交官数・要塞上限+1、列強スコア+100、傭兵範囲+50%など
- 【帝国化条件】:列強、いずれかひとつ(総人口1000万人、主要宗教信仰750万人、主要文化または受容文化500万人)、威信70、従属国ではない、帝国化禁止がない。
- 帝国のエフェクト:文化許容量+2、閣僚議席+1、外交範囲+1000、外交許容量・最高外交官数・要塞上限+2、列強スコア+200、傭兵範囲+100%など
なおカトリック国家では、ローマ教皇がいる限り帝国にはなれない(帝国化禁止)。しかし一度主要宗教をカトリックから改宗すると帝国化できるという。再びカトリックに戻しても帝国は維持されるという。
継承法(王位継承)
王位継承の継承法は、F1政府パネルの、子供の欄の下に数字がでているアイコンボタンがある。これを押すと継承法の選択が行える。

女性が継いで王朝が変わってしまうんだけど
上記継承法で(準-や母系-ではない)「サリカ法典」を指定すると男系男子継承を優先するため、例えば長子が女性の場合でも次子以降の長男に継承されるため王朝名は変化しない。
なお安定度50+正統性50を消費するため、なるべく安定している初期に行うほうがいいと思われる。
時代の選択(フォーカス)
各時代突入時に大きなダイアログが開き、統治/外交/軍事のうち、どのジャンルにフォーカスするかを三択できる。
ここで選んだ結果、「進歩」(技術ツリー)に選択肢の10項目が追加され、研究を進めることでアンロックできるようになる。
※例えば従属国タイプ「辺境伯」であれば、ルネサンス時代突入時の三択で「外交重視」を選ぶとその中に「地方領主」が入っている。これで従属国タイプ「辺境伯」が、研究ツリーの[ルネサンス]-[ルネサンス思想]-[常設内閣]-[最高権力]-[ルネサンス宮廷]の下に追加される。だからここで選んでも即座に使えるわけではなく、実際にはルネサンス進歩の伝播と受容を行ったうえで、個別にアンロックする必要がある。
※つまりこの三択は進歩ツリーに特別なツリーを追加するだけである(もちろん選んでいない選択肢は追加すらされない)。伝播が遅い国家の場合、三択の十年後に進歩が伝播し、進歩を進めてようやくアンロックということも充分あり得る。他も同様の手順。※ただし実際にはゲーム中盤以降は各国ともに街道整備などを行うため、特に旧大陸諸国では相当早く伝播すると思われる。
時代の三択間のつながりなどはなく、各時代ごとに好きなフォーカスを選択できる。
この三択で追加された項目は、技術ツリー上では”紫色のバナーにやや明るめの茶色バック”で表示されている(通常ツリーは”緑色バナーにこげ茶バック”)。また選択した統治/外交/軍事のフォーカスマークのいずれかが付いている。
※また国家特有の項目についてはバナーの左側に”国旗マーク”が付いている。これ以外に例えば「君主制」条件であれば王冠マークが、カトリックの場合には十字架マークが、オスマン特有(イェニチェリなど)の場合にはオスマン国旗が付いている。
ルネサンス時代(時代Ⅱ、1342年1月1日)
ゲーム開始5年後に現れる最初の選択。
統治フォーカス
- 知識の渇望:最大識字率+5%
- 経験主義:立法効率+10%
- 宮廷の会計管理:予想宮廷コスト-1%
- 負債と融資:銀行利息-1%
- 傭兵団の保護:傭兵維持費-15%
- 傭兵の雇用:傭兵の雇用コスト-20%
- 地方組織:近接性コスト-5%
- 例幣出席の義務:安定度投資+0.02
- 神がそれを望まれる:アンロック 開戦事由「宗教戦争」
※征服コスト+20%、従属コスト+20% - 対海賊連合:対海賊戦補正+25%
外交フォーカス
- エリート階級の統合:毎月の外交官数+0.10
- 地方領主:アンロック 従属国タイプ「辺境伯領」
※一度従属国に戻さないと併合できないが戦力特化の属国タイプ。従属国での効果:要塞防衛+10%、規律+5%、要塞上限+1.00、防衛敷設維持費-10% - 請求権の作成:開戦事由の作成速度+25%
- 利口な商慣行:市場の魅力+5%
- 商業の伝統:交易における海洋優位性+10%
- 私掠船:私掠船の雇用可能 はい
- 経験豊富な外交官:外交評判+2.00
- 穏やかな外交官:関係改善+20%
- 朝貢:従属国収入+2.5%
- 威圧的な外交:戦勝点コスト-5%
※辺境伯はここでしかアンロックできない。
軍事フォーカス
- 寛容的思考:異端な信仰の寛容度+1.00、異教の信仰の寛容度+1.00
- 栄光ある陸軍:陸戦からの威信+100%
- 戦地昇進:戦闘からの陸軍の伝統+100%
- 最高の軍馬:騎兵戦力+10%
- 指導官の任命:召集軍回復+5%、召集軍の戦闘効率+10%
- 全員徴兵:異文化召集軍規模+25%
- 兵役の強制:召集軍規模+10%
- 海軍の栄光:毎月の海軍の伝統+0.10
- 移乗部隊:海軍与ダメージ+10%
- 海軍連隊:陸軍下船速度+20%
発見時代(時代Ⅲ、1437年1月1日)
統治フォーカス
- 革新的な宮廷:わが国の内閣の効率化+5%
- 宣教師学校:POPを改宗速度+10
- 宣教活動:POP改宗速度+10%、POP同化速度+10%
- 建設の組織化:建造物コスト-10%
- 傭兵給与の体系化:傭兵の雇用コスト-20%
- 茨のなかに蒔かれた種:統合速度+10%
- 迅速な入植:毎月の植民地移住+50%
- 商人の招請:交易許容量+25%
- 効率的な採掘:鉱山の拡大コスト-10%、鉄生産量+10%、銅生産量+10%
- 効率的な建設計画:都市建造物コスト-10%
外交フォーカス
- 新大陸の探求:毎月の探検進行度+0.10、探検準備期間補正-10%
- 富を求める者たち:植民範囲+50%
- 海外交易:交易範囲+50%
- 植民地探検:毎月の植民地移住+50%
- 探検アイデア:植民範囲+500、アンロック開戦事由「探検」
※開戦事由「探検」:征服コスト+50%、従属コスト+30% - 外国大使館:毎月の外交関数+0.10
- 効率的な諜報員:諜報網構築+50%
- 身辺調査:防諜活動+33%
- 冒険的商業主義:海上の交易範囲消費-10%
- 船舶用基金:造船速度+10%
※植民範囲増加が大きく、探検・植民地プレイならこれ一択か。これを取らない場合の植民範囲(F7地政学-領土の右上表示)は、全国家基本値である1000に(ルネサンス時代の”銀行業”の”商人と交易”で増えた)+250だけである。これだと例えばポルトガルやカスティーリャからでもアフリカ西岸(カーボベルデや上ギニア)程度にしか届かない。植民地を中核化後にそこからさらに順番に伸ばしていくしかない。※おそらくこの外交フォーカスの「海外探検」でアンロックされる”外洋探検”がないとカリブ・コロンビア・ブラジルなど新大陸側には届かないと思われる(もしかすると北大西洋周りだと着くかも知れないが、相当遠回りで新大陸には出遅れ確定なのでアフリカ南端経由インド方面に専念するしかなさそう)
※なお統治フォーカスの「迅速な入植(植民地移住+50%)」が気になるが、外交フォーカスで追加される法律ポリシーや内閣アクションでカバーできる。 ※詳しくは後述「毎月の移住者数のバフ」を参照
軍事フォーカス
- 軍事教練:陸軍士気+10%
- 行政的指導力:相談役の雇用コスト-10%、将軍の養成コスト-10%、提督の養成コスト-10%
- 機動力の改善:戦闘速度+10%
- 良質の教育:毎月の陸軍の伝統+0.10
- 海軍教練:海軍士気+10%
- 高齢兵の活用:陸軍維持費-5%
- 強化衝角:ガレー船能力+25%
- 軍艦用のオーク材:大型船戦力+20%
- 海軍士官候補生:海軍率先力+50%
- 適応性:他国からの敵対心-10%
宗教改革時代(時代Ⅳ、1537年1月1日)
統治フォーカス
- インフラ網の拡大:砂利道敷設コスト-10%、舗装路敷設コスト-10%、近代的街道敷設コスト-10%、街道敷設時間-10%
- 神意至上主義:POP改宗速度+10%
- 信心:真の信仰の寛容度+1.00
- 宗教的伝統:毎月の威信+0.10
- 高度な官僚制度:税効率+2.5%
- 国立銀行:貨幣鋳造からの収入+10%
- 競争力のある商人:交易優位性+20%
- 人道主義的寛容:異教の信仰の寛容度+1.00
- 文化的連帯:文化許容量+2.00
- エキュメニズム:異端な信仰の寛容度+1.00
外交フォーカス
- 監査:税効率+10%
- 内閣:わが国の内閣の効率化+20%
- 壮大な宴:最大外交官数+1.00
- 素早い交渉:交易維持費-10%
- 交易操作:市場の魅力+5%
- 外交的影響力:外交評判+2.00
- 自由貿易:交易許容量+10%
- 好機に満ちた土地:毎月の植民地移住+50%
- 自由植民地:植民地維持費-20%
- 大海軍:海軍維持費-10%
軍事フォーカス
- 防衛精神:要塞の防衛+20%
- 多文化的拡大:文化許容量+25%
- 補給の強化:ユニットの食糧消費量-10%
- 補給部隊の拡張:陸軍消耗-10%
- 非戦闘従軍者:供給限界+10%
- 工兵部隊:包囲能力+20%
- 防衛軍:敵対消耗+1.00%
- 守備隊の徴兵:守備隊の成長度+1%、守備隊規模+20%
- 船底用同藩被覆:海軍消耗-25%
- 改善された倉庫:原材料へのローカルアクセス+2.5%
絶対主義時代(時代Ⅴ、1637年1月1日)
統治フォーカス
- 将校団の公式化:陸軍率先力+25%
- 宗教的統一:POP改宗速度+10%
- 中央集権政府:近接性コスト-5%
- 従属的経済:毎月の開発度+0.0010
- 入植者の招請」毎月の植民地移住+50%
- 外交官の招請:外交許容量+1.00
- 簿記:銀行利息-1.00%
- 公務員:毎月の支配度+0.10%
- 地方の伝統:階級満足度均衡値+2.5%
- 人文主義:最大識字率+10.00%
外交フォーカス
- 諜報員の訓練:最大外交官数+1.00
- 従属国への使節団:従属国の評価+25
- 国家プロパガンダ:他国からの敵対心-20.00%
- 正式な外交:外交評判+2.00
- 外交団:毎月の外交官数+0.10
- 国家交易:交易許容量+10.00%
- 国家敵交易方針:交易効率+2.5%
- 植民地総督:植民地従属国からの収入+50%、外交範囲+25%
- 避難港:海軍修理コスト-20.00%
- 海軍先頭訓令:封鎖効率+50.00%
軍事フォーカス
- 沿岸での海上修理速度:+5.00%
- 食料調達の改善:陸軍消耗-25.00%
- 規律ある訓練:規律+5.00%
- 絶対主義の行政:毎月の支配度低下+0.20%
- 攻撃的な軍勢:陸軍士気回復速度+2.00%
- 火力優勢:砲兵火力+10.00%
- 大陸軍:人的資源+10.00%
- 連隊制度:陸軍維持費-5.00%
- 兵卒から元帥へ:歩兵戦力+10.00%
- コルベット:海軍被ダメージ-10.00%
革命時代(時代Ⅵ、1737年1月1日)
「変容(変態)」について
Europa Universalisにおいて変容(変態)とは、ある条件を満たした国家が別の国家へと政体を変更することをいいます。前作EU4においては、強力な国家へと変態できたりあるいは固有ミッションでフレーバー要素的なものもあったりするなどゲームプレイの幅を広げる重要な要素の一つでした。※前作EU4の日本語Modでは「変態」としていたが、今作EU5の日本語版では「変容」という翻訳になっている。
※ここでいう変容(変態)は、国家ランクの上昇(公国→王国→帝国)とは別のものです。前作EU4での変態については日本語Wiki「各国戦略/変態戦略 – EU4 Wiki」参照のこと
しかし今作EU5ではミッション自体が廃止されたことや、事前のTintoTalksで新たな国家になっても得られるものはないと表明されたこともあってか、現時点では今ひとつ盛り上がりに欠けるというか、多くのプレイヤーはまだそんなところにまで行けていない気もします。
※ただしロシア変態することで支配度ボーナスを得られることなどが知られており、「得られるものがない」ことはないようです。
ただし変容要素が存在するのは事実であり、ある種大切なロマン要素でもあるため、一応ここでまとめようかと思います。条件の羅列ではなく、主に初心者にとって躓きがちな条件を満たすための行動について記述します。
日本語情報はまだないようなので、英語での条件まとめ
- Formable country – Europa Universalis 5 Wiki:公式英語Wiki
- Europa Universalis 5 Formable Nations Guide – Deltia’s Gaming
- Europa Universalis V: All Formable Countries and How to Get Them
カスティーリャからスペイン(ティアⅢ)変容
カスティーリャ(スペイン)でロケーション領有条件さえ満たせば変容できるスペイン。
条件は、ナバラ、バレアレス、ポルトガル北部、ポルトガル南部のうち18ロケーションを領有すれば条件達成。条件としては、これは比較的簡単な部類。どんな開戦事由でもとにかく領有さえすれば良い。
※今作の1.0.8時点でもカスティーリャ(スペイン)とポルトガルは歴史的友好国などの設定はないようで、かなりの確率でポルトガルはカスティーリャに併呑されるか、少なくともライバルに指定されたりする。※事実ペドロ1世(カスティーリャ王)とアフォンソ4世(ポルトガル王)の間で婚姻問題のこじれを受けて1335年から戦争を行っているが、マリーン朝(モロッコ)の進出を受けて1339年に和平する。しかし後に王位継承問題や新大陸問題で対立する。EU5開始年の1337年はまさにこの戦争中である。
ただしプレイヤーでカスティーリャをやってみると、ポルトガル陸軍は意外に強く攻めあぐねる可能性が高い。翻ってアラゴン側はフランスと揉める機会が多いため、それに相乗りすることで結構簡単に領土を奪うこともできる(カスティーリャはフランスとも同盟が組めたりする)。そこで無難なのはナバラとグラナの属国化で18ロケーションを獲得することでスペイン化するのが1.0.8時点のカスティーリャプレイでは比較的容易な戦略だと思われる。グラナダについてはモロッコと同盟を組むと思われるが、対モロッコ戦では初期のモロッコ騎兵は圧倒的に強いが海峡さえ封鎖すれば勝てると思われる。とにかくグラナダの属国化を勝ち取れば良い。
2025年12月の1.0.10で、”カスティーリャとポルトガルの間に「良好な関係」開始修飾子を追加しました。これにより、ゲーム開始時に両国が互いに攻撃する可能性が低くなり、「リオ・サラドの戦い」イベント チェーンのトリガーも容易になりました。”ため、スペイン化するうえではむしろ少し面倒になった(ポルトガルを攻めるには停戦明けまで待ち、かつ友好国での安定度低下ペナルティも発生するので随時「侮辱」するなどが必要ではないかと思われる)。やはりアラゴン側を攻めるのが良いと思われる。
スペインに変容することで利用可能な「進歩」として、下記が得られる。※即時ではない。時代要件など注意
- Ⅳ時代:
- 進歩「サラマンカ学派」:毎月の研究進行度+5%(宗教改革時代、征服への神権が必要)
- 進歩「スペイン副王領」:毎月の植民地移住+50%(宗教改革時代、士官学校が必要)
- Ⅴ時代:
- 進歩「スペイン黄金世紀」:芸術家後援数+1、新しい芸術のスキル+5%(絶対主義時代、絶対主義者の野心が必要)
- 進歩「境界規律の復活」:毎月の宗教影響力+0.20(絶対主義時代、絶対主義の宮廷が必要)
- Ⅵ時代:
- 進歩「スペイン海軍の改革」:毎月の海軍の伝統(革命時代、大規模訓練が必要)
- 進歩「スペイン啓蒙主義」:毎月の開発度+0.0010(革命時代、啓蒙の宮廷が必要)
イタリア(ティアⅢ)変容
ティアⅢイタリアは、イタリア半島国家などで狙えます。
条件は、下記の3ロケーションおよび、イタリア半島の224ロケーションを領すること。
- ミラノ
- フィレンツェ
- ナプーレ ※ナポリ首都
対象範囲は、変容パネルの「変容イタリア」をホバーすると表示されます。現在のイタリア共和国をイメージするとわかりやすいでしょう。
狙いやすさで言えば、ナポリからシチリアを併呑して「両シチリア王国」へと変容し、徐々に北進するのが一番楽かもしれません。逆に北のミラノやフィレンツェから南進する形だと、ナポリはほぼ両シチリア化したうえで、下手すると(ビザンツを併呑した)セルビアやハンガリーなどとも同盟を組んでる可能性があります。もちろん慣れている人なら好きなようにやればいいのですが。
※ナポリは開始当初からバルカン半島に従属国を持っているのですが、あまりそちらに力を入れるとセルビアやブルガリア、オスマンなどバルカン国家との絡みも出てくるためあまり欲を出して手出ししないほうが良いかも知れません。コンスタンティノープル市場も気になりますが、どうせ支配度も上げれずまた兵を送るのにも苦労することになります。またハンガリーとの同君連合も出てくると思いますが、こちらも併合するには数百年かかるためあまり本腰を入れないほうが良いかも知れません。
※両シチリアだと植民地も狙えるポジションにありますので(カスティーリャなどでプレイすると度々アフリカ西岸で見かける)、色々楽しみ方はあるかと思います。なお両シチリア王国変容には「首都が両シチリア地域にあること」という条件がありますのでご注意ください。
イタリアに変容することで利用可能な「進歩」として、下記が得られる。※即時ではない。時代要件など注意
- Ⅰ時代:
- 進歩「半島の大学」:毎月の識字率+0.01%、最大識字率+5%(伝統時代、ギルドが必要)
- Ⅱ時代:
- 進歩「Continuation of the Renaissance」:文化伝統力+10%、文化影響力+10%(ルネサンス時代、ルネサンス彫刻が必要)
- 進歩「Connect the Interior」:街道敷設時間-20%(ルネサンス時代、パウンドロック運河が必要)
- 進歩「イタリアの名門家」:毎月の威信+0.10、外交許容量+10%(ルネサンス時代、将校の任命が必要)
- Ⅲ時代:
- 進歩「A Prized Possession」:水兵+10%、人的資源+10%(発見時代、標準化パイクが必要)
- 進歩「Influential Clergy」:毎月の宗教影響力+0.10(発見時代、外交訓練が必要)
- 進歩「イタリアの適応力」:制度の受容コスト-20%(発見時代、知識の共有が必要)
- Ⅳ時代:
- 進歩「Hardships of War」:毎月の戦争疲弊-0.02、要塞の防衛+10%(宗教改革時代、口径の標準化が必要)
- 進歩「Flourishing Cities」:都市建造物コスト-5%、POP昇格速度+10%(宗教改革時代、農業市場が必要)
- 進歩「コンドッティエーリの偉大なる指揮官」:傭兵指揮官の雇用コスト-20%、傭兵の雇用コスト-20%(宗教改革時代、交易使節が必要)
- Ⅴ時代:
- 進歩「Appealing Landscape」:POP移住速度+10%、市街地の移住地の魅力+0.10(絶対主義時代、絶対的忠誠が必要)
ヤサウリ(ティムール)での「属国からの独立運動」
変容の中には1337年時点ではどこかの従属国な国があり、そこから独立を果たして独立国家となって初めて権利が得られるものもあります。ここではその属国からの独立過程を記しておきます。
例えばティムールを建国するための基礎国家の一つとしてヤサウリ(ヤサウリウルス)という国があります(現代のウズベキスタンあたり)。
※他にティムールでプレイするには、チャガタイ・ウルス、バルラス・ウルスなどもありますが、恐らくヤサウリで変容するのが一番良いのではないかと思われます。史実的には彼はバルラス族出身なのですが、EU5では貧乏国家でありなおかつ事故でティムールを殺してしまう可能性もあります。またチャガタイ・ウルスではヤサウリを追放してサマルカンドを領有する必要があり、また23歳になるまでティムールを操作する事ができません。
チャガタイ・ウルスとジョチ・ウルスに挟まれた弱小国家の一つで、開始時にはチャガタイ・ウルスの数ある従属国のひとつです。ですがある状態にするとティムール朝と化すことが可能な国でもあります。そのために独立する必要があります。
このヤサウリで独立するにはいくつか手段があるようですが、ゲームの仕組みとして用意されているものに「独立運動」というものがあります。これはAI宗主国の下にいくつかの属国がある場合に、共に独立を目指す国家や応援してくれる国家を募ってから独立戦争を起こす仕組みです。※普通に開戦事由「独立戦争」で宣戦布告しても可能だと思われる
- ヤサウリの場合は宗主国はチャガタイ・ウルスで、まずこのチャガタイ・ウルスの外交場面を開いて敵対アクションから「チャガタイを標的とする新たな独立運動を設立」を選びます

- すると国際機関「ヤサウリの独立運動」という組織が設立され、まず自国が自動的に参加します。
- ※後でも使うので★を付けてアウトライナーに登録しておくと良いでしょう。
- ※(チャガタイに限らず)他の宗主国側でプレイしていても「独立運動が設立されました」という表示が出てきてメンバーなどを確認できる。関係改善など速やかに手当するようにしよう。
- 続いて参戦を呼びかけたい国家の外交画面を開いて、次は友好アクションの中から「ヤサウリの独立運動に招待(標的:チャガタイ)」を選ぶと条件を満たせば独立運動に参加してくれます
※ヤサウリの場合には、北側の大国ジョチ・ウルスや南東のカラウナス・ウルス(チャガタイの属国)が参加してくれるんじゃないかと思います。注意点は独立運動に参加しても裏切って独立戦争に参戦しない場合があること(とは言え敵側に回らないだけでもありがたい)。 - 陸軍を揃えるなど準備が整えば、次の2通りで「宣戦布告」できます
- 普通に宣戦布告画面から開戦事由を「独立(チャガタイの独立)」を選ぶ
- 国際機関「ヤサウリの独立運動」パネルにある「運動を呼びかける」を選ぶ
- どちらを選んでも同じ開戦理由(独立)での宣戦布告となります
- あとは頑張って戦勝点を60点以上貯めましょう。これで「宗主国からの独立(1.0.7時点で翻訳ができてないが”independence:60.00”などと書かれている)」の条件を満たすことができます。同時に60点以上あればいくつかの州やロケーションを割譲させることも可能です。
※内政をしてからなどとじっくり構えていると攻める機会を失う可能性もありますので、電光石火の勢いで全力で召集して一気に独立を勝ち取りましょう。チャガタイ・ウルスは図体はデカく見えますが内情はほとんどスカスカであり、むしろ数ある属国のほうがめんどくさいです。チャガタイ側も早期に動き出すためじっくり構えていると独立運動に参加してくれる国家も減ってしまう(=敵が増える)ので、難しければ逆に早めに評価改善などを行ってでも独立運動への参加を呼びかけ、一気にカタをつけてしまいましょう。ティムール化できさえすれば後はこちらの思う壺です。
ここまでが独立戦争の流れ。
ティムール変容について
なお肝心のヤサウリのティムール化についてはやや変則的で、条件を満たした状態で1360年1月1日になるとイベント「テムル ハンの台頭」が発生し、ここで選択肢2「彼の今後を注意深く見守ろう」を選ぶとティムール国家へと変容し、その後は統治者ティムール本人(ゲーム内ではテムル・ボルジギン100-85-68)としてプレイすることになる。※これ以前の数年前から頻繁に(反乱リーダーとしての)テムルハンが登場するイベントが発生するが、それとの関係性(選択肢の影響)は不明。なおヤサウリからの変容時には、借金はすべて帳消しになり、各階級忠誠度は変容した途端100になる
こうしてティムール化すると、意味不明なほどの強力なバフが即時得られる。※他の変容国家と異なり成立要件はなく下記が即時発動する。
1.シチュエーション「テムル ハンの台頭」が発生し、その中のアクション「侵攻を計画」をクリックすると、国境を接している任意の国家に対して開戦事由「テムル ハンの征服」が即座に得られる。これがなんと攻撃側の征服コスト0%、攻撃側の従属コスト-75%というぶっ壊れ開戦事由となっている。
- 「テムル ハンの台頭」終息条件:少なくともどれか一つ
- ティムールは統治者の能力が150ポイント未満か、統治者または後継者がいない
- ティムールが併合または従属させられた
- ティムールがモンゴルを復興させた
- 「テムル ハンの台頭」終息条件:少なくともどれか一つ
2.さらにテムル・ポルジギン(ティムール本人)が生きている限りにおいて補正「中央アジアの災厄」を受け、テムル ハンが包囲したロケーションを自動的に併合できる(まだ該当地での戦争中にもかかわらず州・ロケーションの統合が開始され、文化が同じならば戦争中にもかかわらず中核化される)。
※戦争中からすでに自国領土化して併合しているため、”敵国の全領土を併合しつつあるが白紙和平”という意味不明な和平となることも多い(終戦時には相手は滅亡が確定するためもう取り上げるものがない)。一定以上を占領(併合)した時点で戦勝点は100に張り付き、同時に統合しながら延々と継戦できてしまう。大きな国だと戦争が終わる頃にはすでに中核化されていたり、あるいは統合手続きがかなり進行していることもある
ちなみにその後発生する「我々の遺産」の選択肢の効果は次のようになっている。
- アッラーが定めたサーヒブ・キラーン:陸軍士気+15%、真の信仰寛容度+1.00、神秘主義への毎月傾き+0.05
- チンギス・ハンの継承者:陸軍士気+15%、毎月正統性+0.10、毎月遊牧民の結束+0.10、分離主義-5%
モンゴル帝国変容
さらに条件を満たせば「モンゴル帝国」に変容することも可能となっている(変容前のヤサウリのままでも一応可能だが恐らく相当難しい)。ただしこちらの条件は東西範囲が広いため結構厳しく、まさに獅子奮迅の動きを見せないと実現は難しい。
- わが国が内戦ではない
- わが国がサライを所有している
- わが国がカザンを所有している
- わが国がサマルカンドを所有している
- わが国がカッファを所有している
- わが国が大都を所有している
- わが国が廣州を所有している
- わが国がカラコルムを所有している
- 以下の地方/地域のうち3,324を所有している:
- 地方:モンゴル、華東、華北、華南、華西、ポントス・ステップ、ロシア、新疆
- 地域:アゼルバイジャン、ファールス、イラーク・アジャミー、ケルマン、フーゼスターン・ルリスターン、コルデスターン、マザーンダラーン、クヒスターン、デシュト・イ・キプチャク、西ホラーサーン、ジェティス
ムガル帝国変容
いっぽうムガル帝国への変容には、早期にヒンドゥスターン地域(北部インド)と国境を接し、デリーへと首都移転しておく。ティムールが死んで(ステータス合計150以上の後継者が必要)、「彼の遺志を継ぐ」フラグを建てた後、ムガルへと変容する。
- 宗教グループがイスラム教である
- 少なくともどれかひとつ:
- ホラズムがイラン文化圏に属している
- ホラズムがテュルク文化圏に属している
- ホラズム文化にアフガニ語がある
- わが国がデリーを所有している
- わが国がアーグラを所有している
- わが国がラホールを所有している
- 以下のロケーションのうち266を所有している:ヒンドゥスターン
マップ関係
EU5(Europa Universalis V)ではプレイの大半が地図とにらめっこして進めることになり、この操作をいかに習熟するかでプレイフィールは大きく変わってきます。
従属国の表示方法のカスタマイズ
マップ上で従属国の表示が(どこの国家の従属国なのか)分かりづらい場合には、「従属国の宗主国色」を「表示する」に変えて、マップモードを一度切り替える(政治マップモード⇔外交マップモード)と指定内容で表示される。
「設定」-「マップ」の国家
- 従属国の宗主国名:
- 表示する:デフォルト。カメラを引いたときに従属国名ではなく宗主国名を表示する
- 表示しない:カメラを引いても従属国名を表示し続ける
- 従属国の宗主国色:
- 表示しない:従属国は個別の国家色で塗り分けされる
※従属国の国家色がかなり異なるため初心者は避けたほうが良いと思われる - 混合:従属国が宗主国と同系色で表示される

※国際組織を宗主国として表示+従属国の宗主国色混合。1337年4月1日開始直後
- 表示する:デフォルト。従属国が同じ色で表示される

※国際組織を宗主国として表示+従属国の宗主国色で表示。1337年4月1日開始直後
- 表示しない:従属国は個別の国家色で塗り分けされる
- 国際組織を宗主国として表示:
- 表示しない:デフォルト
- 表示する:わかりやすいところでは「神聖ローマ帝国(HRE諸侯国)」が1国として塗り分け表示される
マップ高速移動
TABキーを押すと全世界マップ(最大ズームアウト)へとスムーズに切り替わり、TABキーを離す時にマウスホバーしていた国家(ロケーション)を中心に再ズームされる。
例えばヨーロッパの国でプレイしていて、中東方面や新大陸に地図スクロールしているとやや煩わしいが、この最大ズームアウトを使えば素早く移動できる。もちろん何度も見たい国はピン留めして右サイドのアウトライナーからショートカットすることもできる。
[HOME]キーを押せば自国首都へと戻る。
マップのズーム挙動
例えばアウトライナーあたりでホイールすると、(アウトライナーの隙間から突き抜けて)そのアウトライナーの直下あたりのロケーションにズームイン・ズームアウトしてしまうという挙動をする事がある。
これは「設定」-「コントロール」の”ズーム挙動”で設定できる挙動で、下記のような設定ができる。
- 相対カーソル:画面中央ロケーションとマウスカーソルとの相対位置(ロケーション)にズームイン/アウト
- カーソルにズームイン:マウスカーソル位置(ロケーション)にズームイン/アウト
- カーソルを無視:(マウスカーソル位置にかかわらず)常に画面中央地点にズームイン/アウト
マップパネルの常時表示
画面中央下にあるマップパネルをいちいち閉じずに常時表示したいときは、マップパネル左端にあるピン留めをするとよい。そのまま画面に残って常時表示される。

※現在は閉じる動作が重なっていてやや不自然な動きになっている。またセーブデータ読み込み時に初期化される
- あるいは、「M」キーを押すと(マウスカーソルがどこにあっても)即座にマップモードパネルが開くので、画面下部にタッチしてしまってマップがスクロールしてイライラすることもやや減ると思われる。
- ※私はキーバインド+Mod(Nice Wide Mapmode UI)を併用することでなるべくマップモードパネルを使わないようにしています。※Mod利用は自己責任で。キーバインドメモはこのページ下部参照
コントロールパネル
マップモードメニューの上にピン留め表示できる機能。ピン留めできる対象は画面右サイドのアウトライナーと同じ。
ただし特に縦方向は圧迫感が大きいためアウトライナー利用で良いのではないかと思われる。
マップの角度変更
右ドラッグするとマップに対するカメラ角度を変更できる。
ただし、ドラッグを止めると東西方向については自動的にノースアップ(北が上)ポジションへと戻るが、俯角については保存されそのままの俯角でプレイできる。
※「設定」-「マップ」のフラットマップモードにもよる
マップのエッジスクロールを切りたい
エッジスクロールはマウスで画面端にタッチするとその方向へとマップをスライド(パン)させる仕組みのこと。
「設定」-「コントロール」の”マウスパン”を「フリー」から「無効」に変える。
あるいは「8方向」に切り替えても多少判定が鈍くなる気がする。
国家ウィンドウ
マップ画面から他国家の国家ウィンドウを開きたい時は、その国家のいずれかの州・ロケーションを「Ctrl+右クリック」すればオープンできます。※右クリックメニューから国家ウィンドウでも良い
この時、国家ウィンドウのタブ(外交・国家・キャラクター)を切り替えておけば、Ctrl+クリックにより次々と国家の該当タブを見ていくことが可能です。
- またマップモードに「Political(Selection)」というモードがあり、これにキーバインドを行って開くと、左シングルクリックで直接該当国家の国家ウィンドウが開くようになります。※(政治・外交マップモードで)ある程度カメラを引いてから選択するのと同じ
- あるいは、気になる国家については国家ウィンドウなどからピン留めすれば、右側のアウトライナーにピン留めでき、そこからのクリックで国家ウィンドウを開くことができるようになります。
王朝画面(家系図)
なお家系図(王朝画面)は、F1キー「政府」の君主の肖像画を右クリックすると出るメニューで「王朝を開く」と出てくるほか、画面左上の君主肖像画の右クリックでも同じメニューが開く。
他にも誰かキャラクターが表示されている画面の中央の国旗アイコン左クリックでも王朝画面が開く。
州・ロケーション
ロケーション
ロケーションとはEU5での土地管理の基本区分で、州の一部をなす。都市と街と田園集落がある

- 【都】:ギルドと建造物を建てられる
- 階層:貴族、聖職者、労働者、農民、市民、兵士
※この「都」とは首都でも州都でもなく、1国家に複数存在できる。むしろ田園集落ランクの首都を持つ国家もいっぱいある。
- 階層:貴族、聖職者、労働者、農民、市民、兵士
- 【街】:ギルドと建造物を建てられる
- 階層:貴族、聖職者、労働者、農民、市民
- 【田園集落】:建造物のみ
- 階層:貴族、聖職者、労働者、農民
これらはロケーションランクで区別され、「経済マップモード」-「ロケーションランク」で表示できる。
ロケーションランクごとのボーナス

※インゲームヘルプによる。ただし公式Wikiでは食糧上限が550、300、50となっている。またその他人口増減などもけっこう違う。
人口収容力
人口マップモードに切り替えてロケーションにマウスホバーするとそのロケーションの情報がホバー表示され、その計算式も表示される。基礎値はロケーションランク(都:100k/街:20k)で決まり、さらに植生や開発度、気候などで加算されていく。
下記「プロウサ」ロケーションであれば、上限は692,000となっており、現在は60,933人が居住している。

なおF3生産-建造物で「集落」(移住地魅力+1.0、人口増加+1%)を建てようとするとフィルターに「利用可能な農民あり」が入っているがこれだと見つからないため、クリックしてフィルターからその条件を外すと建設可能なロケーションが表示される。
ロケーションの名前を変えたい
ロケーションの名前を変えたい場合には、ロケーションパネルを開いて右クリックすると開くメニューの一番上に「ロケーションの名称変更」が出てくるのでそれで変更できる。
ロケーションランクを上げたい(下げたい)
ロケーションランクを上げるには、条件を満たしたうえでロケーション画面左上にある「□」や「◎」をクリックすれば良い。ここに条件も書かれている。
右クリックでダウングレードも可能。
公式Wiki:Location – Europa Universalis 5 Wiki
州都
EU5の戦争では「州都を占領すれば敵国の州全体を抑えることができる(ただし別要塞ロケーションを除く)」が、その肝心の州都の表示方法は「地理マップモード」-「州」で”★”がついているのが州都となっている。
なお州が複数国家に分断されている場合には、州都を領有していない国家のいずれかのロケーションに「暫定的な州都」が置かれる。この「暫定的な州都」を占領すれば、敵国の(そのロケーションを含んでいる州の)残りのロケーションを占領したことになる。※州都占領後にゲージが(該当ロケーションに兵がいなくとも)勝手に一斉に回りだす。これで戦争をスピーディにしている
※この「暫定的な州都」については一定の計算式で自動的に決まるが、ロケーションが対等な場合にはあらかじめ決められている設定ファイルによって決まるという。
またプレイヤー発言によれば、州都は最も人口が多くて発展しているロケーションが自動的に州都として選択されるということで、実際に移るケースもあるようです。
同時に占領ルールには、「要塞を落とせば要塞のZoC範囲のロケーションを占領したことになる」というルールも追加されている。逆に要塞のあるロケーションは、州都を落とした際の自動占領から除外される
要塞マップモードにすれば、全世界の要塞のあるロケーションとそのZoC範囲が綺麗に描画される。侵攻作戦前にはきちんと確認するようにしよう。
建造物を建てる
建造物とは、あらゆる建物を含んでおり、特に今作EU5では内政用の原材料採集施設からそれの加工施設、さらには村(農村・漁村・森林村など)、王宮、城、病院などが建設でき、それぞれに細かな効果が設定されており内政などに大きく影響してくる。また上位施設は建設時に下位生産施設で生産された品物がなければ建設や稼働ができず、必要に応じて市場(マーケット)から輸入したりも行われる。
ロケーション右クリックから「現在の建造物」に入り、建物を選ぶ。

※これは都・街の場合のロケーションメニュー
この建造物は、影響がよくわからないところもあって特に初期プレイでは自動化してしまってよくわからないままプレイしている場合が多いかと思います(私自身がそうだった)。
しかし結局どこかで理解しておかないと、例えば植民地プレイで植民したものの放置してると植民地が育たずにっちもさっちも行かなくなることがありますし、もっと言えばあまり恵まれていない国家でスタートするとこのあたりで躓くことにもなりかねません。
そういうときのために基本操作を学んでおきましょう。
建造物メニューのフィルタについて
ここでは開始直後のカスティーリャ(複数市場を持っている)を例にしてみます。※Modを入れているため、細かい表示でベースゲームと若干異なる部分があるかも知れません。
1.建造物全体のフィルタ
まず建造物全体の画面について見ておきましょう。
F3生産-建造物を開くと次のようなパネルが開きます。

上段左の4つアイコンが並んでいるものは、次のようになっています。
- 初期表示:全カテゴリーの建造物が並ぶ。下段の雇用種類で「貴族」「聖職者」「農民」「労働者」「兵士」などで建造物種類を絞り込める。
- カテゴリーごと表示:カテゴリーごとに建造物をまとめた表示。「原材料生産」、「農業建物」、「武器産業」、「宗教施設」などのカテゴリーごとに建造物種類を絞り込んで表示できます。
- 外国建造物:外国に建造する建造物のみを表示します。
- 階級建造物:プレイヤーではなく自国の各階級(貴族・聖職者・市民など)が勝手に建てる階級建造物に絞り込む。ロケーションごとではなく個別階級ごとに一括して破壊したいときにこのメニューを使うと早い(ただし破壊には条件がある)
また青い囲みは次のようになっています
- 自国の1ロケーション以上に建設可能な建造物に絞り込む
※クリックするとフィルタ「ロケーションに建設可能」が追加される。解除するにはフィルタをクリックする - 建造物建設の自動化アイコン
- 生産方法の自動化アイコン ※詳細は「生産方法の選択」に記しています
- 自国の1ロケーション以上に建設可能な建造物に絞り込む
さらに上段の中央に「雇用制度」と書かれている幅広ボタンは、就労先として複数選択肢がある場合に”どの建造物で働かせるか”という指定ができる画面です。これを押すと次のパネルが開きます。

- 平等:ランダムじゃないかと思います。「共同体主義への毎月の傾き+0.10」の効果あり。
- 建設順:建てられた順に雇用していく。「伝統経済への毎月の傾き+0.10」の効果あり。
- 収益性優先:建造物で取り扱う生産品の収益を基準に割り当てる。「資本経済への毎月の傾き+0.10」の効果あり。
- インフラ最優先および収益性順:インフラ系建造物と収益性を基準に優先雇用する。「”資本経済”および”共同体主義”への傾きがそれぞれ+0.05」の効果あり。※なおこの雇用制度の選択のうち「インフラ最優先および収益性順」については、1.0.10時点では機能していないということです。
ゲーム序盤では「収益性優先」が良く、いっぽう「建設順」にすると偏るためかいつまでも雇用されないこともあるそうです。
ここまでは建造物を絞り込んでいないときに使える機能です。
次に個別の建造物パネルでのフィルターを見ていきます。仮に「市場の村」を選ぶと以下のような画面が開きます。※税基盤寄与額(ビルバオの+0.09)表示はMod

この画面がけっこう罠で、自分の建てたいと思っているロケーションや市場(マーケット)でない場合には、ロケーションに「建設可能」を意味する緑色が塗られません。
※この状態でもマウスカーソルをホバーすると建設可能なロケーションではマウスカーソルが建設可能を示す「ハンマーアイコン」に変わります。しかしいちいちホバーして探すのも面倒です。
2.マーケットのフィルタ切替
そこでスクショ右上のピンク色の囲みを見てみましょう。”マーケットのフィルタ”が表示されており、よく見ると市場(マーケット)が切り替えできるようになっています。
カスティーリャの場合はゲーム開始時に5つの市場へのアクセスが可能で、仮に矢印上下(↑↓)を押してみると、下図のように自国がアクセスできる市場(マーケット)が順送りに切り替えできます。


3.マーケットのフィルタ削除
例えばカスティーリャのように複数市場(マーケット)を所有しているときには、市場範囲で見ずに全国土で「必要なところに全部建てたい」という気持ちもあるかと思います。そんなときはピンク囲みの「×」をクリックすれば、市場(マーケット)での絞り込みを削除できます。
「×」をクリックすると、上部の「~の市場」で絞り込まれていたのが「すべての市場を表示中」と切り替わります。

カスティーリャの場合はゲーム開始直後に5市場(マーケット)へのアクセス権を持っているのですが、全市場への建設可否が一気に可視化されるようになります。
4.立地条件フィルタ
次は”市場フィルタ”の下にある”立地条件のフィルタ”です。
例によってピンク囲みをしてみました。これは、(無理な建物を建てないように)ロケーションごとに”建設しようとしている建物に必要な条件”を満たすように絞り込みをかけてくれているわけです。

ここでは「市場の村」を建設しようとしているため、「利用可能な農民あり」というフィルタがオンになっています。続いて「建造物レベル上限未満」、「所有ロケーション」、「利用可能なレベルあり」というフィルタがデフォルトで入ります。
もし建設した「市場の村」で労働可能な農民がいないと、”労働者が不足している”というアラートが出ることになり、せっかく建てた市場の村で製品が生産されないということにもなりかねないため親切心でフィルタしてくれているのです。ただしそれはプレイヤー自身が内閣アクションなどでも手当できる(例えば移住や部族定住など)ということがわかってさえいれば、このフィルタを(1つずつ)削除することで無理やり建てることができます。
5.他のフィルタ指定
これらのフィルタは、ピンク囲みしている「漏斗アイコン」をクリックすると、右側にフィルタパネルが開いてそこでも選択できます。下図は立地ロケーションフィルタパネルを開いた例。

市場(マーケット)フィルタでも順送りでなく市場一覧からダイレクトに選択可能です。しかし植民地開拓時などは、さすがに選択ではなくフィルタ削除して全部市場を対象にしたほうが早いでしょう。
また立地ロケーションフィルタパネルでは下記のような詳細な絞り込みも可能です。
- ロケーションランク:都・街・田園集落
- ロケーションの支配度(%)や市場アクセス(%)、失業率(%)、ロケーション人口(人)のゲージ指定
- 最大まで拡大されているか否か
- 沿岸/非沿岸ロケーション
- 市民/労働者の不足なし
- 中核地/統合済み/征服済み/植民地化
- 利用可能なレベルの有無、所有ロケーションか否か、建造物レベル上限未満か超過を含めるか
実践的な建造物建築
※基本的には、生産方法、建造物、RGOなどを自動化しておけばそのうちに満たされますが、基本的な操作ですのでどこかでマスターする必要があるかと思います。その基本的な対応方法を書いておきます。
1.POP必需品を建てる
※次に記述する方法でやっていってもいいのですが、まず最初はこちらの「POP必需品」でチェックしていったほうが良いでしょう。慣れるとこれは非常に便利です。
アラートに「満たされないPOP」という表示が出るときがあります。書かれている通り、満たされないPOPはやがて反乱活動へと走らせてしまう恐れがあるため、これの手当も必要です。

これ最初のうちは「どうすりゃいいんだよ」と思うでしょうが、アラートでは市場名と件数だけしか出ていませんので、とりあえずクリックしてみます(アラートクリックだけでは何も起きません)。複数ある場合はサイクリックになっているため、どんどん左クリックしながら各市場で何が要求されているのかを確認してみましょう。
するとまず先頭のブルゴス市場での必需品が表示されます。

上のスクショで分かる通り、ご丁寧にブルゴス市場での不足品のRGOロケーションが色塗りされています。これは便利ですね。市場内にRGOがあるものは、まずは素直に示されているRGO建造物のレベルを上げるのがいいかと思います。このブルゴス市場では、薄赤色の果物は1ロケーションしかありませんので、ここを強化(レベルアップ)するしかありません。2行目の雑穀も(市場内では)2ロケーション限定です。※これでも不足が続くようなら建造物(果物の場合は「果樹園」労働者1000人)を建てる手もあります。
次に生産方法のあるものはその生産設備を建てていきます。左パネルを詳しく見ていきます。この画面で2列目の交易品収支で並べ替えると、どの産品がどれくらいの(輸入による)収益赤字を出しているかがわかります。※細かい数値はゲームリロードごとにかなり変動するので参考程度に
そしてその列を順に見ていくと、交易品価格(単価)、輸入/輸出、建造物、RGO建造物と並んでいます。以下は収支での並べ替えをしたもの。特に上位の不足品をなんとかしたいですね。手段が複数ある場合には、右列から左列へと順番に手当していくことを目標としましょう(つまりRGO→生産品建造物→輸入の順)。

先程のRGOはレベルをカチカチ上げるだけで済むのですが、生産施設の方は建物アイコンをクリックすると複数選択肢がある場合があり、そのどれかの生産施設を雇用する階級の余剰数などに合わせて選んで立てる必要があります。
※詳しくはRGO建造物および生産施設の方法についてはひつ下の”2.市場(マーケット)を選んでから~”に書きましたのでそちらを参考にしてください。
問題はRGOや生産方法すらない必需品で、これは輸入してくるしかありません。輸入については”F2キー「経済」の交易での手動取引”のところに書いておきましたので、それで輸入を行いましょう。
※ただしF2「経済」-「交易」で管理されているのはあくまで「公的な交易」であって、EU5ではこれ以外に民間での交易も行われていることになっています。その民間交易で賄えるものもあり、あるいはゲーム後半で必需品として上がってくるコーヒーやココアなどの特定方法でしか入手できないものもあります。後者については植民地交易などを行っていく必要があり、少し上級プレイになってきます。
2.市場(マーケット)を選んでから不足品建造物を建てる
※こちらは主にPOP必需品アラートが出ていない場合の手段です。結局上の1番の手順を別々に進めているようなものです。
市場マップモードに切り替えて、(市場名が表示されるまでカメラを引いてから)自国市場をマウスホバーすると次のような画面になります。※カメラを引くとロケーションごとの市場情報表示から切り替わる

ダイアログ中央の左側には利益順5品、右側には満たされていない(ので輸入しているため赤字になっている)必需品5品が並んでいます。とりあえず必需品が満たされていないため、特にゲーム開始段階ではこれをどうにかすることを考えましょう。
この例では不足しているのは、果物-11.82、雑穀-10.63、家具-8.83、工具-7.63、オリーブ-7.46となっており、ここで取りうる手段は3通りあるかと思います。
- RGO建築物を建てる:経済-原材料マップモードに切り替えて、不足していた物品の産地ロケーションを選択し、右肩のRGO建物クリックして増築します。先程見たブルゴス市場では果物RGOは貴重で1ロケーションしかありません。ここではできるだけレベルを挙げておきたいところです。※ロケーションごとのRGO産品はどの国家でプレイしても完全固定

- 生産建造物を建てる:労働者雇用の建造物に「果樹園」があり、これは0.17の木材から0.3の果物を生産できます。ありがたいことにブルゴス市場のほとんどで建てることができ、原料と成る木材も多くのロケーションで生産可能です。こちらで手当しても良いでしょう。

- 輸入する:今回の果物の場合は選択肢1および2で手当できましたが、どうしても自国で生産できない場合は輸入も考えましょう。※何でも輸入で済ませることもできますが、いざ禁輸されれば一気に国内の不満が高まる可能性もありますので、究極的には国内生産(市場内での地産地消)が理想でしょう。
- RGO建築物を建てる:経済-原材料マップモードに切り替えて、不足していた物品の産地ロケーションを選択し、右肩のRGO建物クリックして増築します。先程見たブルゴス市場では果物RGOは貴重で1ロケーションしかありません。ここではできるだけレベルを挙げておきたいところです。※ロケーションごとのRGO産品はどの国家でプレイしても完全固定
同様に、雑穀、家具、工具、オリーブなども手当していきましょう。雑穀はブルゴス市場で2ロケーション、雑穀も2ロケーションRGOで産出しています。家具および工具は上記2の生産施設建設(工具は市場の村など、家具はゲーム初期では作れないんじゃないかと思います)、オリーブはブルゴスではありませんが、南側のセヴィリア市場では複数ロケーションRGOにあります。このように、自国(市場内)で調達できるものと、輸入などで手当する必要があるものとがあることを把握しておくことが大切です。
生産方法の選択
少し分かりづらいのが複数の産品を生産できる建造物だと思います。
例えば農民の建造物にある「市場の村」を例に見てみると、次の6種類もの生産方法が選択できる多機能な建物だとわかります。

上から、次のようになってます(1.0.10時点)。
- 0.4の鉄 → 0.5の工具
- 1.0の砂 → 0.3のガラス
- 0.5雑穀+0.1木材+0.07工具 → 0.5のビール
- 0.32の木材 → 0.2の武器
- 0.4の石材 → 0.1の宝飾品
- 0.33の粘土 → 0.2の陶器
このうち実際にどれが生産されるのかは、右サイドの「自動化」パネルにある「生産方法」を自動化すると自動的に選択されます。※自動化中でも選択できるように見えますが、翌月などに自動選択に戻ります
※もし自国市場で何かが不足してる場合には、これらを選択することで生産品を変更することもできます。ただしよほど極小ロケーション国家かつ小さな独立市場でない限りは、おそらく特定の生産品を管理するというのは至難の業ですから大人しく自動化に任せたほうが良いかも知れません。
例えば「ビール」は1337年から建設できる「醸造所」でも生産可能で、例えばカスティーリャでは開始時点で(ブルゴス市場だけで)13ヶ所も建っています。同様に見ていくと、工具ギルドは14軒、ガラスギルドは1軒、宝飾職人ギルドは1軒、陶器職人ギルドは14軒も建っています。つまり”この瞬間のブルゴス市場”ではガラスと宝飾品がやや貴重だとわかります。しかし実際には日々変動する需要も関係してくるため、このようなまるでAnnoシリーズのようなミクロな管理をやっても仕方ないので大抵は自動化で済む話だと思います。
しかし開いたばかりの植民地などで特定物資(たとえば”れんが”だったり)が少ない場合などは、この自動化を解除して指定物品を生産させることが必要になってくるかも知れません。”れんが”は、「石造り」施設で石材0.4あるいは、粘土0.8でそれぞれれんが0.5が生産可能となっていますので、まずこの石造り施設を建てるところから始まる(もちろん粘土・石材のRGOロケーション確保)ということになります。
※農民雇用の「~村」や「集落」「灌漑」では建設に漏れなく”れんが”が必要なため、周囲に既存の国家がない植民地(例えばブラジル)などでは、まず「石造り」建設に必要な”労働者500人”(素材は不要)というのが発展への第一歩になるかと思います(なおかつ石材か粘土を産出するロケーションがあること)。あるいは本国から”れんが”を輸出するのも手でしょう。※交易枠はあくまでアクションを起こす側が消費するので、タダでさえ交易枠が小さい植民地側で輸入するのは得策ではありません。
では具体的に生産方法を選択してみます。
F3生産-建造物で「市場の村」を選択(ホバー)すると、例えばカスティーリャでは北部の「ビルバオ」というロケーションに1軒だけ建っています。このビルバオロケーション画面を開いて、一番下の「農民」カテゴリーにある「市場の村」をクリックすると、生産方法選択画面が開きます。

↓

生産したい生産品行をクリックすると、左端にある●印が移動し、その生産品を生産し始めます。通常は指定することなどはないでしょうが、こういう手段で生産品を指定できるということは覚えておくとよいでしょう。
建造物に助成金を出したい
必需品だったり、漁村など水兵を確保するために赤字でも運営を続けさせたい場合もあります。そんなときは助成金(補助金)を出すことで運営を助けることもできます。
※「赤字でも良いじゃん」というわけではなく、赤字だと必要な交易品を購入できず操業できません。それでは維持している意味がありません。
F3生産-建造物で建造物メニューを開き、例えば農民で絞り込むと次のような画面が出ます。このとき中央辺りに小さなアイコンが1つか2つ並んでいます。※雇用種類アイコンはMod

このうちの左側が助成金のオンオフボタンになっています。漁村は(特にゲーム序盤では選択肢がない)水兵維持のために国家に必要な施設ですが、魚は必需品扱いされていない(必要度合いが低い)ため赤字が出やすくなっています。
このときに、このアイコンをポチっと押しておくことで助成金を出すことができます。
この助成金は、個別の1軒ごとに出すこともできます。先程の画面で漁村をクリックすると、皆さん見たことがある次の画面に出ます。※建造物レベルアイコン・RGOアイコン・有効支配度アイコンはMod

この画面のピンク囲み部分は個別のロケーションでの建造物ごとの助成金や操業停止アイコンになっています。植民地化できて国家が広まった場合など、全体での操業停止は困るけど、植民地部分だけは止めたい(あるいはその逆など)場合には、この画面に入ってポチポチクリックすることで個別の操作が可能です。
建造物を操業停止させたい
1つ上の項目の助成金と同様の画面で、操業停止指示も可能です。※建造物はそのまま、雇用していたPOPを解放して他の施設で雇用可能にする

これも同様に、その建造物全体で操業停止できるほか、個別の建造物ごとの操業停止/再開指示も可能です。
漁村などでは赤字幅も小さいですが、巨額赤字を出すような施設では、一時的に赤字を抑えたいときなどに活用できるでしょう。
建造物の建設をキャンセルしたい
- マップの該当ロケーションの建造中アイコンで右クリック
- Shift右クリックで確認ダイアログなしにキャンセル
建造物自動化していないのに気づいたら勝手に建設されている
これは次のケースがある。
- 各階級が階級建造物(荘園)を建てている
- これは各階級の持ち出し(国庫からの支出ではない)のため、勝手に建てさせておけば良い。自動化で階級建造物の破壊というのもある。アウトライナーからキャンセルもできるが、マウスホバーして見ると効果(階級別の各種バフ)も表示されるのでよく考える必要がある。

- これは各階級の持ち出し(国庫からの支出ではない)のため、勝手に建てさせておけば良い。自動化で階級建造物の破壊というのもある。アウトライナーからキャンセルもできるが、マウスホバーして見ると効果(階級別の各種バフ)も表示されるのでよく考える必要がある。
- 他国が外国建造物(交易施設)を建てている
- これも他国が勝手に建てているもの。これを止めさせるには、戦後和平で「建造物を禁止する」を選ぶ必要がある。マウスホバーするとどこの国が建てたのかが表示される。

- これは自国でも他国内に建てることが可能だが、一定の国交が必要で、また外交許容量を消費する。代わりに該当ロケーションの「戦場の霧」を消すことができる。
- これも他国が勝手に建てているもの。これを止めさせるには、戦後和平で「建造物を禁止する」を選ぶ必要がある。マウスホバーするとどこの国が建てたのかが表示される。
- RGO建設を自動化していてRGO建造物が建てられている
- 止めたければRGO自動化を止める
RGO建設メニュー
RGOはResource Gathering Operationの略で、要するに原材料採集施設のこと。
EU5では、あるロケーションで産出する産物は1ロケーションごとに1品で固定で決まっており、F2「経済」-「原材料」マップモードに切り替えると原材料名とアイコンが表示される。
※どの国家でプレイしても固定。Modで変更するものがあるほか、公式のパッチにより変化することはある。
RGO建設とは、この各ロケーションごとに固定で決まっている産物の生産施設を強化することに他ならない。
これを強化するには、ロケーション画面を開いて右肩のRGO建物を左クリックすると増築(レベルアップ)が、また右クリックで減築(レベルダウン)できます。

もっと手っ取り早いのは、F3生産-交易品に切替え、そこにある大きな「RGOビルダーを開く」ボタンです。
RGOビルダーを開くと、各市場ごとにRGO産品とロケーション、そのロケーションでの雇用可能な労働者/農民数、RGO施設レベルごとの収益、現在のレベル/総レベル、そしてマップにはRGO産品が表示されます。これで集中的にRGO管理ができます。
実際には上の方の”市場(マーケット)を選んでから不足品建造物を建てる”の項目で書いている通り、市場(マーケット)での不足品を調べた上で、それを産出するロケーションでのRGO施設を強化するという手順が良いでしょう。※もちろん上級者になって必ず不足しがちなRGOや、儲かるRGOがわかってくれば、最初からガンガン増築などすればよいでしょう。
公式Wiki:Resource gathering operation – Europa Universalis 5 Wiki
支配度・近接性コスト
税収など様々なものに影響のあるものに、「支配度」とそれを伝播させる「近接性コスト」がある。近接性とは首都からどれくらい管理しやすいかを表しており、近接性コストが高いと国全体の統治が行き届きにくくなり、ロケーションの支配度が下がり、結果的に税収などに影響する。
そのため、この近接性コストを如何に下げるかが問題となってくる。
近接性コストは、陸上経由の場合はまず基本近接性コストが40発生する。砂利道でつながっている場合には-20(舗装道路-25、近代的道路-30、鉄道-35)、その他諸々のバフなどを計算して算出される。
※ちなみに街路には移動コスト(陸軍移動速度)、市場アクセスコスト、近接性コストの3つが設定されている。
また「支配度」は、平均満足度+中核地(30%)+ロケーションランク(街5%)+首都への近接性などで算出される。
近接性コストには陸上経由のものと、海上経由のものとがある。また固定値の項目と%の項目が混じっている。真っ先にやるべきは固定値で減算できる街路であることは間違いがない。
※ただし首都(またはその他のソース)から恐らく10ロケーション程度も離れると累積の減少効果でほとんど伝播せず、その上に地形(山岳・丘陵など)での減少効果もあるためその先まで街路を敷く必要はない。沿岸ロケーションを持っている場合には海上経由の近接性計算もされるため話はまた異なる。
- 陸上:
- 街道を敷くと近接性コスト-20(砂利道-20、舗装道路で-25、近代的道路で-30、鉄道で-35)、橋(労働者)で-5%、執行官(兵士)で近接性供給源+20 ※ただし川下流ボーナスと被った場合は低い方は打ち消される
- 法律「統治法」の王宮法の「移動王宮」で-10%
- 建造物:
- 建造物「橋」(皮のあるロケーション限定かつ街道設置済)-5%。
- その他、建造物「パウンドロック運河」(街または都限定)-5%、「地方インフラ」?R2で-2.5%、首都の「最高裁判所」(4つ目の時代)で-5%
- 価値観:
- 価値観「陸軍と海軍」の”陸軍”で土地近接性コスト最大-10%、”海軍”なら100%で海上近接性コストが-0.01となる。陸上ロケーションでも首都から4個程度離れると海洋経由で接続するため、海洋国家を目指すなら選択の余地なく”海軍”側に倒そう。
- 「中央集権」で近接性コスト最大-10%
- 君主力(統治力):100点で-10%
- 地形:
- 首都が上流にある場合、その下流のロケーションはすべて-30.00。※首都移転時には上流が有利ということ。
- 丘陵地帯の場合コストが25%増加
- 参考)Location – Europa Universalis 5 Wiki
- 海上:
- ※近接性コストという意味では、首都から海上経由の基本近接性コスト40が加算され、そこから港湾コストで減算、さらに統治者統治能力でも減算。さらに該当ロケーション開発度も減算される。
- ※また海上プレゼンスは交易優位性の算出に繋がる。陸上の場合には道路に市場アクセスコスト(砂利道-10%、舗装道路-15%、近代的道路-20%、鉄道-25%)があり、それで算出される。
- 海上近接性コスト
- 常設海軍:近接性コストが外海は30、内海は5だが、常備海軍で「海を巡視」で巡回させることでコストは5になる。
- 海上プレゼンス:
- ※海上プレゼンスは海域ごとに計算され、その海域を含む市場(マーケット)での交易シェアに影響を与える
- 交易機関:所有国の海洋プレゼンス:+0.05
- 漁村:設置ロケーションの海洋プレゼンス(ローカル)+0.01
- 価値観の「陸軍と海軍」の”海軍”で海上プレゼンス+30%+海洋近接性コスト-10%
- 常備海軍による「海の巡視」(効果が出るのは20隻で4タイル程度だといい、またガレー船よりも小型船の方が海上プレゼンス維持力が高い。輸送艦はほとんど無意味)
- ※なお艦隊に巡視を指示しても1ヶ所にとどまっているように見えるが、これは指示を受けた艦隊が1海域(エリア)ごと留まって海上プレゼンスを100まで上げたら次の海域に移動するという動作をしているためであって、サボっているわけではない。
街道の敷き方
街道とはEU5から導入された概念で、首都からの通行を便利にすることで様々な伝播をサポートし、逆に街道がなければ隣接ロケーションといえども伝播にペナルティが発生する。
特に首都から離れた僻地ではなかなか制度が浸透しなかったり支配度が上昇しなかったりするなどペナルティがあり、軍事行動上でも進軍速度に影響を与えるため、街道整備は重要な内政となっている。
ロケーション右クリックから「街道を敷設」で街道メニューに入る。

※これは田園集落の場合のロケーションメニュー
※なおEU5の街道の概念は少し変わっていて、例えばA・B・Cというロケーションが並んでいる場合、ロケーションBを中心に見ると、ロケーションA-B間(B-Aも同じ)、ロケーションB-C間(C-Bも同じ)という別々の街道を2ヶ所敷設する必要がある(A=B=Cで初めてAからCに通ずる)。つまりロケーション内の街道を整備するのではなく、ロケーション”間”をつなぐ街道を敷設しているイメージである。
ただし「街道マップモード」ではロケーション間の街道は表示されず、(1本でもロケーション間街道があれば)ロケーション単位で赤色に塗られているだけである。例えばABCDという4つのロケーションの並びの場合、A-B間、C-D間だけに街道を敷いている場合(つまりA=B・C=D)でも街道マップ上はABCDすべてのロケーション全体が赤く塗られた表現となる。一見A=B=C=D全部がつながっているのかと勘違いするがそうではなく、そのロケーションとどこがつながっているかについてはそれぞれの州にホバーして確認する必要がある(3Dマップモードでは超拡大すると点線で描かれているらしい)。
※隣接ロケーションが4方向や6方向に存在する場合には、その4あるいは6方向へと(あるいは隣接ロケーションからそのロケーションへと)すべて街道を敷く必要があるということ。
非常に不便としかいいようがない。※河川マップモードというのがあり(ベースゲームデフォルトでは無いがキーバインドすれば使える)、そこではきちんとロケーション間を流れる河川が表現されているため技術的に出来ないというわけではなさそうだ。→1.0.10オープンベータで削除された模様→1.11オープンベータで新しい河川マップが実装
首都までの道路を一気に敷く
なお自国の端から首都までの街道を敷く場合には、その”端のロケーション”のロケーションパネルを開いてインフラタブにある「街道」ボタンを右クリックすると、自動的にルート上の複数ロケーションで街道建設を行ってくれる。
首都からの道路接続を確認する
首都ロケーションを開き、インフラタブにある「街道」をクリックすると、首都からどのロケーションに接続されているかが一覧表示される。ホバーするとどのロケーションには敷けていてどのロケーションには敷けていないかがわかるようになっている。
※首都以外でも同じ表示ができるが、首都が最大の近接性基準点(100%+バフ)なので、基本的には首都からのルートだけチェックすればよい。
この画面でクリックできるのはまだ街路が敷けていないロケーションであり、上の方に近くのロケーションが集まっているようなので、ダカットと資材に余裕ができたら上から順にカチカチとクリックしていきどんどん敷いていくようにしよう。
同じように、地方の中心都市のロケーションパネルを開いて街道をクリックすると、その都市を中心とした街道のチェックもできる。同様に上の方からカチカチしていくとその都市を中心とした街道が整備できる。
つまり、この機能を利用すると、そのロケーションを中心にあらゆる方向に道路を敷くことができる。
- 最初は首都ロケーションを選んでから「街道」ボタンから大まかなところを敷く
- 次は市場中心地のロケーションを選んでから「街道」ボタンから大まかなところを敷く
- 市場中心地が2個以上ある場合は、2を繰り返す
ことで、自国内の首都への街道整備(支配度)、および市場中心地への街道整備(市場アクセス)の両方を改善できる(余地がある)。
ただしこれをやると膨大にお金がかかるので、よほど余ってきてからやるようにしよう。また、これを実行する際には例えば議会の「街道整備」とかの議題(敷設コスト20%オフなど)を議決してから実行するようにしよう。
国家
政府改革
F1「政府」ウィンドウの「階級」ページに並んでいるボタンは同じ機能に見えるが、一番上の「王室」欄の”+”だけは政府改革となっている。
※それより下の各階級(貴族や僧侶・市民など)の場合は「階級特権の付与ボタン」となっている。
法律
F1キー「政府」-「法律」タブ
大カテゴリーの中にいくつかの法が入っており、それぞれの選択肢から一択する。
- 宗教法:
- イクター:[土地の取得]=最大RGO+10%、原材料時間拡大+10%、中央集権+0.05(近接コスト-)
- 奴隷改宗:[奴隷の信仰を許容]=奴隷の最大識字率+1%、生産量+10%、人文主義+0.10(異教寛容度+)
- 婚姻法:イスラムで一夫一妻にすると複数婚姻できない
- 後継者:[任意の宗教]異教の寛容度+0.50、[同一宗教]真の宗教の寛容度+0.10、[同一の宗教G]異端な信仰の寛容度+0.10
- 検閲:異文化異教徒が入り混じる国家なら、[検閲なし]で異端寛容度+1.00、異教寛容度+1.00が大きい。
- 軍法:
- 召集法:たぶん最初は貴族召集軍(戦闘効率+25%)一択?後で維持費も絡むので開放的召集軍か?途中で変更しても数年かかる
- 徴兵制度:[傭兵軍]=傭兵維持費-15%、個人主義傾き。[海軍徴用制度]=召集海軍規模+20%、金権政治傾き。[貴族軍隊]=貴族召集軍規模+20%、貴族政治傾き。[エリート軍隊](革命時代条件)=人的資源-25%、規律+5%、質傾き。[初期常備軍](絶対/革命時代条件)=人的資源+10%。[召集軍拡大]=農民召集軍規模+5%、自由民傾き。[大規模軍政策](革命時代条件)=人的資源+20%、量傾き。
- 海事法:維持費-5%、造船速度+10%、水兵+10%、海軍用品生産量+10%、交易範囲+10%などに影響する ※最初は交易範囲で、海軍を持ち始めたら変更か
- 海賊法:[反海賊行為]=対海賊戦補正+25%、開戦事由「対海賊戦争」可能 ※変更時にすべての「国家海賊行為」国家の評価±25。[国家海賊行為]=私掠船維持費-33%、私掠船雇用可能 はい、開戦事由「対海賊戦争」の標的になる。[私掠免許]=私掠船雇用コスト-25%、海軍維持費+10%。
- 統治法:
- シャーリア法学:[ザーヒル]=融和+0.05、[シャーフィイー法学]=交易効率+2.5%
- ハーレム法:威信(絢爛)、君主力(権力)、正統性(公衆)、後継者教育(分散)などに好影響を与えるが宮廷コストにも影響あり。融和に傾くのは権力
- 封建的慣習法:[伝統]=農民満足度+2.5%、[血縁重視]=統合速度+10%
- 法典法:[民法]=立法効率+10%、[伝統]=階級満足度均衡+1%
- 王宮法:貴族+5%、[移動王宮]=近接コスト+10%、立法効率+10%、[文化宮廷]=文化影響力+1%ほか ※最初は近接性コスト-10%の移動王宮が良いか
- 行政制度:[自治評議会]=立法効率+10%+地方分権傾き、[封建制]=食糧生産+5%+地方分権傾き。[地方裁判所]=最大支配度-5%+反乱軍参加しきい値-5%。[中央評議会]=内閣効率化+5%+中央集権+貴族性傾き
- 社会経済法:
- エリート層の教育法:各階級の最大識字率、内閣効率化など。貴族政治/精神主義/革新主義/人文主義への傾きあり。
- 国境管理法:[国境封鎖]=他国居住禁止+伝統主義傾きか、[国境解放]=他国移住許可か。※解放の方も「移住不可」となっているが誤字だと思われる
- 大衆の教育:[無学の大衆]=貴族と聖職者の最大識字率+伝統主義+農奴制か、[宗教的教育]=貴族/聖職者/市民/農民/労働者/兵士の最大識字率+聖職者満足度+精神主義
- 文化的伝統:[市民社会]=農民階級最大税率+2.5%、融和的傾き。[軍事的社会]=毎月陸軍伝統+0.05、好戦的への傾き
- 貴金属分配:[無制限輸出]=交易優位性+10%、金/銅生産量+5%、貨幣鋳造収入-33%。[規制輸出]=交易効率+1%。[輸出禁止]=金/銅輸出禁止、金/銅生産量-5%、貨幣鋳造収入+33%
- 鉱業法:[市民管理]=市民満足度均衡+2.5%、鉱山拡大コスト-10%、金権政治・資本経済傾き。[庶民管理]=農民満足度均衡+2.5%、自由民への傾き。[貴族管理]=貴族満足度均衡+2.5%、原材料時間拡大-10%、貴族政治/伝統経済傾き。[王室五分税](時代条件?)=植民地従属国収入+25%、金/銅生産量+10%、水銀生産量+15%。
- 階級法:
- 権力分配:各階級の「聖職者」「庶民(農民)」「富裕層(市民)」「上流階級(貴族)」は、それぞれの最大税率+、食糧消費量-などの効果。「統治者」だと君主力+、最大税率+5%。
- ※最初は農民が圧倒的に多いので食糧消費を考慮して農民は避けたい。価値観で「金権政治」に倒したいなら市民で+0.10だが、価値観で「自由民」に倒したいなら農民か。
- 貴族の権利:[貴族抑制]=貴族満足度均衡-5%、貴族最大税率+10%、貴族階級権力-10%、貴族入閣禁止 はい。[貴族有権者]=満足度均衡+5%、貴族階級権力+10%、毎月正統性+005 ※後継者選びでアンロックあり。[貴族権利強化]=満足度均衡+5%、貴族召集軍規模+20%、貴族階級権力+10%、王室入閣禁止 はい。[地方貴族権威]=満足度均衡+2.5%、貴族階級権力+5%、防衛敷設維持費-20%、農奴制傾き。
- 権力分配:各階級の「聖職者」「庶民(農民)」「富裕層(市民)」「上流階級(貴族)」は、それぞれの最大税率+、食糧消費量-などの効果。「統治者」だと君主力+、最大税率+5%。
価値観(~主義など)
F1キー「政府」-「価値観」
この「価値観」は自動化対象ではないため、各自で設定する必要がある。
価値観を変更するには、イベントなどの選択肢で倒したい選択肢を選ぶと徐々に変わっていく他、内閣アクション「価値観の変更」でも集中して変えることができる。ただし後者は内閣メンバーを張り付かせる必要がある。
価値観は全項目ニ択で、どちらかを選ぶとそちら側に傾かせる事ができる。ただし上記「法律」の選択肢や、様々なイベントの選択肢でも影響する。
- 中央集権と地方分権:
- 中央分権:君主力+50%、近接コスト-10%、最大戦争疲弊+3、防諜+30%
- 地方分権:階級満足度平均+5%、最大戦争疲弊-3、従属国忠誠度+20、防諜-30%
- 主義伝統主義と革新主義:
- 伝統:階級満足度+2.5%、制度受容コスト+200%、文化伝統力+100%、安定度コスト-20%
- 革新主義:制度受容コスト-50%、文化影響力+100%、最大識字率+10%、安定度コスト+20%
- 精神主義と人文主義:
- 精神主義:聖職者市街地人口制限+20、POP改宗速度+50%、POOP同化速度-50%、敵対心宗教影響+50%、真の信教寛容度+2.00
- 人文主義:改宗速度-50%、同化速度+50%、敵対心宗教影響-50%、異端寛容度+1、異教寛容度+1.00
- 貴族政治と金権政治:※貴族と兵士の関係によるか?
- 貴族政治:貴族市街地人口制限+10、貴族階級権力+50%、規律+5%、宮廷コスト+2%
- 金権政治:市民市街地人口制限+100、市民階級権力+50%、交易効率+2.5%、宮廷コスト-2%
- 農奴制と自由民:※なお農民の税額は人数比(F4社会-人々)の割に意外に低いので税収分布(F2経済-収支)を確認のこと
- 農奴制:農民階級最大税率+20%、農民食糧消費量+10%、原材料生産+10%、供給限界+10%
- 自由民:農民階級最大税率-10%、農民食糧消費量-10%、POP昇格速度+100%、毎月繁栄+0.1%
- 好戦的と融和的:※融和がやや有利か
- 好戦的:開戦事由作成速度+33%、土地奪取/休戦協定破棄/開戦事由なし宣戦布告での敵対心-、戦勝点コスト-10%、外交評判-4、諜報網構築+10%
- 融和的:内閣効率化+10%、従属国忠誠度+10、開戦事由作成-33%、土地奪取/休戦協定破棄/開戦事由なし宣戦布告での敵対心+、外交評判+4
- 質と量:※陸軍規模がデカくなれば量か。戦間期も雇う常備軍から変更か?
- 質:陸軍維持費+10%、陸軍士気回復+2%、軍事技術+0.1、陸軍率先率+25%
- 量:陸軍維持費-10%、許容戦闘幅+25%、陸軍率先力-25%、ユニット食糧消費量-10%
- 攻撃的と守備的:行軍と要塞どちらを優先したいか
- 攻撃的:陸軍移動速度+10%、要塞防衛-50%、包囲能力+10%、突撃能力+10%、開戦事由なし宣戦布告-10%
- 守備的:陸軍移動速度-10%、要塞防衛+50%、戦闘速度+10%、要塞上限(管理できる要塞数上限)+50%、防衛施設維持費-20%
- 陸軍と海軍:※海洋国家なら海軍か。近接性コストが絡むため支配度の点からも要検討。
- 陸軍:最大RGO規模+5%、土地近接コスト-10%、陸上交易範囲消費-10%、海上交易範囲消費+50%
- 海軍:海上プレゼンス+30%、海洋近接性コスト-10%、陸上交易範囲消費+50%、海上交易範囲消費-10%
- 資本主義と伝統主義:
- 資本経済:建造物コスト-10%、食糧生産-20%、銀行利息-3%、生産効率+20%
- 伝統経済:建造物コスト+10%、原材料生産+20%、人口収容力(ロケーションごとPOP居住可能数)+25%、食糧生産+20%
- 個人主義と共同体主義:※特に初期など軍を強化しながら都市化を進めたいのであれば、階級満足度さがるのだけ注意して個人主義か。荒廃・飢饉・不満を抱くPOPをは同文化で市場内なら自由に移動する
- 個人主義:階級満足度均衡-5%、陸軍士気+10%、海軍士気+10%、POP移住速度+50%
※植民地移住には関係しない。 - 共同体主義:特権剥奪コスト-50%、階級満足度均衡+2.5%、POP移住移住速度-50%、反乱軍への参加しきい値-5%
- 個人主義:階級満足度均衡-5%、陸軍士気+10%、海軍士気+10%、POP移住速度+50%
- 神秘主義と法学:※自領内での改宗の必要性薄いなら法学か
- 神秘主義:聖職者満足度均衡+10%、陸軍士気+10%、POP改宗速度10%
- 法学:聖職者満足度均衡+10%、毎月研究進行度+10%、内閣効率化+10%
- 外的と内的:※発見時代(時代Ⅲ)でアンロック
- 外的:文化伝統力-50%、戦力投射+5.00、敵対心への言語の影響-50%、外交許容量+33%、毎月植民地移住+100%
- 内的:君主力+25%、文化伝統力+50%、毎月支配度+0.5%、敵対心への言語の影響+50%、毎月植民地移住-50%
- 重商主義と自由貿易:※宗教改革時代(時代Ⅳ)でアンロック
- 重商主義:交易維持費-10%、交易効率-2.5%、市場保護+50%、外国市場への輸出コスト+10%
- 自由貿易:交易効率性+20%、交易効率+2.5%、市場保護-25%、市民の交易上限+100%
- 絶対主義と自由主義:※絶対主義時代(時代Ⅴ)でアンロック
- 絶対主義:特権の剥奪コスト-30%、君主力+100%、階級満足度均衡値-5%、POPの反乱軍への参加しきい値-2.5%
- 自由主義:階級満足度均衡値+5%、文化許容量+20%、POPの反乱軍への参加しきい値+2.5%、議題の要請に必要な議会の支持-10%
外交・同盟国・従属国
F5キー外交パネル
外交パネルから様々なことが行える。
左端の囲み点線はボタンになっており、例えば従属国であれば従属国管理画面へ、開戦事由であれば開戦事由の創出画面、ライバル国家であればライバル国家指定画面へと画面遷移する。

画面遷移するボタンがないのは、プレイヤーからは介入できない機能(情報)となっている。
また停戦中の枝模様のアイコンは、残り停戦期間に従って周囲をぐるっと青いリングが描写されるが、停戦までがながければ線は短く、短くなればなるほど線は円周をグルっと回っていくようになっている。
※停戦以外でも併合など期限のあるものについても円形プログレスバーで表示される。
なおEU5の戦争は基本的に「開戦事由」(casus belli:CBと略されいくつか種類がある)が必要で、停戦(安定度-50)や同盟・王室婚姻などがある相手に宣戦布告するとけっこうなペナルティが与えられる。そのためこれらの外交画面に表示される情報はかなり重要となっている。
ライバル国家の切り替えなど
ライバル国家に対して戦争で勝利したりするとライバルを打ち負かしたということで威信値が大きく上昇する。逆にライバルを一定数指定していなくてもこれまたペナルティが発生し、プレイに緊張感とカタルシスを与えている。Europa Universalisシリーズの基本的な仕組みとなっている。
すでにライバル指定しているライバル国家の廃止は、この外交パネルから左端の「ライバル」ボタンをクリックしてライバル指定画面(マップモード)に入り、そこでライバル指定中の国家を右クリックすれば取り消せる。ただし安定度が-25されるので注意。
追加指定する場合も同じライバル指定画面で行える。
従属国画面
「外交」-「関係」の「現在の関係」タブの「従属国の管理」から入る。※上の外交パネルのスクショ参照
この従属国画面では、下記のことが行える。
- 従属国アクション:
- ポリシー変更、ライバル禁輸、ロケーション割譲、交易転換、体制支持支援、併合開始、収入吸い上げ、土地返還、士官派遣要請、封土に変更、属国の地位取り消し、州の割譲、新しい統治者就任、水兵強制徴募、負債の完済、軍事支援、軍役代納金、領土接収
- 従属国タイプの変更:併合、封土、属国の地位取り消し
- 従属国の軍事スタンス:通常、攻撃的、支援、消極的、防衛的
※従属国の忠誠度が低い場合には、(従属国アクションではなく)通常の外交アクションの「評価改善」を行えば改善できる。
参考)従属国の種類
宗主国やリーダーに従属している形態の国家を広く”従属国”と呼び、その形態には様々なものが用意されている。※プレイヤーの従属国であれば宗主国=プレイヤー自身
- 「属国」は従属国の1種類でもっとも一般的な従属国。領内統治は従属国が行い、戦争にも従軍(AI操縦)するほか、宗主国は威信値を獲得できる。
- 「封土」は従属国の1種類で同宗教のみに限定される。宗主国が直接統治できる。受容制度の伝播+50%
- 従属国には、「辺境伯」という軍事に特化するが宗主国への支払いが軽減されるという形態も存在する。
- なお辺境伯は、ルネサンス時代突入時の三択で「外交重視」を選ぶと、その中に「地方領主」が入っている。これで従属国タイプ「辺境伯」が、研究ツリーの[ルネサンス]-[ルネサンス思想]-[常設内閣]-[最高権力]-[ルネサンス宮廷]の下に追加される。
- ほかに、コンキスタドール、自治領やハンザ同盟メンバー、帝国自由都市、帝国直轄自由都市、フランス特有のアパナージュ、インド地域でのサーマンタ(マハーサーマンタ)、新大陸での植民地国家、中国特有の朝貢国や土司、テュルク特有のウチ・ベイ、国営銀行、交易会社など様々な形態がある。
参考)属国のメリット・デメリット
宗主国にとっての従属国化のメリット・デメリット。
- メリット:
- 国内統治をやってくれる
※ベースゲームがローンチして間もない現状では、この国内統治を代行してくれるのが一番大きいと評価されている。なにしろ強制的に占領すると支配度はいったんゼロまで下がり、さらに首都からの距離もあるだろうからなかなか上がらない。こうしたことを考えると併合せずに属国に任せておくほうが良いことが多い。外交許容量の関係もあるのでずっと従属国のままというわけにも行かないため、その間に首都からその従属国までの街道を整備するなどして10年以上経って準備が整ってから併合手続きを開始すると良いのではないかと思われる。 - 「威信値」への好影響のほか、戦争に友軍として出兵してくれる(AI操作)。軍事行動もある程度指定可能(包囲メインなのか敵軍殲滅なのか自国/沿岸での防衛なのか)
- 上納金(あるいは出兵しない代わりの軍役代納金)を毎月入手できる
※F2経済の収入欄に「外交」として計上されホバーすると内訳が見れる
- 国内統治をやってくれる
- デメリット:
- 「外交許容量」を消費する
※F5外交-関係の左上「外交許容量」ホバーすると内訳が見れる。これは前作EU4での外交枠と似た概念で、例えば初期オスマンでゲルミヤを属国にした場合には外交許容量を12%も消費している。それより小さなカラシドの場合は6.7%。なお外交許容量は他国ロケーションに「大使館」建造で+0.10、「経済」-「収支」の外交費予算で伸びる - 勝手に戦争をすることもある
※仕組み上は外交権や戦争権も保持しているためそのあたりは隙があれば自由にやっている。恐らく「封土」に昇格すればそういう勝手な行動は無くなると思われる。しかし統治作業も宗主国であるプレイヤーが行う必要がある。 - 属国化後10年経過するまでは併合できず、(文化・宗教が違えば)年単位のけっこうな併合期間が必要
- 「外交許容量」を消費する
以下属国の詳細
- 宗主国のメリット・デメリット
- 毎月宗主国威信値に+影響を与える(+0.01) ※封土を除く
- 内閣効率化+5% ※ゲームテキストでは従属国側のメリットとして書かれている?
- 属国が受容した制度を宗主国首都に+20%広める ※となっているが逆ではないか?
- 宗主国は従属国内で資源採取、街道建設、建造物建造が可能
- 領土内の管理を任せられる
- そもそも占領後の統合作業がいらず、(統合に年単位の非常に時間のかかるEU5では)これは非常に大きなメリットとなる。統合しなければ暴動が起きる可能性があるし税金も入らない。文化・宗教が宗主国と異なれば統合時間は伸びる。※異文化異宗教だと併合時間が増加する。ただしノーペナルティに増やせるわけではなく「外交許容量「を圧迫するので自然と上限が決まっている。なお外交許容度は、建造物「大使館」一つあたり+0.10増やすことが可能
- また街道の整備や支配度上昇などのいわゆる内政も一切を任せられる。その上に上納金も入る。EU5ではお金以外に兵站(食糧)も重要になったが、この食糧についても軍事行動時の食糧提供権を要求できる。
- 戦争時の友軍
- (忠誠度50以上あれば)戦争時には従軍して一緒に戦ってくれ(AI操作)、敵要塞包囲やロケーション占領行動なども行ってくれる。仮に自分で全部隊を移動させることを考えれば格段に楽になる。
- ※軍事スタンスは「通常/攻撃的/支援/消極的/防衛的」の5種類が選択できる
- もし弱小国家で戦争に来ても意味がないなら、出兵しない代わりの軍役代納金を毎月支払わせることもできる(指定解除に若干のペナルティあり)。また戦争時には弱小属国が敵方から真っ先に狙われる可能性もある(出陣有無に無関係)。
- (忠誠度50以上あれば)戦争時には従軍して一緒に戦ってくれ(AI操作)、敵要塞包囲やロケーション占領行動なども行ってくれる。仮に自分で全部隊を移動させることを考えれば格段に楽になる。
- 外交
- ただしいつまでも従順な部下というわけではなく、「忠誠度」及び「独立欲求」の管理が必要(いずれも従属国管理画面で表示されている)。この忠誠度は宗主国との体力差(国力・兵力)などが考慮される。またある程度自主的に外交や戦争などが行えてしまうため、従属国管理は必要。
- 「史実の従属国」として独立させた場合、その従属国が持っている中核州(ロケーション)に対する請求権「有言実行」(征服コスト-25%、従属コスト-25%)が得られ、その請求権を元に宣戦布告できる。
なお”属国”と”封土”では別計算をするため、すべてを属国にするよりも同宗教同文化の場合には封土化することも検討しよう。
従属国設立
- (自領土内からロケーション/州を割譲しての)従属国の設立も同画面から行う。
※今作では現状領土内管理が非常に手間で時間がかかるため、属国プレイが推奨されているようである。属国化して領土内管理を任せることで、細々した内政や領土内整備などを押し付けることができる。
※新たに戦争で勝ち取った領土を属国化する(一度領土化してから属国として独立させる)以外に、和平時点でダイレクトに属国化すること(強制属国化と呼ばれている)もできる。また複数ロケーション・州を持っている国家の場合、最初からの自分の領土の中から切り出して属国化することもできる。
同君連合
同君連合は開戦事由「王位の請求」で戦勝すれば要求できる。
同君連合を組むと、F5外交-関係に、国際組織「○○○○の同君連合」が結成される。長い期間見ることになるので、とりあえず★をつけてアウトライナーに登録する。
この国際組織「○○○○の同君連合」を開くと、概要、同君連合ポリシー、議会という3タブがある。

概要
同君連合のメンバーとそれぞれの国力、一番下に統合レベルが表示されている。この統合レベルを上げていけば、「同君連合」のサブメニューから同君連合下位国の「併合の開始」(統合)が開始できる。
同君連合ポリシー
統合レベルを上げるには「同君連合ポリシー」で、各種法を順番に通過させていく必要がある。
まず基礎法、次に中央集権法、連邦法とある。
- 中央集権法
- ”継承法成文化”で+1、”連合の経済”で+1、”外交権”で+1、”同君連合の立法制度”と進み、”統一の是非”で+1~+3まで進めることができる。
- ”統一の是非”で+1を取ればとりあえず「統合」は開始できる。その上で”迅速な統一”、”急速な統一”へとススメば統合速度をさらに早めることができる。
- 連邦法
- 攻撃を開始したときに、必ず参加するのか、自動参戦要請するのか、要請可能にするのか、共同攻撃しないのか。
議会
同君連合に後から招き入れた国家に対しては、それまでの法案は通過していないため、そのままでは同君連合を離れてしまう。そのため、議会を開いて通過させる必要がある。
統合完了までの期間
外交アクションの同君連合のところに「併合の開始」があり、そこにホバーすると併合完了予定年月日が表示される。
同君連合を統合するのにどれくらい時間がかかるのかについては、被統合国家のロケーション数(都・街・田園集落)や、宗主国との国力比較、文化・宗教、宗主国の文化影響力などにより大きく変化するため、一概には言えない。このあたりは従属国併合と同じ。※従属国併合時のウィンドウを見ればどういう変数で変化するのかが書かれている。
※まず被統合国家のロケーション数を計算して補正値で増減したものを「併合に係る総コスト」とし、それに対して規模の比較や被統合国家の属性(属国・封土・同君連合)や、統合側の文化影響力と被統合国家の文化伝統力の比較をした数値、その他諸々の影響を勘案して算出した「進行値」を毎月引いていくことになる。
相手国(下位国)が大きければ当然時間もかかるし、同君連合の統合レベルにも大きく左右される。最低でも十年単位であることは確実で、長ければ数百年かかることも充分あり得ると思われる。統合(併合)期間を短くするModもいくつかあるため、どうしても統合期間を縮めたければそういうMod利用もありだと思うし、実績(鉄人モード)に拘る人は頑張ってくださいとしか言えない。
※統合(併合)の手間が嫌なら最初から全併合で良い訳だが、それだとフレーバーもクソもないのでこういう選択肢が用意されている。もし仮に同君連合や従属国が簡単にボタンクリックで一発併合できてしまえば、それあきりなゲームプレイになってしまうためあまり簡単にしてしまうのも良くないとは思われる。
軍事・戦争
募兵(陸軍)
F6キー軍事で陸軍を募集しようとすると、召集軍、正規軍(常備兵)、傭兵の3種類が出てくる。
- 召集軍:戦争が始まってから召集し(戦争状態でなければ召集できない)、戦争が終われば解散する(召集軍が残っていると次の宣戦布告ができない)。召集はPOP(主に農民)から行われるため人口が減少し、原材料生産-20.00%、食糧生産-20.00%のペナルティを受ける。解散すればその時の残存兵数に応じて人口はもとに戻る。
- 正規軍:戦争状態でなくとも募兵して常駐しておける軍隊(いわゆる常備軍)。ただし募兵には募集建造物が必要で、「役務保有地」などが該当する。
※なお正規軍を募兵できるのは首都にある「役務保有地」だけである。 - 傭兵:召集兵とは逆に戦争中は募兵できない。正規軍にお金を払って傭兵化することもできる。
要するに最初の方は召集軍しか動員できない(当分の間正規軍は数百程度しか募兵できない)ので、めんどくさいが「戦争勃発→召集→戦勝終結→解散」のサイクルを繰り返すことになる。
なお召集軍は戦争が終われば、「軍事」-「陸軍」タブの中にある「召集軍を動員」ボタンを右クリックすれば召集軍のみを一括して解散できる(連隊統合していても正規軍だけが残される)。※召集軍を残しておくと「平時の召集陸軍動員」というアラートが出る上に、次の宣戦布告もできないので素直に解散しよう。
※ただしある戦争遂行中に別の第三国から宣戦布告された場合には、(第三国の宣戦布告”前”に召集され戦争に出兵している)召集軍を第三国との戦争に継続して利用でき、わざわざ解散する必要はない。また先の戦争が終結すれば片方だけ和平を行うことも当然可能。
※召集軍の解散は自領土内に手動で戻してから可能になる(敵領地や、あるいは自分の従属国でも不可能なはず)。「完全撤退」というコマンドがあるが、これは損耗が50%もあるのでよほど危険なエリアで立ち往生した時以外は素直に手動で戻そう。自領土に入った召集軍(連隊)から順次解散が実行できるので随時右クリックして解散していこう。
正規軍の募兵の方法には下記3種類がある。
- 通常:初期兵員数:普通、募集期間:普通、初期経験値:普通
- 延長:初期兵員数:普通、募集期間:+50%、初期経験値:20.00
- 短縮:初期兵員数:-75%、募集期間:-75%、初期経験値:普通
正規軍は首都にある「役務保有地」でしか募兵できないためかなり少数しか募兵できない。ルネサンス時代の制度「職業軍隊」伝播(及び「軍事庫」のアンロック)を待つ必要がある。それまでは戦争のたびに召集軍を雇っては解散してを繰り返すしか無いと思われる。
※一応戦争発生時に自動で召集軍を限界まで召集する自動化ボタンがある。恐らくルネサンスの「軍事庫」設置までは正規軍を常に残していると人t系資源が常にマイナスに成ると思われる。
※ルネサンス時代「職業軍隊」の受容後に、「組織的採用」-「軍事教練」のツリーで「軍事庫」アンロック後に建造物「軍事庫」を設置すると、そのロケーションで正規軍の召集可能(ただしギリシャ文化必要)。これで募集できる正規軍の「武装兵」は最大兵員数200人/ユニットとなる。
※オスマンであれば、そのツリーの先に「イェニチェリ」と「イェニチェリ衛兵」があり、アンロックすると奴隷階級の建造物に「イェニチェリ兵舎」が可能となり、募集できるイェニチェリ正規軍の「衛生兵」は最大兵員数200人/ユニットとなる。
陸軍編成・将軍提督管理の自動化
陸軍で自動化できるのは、下記のみとなっている。
- 陸軍編成:開戦時に自動的に召集する ※ただし召集後の連隊再編成(ユニット調整)などをやるかどうかは不明
- 将軍の交代:将軍指定と死亡時などの再指定
陸軍行動の自動化
また陸軍行動の自動化は、自分で指定する必要はあるものの下記を指示すれば、半自動行動してくれる。全部自動でなくとも例えば後方の色塗り(包囲)だけ任せたり、逆に包囲は自分でやって追いかけっこは自動でさせることなども可能。いずれも範囲指定などをミスらなければ相当省力化できる。
- 【一斉包囲・集中包囲】:指定した地域・州・ロケーションを包囲する。州都を優先して包囲してくれるのでかなり早く占領してくれる。対象地域指定は複数を同時に選択でき、また大きい範囲から州やロケーション単位まで柔軟に指定できる
※範囲指定はロケーションをカチカチやっても良いし、左側に出る地域・州・ロケーションの一覧から該当エリアを一括して指定もできる。またCtrlキー・Shiftキーを押下しながらだと、より広い範囲(州・地域)を一括して指定(左クリック)/指定解除(右クリック)できる。
※「一斉」と「集中」の違いは、どうも部隊を分散させてでも色塗りを行うか、部隊を分散せず州都・要塞などを優先するかの違いのようだ。 - 【敵軍の殲滅】:敵連隊を追尾して戦闘をする。動き回る敵連隊を自動で追っかけて戦闘してくれる。色塗り(包囲・占領)も行ってくれるため戦力差で圧倒的に優位な場合にはこれもあり。これも追尾する範囲を指定できる
- 【沿岸・自国領の防衛】:今作でも「戦場の霧」が存在し不意に敵軍が現れることもあるので、敵陣に攻めない連隊は自国を防衛させよう
※自軍はもちろん敵側の軍事通行権も監視しておこう - 【反乱の抑制】:平時に反乱軍の起きそうな地域を勝手に巡回して反乱の兆候を抑え込ませる。※召集軍ではなく正規軍(常備軍)を使う
- 【陸軍兵站の実行】:補給拠点を建設する。※沿岸ロケーションの場合は海軍による補給も可能
- 【部隊の本国送還】:戦争後に「追放陸軍」(敵陣地で孤立して取り残されたユニット)を海軍で本国に輸送する。
範囲再指定
同じ行動で範囲を再指定したい場合は、ユニット右クリックからの「達成目標の選択」で範囲指定からやり直せる。範囲指定が漏れていたり戦争が進んで範囲が変わった場合などは、これを使うと手順が少なくて済む。
行動の切替え
また行動を切り替えたい(たとえば包囲していた部隊に敵軍殲滅をやらせたい)場合には、ユニット選択して左パネルの目標アイコンをクリックすれば、最初の行動選択からやり直せる。
包囲戦での突撃
包囲戦で要塞に突撃すると包囲戦の短縮することができる(場合もある)。
- 包囲してるユニットのメニューの「包囲:○○○○」がボタンになっているので、これを押すと包囲戦画面に遷移する ※画面中段「新しいユニットの作成」や「ユニット重量」の下

- その包囲戦画面の攻撃側の右側にアクションが並んでいるので、そこから「突撃を命じる」をクリックすれば突撃する
- アクション
- 「包囲の引き受け」:包囲戦の指揮を取り勝利すると占領権を得る
- 「突撃を命じる」:突撃を行う。1包囲戦で1回きり?
- アクション
反乱軍抑制
反乱軍のパーセントが上昇している(徐々に上昇しているが発生前の)場合、そのロケーションに少数でも軍隊を派遣すれば抑えられる場合がある。
※まずは内閣アクションの「反乱の抑制」を行い、それでも増加するようならば連隊を派遣して常駐させるのが効くと思われる。もちろんそれ以前に戦争で併合した地域を内閣アクションで「統合」(ついでに戦争疲弊除去も)することが最低条件。
反乱軍の起こりつつある地域を特定し、連隊コマンドの「反乱の抑制」で地域を指定しよう。
正規軍(常備軍)の強化
正規軍がまともに使えるようになるのは「ルネサンス時代」か、「宗教改革時代(1537年)」まで役に立たないと言われている。
※ただしルネサンス時代に入ると召集陸/海軍にデバフ(戦闘効率-10%、維持費-10%、海軍規模-10%)が入るためどのみち正規軍移行せざるを得ない。
※その点海軍についてはけっこうめんどくさい手順だが、金と時間さえかければルネサンス以前から常備艦隊を編成できるようになる。
最初は常備軍は首都限定の「役務保有所」でしか募集できない。
「ルネサンス時代」の「職業軍隊」を受容すると、ツリーがアンロックできそこから繋がる一連のツリーで正規軍がどんどん強化されていく。「武器庫」(毎月人的+10)の建設が可能となるが、これは都と街のみ建設可能。
※国家によっては、議会の議案で『武器庫」の建築が出され(1kダカットを要求される)、それを実行すればアンロックされる。らしいがその国家をプレイしたことがないので不明。
「発見の時代(大航海時代)になると、「槍と銃」ツリーで田園集落でも設置可能な「訓練場」(毎月人的+10)や、街・都条件の「乾ドック」(毎月水兵+32、造船+2、港湾適合性+0.15)が建設可能となる。
そして「宗教改革時代」に入ると、「兵舎」(毎月人的+15、訓練+1)、「造船所」(毎月水兵+64、造船+4、港湾適合性+0.20)が建設可能となり、本土以外の新大陸などでも常備軍が設置可能となる。また要塞レベル4の「砦」が築けるようにもなる。
海軍(水兵募兵と造船)
召集艦隊
陸軍の召集軍と同様に戦争が始まったら、「軍事」-「海軍」タブの中にある「召集軍を動員」すれば輸送艦(漁船)が動員できる。
これも同様に戦争が終われば、「軍事」-「海軍」タブの中にある「召集軍を動員」ボタンを右クリックすれば召集艦隊のみを解散できる。
ただし海軍がなくとも渡海できてしまう海峡もあり、よくわからない。有名なところでは、ボスポラス海峡及びダーダネルス海峡は海軍はいらなくて直接渡れる。逆にジブラルタル海峡は海軍が必要となっている。
陸軍の海上輸送
※陸軍の海軍輸送は、直接陸軍の移動先を指定しても自動的にアテンドされて輸送される場合もあるし、海軍が反応せず陸軍が沿岸で待ちぼうけになることもあり、どうもバグだと見られているようだ。
一番確実なのは、手動で海軍を沿岸ロケーションに移動しておいて、同一ロケーションに陸軍を移動させて輸送指示する方法である。
陸軍を自艦隊で海上輸送するには、次のような手順を取る。
- 連隊(陸軍)を港のある沿岸ロケーションに移動する
※敵領土の場合には入港できないため、先に陸軍連隊で港のある沿岸ロケーションを占領しておく。 - 連隊(陸軍)の重量を輸送可能な輸送艦を含む艦隊を、その沿岸ロケーションの港に入港させる
※艦隊を指定したあと港のあるロケーションを右クリックすると入港する - 連隊(陸軍)画面で連隊名の2個横にある「乗船ボタン」を押すと乗船して自動的に艦隊画面に遷移し、乗船している陸軍情報が艦隊側の画面に出る

※船アイコンに2,350と書かれているボタン(”カルーサ”の左側) - 艦隊を上陸地点に移動させたあと陸軍を選択してロケーションを指定すれば上陸する
※上陸先が自国領土なら、海軍の移動先として直接沿岸ロケーションが指定できて上陸まで自動でやってくれる。しかし敵国領土の場合には一度沿岸の水域へと移動し、陸軍を選択して上陸指示する必要がある。すると上陸戦をやった後に包囲戦などへと移る。
基本的な操作では陸軍を対岸を指定すれば自動的に海軍が輸送してくれるが、戦争時にそんな自動輸送をしていると敵艦隊の餌食になるため、手動で輸送しなおかつ自艦隊に警戒させる必要がある。そのためこの手動での輸送をマスターしておくに越したことはない。
※初心者は餌食にならないように輸送艦もガレー艦隊などに組み込んでしまうのが一番楽である。個別に運用したい場合には、まずガレー艦隊などで制海権を取って制圧してから輸送艦を移動させるなどの手段を取ろう、また敵国が複数ある場合には残存艦隊などにくれぐれも注意が必要。
海軍による食糧補給
上陸作戦時に陸軍に対して食料補給を行うには、艦隊画面の「食糧分配」および「食料調達」をオンにすれば良い。※どちらのボタンも始めはオフになっているためオンにして沿岸ロケーション近くに配備する。

すると地上の連隊が食糧不足になると自動的に艦隊から補給を行う。
常設艦隊
(召集艦隊=漁船とは違って)常設の海軍編成はけっこうなめんどくさい手順となっている。※特に内陸国の場合は沿岸ロケーションを獲得するところから始まる。ただし開始時点で海洋国家の場合は最初からドックや艦隊も揃っている(ポルトガル、カスティーリャ、イギリス、ナポリなど)
- 水兵を集めるための「漁村」を沿岸ロケーションに建てる
- 漁村を建てるには沿岸ロケーションであればどこでもよく(埠頭有無には無関係)、集まった水兵は国家としての共通のプールに溜まっていく(漁村ロケーションの位置と無関係に造船開始できる)。
- 漁村1つあたり毎月水兵+1される。つまり将来海軍を保有するつもりならば、相当早くから漁村を建てて水兵をため始める必要がある。
- 漁村も1ロケーションごとに複数建てられる。
- 造船するための「埠頭」を沿岸ロケーションに建てる(毎月水兵+1、港湾適合性+0.10)
- ロケーションは”田園集落”ではダメで、ランク”街”かランク”都”が条件。必要なら、沿岸にあるロケーションを”田園集落”から”街”へランクアップしておく必要がある(デフォで365日かかる)。※ロケーションパネルの名前の左側の「◎」的なアイコンからランクアップする。
- 埠頭は1ロケーションごとに複数建てられるがロケーションごとに上限が決まっている(たいてい1軒まで)。
- (水兵が規定人数集まれば)「埠頭」で「造船」に取りかかれる
- 「軍事」-「海軍」-「船の建造」で船の種類を選んだ後に埠頭のあるロケーションを選択する。
- 伝統的ガレー船:水兵30人+25ダカット
- コグ船:水兵40人+25ダカット
1隻でこれなので、何もないところから艦隊を編成するとなると、水兵を集めることを考えれば恐らく軽く数年かかると思われる。もちろんお金もかなりかかる。※2隻目以降は都度の建築は不要で、お金があってキューさえ開けば量産体制に入れる。カスティーリャなどでは最初から造船が可能。
なお海上を移動するには、陸軍で渡りたいロケーションを指定すると(コグを含む付近にいる艦隊が)自動的に割り振られ、輸送される。
その艦隊が何名の陸軍を載せられるかは艦隊に含まれる輸送船の数に依存し、艦隊をクリックすれば開く艦隊画面の上部に書かれている。下記スクショの場合は「”第1海軍” 550 ”ブルサ(所属ロケーション)”」の550人が乗船可能人数となっている。
海軍の編成(陣形の組み換え)
海軍を選択し、「陣形」ボタンをクリックすれば陣形の組み換えが行える。それぞれの列で後列に回したい場合は、一度別の列に移動してから再度同じ列に戻すと最後列へと並ぶ。

(効果があるかは別にして)全船を中央列に指定することで縦一列のような陣形(単縦陣)も可能。輸送船はなるべく「予備兵」か後方に置くようにしたい。
予備兵指定は、ユニット移動コントロールの上で右クリックすれば良く、またShiftキーを押すと「このカテゴリーをすべて予備軍へ移動」することもできる。この予備兵は戦闘を行わないが、必要に応じて正面またはいずれかの側面に移動する。
開戦事由
開戦事由を作ってから宣戦布告するか、一般的な開戦事由で宣戦布告と同時に行うかでいくつかのルートがある。
- 該当国家右クリックメニューの「開戦事由を作成」
- 該当国家右クリックメニューの「宣戦布告」のパネル下部の開戦事由を選択
- 該当国の国家パネルの敵対アクションの「開戦事由を作成」
なお開戦事由タブイは切り替えができるがデフォルトは右側タブ)、左側のタブにイベントで入手した開戦事由なども入っているので忘れずチェックしたい。
初心者にとっては開戦事由の種類がいっぱいあってよくわからないが、コストの%が低いほうがいっぱいロケーションを奪え、従属化する可能性も高まるということだけ理解しておこう。要するに開戦事由のコストは低いほうが攻める側が有利ということである。他と差異があるものには下線を、また特にマイナスのものは赤字で記しておいた。このマイナス付きの開戦事由を手に入れた場合には有効に活用したい。
※逆に+900%というのは(領土割譲や従属化する点で)攻める側が大きく不利ということである。例えば「(ライバルに)屈辱を与える」という開戦事由は屈辱を与えるのが主目的であって、領土割譲は主目的ではないため、領土割譲要求や従属化要求には大きなペナルティ(通常開戦事由の1/9しか取れない)があるということである。そのためこれらの開戦事由では、主に威信値を稼いだり、要塞を破壊したり、面倒な条約を破棄させたり、属国を解放させたり、同盟関係を破棄させたりを目的としよう。それらを実行することで敵の弱体化を狙おう。その後、次の(条件の良い開戦事由を得た)機会に併合を狙えば良い。が、大抵の場合弱った国はAI国家に横取りされるのが悩ましいところ
開戦事由は下記の種類がある。
従属国の請求権を使った開戦事由
「史実の従属国」として独立させた場合、その従属国が持っている中核州(ロケーション)に対する請求権「有言実行」(征服コスト-25%、従属コスト-25%)が得られ、その請求権を元に宣戦布告できる。
- 有限実行:征服コスト-25%、従属化コスト-25%、最大敵対心0%
※前作EU4では「属国の再征服CB」などと呼ばれていたもの。今作EU5では強制属国化がどうもうまく行かないようなのでよくわからない
手順としては下記となる。
- 自国の従属国が他国に対して請求権を所持している場合、「統合」マップで従属国をクリックすると「緑色斜線の入ったロケーション」が表示される。
- ※このマップでは従属国以外の他の国家でも、それぞれの国家が請求権を持っているロケーションが緑色斜線表示される
- (従属国が出来てから数年?程度経つと)その請求権を元にした開戦事由「有限実行」が得られる。※作成までだいたい4年程度だと思われる。開戦事由自体の有効期間も4年程度
- その領土を持っている国に対して宣戦布告し、開戦事由に「有言実行」を選択する
- すると「征服コスト-25%、従属化コスト-25%、最大敵対心0%」という有利な条件で併合できる
- ちなみに「開戦事由なし」の場合は、征服コスト50%、従属化コスト+30%なのでどれだけ有利かがわかる。つまり同じ戦勝点でも征服できるロケーションがまったく違ってくる
「有言実行」従属国の仕込み
ではどうやって請求権を掘り起こすのか?
この手法には戦争が最低でも2回必要となり、2回目の併合/従属コストを抑えるのが目的となる。そのために1回目の戦争(同盟国に呼ばれていくのでも何でも良い)では、仕込み国家を見つけてそのロケーションを1個でも良いので奪い取るようにしよう。
(2025年12月時点で)確実に使えるのが、一度併合した後に「史実の従属国」として独立させる手法
※「カスタム従属国」だと中核州はすべてなくなった状態で設立されるのでこの手法には使えない。「史実の従属国」だと請求権ができるロケーション(中核州)が黄色く表示されている。
以下詳細な手順。
- (1回目の戦争の)和平時に、占領対象のロケーションを「軍事」タブに切り替えてチェックしていき、現在の国家以外の国旗があれば、それはかつて他国領土だった土地であることを示している。マウスホバーするとその中核ロケーションがハイライト表示される
- 講和時に「国家の解放条約」が選択できる場合には、解放できる国家をホバーしながら併合するロケーションを決めれば楽に見極める事ができる。併呑された国家が白い枠で表示されるので、その中から複数ロケーションを所持していた国家の隅っこ1ロケーションを取っておけば良い。
- 次にその国家が現在存在しているかを確認する
- マウスホバーしても国家情報が表示されず、国旗をクリックしても国家情報が出ずに統治者が全員グレーだったり(併合されたか滅ぼされた)、または統治者が出なかったり(ゲーム開始時からなかった国家)する。現在存在していなければ、この手法に使えるということになる
- こうして確認できたロケーションを併合する。
- なおこの仕込み用に併合する場合は、掘り起こす旧国家の端っこ1ロケーションだけで良い。
- 理由は下記2つ。
- 史実従属国だと1州だけではなく(範囲内からランダムに)複数のロケーションや州ごと独立するため。いっぱい奪ったところで敵対心(AE)を被るだけだし、設立時に持っていかれるだけ。※もし同じ国相手に攻めるならどうせ停戦はさんで10年待つからその間に敵対心下がるのではというのはあるが、その国以外の周辺国(同文化・同宗教)との戦争にも影響はするので注意。
- (2回目の戦争で)開戦事由「有言実行」で戦勝した際には、その開戦事由を持っていた従属国に併合させる必要があるから。もし従属国に与えないと、「(宗主国が)自国の中核州を持っている」云々という理由で対象従属国の忠誠心が上がらないことになる。だいたいこうやって奪う国家は文化や宗教も違って扱いにくい上に、そういう属性までつけるとかなりやっかいになるので、まずは従属国に与えてしまい従属国設立から10年経ったときに丸ごと国家併合するほうが手っ取り早い(ただし大きいと併合に時間がかかることになる)。
- 併合後、6年後くらいに適当な1ロケーションで「史実の従属国」として独立させる ※史実従属国であれば、封土でも属国でもOK。停戦期間(10年間)破りを避けつつ、「有限実行」の有効期間4年を考慮する
- まもなく従属国が対象国家に開戦事由を作成し始め、数年程度待つと従属国の開戦事由に現れる ※0から基礎値4.0ずつ増加。約25ヶ月
- この時「有言実行」(つまりはロケーション返還要求)について、対象はどの範囲なのかを確認しておくようにしよう。
- 対象国に宣戦布告し、開戦事由から「有言実行(属国から対象国への請求)」を選んで開戦しよう。
ただ、どうも開戦事由が付いてもダイアログやログにも表示されないため(宗主国のものではないため)、注意しておく必要がある。
- ※(宗主国ではなく)従属国の開戦事由欄に追加される。設立後2年程度経つと、対象国家に対して従属国が「開戦事由の作成」を開始する。基本値は+4.00で対象国との友好度合いにより増減し、100で作成完了。基本値だとすれば開戦事由作成完了までに25ヶ月かかることになる。
- 2025年12月5日の1.0.10オープンベータで画面上部アラートに表示されるように修正された(Add subjects’ CBS to the unpressed casus belli alert. Mark the subjects’ CBS with an icon in the select casus belli tab)ただしダイアログではないので気づきにくい上に、メッセージ設定も無いようだ。
宣戦布告
いくつかの方法がある。
- 該当国家右クリックメニューの「宣戦布告」
※このパネルで開戦事由を選択できる - 該当国の国家パネルを開いて国名バナーの右下にある”剣のアイコン”をクリック
- 該当国の国家パネルの敵対アクションの「宣戦布告」
カジュアルに開戦するのもいいが念の為に同盟関係などを確認したうえで実行したほうがよいので、2番が良いのではないかと思われる。
戦争開始時に遅くなる
「設定」-「ゲーム」に、開戦時のゲームスピードという項目がある。これを”変更しない”にすると速度低下はしない。逆に開戦時に遅くなってほしい場合にはこの設定を変更すると良い。
その1つ下に”選択ユニット交戦時のゲームスピード”という項目もあり、ターゲットしているユニットが交戦したときにゲームスピードを遅くすることもできる。
戦闘
自動包囲
相手が召集軍などを用意していなく戦力数で圧倒している場合などのケースでは、(前線ではない後方地帯において)自動で包囲させることもできる。
ユニットの右クリックメニューの一番下に「達成目標を選択」があるのでそれを選び、左パネルで「一斉包囲」か「集中包囲」を選んで対象地域を指定すれば実行してくれる。
なお地域の指定は、地域・州・ロケーションの単位で指定でき、また州や地域をまたがって複数指定できるので、例えば小規模連隊などには危険の少なそうな周辺を狙って包囲活動などもできる。
「一斉包囲」と「集中包囲」があるが、一斉包囲の方は連隊を分解してまで包囲をするので避けたほうが良いかもしれない。集中包囲は連隊を分解せずに州都を優先して包囲してくれる。
和平交渉
同盟国/属国への占領権の移譲
戦争で占領したロケーションの占領権を他国(従属国含む)に譲渡したい場合には、和平画面に入る前にロケーション画面に入り画面上部右端の「要塞情報」ボタンから行う。

この時「要塞情報」ボタンを左クリックするとロケーション単位での譲渡が、また「要塞情報」ボタンを右クリックすれば州単位での譲渡が行える。政治マップモードに切り替えるとどの州を移譲したのかがわかりやすい。
※ただし1.0.7現在はどの州を選択したのかは表示されない(わかりづらい)ため、州マップモードに切り替えて確認しておいたほうが良いかもしれない。
いずれの場合も、次の「支配権を譲渡する国家を選択」する画面で譲渡先国家を選択する。なおあくまで自分が持っている占領権を渡せるだけであり、取り上げることは出来ない。
※ただし注意しないといけないのは、譲渡後にシミュレーションを進行させると、せっかく譲渡したロケーションをわざわざ戻してくる場合があるので、講和直前にシミュレーションを停止したまま譲渡を行い、そのまま(シミュレーション進行させずに)和平画面に移って講和完了まで行ってしまおう。
和平の開始
戦争が開始されると上部アラートに、少し長めの”戦争のアイコン”が出るので、それを右クリックすれば直接和平画面に行ける。
※このアイコンに表示されている数値は戦勝点で、これが100点に成ることを目指そう。例えば敵側に同盟国が出てきていて、しかしその援軍国には軍事通行権がなくて手が出せない場合などは、本来の敵国ロケーションを全部占領しても100点に届かない場合がある。しかしそれでも和平に持ち込むことは可能である。
あるいは同じアイコンをクリックして開いた戦争状況画面から中央上部にある”和平の訴え”アイコンから和平画面に入る。
交渉
例えば下図はオスマンで侵攻して適当なところで和平交渉に入ってAI和平提案ボタンを押したもの。

パネル下部に並んでいるアイコンの左端を押せば「AIによる和平提案」となり、自動的に和平案が提示されるので、それで良ければパネル最下段の「要求を行う」をクリックする。
ロケーション/州別の占領(割譲指定)
あるいは自分でロケーションをカチカチとクリックして占領(割譲)するロケーションを選択しても良い。合わせて、パネル中段に並んでいるアイコンを切り替えて条約、要塞解体条約(敵領内の要塞破却)、従属国の取り消し(敵の従属国を通常の独立国に戻す)、国家解放(敵が過去に併合した国家を解放する)、中核地条約、その他の条約を組み合わせることもできる。
このときにCtrlキーを押しながらクリックすると州全体を占領(割譲)指定できる。同様にCtrlを押しながら右クリックすると州単位で占領(割譲)指定を解除できる。
またまだ戦勝点に余裕がありそうなら賠償金もしっかり要求しておこう。
敵対心(侵略的拡大)
「敵対心」は前作EU4の侵略的拡大(AE)に相当するもので、気分良くガンガン侵略しているとこの敵対心が周囲の国家に蓄積していき、ある日突然あなたの国を対象とした「包囲網」が構築される。こうなるとどこかその1ヶ国に宣戦布告しても包囲網参加国家全部を敵に回すことになり、最悪の場合は包囲網側から懲罰戦争を仕掛けられることになる。マウスホバーするとどの国家にどの程度影響を与えるかが表示される(時限的に自然減少するが微々たる数値しか下がらない)。欲張ってロケーションを取りすぎて敵対心を上げ過ぎないように、適度に威信値を上げる条件に変えたりする必要がある。
国別の個別和平
なおパネル上部右側に並んでいる国旗は敵側参加国家の国旗であり、国旗で切り替えて個別に交渉することもできる。
納得の行く条件になったら、最後に「要求を行う」を押せば良い。※良くわからない最初のウチは、AI提案でそのまま要求を行えば良いと思われる。ただしその時に一応提案された和平条件の中身をよくみておくようにしよう。「こういうときにこのように使うんだな」というのがわかる。
戦後処理
自国で占領統治する場合
F1政府の内閣タブから、該当州に対して「統合」を実行させる。広域を一気に占領した場合には同時並行で統合処理することもできる。
その他、自国と同様に内政を行う。なお中核化するには、該当併合ロケーションの文化が宗主国の主要文化になればよい。そのため同じ内閣政策の「POPを我々の文化に同化させる」を実行する。
従属国化した場合
忠誠度などの数値に気を配る。必要に応じて機嫌取りをしておく。
探検・植民地
探検および植民地の基本的なやり方。
概要
- Ⅲ発見の時代(大航海時代)で解放
- 制度の受容が必要
- 探検家を雇って「海域」→「沿岸」の順で探索
- 地域を発見したら植民開始
- 植民完了で領土化(中核化)完了
なお近場(隣接海域など)であれば発見の時代や探検家登場をまたなくとも適当な提督を載せて探検に行かせることが可能となっている。その際には軍事力の高い人物に任せるようにしよう。※毎月の探検の進行度にボーナスが加算される。
手順
- 事前準備(制度受容):
- ゲーム内時間をⅢ「発見の時代」まで進める
- 「新大陸」の制度受容
※発見の時代には「新大陸」、「印刷機」、「槍と銃」の3要素があり、ランダムに決まる出現地から別々に伝播してくる。3つのうち探検・植民地に必要なのは「新大陸」。伝播してくれば受容すること - 進歩(技術ツリー)で”新大陸”、”探検家の派遣”をアンロック。これで探検家を募集可能になる
- 探検家募集~派遣準備:
- F7「地政学」-「領土」-「探検」タブの「探検家を募集」ボタンで探検家属性の人間を募集する

※探検家は募集すると即座に来る - 地域(海洋)を選んで準備を開始させる
※この時に出発する港により距離が決まる - 探検家を指定
※人物一覧が出るためフィルターアイコンから”探検家”で絞り込み指定。なおまだ探検家を募集できない場合には軍事力の高い提督を乗せて出発させよう。
※この準備段階でゲージが進まず「停止中」になることがあるが、それは探検用の資材が入手できないためである。ホバーすると何が不足しているかが表示される。 - 準備期間が経過後、自動的に探検へ出発

※行き先と探検家を指定すれば報告があるまで一切操作の必要がない。探検中は表示されたお金が毎月発生する。
- F7「地政学」-「領土」-「探検」タブの「探検家を募集」ボタンで探検家属性の人間を募集する
- 探検進行:
- 発見(「~海の地図を製作し帰還」などと出る)
※このときに隣接海域を発見する場合もある - その発見した地域(沿岸地域)へともう一度探検し地域を発見させる
※一度探索して”真っ黒”→”濃紺”に変わった海域や、”焦げ茶”に変わった陸地は、右クリックで探索メニューが出る。ただしこれが1.0.5より後のバージョンで出なくなっている。この項目の末尾に対応方法記載。
- 発見(「~海の地図を製作し帰還」などと出る)
- 植民:
- 植民可能な地域を発見すると、F7「地政学」-「領土」-「植民地」タブに発見した地域名が出るので

※1つ目はすでに入植開始している状態。 - 「認可植民地を設立する」をクリックして、自領土のどのロケーションから移住させるかを決める
※植民中は表示されたお金が毎月発生する。パッチ1.0.10あたりで植民元の選択はなくなった模様
- 1000人に達すれば「完全定住地」となり領土化(中核化)完了
※入植の経過は右サイドのアウトライナーにも出る
- 植民可能な地域を発見すると、F7「地政学」-「領土」-「植民地」タブに発見した地域名が出るので
※ここまで船などの用意は不要。探検家が勝手に用意しているという建付けなので、探検家とお金さえ用意すれば入植前までは終わる。いろいろ意識し始めないといけないのは入植開始後から。
入植関連の詳細
基本として、毎月の入植者数はF2「経済」-「収支」の支出欄にある「植民地コスト」が大きく関係している。探検・植民地を目指すならこれは最大にしておこう。※入植を開始していないデフォルトでは非表示になっている。F2経済-収支の収支表示部分の上部中央の”目を閉じた”アイコンを押せば「すべて表示」される
毎月の移住者数
時代により変化する模様。
- ルネサンス時代の毎月の移住者数=植民地コスト×出発港の所属する海域海洋プレゼンス×入植元からの距離
- 海域は「地理マップモード」-「地方」のエリアごと。
- 例えばイベリア半島組なら”イベリア”で1つであり、半島西側はポルトガルとカスティーリャで海洋プレゼンスを分け合っており、半島東側ではアラゴンとカスティーリャ、フランス、サルディーニャ島西側などで分け合っている。出発州沿岸だけの海域プレゼンスではなく、エリア全体でのプレゼンスを算出している模様。
- またイベリア半島組でマグリブに州を持っていてそこから移住させる場合、キレナイカまでのかなり広大な領域での全体海洋プレゼンスが影響するということになる。
- 発見時代以降?の毎月の移住者数=植民地コスト×入植元からの距離
- ※「出発港の海域海洋プレゼンス」条件が外れる=カスティーリャなどでも初期イベリアでは50%そこそこしかないため、単純に倍近くになる計算 ※発見時代でも付いている国家があり、なんの条件で外れるのか不明。植民地政策なのか?
毎月の移住者数のバフ
なお入植には下記が有利かと思われる。
ルネサンス時代以前より:
- 価値観「外的」:毎月の植民地移住最大+100%。内的だと最大-100%
- 政府改革「植民地の拡大」追加:植民範囲+10%、外的傾き+0.05、
- 法律「社会経済法」-「植民地政策」ポリシー「定住用植民地」追加:毎月植民地移住+100%、移民地維持費-10%、外的傾き+0.05
- 価値観「個人主義」:POP移住速度最大+50%。共同体主義だと最大-50%
発見の時代以降:
- 内閣アクション:「認可植民地の強化」(植民移住)、「人々を植民地国家に送る」(植民地国家への移住)※いずれも進歩「新大陸」でアンロック
- 進歩「新大陸」:+25% ※進歩「海外探検」(外用探検許可、植民範囲+1500)条件
- 進歩「植民地憲章」:認可植民地設立コスト-20%、毎月植民地移住+50%、移民地維持費-20%
- 進歩「植民地探検」:進歩「沿岸の拡大」条件で+50%
- 法律「階級法」-「市民の権利」:植民地における権威を付与:+25%
- ※進歩「新大陸」-「市民の権利」でアンロック
- 進歩「植民地政策」で法律「植民地政策」ポリシー追加:「交易用植民地」=植民範囲+20%、個人主義傾き。「定住用植民地」=毎月植民地移住+100%、植民地維持費-10%、外的傾き
探検・植民地のFAQ
- 植民できる地域がわかりづらい
- マップモード「植民地」に切り替えると以下のように表示される。緑色は認可植民地(か領土)。青色は植民中(建造物未建設)。黄色が植民範囲(可能だがまだ植民を行っていないところ)。
- なおこの表示は当然各国ごとに異なり、他国に切り替えるとどこに植民中なのか(青色表示)、どこまで発見しているかがわかるようになっている。

- 植民を加速する方法
- 内閣アクション「認可植民地の強化(統治)」で認可植民地に移住させる。移住元のロケーションを指定する
- 内閣アクション「人々を植民地に送る」で”設立済の植民地国家”に移住させる。移住先の国家を指定する
- どこから植民(移住)するのが良いのか?
- ※オープンベータ1.0.10の頃から移住元の指定が無くなった模様
- ”戦争で入手したが領土化(中核化)する予定がない”ロケーションなどを、統合せずにそのまま植民元ロケーションとして指定し、人が減ってしまえば他国に売りつけるテクニックもある。
※現段階ではバグなのか仕様なのかは不明だが、送り元の文化・宗教に関係なく植民先は本国首都の文化・宗教になる模様。例えばカトリック国家でイスラム圏を占領した時、植民地に送り込むと自動的にカトリック(及び国の文化)になる。 - そのくせ、恐らく植民先から入った人間が堂々と「地方貴族」として現れる。これと結婚していくと、王朝がどんどん多様化していく羽目になるので注意しよう。
- 植民地の名前を変更したい
- 植民地国家の画面を開き、国旗の横の国家名称ボタンを右クリックして開くメニューに「国名を変更」がある。なお変更してもマップ上の表示はしばらく変わらない(翌月初更新?)。
- 植民地を従属国として独立させたい
- 該当地方?で5州(ロケーションではない)を中核地にすると、「植民地化するかどうか?」のダイアログが開く。ここで「新たな植民地国家を設立する」を選ぶと従属国(植民地国家)となる。該当1州のみで独立するので、その周辺の州をどんどん割譲すれば良い。

※大抵の場合は一番上を選ぶ。
3番目の選択肢は近隣に配下の植民地国家(従属国)が存在する場合に表示され、いちいち割譲する手間が省ける。4番目は植民地国家として独立させず直接自分で(宗主国として)統治する場合。 - ※ここで2番目(緑色)の「植民地で新生活を始めるのも悪くないのでは?」を選ぶと、その後は(それまでプレイしていた植民した国家ではなく)植民地国家としてのプレイが始まる。この選択肢が緑色で目立つようになっているためか、間違ってこれを選んでしまう人が多いようなので注意(確認も出ず切り替わる)。
- なおこのときに全部の植民地を植民地国家に渡してしまうと、その次の探検や入植をするときに困るので、地域ごとに拠点となるロケーションや州は残しておくとよいでしょう。
- 該当地方?で5州(ロケーションではない)を中核地にすると、「植民地化するかどうか?」のダイアログが開く。ここで「新たな植民地国家を設立する」を選ぶと従属国(植民地国家)となる。該当1州のみで独立するので、その周辺の州をどんどん割譲すれば良い。
内陸探査の方法(地図を盗む)
(植民地探検とは別に例えば旧大陸でも)未探査で地図が見えず、首都すら見つかっていないために諜報網構築すらできないことがある。
この場合は、その目的地に接している(あるいは近いところにある)国家に対して諜報網構築を行い、諜報網がある程度(確か50程度)貯まると「地図を盗む」アクションが可能になる。
※ただしこのときに(地図を盗んだ国家ではなく)対象地域の国家からの評価がかなり下がるため、調子に乗って盗みすぎないように注意が必要。近隣国Aに対してB国家周辺地域の地図を盗むと、(A国ではなく)B国家周辺地域にある国家群から反感を買い、攻める前から敵だらけということになりかねない。自国周辺の地図を盗られるということは攻める準備などをしているということなので、怒るのは当然。
「交易会社」のメモ
時々掲示板などでも質問が出る「交易会社」(交易会社本部)ですが、一応設立までの手順を書いておきます。しかしどうも未完成状態っぽい気もします。
- 「宗教改革」時代(時代Ⅳ 1537年)まで進める
- 「国際交易」を伝播させ受容する
- ツリーの一番左端の8段目にある「交易会社」をアンロックする
- ※ここでF3建築物メニューに入ると「交易会社本部」なる建物があるが建てられないマークが付いており、試しに強引に選んで緑色のロケーションでホバーしてみても「交易会社本部を建設するには進歩交易会社の研究が必要」と表示され建てることができません。
- また色のついていないロケーションの場合は「わが国に優先的な市場アクセスを付与している外国のロケーションにのみ交易会社本部を建設できる」と表示され建てることができません。試しに優先的な市場アクセス許可をもらった上で1.治外法権従属国、2.交易会社本部の両方を試してみましたが、いずれも不可能でした。
- F5外交画面-「従属国を設立」に入り、「治外法権従属国」をクリック
- 設立可能な地域が出るので、その中から選び、執政官(代表)も指名する
- するといわゆる建築物主体国家である「交易会社」が設立される
- 国家ができるわけではないため領土は示されず、会社の国旗をホバーすると、交易会社の支店?があるところだけ光る。交易会社との外交は、通常の従属国管理画面で行う
- 少し待つとF2経済-収支画面の「外交収入」欄のチップにその交易会社の収益が上がってくる
- ※”収入”の1%もありませんので、夢を持って試しても後悔するような額です(しかも設立すると20ロケーションに支店展開するような大規模な交易会社での話)。同じような組織であれば、F5外交-外交アクションから入ったところの従属国アクションに「わが国の国営銀行となる」というアクションがあり、これを選ぶと銀行を従属国扱いすることができるがあれとほとんど同じ。
けっきょく1.0.10時点では、(ゲーム指定の)エリアに治外法権従属国として「交易会社」を建てられ、そこでの収益が上がってくる以上の仕掛けはないようです。
以上
※なおツリーアンロック時に「会社統治施設」「会社警備隊」「会社用港湾」「会社の現地事業」「会社の他国影響施設」などがアンロックされたと出てくるが、これらは建築メニューや外交の従属国メニューにも出てこない。ただし掲示板などを見ていると「交易会社を建てると(本部以外に)貿易事務所などが設立できた」と書かれており、よくわからない。またこの交易会社関連を修正するというMod「Steamワークショップ::Fix Trade Companies」も存在する
HUDなど
アウトライナー(右パネル)
アウトライナーとは、画面右端に常駐して様々な進捗度を表示しているバーのこと。
画面右上の(≡アイコンの下に)「時計の8時のような●」アイコンがあり、この左クリックで表示項目のカスタマイズが、また右クリックでアウトライナーの幅拡縮(省略表示)が行える。

またアウトライナー設定で「アウトライナーをピン留め」を外すと非アクティブ時には小さく折りたたまれマウスホバーで展開するようにもできる。
※右パネル(アウトライナー)を閉じるキーバインド設定も可能
なお期限がある進行状況については、画面右端に円形プログレスバーで進行状況が表示される。これはアウトライナーを幅縮小しても、小さく折りたたんでも(アウトライナーピン留めを解除)表示されている。
また縦に伸びすぎて画面をはみ出してしまった場合でも、その時点で重要度の低い項目については項目ごとに折りたたむことも可能で、いつでもタイトルをクリックすれば展開する。
国家のピン留め
ロケーション右クリックメニューの最上部の国家名の☆をクリックして★に変えることで、アウトライナーに国家をピン留めすることもできる。※他の画面でも国家名が出ていれば★できる

※戦争状態なども表示されるため非常に便利なので、ライバル国や周辺主要国は全部ピン留めしても良いかもしれない。なおピン留め国家が増えた場合には、アウトライナーの「国家」バーをクリックすれば折りたたむこともでき、再度「国家」バーをクリックすれば展開する。
国家をピン留めすると、その国家から見た自国への評価値が表示される。クリックすれば該当国の国家ウィンドウが開き、もう一度クリックすれば「すべての外交アクション」画面が開く。
- またアウトライナーの国家パネルを右クリックすると、首都へ移動、国家パネルを開く、すべての外交アクションを開くなどのほか、評価改善の実行(確認ダイアログ)、信頼の公言、取り入る、諜報網の構築、開戦事由を作成、宣戦布告などのアクションが行えるようになっている。
左ウィンドウ(左パネル)
左ウィンドウにはF1キー政府やF2キー経済などのパネルが表示されるが、これは階層ではなく入れ替え方式で表示される。
ESCを押すと一気に全部閉じられるが、一つ前の画面に戻りたい時は「Alt+←」を押すと戻ることができる。また(なにかから戻った後に)「Alt+→」を押せば次のパネルに進めることができる。
- ※左パネルを閉じるキーバインド設定も可能
台帳参照
自領土の台帳(州一覧など)を参照したい場合は、F7「地政学」-「州」画面で、
- 人口をクリック:自国の台帳の人口一覧が開く
- 税基盤をクリック:自国の台帳のロケーションが開く
台帳そのものは、右サイド画面上部にあるアイコンの並びの1番目をクリックしても良い。
設定・キーバインドなど
黒死病のオンオフなど
黒死病はデフォルト設定だと1337年ごろにアジア西方で発生してヨーロッパへと広がり、一説には人口の三分の一が亡くなったとされており、EU5でも大きなテーマ(「シチュエーション」)の一つとして組み込まれている。
しかし実際にゲーム中に三分の一も死亡するとやってられないという人も多くいるようで、ベースゲームでも黒死病発生有無の選択肢を用意している。
黒死病をオフにするには、起動メニューやセーブゲームロード終了後のメニューで、「ゲームルール」というメニュー項目があり、そこでいつでも変更できる。

ゲームルールには「一般」・「マルチプレイ」・「フレーバー」の3タブがあり、一般タブではプレイ難易度の他、AI難易度、史実忠実さ、国家の変更、ミッションの有効/無効、台帳情報の開示レベルなどが変更できる。フレーバータブは下記スクショ参照。
例えば黒死病を無効化したければ、「ゲームルール」-「フレーバー」の「黒死病大流行の年」および「黒死病の発生地」から。

キーバインド
キーバインド設定は、「設定」-「入力バインディング」で行う。
以下デフォルトバインドのメモ
- シミュレーション速度:テンキーの1~5、+-で上下
- 政府ウィンドウ:F1~F8までに割り振られている。政府、経済、生産、社会、外交、軍事、地政学、進歩
- HUD(UI)非表示:Ctrl+F9でトグル
- マップモード:Ctrl+Q~Rまでに割り振られているが、これの変更はキーバインド画面で行える。
- スクリーンショット:F11
- マップのスクリーンショット:Shift+F11
個人的なキーバインドメモ(設定飛んだ時用)
保管場所は「%USERPROFILE%\Documents\Paradox Interactive\Europa Universalis V\user_bindings」 ※直接のファイル操作は自己責任で
- ベースゲームではCtrl+QWERTYに割り振っているが配置的にも非常に操作しづらく直感的ではない(だいたいマップ操作のWASDと被っている)。他ゲーでメインキー割り振り操作に慣れており(WASD行と被らない)メインキー1~0に割り振ったほうが楽なので振り直している(マップはしょっちゅう切り替えるので、他の連隊コマンドなどとは分けておきたい)。
- またCtrl+W(ブラウザのタブ閉じ)を多ボタンマウスに割り振っているため、それを左パネル戻る(前の左ウィンドウ)に当てている
- 下記は、列ごとにメインキー1~0の「ノーマル / ALT+ / SHIFT+ / Ctrl+」の順のメモ。メインキー左側(およそ1~6)によく使うものを入れ、右側(およそ7~0)は戦争関連などあまり使わないものなどAltは生産系、Shiftは文化宗教系、Ctrlは人口系のようなイメージ。
- 政治 統合 主要文化 貴族人口
- 外交 POP満足度 文化圏 聖職者人口
- 支配度 州内食糧 文化(ロケーション) 市民人口
- 近接性 食糧生産力 宗教(国家) 労働者人口
- ロケランク 開発度 宗教グループ 兵士人口
- 街道 安定度 宗教(ロケーション) 農民(人口)
- 評価 原材料 - 部族民(人口)
- 敵対心 識字率 河川 奴隷人口
- 戦争 防衛条件 海洋プレゼンス 人口
- 要塞 軍事通行権 港湾適合性 移住(魅力)
- その上で(画面中央下部の)本来のマップモードパネルには、主に疫病や制度など地方・大陸をまたいで確認したいものや、地理マップ関係のものを入れている。
Mod
EU5のModの紹介については別記事「EU5のMod情報などまとめ」を参照ください。
ここでは適用方法だけ載せておきます。
Modの適用方法
EU5でModを適用するには次の手順で行います。
- まずSteamワークショップでサブスクライブ
- ベースゲーム起動中なら(起動していなければ一度起動する)起動時のメインメニュー画面の右上隅にある■をクリックしてModメニューに入る

- Modリストで「n/m個のMODELを選択中」で■を押してすべてのModを有効化するか、あるいはリストから個別に■を押して有効化する
- 画面右下の「適用」ボタンを押す
- 自動的にModが適用された状態でゲームが再起動する
つまり、今までのMod適用手順とは少し異なってきます。
初めにやるべきこと
F1キー「政府」
階級★
- 王室★★:
- ”+”マークは政府改革の実行。王室権力25%未満だと様々なデバフが付いているため、枠が空いている場合にはフルにして王室権力25%超えを目標に高める。
- 各階級:
- 不要な特権も付いているが剥がすと安定度が下がったりするため(階級の権力で算出)、特権剥奪時の影響を下げ安定度を高めたうえでしか実行できない。特権付与や剥奪、賄賂も行える
- 例えば開始直後のオスマンだと階級の割合は農民81%(557k)、部族6.6%(45k)、労働者6.4%(44k)、市民2%弱(14k)、奴隷1.8%(12k)、聖職者0.59%、兵士0.45%、貴族0.36%となっている。
議会
- いつごろ開催できるのかを確認しておく。
内閣★
- なおわからない場合は内閣も自動化しても良いかもしれない。勝手にメンバー指定したりするが、まあまあ良い政策を行ってくれる。
- 例えばプレイヤーが参戦すると先回りして「復興への取り組み」を行い、併合すれば「州の統合」を臨機応変に行ってくれる。暇なときには「外交努力(関係改善)」や改宗、州支配強化などを豆に行ってくれる。
- なお自動化はするが特定の内閣メンバーだけ固定にしたい場合には、「内閣」パネルのメンバー名の横にあるロックボタンを押せばよく、自動化の管理対象から外れる。
- 廷臣から内閣メンバーを指定すると内閣効率(内閣で実行中の政策効率)が+20%向上する。
- 内閣枠が空の場合の指定にはダカットのみが必要であり、すでに指名されている内閣枠のメンバーを入れ替えると安定度が下がる。
- 内閣に指名したメンバーは指揮官や提督として出陣できないので、特に軍事力の高い廷臣は慎重に。内閣メンバーの総数は国家毎に異なり、国家が拡張することで増えていく。
- 内閣メンバーを「内閣長」にする指定があり、「内閣長」に指定すると解任不可能+陸海軍指揮不可能になるが内閣長内閣効率+25%。ただし正統性-5.00、100くらいのダカット条件
- 発見の時代:「製本の改善」(印刷法条件)条件に法律「内閣法」が制定できる
- 行政聖職者、法眼貴族、能力主義の登用、王家による統治、ヨーク家の伝統、中国式内閣、船長会議などが利用可能
- 宗教改革時代:内閣の効率化+20%。執行評議会設立が可能
- ルネサンス時代:常設内閣(ルネサンス思想条件)で政府改革実行数+1
- 内閣の政策:「統治・外交・軍事」の3分野に振り分けられており、それぞれ得意とする内閣メンバーはほぼ固定したうえで状況に応じて随時下記政策を切り替えながら実行させる。
- 統治:統治力の高いメンバーに
- 統制力(州支配)の強化★:州別に支配度を+2%上昇させる。支配度は税収などに影響を与えるため州支配の低い初期は大事。ただし効果は永続的なものではなく、維持するためには内閣で強化し続ける必要がある。
- 移住の奨励★:POP移住速度+50%上昇、居住地の魅力+1.00
- 州の開発:開発度上昇+0.0025
- 新しい文化の育成:革新主義への傾き+0.10。実行完了時に新たな主要文化を形成
- 外交:外交力の高いメンバーに
- POP文化の同化★:POPの同化速度+20。同化して中核化する
- 外交努力★:関係改善+25.00%、外交評判+2.00。外交評判は「威信」に影響
- 復興への取り組み★:人口増加+0.10%、繁栄の回復+5.00%。戦争後など
- 戦争疲弊を軽減★:戦争疲弊-0.05。戦争後など
- 社会的価値の変更:毎月の社会的変化+0.15
- 軍事:軍事力の高いメンバーに
- 州の統合★★:統合速度+2.50。戦争で勝ち取った領地はPOP満足度が低く、統合しなければ反乱が起きる。和平後は真っ先に「統合」を行う。
- 国家の安定化★:安定化投資(安定度)+0.05
- 政府の強化★:正統性+0.10
- 州の改宗★:POP改宗速度(ローカル)+20
- 部族の定住★:部族から農民へ+500.00%昇格させる。部族では税金が発生しない上に労働する施設もないためかなり重要
- 反乱軍の弾圧:反乱軍が発生した際に実行する。
- 住民の追放:他の州への強制居住。
- 統治:統治力の高いメンバーに
内閣ポストもこの画面で個別にロック可能で、ロックしたメンバーは自動化で入れ替わる対象外となる。
法律
制定できる法律を制定しておく
例えばオスマンだと、※パッチ1.0.5でゲーム開始時から設定されているように変更された。
- 「統治法」-「シャーリア法学」の種類選択ができ、交易効率+2.50%などがある。
- また「ハーレム法」もあり、ここでも後継者教育+5.00%、君主力+10.00%や威信+0.10、防諜活動+20.00%の効果を持つものがある。
F2キー「経済」
収支
- 右側の収入
- 貨幣鋳造:インフレを起こさない程度に調整する。上がってしまったインフレを下げるには、貨幣鋳造を最低限に下げれば毎月-0.10%ずつ変化する。他には議会でインフレ抑制策が出ることもあるという。なお0.00%でも赤字になっていると実際には微妙にインフレが発生する(画面上部のダカット表示ではそう表示される)。
- 各階級の税金:(特に初期はそんな余裕はないだろうから)各階級の税金は自動化しておく
- 左側の支出
- 宮廷コスト★★:国家の「正統性」に影響するためその増減を見ながらプラスを維持するようにしたい
- 陸軍維持費:
- 海軍維持費:
- 要塞維持費:
- 外交費:※現時点では外交によるCB創出はあまり効果がなさそうなので思い切って下げるのもありか
- 安定度★★:国家の「安定度」に影響するためその増減を見ながらプラスを維持するように
市場
国家をまたいだ広域のマーケットのこと。例えばオスマンの近くだと「コンスタンティヌーポリス」が、またイベリア半島なら「セヴィリア」などが市場(マーケット)になっている。
※日本語版では、建造物の交易施設「市場(いちば)」も、広域マーケットも「市場(しじょう)」なので混乱するため、このページでは「市場(マーケット)」と記述している。他に「市場の村(いちばのむら?)」という建造物もある。
ここに緑色のバーで出ているのは自国が所有しているマーケット。バーにホバーすると、その市場での順位と規模などが表示される。
自領内に市場を創設することもできる。
市場(マーケット)の境界は動的に変更され、各ロケーションは最も市場の魅力が高い市場(マーケット)に属する。また他国の市場の魅力は、市場保護することで打ち消すこともできる。
交易
交易も自動化できるが、どうも精度が良くない(短期的な利益追求をしておりPOP必需品を考慮していない)という指摘がある。※他国市場はままあ利益を出すが、自国首都を含む市場は手動でないと最大利益を出していないなども見ます。
そのため、上部の「市場の自動化」を100%にせず80%前後にして、残りは自分の手動取引で「POP必需品」を輸入すると良いらしい。
※ただし初心者のうちは素直に自動化が良いと思われますが一応操作手順だけ載せておきます。戦争などもありとてもそんな操作をしている余裕はないので、戦間期でよほど暇なときだけちょっといじればよいかと思われる。
例えば下図はオスマン初期に交易許容量5.25のうち適当に1.25を手動取引に指定したもので、この1.25は自分で取引をする必要がある(余らせると許容量が無駄になる)。要するに自動取引をオンにしながら、一部だけ手動取引するということ

そこで下の方の「POP必需品重視の推奨交易」、「推奨食料輸入品」、「利益重視の推奨輸入品」、「利益重視の推奨輸出品」の中から取引する。下2つの利益重視はどうも自動取引がやってるらしいので、上2つのどれかを行うことになる。
利益の高そうなもので、かつできるだけ優位性の高い市場の取引をクリックすると実際にその取引が予約され「現在の交易」に移る。
※「交易許容量」を増やすには、「市場」や「市場の村」などの交易許容量を増やす建造物を建てれば良い。なお交易許容量とはあくまで輸入や輸出のアクションを起こす側での話。例えば新大陸/アフリカで建材(れんが等)が不足している場合は、自国市場から輸出すると輸出先の交易許容量は食わない
※「交易優位性」は、交易の際に国家ごとの購入順を決定する。この交易優位性を増やすのは、市場アクセスで決定される。市場アクセスを上げるには、1.その市場(マーケット)に属するロケーションを多く所有する、2.市場沿岸の海洋プレゼンスを高める、3.「市場」などの建造物を建てるのいずれかとなっている。この優位性が低いといくらリクエストをしても実際には交易がされない=枠の無駄になる。交易優位性は、海洋プレゼンスを増やすほか、進歩「商人のパートナーシップ」などでもプレゼンス効果をさらに向上させることができる
そして下図は適当に「POP必需品重視の推奨交易」からカチカチと指定してみたもので、「現在の取引」に(左端が■になっている)4件の交易が入っている。ちょっとオーバーして1.68になっているが、その分自動的に自動取引から引かれている(コンスタンティヌーポリス市場の総量は5.25のまま)。

この手動取引の先頭に■と付いているのは取引のロックで、ロックされている取引は自動取引対象から除外されキープされる(通常はこの下にAIによる自動交易リストが並ぶ)。
なおここで表示されている”利益”は受容の変化などによりけっこう上下するため、「設定したから後は放ったらかしで大丈夫」とはならないので注意が必要。少なくとも年に一度程度は利益の出ていないものの見直しなどを行うようにしたい。
※どうもまず必要とする取引を手動設定してロックした後、残りを自動で行わせるとちょうどいい感じになるという指摘がされている。少しずつわかってきたこと… : r/EU5
F3キー「生産」
建造物
建造物をたてる。”生産”というくくりだが、王宮や城、寺院や病院、ギルドや生産工房、穀物庫や原材料生産まで様々なものが含まれている。
(パッチ1.0.2時点では)ここは自動化しても何もしないらしいので手動で行う必要があって、方法は大きく2通りある
- いきなりF3キー「生産」に入り、自領土の全ロケーションで建設可能な建造物からロケーションを決めて建設する
※すべての建造物が表示され面食らった上に、建造物は建設可能なロケーション制限があったりするし、何かを押せばあちこちのパネルに飛ばされるためよくわからないまま終わってしまう。 - まずロケーションをクリックしてロケーションパネルに入ってから、そのロケーションで建設可能な建造物を絞り込んでから建設する
※よくわからない間はこちらをお勧め。
恐らく最初は2番のロケーション別に建造していた方がやりやすいと思われるため、下記でロケーション画面経由の手順を書く。
ロケーション画面
どんなマップモードでもロケーションをクリックすると、左パネルにロケーション画面が開く。このロケーション画面で雇用可能な階層別の人数を把握し、その上で必要な建造物を選んで建てれば非常に楽である。また既存の建物がある場合にはそれを「+」するだけでも建設が始まる。
このパネルのインフラタブの特に下半分にRGO関連の情報が詰まっている。
※また「街道ビルダー」も付いており、右クリックすることでそのロケーションから首都までの街道を複数ロケーションに渡って一気に敷くこともできる。

街道ビルダーの右から左へ順に以下のような情報が載っている。
- 一段目:
- 近接性
- 有効支配度
- 税基盤:パイグラフの内訳はホバーすると表示される。青は貴族(33%)、茶色は市民(27%)、赤はズィンミー(キリスト教徒、20%)となっている。ここまででこのロケーションの税金の8割を占めている。人口統計によればこのロケーション人口の68.7%は農民(庶民)だがその税金は9%に過ぎない

- 右端はそのロケーションの原材料(特産物)。この州だと魚を生産している
- 二段目:
- 開発度:識字率や街道の有無、植生、沿岸などにより決まり、またこの開発度が、RGO規模や建造物レベル、建造物コスト、近接性コスト、食糧生産など様々なエフェクトを発生させる
- 繁栄:
- 芸術:
- 建造物レベル上限(現在のレベル)
- 制度普及率n/m:
- 食糧生産力:
- ロケーション内食糧:
- 三段目:
- 左列に階層別の雇用可能人数/階層全人口
- 右列に現在ロケーション内に立っている建造物
この三段目の右列はボタンになっており、押すとその階層ごとの建造物が絞り込まれて表示される。前の画面で階層別の「雇用可能人数」(要するに職にあぶれている人数)もわかっているので、いきなり労働者不足になることはない。
また右列は現在そのロケーションに立っている建造物の階層別一覧を示している。数字は建物の数となっている。
各ロケーションでの建造物はそのロケーションの「建造物レベル上限」まで建てられる。
※「建造物レベル上限」は、「人口+ロケーションランク+州都の有無+開発度」の総合計となっており、なかでもロケーションランク要因(田園集落は+0、街で+25、都で+100)が非常に大きい。※このイズミットロケーションの場合、合計133のうち、人口+5(51,000人)、ランク+100、州都+2、開発度+26となっている。
(初期)建造物一覧
それぞれ、ロケーション(都・都市・田園集落の種類)ごとに建設可否があり、その上で建設時に物資を必要とするため注意が必要。※赤字=各階級権力影響あり、下線:重要指標ぽいもの
- 貴族雇用施設:
- 王宮:君主力+10.00%、内閣効率化+2.00%
- 王宮庭園:毎月の威信+0.02、毎月の外交官数+0.20
- 大使館:外交許容量+0.10。ロケーションの戦場の霧を消す
- 聖職者雇用施設:
- 病院★:キャラクター寿命+5、疫病耐性+10%
- 寺院★:聖職者の最大識字率(ローカル)+5.00%、最大支配度+5.00%、不穏度-2.50%
- 写字室★:交易品「書物」の生産 ※活字の登場はだいぶ後
- ミッション:部族から農民へ+50.00%、毎月の改宗+100、疫病耐性+5%
- マドラサ:聖職者の最大識字率(ローカル)+5.00%、聖職者の食料消費量(ローカル)+10.00%、POP改宗速度(ローカル)+10.00%、部族から農民へ+10.00%
- (イスラム?)スーフィー修養所:聖職者の最大識字率(ローカル)+10.00%、聖職者の食料消費量(ローカル)+10.00%、POP改宗速度(ローカル)+10.00%
- 市民雇用施設:
- ギルド:生産設備
- 生産施設:生産設備
- 市場の倉庫:交易優位性+0.10、所有国への交易許容量0.10、市民の交易上限+1.00%、(市場中心地:最大市場在庫量+200)
- 市場:市民の階級権力(ローカル)+10.00%、POP同化速度+1.00%、交易優位性+1.00、所有国への交易許容量+1.00、市民の交易上限+20.00%
- 奴隷市場:毎月の奴隷化+20
- 埠頭:毎月の水兵+1、交易許容量+0.10、港湾適合性+0.10、船の建造可能
- 図書館:文化影響力(ローカル)+0.10、POP昇格速度(ローカル)+10、毎月の識字率(ローカル)+0.10%、最大識字率+5.00%、制度の成長度+25.00%
※書物と紙が必要 - 交易機関:所有国の海洋プレゼンス:+0.05、交易優位性+0.20、所有国への交易許容量+0.30
- 事務局:貴族の最大識字率(ローカル)+2.50%、市民の最大識字率(ローカル)+2.50%、(首都:内閣の効率化+2.50%)
- (イスラム?)フンドゥク:(市場中心地:最大市場在庫量+200)、交易優位性+0.50、所有国への交易許容量+1.00、市民の交易上限+10.00%
- 労働者雇用施設:
- 生産施設[労働者250~1000人]:原材料生産設備
- 穀物庫[労働者50人]:食料上限(ローカル)+200.00
- 橋[労働者250人]:移動コスト-10.00%、近接性コスト(ローカル)-5.00%
※街道(砂利道)で移動コスト-25%、市場アクセスコスト-10%、近接性コスト-25.00、両ロケ内:制度成長度+10%、毎月開発成長度+25%、建設速度+5%。
- 兵士雇用施設:
- 役務保有地[兵士500人]:君主力(ローカル)+25.00%、毎月の人的資源+5、連隊募集可能 ※首都のみ
- 執行官★[兵士200人]:貴族の階級権力(ローカル)+100.00%、ローカル近接性供給源+20.00
※支配度が20未満の地域に建てると、その周辺に影響を与え支配度を上げる。コストが高いため建てすぎに注意し、20%を超えれば破壊も。 - 城[兵士1000人]:貴族の階級権力(ローカル)+100.00%、守備隊規模+250、不穏度-5.00%、貴族の人口制限+20、要塞レベル+2、ZoC許可
- 農民雇用施設:
- 集落[農民250人]:居住地魅力+1.00、人口増加+1.00% ※農民人口すら少ない田園集落で
- 灌漑[農民250人]:人口収容力(ローカル)+1,000、食糧生産%(ローカル)+5.00%
- 農村★[農民1000人]:労働者の人口制限+100、兵士の人口制限+50、農民の階級権力(ローカル)+25.00%、食料上限+100.00、食糧生産(ローカル)+4.00%
- 市場の村★[農民1000人]:労働者の人口制限+100、兵士の人口制限+50、農民の階級権力(ローカル)+25.00%、食料上限+50.00、交易優位性+0.10、交易許容量+0.10
- 森林の村★[農民1000人]:労働者の人口制限+100、兵士の人口制限+50、農民の階級権力(ローカル)+25.00%、食糧生産(ローカル)+1.00%
- 漁村★[農民1000人]:労働者の人口制限+100、兵士の人口制限+50、農民の階級権力(ローカル)+25.00%、海洋プレゼンス(ローカル)+0.01、毎月の水兵+1、食料上限(ローカル)+50.00、交易許容量+0.25 ※沿岸ロケーション限定。常備海軍持つなら必須
- 部族・奴隷の建造物:
- なし:※つまり農民に変えるしか無い。「政府」-「内閣」アクションの「部族の定住」で+500%
社会階層
- 上流階級
- 貴族:同化・改宗:5%、昇格:10%、移住:100%
- 聖職者:同化・改宗:5%、昇格:10%、移住:100%
- 市民:同化・改宗:10%、昇格:50%、移住:50%
※生産をおこなう建造物で働く
- 下層階級
- 労働者:同化・改宗:50%、昇格:150%、移住:10%
※都市や田園集落で原材料を生産・収穫・採取するかギルドなどで働く。原材料を採集できるのは労働者と奴隷のみ - 兵士:同化・改宗:50%、昇格:100%、移住:5%
※陸海軍の人的資源を供給する - 農民:同化・改宗:100%、昇格:50%、移住:10%
- 部族:同化・改宗:0%、昇格:100%、移住:100%
- 奴隷:
- 労働者:同化・改宗:50%、昇格:150%、移住:10%
- 階層の昇格:部族 → 農民 → [市民・聖職者・貴族・労働者・兵士のいずれか]
- 部族→農民:「内閣」アクションの「部族の定住」で+500%
- 農民からの昇格は、それぞれのキャパシティに依存する
交易品
自国が所有している市場(マーケット)で流通している生産品の一覧。
- 右から2列目:市場(マーケット)で生産している建造物一覧
- 右から1列目:自国で生産している建造物一覧
所有している市場(マーケット)で生産されていない生産品は両列とも空欄になっている。
※この交易品全種類で利益を出すなどは(市場内ロケーションごとの算出品および市場の動向も把握する必要があり)難しいため、まずは次の「食料」の不足をなくすことを目指したほうが良いと思われる。
※若干ややこしくなっているのは、このF3キー「生産」-「交易品」は市場(マーケット)全体が対象となためで少し混乱する可能性がある。「生産」の他のタブ「建造物」および「食料」は自領だけが対象となっている。
ただし日常生活に必要な交易品について、POPは市場(マーケット)から購入しようとするが、需要を満たせない場合はPOP満足度が減少する。このPOP満足度が”POPの反乱軍への参加しきい値”を下回った場合には政府に対抗する暴動の支援を始める可能性がある。逆に日常生活の必需品を満たしてPOP満足度を上げれば暴動に加わるPOP満足度が減少するということでもある。なおPOP満足度の要因は必需交易品の需給だけではなく、(国家及びロケーションにおける)宗教・文化の違いなども大きく関係する。POP満足度グラフに切り替えて低いロケーションを確認すると、大抵はそれらが大きく影響していることがわかる。なお「軍事」-「陸軍」のコマンド「達成目標を選択」から「反乱の抑制」を選ぶと不満を抱くPOPがいるロケーションで不温度を下げる活動をやってくれるが、肝心の不温度を表示するマップモードが見当たらない。
食料
州ごとの食料在庫と各ロケーションでの食料保管施設の有無がわかる。州内原材料を採取可能なロケーションで生産される。
各州(のロケーション)で必要な食料を生産できない場合、州の食料貯蔵量は低下し、州内食料が枯渇すると飢餓に苦しむことになる。飢饉が起こる前に市場(マーケット)から食料輸入を行おうとする。各州は、貯蔵量が満杯になれば食料売却を行い、貯蔵量が低下すると食料購入を行い、市場(マーケット)内に充分な食料があるかぎり飢饉は発生しない。
この「生産」-「食料」パネルでは、各州ごとの貯蔵量の増減と現在の貯蔵量を表示する。
もし貯蔵量が減少していて何らかの手当が必要な場合には手段が2つあり、1.食料生産力の高いロケーションのRGO施設を拡大する。あるいは、2.交易許容量枠を使用して別の市場(マーケット)から食料原材料を輸入することもできる。実際の輸入は「経済」-「交易」パネルから行う(自動的に遷移する)。
F4キー「社会」
自国のPOP(住民)がどのような分布になっているかが確認できる。また主要な文化、主要な宗教についても確認しておこう。
※厳密にはPOPとは「同じ社会階級・宗教・文化を持つ人々のこと」と定義されっている。つまりPOPの集合体がその国家の住民ということになる。POPごとに必需品があり、不穏度や文化・宗教などがどれだけ満たされているかというPOP満足度が存在する。
文化
パネル左上に「主要文化」、右上に「共通言語」が書かれている。
また重要な項目としてはグラフの右側一番目の「受容文化」も大事で、文化受容されていると統治効率が上がる。しかし受容文化には上限がありそれを超えると文化伝統力や文化影響力、内閣の効率化へのデバフが付いてしまう。なお非受容文化に降格すると該当する文化のPOPの満足度が-50%低下してしまう。
さらにパネル下半分には現在の国民の文化分布が示されている。それぞれホバーするとマップにも反映されるため、どの地域にどのような文化の人が住んでいるかを大まかに確認しておこう。
宗教
同じように、パネル左上に「主要宗教」、右上に「典礼言語」が書かれている。典礼言語は王朝内での
ここで主要宗教の切り替えもできる。
人々
ロケーション別にどのような文化・宗教属性のPOP(住民)がいるかが表示される。
またそれぞれの識字率、必需品入手率、満足度も表示されている。
F5キー「外交」
関係
- ライバル指定:指定しておかないとデメリット(他国からの敵対心+10%、防諜活動-10%、諜報網構築-10%)がある
- 従属国管理:従属国アクション、従属国設立など
アクション
外交アクション。開戦事由作成や宣戦布告もできる。
ただし対象を指定してからのほうがいいのでここを起点に行うことは少ないと思われる。婚姻なら家族を指定してから、外交なら対象国家を指定してからここに飛んできて、絞り込み表示されると思われる。
F6キー「軍事」
陸軍
現在保有している陸軍の管理ができる
- 動員:
- 召集軍を動員:戦争勃発時に召集できる。戦争が終わって解散すると生存兵がPOPへ戻る(解散しておかないと次の戦争が始められない)。原材料生産-20.00%、食糧生産(ローカル)-20.00%
- 正規軍を募集:常備軍。募兵規模は総人口および主要文化の人口から算出される。建造物「役務保有地」が必要
- 傭兵:
- 達成目標を選択:
- 一斉包囲:ハイライトされたロケーションの占領を試みる
- 反乱の抑制:ロケーション(地域?)を指定して反乱軍の抑制ができる
- 沿岸の殲滅:集まって大軍隊を作り規模で劣る敵陸軍を殲滅する
- 自国領の防衛:首都と接続されている自国領を防衛する
- 部隊の本国送還:割り当てた海軍で追放陸軍を母国まで送還する
- 陸軍兵站の実行:割り当てた陸軍が食料を調達・分配し補給拠点を建設する
- 集中包囲:ハイライトされたロケーションで要塞の包囲に集中する
- 将軍の養成:将軍を育成して自国に仕えさせる(陸軍伝統-5.00)
海軍
- 水兵の募集:建造物「埠頭」が必要
- 提督の養成:将軍を育成して自国に仕えさせる(海軍伝統-5.00)
F8キー「進歩」
進歩
ここに進歩ツリーのなかで取り組む題目を設定できる。キュー形式で積んでおけばどんどん消化してくれる。
定住国家、典礼(宮廷)言語の言語競争力、平均識字率、需要制度の数、聖職者階級満足度などで進行速度が変わる
時代
時代ごとに3項目のルートがありツリー状に習得し解放していく
- 伝統時代:
- ルネサンス時代:
- 発見時代(※前作での大航海時代):
- 宗教改革時代:
- 絶対主義時代:
- 革命時代:
右パネル上部の自動化

※この中央のギアアイコンが自動化指定
次のような項目でそれぞれ自動化が可能。選択して自動化を行ってプレイ負担を減らそう。なお自動化とは言っても随時介入できる。介入した部分だけ従い残りはやってくれる。ただし外交など結構取り返しのつかない(取り戻しがけっこう面倒な)部分もあるのでその点は注意が必要。
- 収支:※F2収支でも階級課税など個別に自動化できる
- 交易:★
- 生産方法:★★
※例えば「紡績業者ギルド」などだと3つほど生産物の生産方法(生産ルート)を変更できるオプションがあり、●のチェックにより変更できる。この選択を自動化するかどうか。つまり生産物の選択(何を一次素材とするかの選択)を自動化するという意味 - 建造物:ここで「■ダカット以外のコスト許可」と書かれているのは、その額以上なら新規建設する(指定額以下なら建設しない)という意味。是非は分かれているようだが、ゲーム開始当初の必要建築物を建てたら自動化のほうが良いんじゃないかと意見もある
- 建造物の操業と閉鎖:
- 建造物の助成:赤字建造物に助成金を出す
- 階級建造物の破壊:各階級が自費で勝手に立ててくれる建造物
- RGO:★
- 研究:★ ※自動化していてもキューを入れ替えたりはできる。時々チェックして優先する研究だけ指定することもできる
- 法律:★
- 政府改革:★
- 内閣:★
- 議会:★
- 階級:★
- 文化の受容:★
- 宗教の教義:★
- 外交:※気づけば勝手に属国併合までやってくれて至れり尽くせりだが、あなたの大方針とは異なる可能性は出てくる。
- ライバル:※ライバル指定は慎重にやるべき
- 探検:
- 植民地:
- 陸軍編成:
- 海軍編成:
- 将軍の交代:
- 提督の交代:
※ただしリリース時点の自動化(AI操作)は、チューニング不足なのかプレイヤーの思い通りには行かないことがあちこちで指摘されている。そのため最初は★をつけた項目などを自動化してみると良いかもしれない(★は私が思いつきでつけただけなので拘る必要はなく各自で取捨選択してください)。
※なお初心者向けとしてお勧めされるオスマンだが、実は宗教と文化が入り混じった素人には難しい国であり、研究、宗教教義あたりをよくわからないまま手動で設定すると危険。気づけば異教寛容度が下がりすぎてギリシャ正教会POPのPOP満足度が激下がりしていることもあるので、内閣自動化しておけば改宗や文化同化を勝手にやってくれてPOP満足度を維持できる。
国家の指標
画面上部に表示されている項目がどのように決定されるか。
- ダカット(現金):
- 安定度:
- 影響:POPの反乱軍への参加しきい値-、反乱軍からの脱退しきい値-、列強スコア
- プラス:階級満足度平均+、POP昇格速度%
- マイナス:
- 変動要因:主要宗教の聖職者比率、投資率、下落値
- ※F1政府内閣(軍事)の「国家の安定化」、支出の安定度
- 影響:POPの反乱軍への参加しきい値-、反乱軍からの脱退しきい値-、列強スコア
- 総人口:文化、宗教、階層ごとの人口分布
- 正統性:
- 影響:君主力+、POPのの反乱軍からの脱退しきい値-、列強スコア+
- 変動要因:基本値、主要または受容文化の貴族比率、伝統的な分配、投資率
- ※F1政府内閣(軍事)の「政府の強化」、支出の宮廷コスト
- 威信:
- 影響:文化影響力、新しい芸術家のスキル、敵対心の変化補正、外交評判、市場の魅力、列強スコア
- 変動要因:貴族階級満足度、王宮のハーレム(イスラム?)、婚姻(自分を含む一族と他王室相手の場合。相手の列強ポイント?で上昇率が変わる)
- 外交官:基本値+外交費
- ※支出の外交費
- 戦争疲弊:
- 人的資源:毎月の人的資源+陸軍維持費
- ※支出の陸軍維持費
- 最大水兵:毎月の水兵
どの国家で始めればよいのか?
公式的には、次のように書かれている。
- まったくの初心者:オスマン、ハンガリー、カスティーリャ(スペイン)
- より挑戦的:ナポリ、ボヘミア、ノルウェー
- より複雑なメカニズムを学ぶのに最適:ヴェネツィア、フランス、ヴィジャヤナガル(南インド)
Europa Universalis V Player Resources | Paradox Interactive Forums
ただしオスマンはよく知られている通り宗教と文化とが入り混じっているため序盤から急速にPOP満足度が減少していき、改宗や文化同化などの対策を打たなければゼロに近づきます。開始時点で国教(イスラム スンニ派)と正教会の信者数(確か6割近く)は逆転しており、ましてやバルカン半島に進出するとなれば文化の違いからさらに苦しむことになります(国教改宗イベントまである)。内閣を自動化するなどすれば勝手に対策を打ってくれますので、オスマンプレイで躓いたときにはこれを思い出しましょう。ただし人間がプレイすればオスマンが強いのは確実で、コンスタンティヌーポリス市場の優位性や内閣メンバー数優遇、イェニチェリ兵制度、ハーレム制などシステム面でも圧倒的に優遇されているとは思います。たとえ包囲網を組まれたとしても、海峡通行権を渡すだけでたいてい見逃してくれるはずです。
なお海外の掲示板などでも「ハンガリーが強い」というのはかなり定説になっています。史実でもオスマン登場までは欧州の強国でしたし、EU5ではAIオスマンは大拡張できないようでアナトリア統一ですら苦労するようですから、安心してじっくりゲーム学習に取り組みましょう。ビザンツはたいていセルビアかブルガリアに併呑され、AIオスマンはバルカン進出どころか下手すると1500年くらいまでアナトリアで手一杯で、ましてやセルビア・ブルガリアを併呑してハンガリー国境に迫るなんてのはたぶん出来ない。ハンガリーとしては念の為にナポリ(両シチリア)あるいはジョチウルスなどと国交を通じておいて最悪彼らと同盟を組めばオスマン対策はまず万全でしょう。このハンガリーで軍隊の動かし方から戦後処理までを覚え、その後内政面でも勉強してから他の国家でプレイするというのも大いにありだと思われます。ボヘミアも相当強いという評価を受けています。
またカスティーリャについてはフランスが属国効果もあって相当強いため、そこだけと喧嘩せず同盟さえ組めれば安心して進められるようです(フランスには大人しく東に進んでもらいましょう)。なおポルトガルとアラゴンはライバル視してきます→パッチ1.0.10で友好国家に修正。南方のモロッコ=チュニス連合が(マラリアもあり特に常備軍獲得までは刃が立たない程度に)強いため、北アフリカに手を出すと良いことはない割に延々と(最悪エジプト=マムルークまで)戦いが続きますので避けたほうが良いでしょう。ケンカを売られたときには海峡を絶対防衛線として防衛に徹しましょう。カスティーリャでは新大陸進出・植民地経営がメインテーマとなるでしょうから、ナバラを併呑してアラゴンを割譲させるなどすればスペイン変容も見えてきますので、イベリア半島を安泰にした後は植民地開拓に向かいましょう。
FAQ
ゲーム内容
観戦モード
ゲームを開始(いずれかの国家で読み込み済)したあと、ESCで左サイドメニューを出し、「世界地図」-左パネルの一番上段の左側「観察」をクリック。確認があり観察モードに入れる。速度変更が可能なほか、国家を選択して同盟関係や戦争状態なども確認できる。
ミッションの食糧投資がクリアできない
食糧を貯蔵するための「穀物庫」(食糧上限(ローカル)+200)を建設して必要数を確保する。
アウトライナーのミッションを消したい
アウトライナー右上の時計のようなボタンを左クリックして「アウトライナー設定」を開き、政府カテゴリーのミッションの★を☆へと変えると非表示になる。
※ミッション自体が消えたわけではなく、あくまでアウトライナーから消しただけ。確認したければ、F1「政府」-「ミッション」を開けばいつでも確認や実行ができる。
食糧飢饉になる
2025年11月18日のパッチ1.0.5で、F2キー「経済」-「収支」の支出側に「食糧」ゲージが追加された。

このゲージにより、食糧をどれくらい備蓄用として確保しておくかが指定できるようになった。この備蓄食料は行軍やロケーション内での食糧不足時にまずこのプール分から消費され、また指定量以上の余剰分についてだけ交易市場(マーケット)で食糧売却が行われるようになった。
戦争の時の「~人の奴隷を送りました」がウザい
戦争の際、敵国ロケーションを占領するたびに出る「~人の奴隷を送りました」的なメッセージがうざい。これはゲーム設定で消すことができる。
ESCを押してメインメニューの「メッセージ設定」を開き、”奴隷”で検索。何も出ていないが「軍事メッセージ設定」をクリックして開くと絞り込まれて次の2つが並んでいる。
- わが国の陸軍がPOPを奴隷化したとき:ログ表示 / ポップアップ有無 / 一時停止切替 / マップ上表示有無
- 他国の陸軍がわが国のPOPを奴隷化したとき:ログ表示 / ポップアップ有無 / 一時停止切替 / マップ上表示有無
通常敵国を攻めているときに表示されうっとおしいのは上の方で、これを”ポップアップ有無”を無しに変えるだけでカチカチポップアップする奴隷メッセージは消すことができる。好みで設定しよう。
成人しましたがうざい
上と同様に、ESCを押してメインメニューの「メッセージ設定」を開き、”成人”で検索。何も出ないが、「社会メッセージ設定」をクリックして開くと2つ並んでいる。
上の方が毎回パカパカ開いてウザいやつなのでこれの”ポップアップ有無”を切り替えれば良い。
マップマーカーを消したい
画面中央下部にあるマップモードパネルの左側の虫眼鏡アイコンをクリックすると、マップマーカーの表示非表示を選択するメニューが開く。
※マップモードごとに表示しているマップマーカーは異なるため、マップモードを切り替えないと表示/非表示の切替がわからないものもあるので注意
特にHRE諸国が密集しているヨーロッパあたりだと、下記をオフにすると相当程度マップパンが軽くなる
- 建造物の建設:(他国を含めて)建造物の表示を切り替える
- ユニット:(他国を含めて)陸海軍ユニット表示を切り替える
スペックなど
Paradoxランチャーが起動しないんだけど
今作EU5ではParadoxランチャーを経由せず直接ベースゲーム本体が起動する。
これは開発元が起動速度の速さにこだわったためとされている。ベースゲームにプレイリスト(Mod管理)機能を含んでおり、さらに起動メニュー表示後もバックグラウンドで読み込み作業を続けることで高速起動を実現している。
そのため、起動直後すぐに「前回からの再開」を選んでも、結局は必要なリソース読み込みを続けるためトータルの起動時間は変わらない。なのでとりあえずPCでベースゲーム起動指示を行っておき、(飲み物を入れるなど)用事を済ませてから戻ってくると、ちょうどバックグラウンド読み込みも終わっていてかなり早くセーブゲーム再開からスタートできるような感じになっている。
PLAYを押すとクラッシュする
Steamの起動プロパティに「-dx12」を付け加えると回避できることがある模様。※もちろん環境次第。一般的にNVIDIA系グラボならDirectX12の方が良いだろうと書かれています
Steam:Black screen on game startup and other known issues :: Europa Universalis V 総合掲示板
Reddit:!! IF YOU’RE CRASHING WHEN YOU CLICK PLAY !! : r/EU5
なおハードウェア能力不足で落ちるときには「起動オプションに-graphic_preset=very_lowを追加しろ」と書かれていますので、お困りの方は試してみると良いかも知れません。
※あとこういうゲーム関係でよくあるのが、「CPU統合グラフィックス(簡易GPU内蔵型CPU)+グラボ」のPC構成で、統合グラフィックスが使われているために能力不足で落ちるケースです。これに該当する場合には統合グラフィックスを切るなどの対策を調べましょう(言うまでもなく自己責任で)。
※またCPU統合グラフィックスだけの環境の場合はとにかく低設定にするしか余地はないでしょう。下記の「Steam起動オプション」も参考にどうぞ。
Steam起動オプション
Steamの場合、Steamクライアントのオプションでも指定できるようです。
ライブラリからEU5の右クリックで「プロパティ」を選ぶと下の画面が出てきます。

ここで下記4種類の起動オプションが指定できるようです。スペックが原因でプレイできないような方の場合は、これを利用しても良いでしょう。
- ゲーム起動時に確認する
- (オプション無指定で)EU5を起動する
- DX12で起動する
※一般的にNVIDIA系グラボならDirectX12の方が良いだろうと書かれています
- DX12の超低設定で起動する
- 低設定で起動する
ちなみにこの確認が毎回出る場合には、上記プロパティ画面の2番目「Europa Universalis Vをプレイ」に変えておきましょう。
メインメニューから先へ進めない
Windows11の場合、メインメニューが起動したときにタスクマネージャに入り「Europa Universalis V(EU5)」を右クリックして「効率化モード(Efficiency Mode)」に設定すると実行できるようになるという報告がSteam掲示板で上がっている。
ただしベースゲーム起動ごとにやる必要があるとのこと。
Steam掲示板:Black screen on game startup and other known issues :: Europa Universalis V 総合掲示板
起動ごとに言語選択が出る
既知のバグ。
※パッチ1.0.2で修正されたと見ましたが事実かどうかは不明。私の環境では一度見たきりでその後見ていません。
一度「英語」を選んでから「日本語」を選ぶとでなくなるとのこと。試してみましょう。
起動オプションに「-language=en/」と指定すると強制的に「英語」で起動できるようなので、そこから「日本語」に変更しても良いかも知れません。その後一度終了し、先程追加した文言を起動オプションから削除しましょう。
DLSSを使用したい
「設定」-「グラフィック」の下の方の「アップスケーリング」を”無効”→”NVIDIA DLSS”へと変更。さらに再起動するとその下の「アップスケーリング品質」が設定できる。
私の環境・設定(品質:バランス)ではGPU温度が5度以上下がった。パフォーマンスだと10度近く下がる。
※FSRなどはなくDLSSのみなので、AMDグラボではアップスケーリング指定ができない(ただし開発中には簡易的なFSRが実装されていると書かれていたような記憶がある)。
※なおベースゲーム1.0.0ではNVIDIA/AMDグラボの両方でアンチエイリアスが指定できたが、1.0.2になるとどちらのグラボでもアンチエイリアス指定ができなくなった。
グラフィック描画を軽くしたい
ノートパソコンでのプレイなど、グラフィック描画を可能な限り軽くしたい人向けの設定ガイド
- RTXシリーズグラボの場合、上のDLSS設定を行う
- 3D地形を無効化:地形マップでの3D描画を止めて平面地形マップにする。これが一番効果が大きい
- アンチエイリアシング:FXAAか、ギザギザが気にならなければ無効でも。
- テクスチャフィルタリング(異方向性フィルタリング):マップ上のものを急角度で見ることは少ないためあまり意味がない。
- トライプラナーUVの品質:山や丘など急勾配のサーフェスにおける拡大時のテクスチャレンダリング品質。最大限まで拡大しないとあまり意味のないもの。
- メッシュLOD品質:カメラから離れた位置の詳細度。
- シャドー品質:NVIDIAアプリで低設定表示にすると、これの無効化を提案してきます
- パーティクルの有効化:オン→オフ
- ブルーム:オフ
- キャラクターSAO:オフ
このあたりが一番効き目が高そうです。
VRAM関係:
- テクスチャストリーミング:オフ
- GPUテクスチャストリーミング:オフ
Linux環境
公式でも確認していましたが動作するようです。しかし当然サポートはありません(特にOS依存関係の不具合問い合わせなどは対応しないと思われます)。
※LinuxネイティブではなくProton互換レイヤー経由の話。私はWindows環境ですので詳細は知りません。
Windows環境がない場合にはLinux(Proton)でプレイするのもアリでしょうが、当然自己責任で、かつ不具合などは公式サポートではなく一般の掲示板などで問題解決する必要があるかと思います。
なお「LinuxとMacについてはコスト要因で今作EU5ではサポートしない」とスタジオマネージャ(開発総責任者)のヨハン・アンダーソン氏が明言しています(「私(=Johan)はもともと PDS ゲームに Mac と Linux を追加することを決定した人間であり、それをサポートするためにどれだけのコストがかかるかも正確に知っていますが、だから、やる意味がないと判断しました。」。(2025/8/23)
発言は別記事「バニラでのEU4初心者向けまとめ」の「今秋発売予定のEU5について」→「公式フォーラムでのスペック関連Q&A」→「その他プレイ環境:」を参照ください。
ちなみにSteamプラットフォームでの2025年11月時点でのOS比率は、OSXつまりMacが2.02%、Linuxが3.20%となっていますが、Windowsの94.79%(うちWin11が65.59%、Win10が29.06%)には遠く及びません。また一時的に開発できたとしても、”DLC商法”と揶揄される10年近く開発を継続する開発モデルにおいて、それだけの開発・サポート要員を継続的に確保できるほどの売上見込がないと判断したのだと思われます。
Reddit:EU5 Works on Linux! : r/EU5
Mac環境
なお「LinuxとMacについてはコスト要因で今作EU5ではサポートしない」とスタジオマネージャ(開発総責任者)のヨハン・アンダーソン氏が明言しています(「私(=Johan)はもともと PDS ゲームに Mac と Linux を追加することを決定した人間であり、それをサポートするためにどれだけのコストがかかるかも正確に知っていますが、だから、やる意味がないと判断しました。」。(2025/8/23)
発言は別記事「バニラでのEU4初心者向けまとめ」の「今秋発売予定のEU5について」→「公式フォーラムでのスペック関連Q&A」→「その他プレイ環境:」を参照ください。
ちなみにSteamプラットフォームでの2025年11月時点でのOS比率は、OSXつまりMacが2.02%、Linuxが3.20%となっていますが、Windowsの94.79%(うちWin11が65.59%、Win10が29.06%)には遠く及びません。また一時的に開発できたとしても、”DLC商法”と揶揄される10年近く開発を継続する開発モデルにおいて、それだけの開発・サポート要員を継続的に確保できるほどの売上見込がないと判断したのだと思われます。
デバッグコマンド(チートコマンド)
チートModなどで利用するデバッグコマンドのまとめ(自分用メモ)
- stability:安定度
- prestige :威信値
- legitimacy :正統性
- Gov.:内閣
- Cabinet:内閣
- CabinetSeats:内閣枠。+すればその分ダイレクトに空き枠が追加される
- Reform Slots:政府改革枠数
- Cabinet:内閣
- Prod. -Food:食糧関連
- MonthlyFood:
- FoodCapacityMod:
- FoodCapacity:
- PopFoodConsumption:階級食糧需要-%。※食糧不足対応には、これを減らすのが一番手っ取り早くて他への影響が少なそう
- Society-Culture:F4文化関連
- CulturalTRadition:文化伝統力 たぶん固定値と率
- CulturalInfluence:文化影響力 たぶん固定値と率
- AssimilationSpeed:同化率(同化速度)
- CulturesCapacity:これも固定値と率がある。許容上限と許容増加率?文化許容枠を増やすには固定値を+すれば良い。
- Society-Religion:F4宗教関連
- ConversionSpeed:改宗率(実態は改宗速度?)
- ToleranceOwn:たぶん真の信仰の寛容度
- ToleranceHeretic:異端許容度。※異端とは同一宗教で別宗派のこと
- ToleranceHeathen:異教寛容度
- Artists:芸術家
- Number of Artists:抱えられる芸術家数(人)。なお作品製作はF2収支の文化投資額で決まるというが、予算最大にしても予算0でも同数値でよくわからない
- Diplo.:外交関連
- Military
- AntagonismRecieved:敵対心影響値?
- AntagonismChange:月間敵対心減少数固定値?
- WarScoreCost:戦勝点コスト?
- Military
- Geo:地政学
- Exploration:探検
- MissionSpeed:探検進行速度
- ExplorationLandCost:陸地探検コスト
- ExplorationSeaCost:海域探検コスト
- Colonization:植民
- ColonialRange:植民距離
- ColonalCharterCost:植民コスト
- ColonialMigratiionSize:毎月植民数
- Maritime:海域
- MaritimePresence:海域プレゼンス
- Privateers:私掠船関連
- Disease:病気関連
- Exploration:探検
- Advanced:進歩(技術ツリー)
- Research:
- ResearchSpeed:研究速度?研究は蓄積値があってそれを消費する形でアンロックされるはず。その蓄積速度がこれだと思われる。
- Institution:
- InstitutionGrowth:制度成長? 内閣アクション「制度の促進(”Promote institutions”)」
- Research:
- その他
- RemoveFogOfWar:戦場の霧
- discover all:全マップを発見済に。「discover 」でTABを押せばヘルプあり
Console commands – Europa Universalis 5 Wiki
Useful Console Command list :: Europa Universalis V 総合掲示板
Steam コミュニティ :: ガイド :: How to get achivements with any mods enabled
Steamワークショップ::Skiar’s Cheats Menu:
- なおコンソールコマンドをミスると再起動などが必要となり手間なので、基本的な数値操作については素直にチートModを使うのが良いかと思われる。ただしどうしてもコマンドを入力したい(例えば文化転向や改宗を一気に終わらせたいなど)場合でコンソールを開きたい時には、このModでDebugModeをオンにした状態でキーバインドで割り当てたキーを押せば良い。
- デフォルトキーバインドの「grave[`]」は日本語キーボードでは入力しづらいのでF12などに変えると良い。それでも開かない場合はSteamの起動オプションに「-debug_mode」を付け加える。
個人的な覚書
初期設定
最初に設定したことのメモ
- グラフィック:
- 垂直同期:これをオンにするとFPS制限をかけることができる。一度オンにして30FPSに変えたが、それでもやや重く感じるので外部ツールで制限することにしてベースゲーム上ではFPS制限を外して垂直同期はオンに戻してみた。
- ゲーム:
- オートセーブ間隔:落ちるというレビューを良く見たのでとりあえず毎年→半年ごとに変更
- インターフェース:
- GUIスケーリング:200%→160%。UIがデカすぎてマップが隠れるのでやや縮小
- ツールチップ設定のロック時間:1.00→0.50秒へ
- オーディオ:
- 環境音(Ambient Map Background):0% ※ギシギシ音や歩き回る音など
公式ガイド「EU5でシステムパフォーマンスを向上させるためのヒント」:Tips for improving your system performance in EU5 | Paradox Interactive Forums
※NVIDIAアプリでのゲーム実行ファイルは、「\steamapps\common\Europa Universalis V\binaries」にある「eu5.exe」。古いドライバだと「最適化に対応していない」と表示される。確か11月4日ごろにドライバがアップデートされた(EU5対応予告もあった)が、チューニングは未対応のようだ。
PC環境メモ
誰かの参考になるかも知れないのでメモしておく。
私のPC環境は以前にも書いている通り、Ryzen3600+RTX3060(12GB)という、まあゲーマーとしては底辺環境だが実際にはSteamでもまだ結構な勢力を持っている環境となっている。4Kモニタでゲーム設定も3840×2160。※Cities Skylines用と言ってよいためVRAMだけは優先している
推奨環境ギリギリだったはずなので実際快適に動くのかどうかが正直不安で返金も覚悟の上で購入したが、ベースゲーム初回起動時に自動的にゲーム(グラフィック)設定の最適化が行われ、まあまあ動く環境で起動できる。
※ちなみにEU5開発元であるParadox Tinto社スタジオマネージャーのヨハン・アンダーソンはこの設定でプレイしているそうです。私自身はグラフィック設定はいじっていない(ベースゲームの初回チューニングのまま)のですが同じでした。なお彼が4年間オフィスで使っていたのはRTX2060環境だそうです。※2025年10月31日の投稿
そこから特に変更もせずチュートリアルを行ったが、常時グラボのファンがうるさく回っているものの、カクつくこともなく比較的良好に動作している。※念の為に書いておくと、貧弱な環境なのはわかっているので別に最高設定・最高速度(FPS)での動作は最初から望んでいない。
個人的には、長時間プレイするゲームなのでもっと静かに動いてほしいため、さらに上記設定(3Dマップオフ)を行うことでPCもうるさくなく快適にプレイできるようになった。
※FPS20制限で、1337年のゲーム起動時点でCPU使用40%前後、GPU使用70~80%前後。起動直後アジェンダが表示されている段階で使用メモリは6GB弱。FPS20だとマップパンすると多少カクつくが、EU4でもこの程度で長時間プレイしていたのであまり気にはならない。「コアをフル使用しているのか?」という定番の疑問に答えておくと、ちゃんと分散はしていて2コアだけ集中というようなことはない(6コア12スレッドの1コア2スレくらいは空きがある状況)。というより重いのは月中ではなく月初前及び年初前処理であってそこは1~数秒固まったようになる。これは如何ともしがたいと思われる。
さらに(上記設定から)「3Dマップをオフ」(設定-グラフィック-品質の一番下「3D地形を無効化」)すると、かなり軽くなりGPU使用は40%前後へと落ちる。この状態でFPS30制限へと戻した。とりあえず習熟期間は相当長そうなのでこれで進めることにする。
まだまだ設定などは煮詰めれていないが、使用VRAMは6.3GBとなっている。3Dマップ(3D地形表現)をオフにしてもVRAM使用状況は大きくは変わらず、6~7GB近くを使っている。※ブラウザなども立ち上げているため純粋なEU5のみの使用量ではない
初期時点での感想
※ほとんど理解できていない2025年11月初段階での小並感
- 内政にとても重心が置かれているゲーム
- 前作EU4では、一端わかってしまえば「色塗り」と呼ばれるくらいイケイケドンドンで占領していけたが、それが「歴史シミュレーションゲームとして」果たして良いことだったのかどうかは疑問が残らなくはない。
- 今作ではその後の「統合」作業に時間がかかり、さらに「支配度」も上げないと税収も上がらないため、そもそもの戦争の意味すら薄れてしまうことにも繋がる。結局かなり内政重視なバランスになっているようだ。「戦争には勝ったが国は滅んだ」というリアリズムが再現されていると言っても良い。
- もちろん前作EU4の色塗り作業が楽しかったかと言われれば、はっきり言えば楽しかったが、飽きが来るのも早いという意味においては(多くのプレイヤーは長くともだいたい1600年ぐらいでプレイを終えていたという)、個人的には今のところこの方向性を好感を持って受け止めている。
- しかし何にせよやることが多すぎる。どこまでも奥が深く、データ量は膨大で、設定は微に入り細を穿つ細かさで、「本当に全部理解できるんだろうか?」という不安がちらっと頭をよぎったりもする。ただしこれを徐々に理解し始めればかつて無いほどの奥深いゲームプレイになることが想像できる。
- 戦争は前作とほぼ同じ
- 戦場の霧の中、敵国の軍勢の裏をかき地形を生かした作戦の妙で勝利していく楽しさは充分ある。しかし今作では冬期の移動に制限がついたりするなど、前作の「季節感もへったくれもない単純な色塗り作業」とはまたかなり違ってくると思われる。
- また常備軍創設まではPOP(人口)管理がダイレクトに戦争に直結するため、そうそう無駄な戦争はできない。戦争疲弊の意味が身にしみるゲームになっている。
- 外交面では「諜報網構築→請求権捏造→戦争」の単純作業だった前作とは異なり、議会での開戦事由作成も可能になっている。しかし現時点では、外交についてはとても手が回っておらずよくわからない。
- 開発陣の本気度は伝わってくる
- 「果たしてこれはゲームなのか?」と疑うくらいに世界を網羅した膨大なデータが詰め込まれており、これを土台にしたゲームが長期間の大人のプレイに耐えうるものであるというのは十分伝わってくる。
- それに加えて、開発スタジオであるParadox TintoではすでにCustodianチームと呼ばれる品質管理チームが2つ開発スタジオ内に立ち上がっており、それぞれ”短期的なバグ取りとバランス調整”、”中期的な課題へ取り組む”という作業が同時並行で行われているという。これはParadox Tinto(及び販売元ParadoxInteractive社)がこのEU5を非常に長期間同社の主力製品として注力していくという意欲の表れであると感じる。
- 様々な歴史シミュレーションゲームを世に送り出してきたヨハン・アンダーソン氏が(恐らくは)「開発リーダーとしての晩年」に精魂込めて作り上げた超大作であることは間違いなく、今後に期待せざるを得ない。
ゲームバージョン
※過去分となったパッチ履歴をメモしておきます。最新情報は「EU5の動き」を参照のこと。