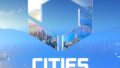「Europa Universalis IV(EU4)」は2013年発売らしく、さらに既に次作「Europa Universalis V(EU5)」も発表されており完全に今さらですが、自分の知識を整理するためにも(有償DLCを含まない)バニラ1.37での初心者向け説明を書いておこうかと思います。
※なおParadox界隈では古くからDLCも込みの状態を”バニラ”と呼称するのですが(この風潮自体は少し特殊)、ここではそういう風潮に馴染んでいない一般読者層向けに、”DLCを含まないベースゲーム状態”のことを(一般ゲームと同様に)”バニラ”と呼びます。つまり以下では、バニラとは発売時のベースゲームにパッチのみを当て続けた状態のことを指します。いずれにしろSteamストアでベースゲーム状態を販売しており、それ単体をセールで買ったという読者もかなりいるでしょうから、そういう方向けの文章だと思ってください。それで気に入ればDLCも買ってくれるでしょうし、実際に私も買いました。
要するに「今さらまとめるEU4(2025年版)」です。いよいよ公式に日本語対応するらしい「EU5」に向けて予習しようとする初心者向けな文章です。
ついでに自分用のEU5の発売に向けた情報まとめもここで行います。
変更履歴:
- 2025年10月23日:EU5プレリリースストリームについて追記
- 2025年9月10日:「領土管理限界はどうやって増やすのか」などを記述したFAQ形式のメモを追加しました。※2ページ目末
- 2025年8月24日:EU5ベータプレイ映像とYoutuberによるQ&A
- 2025年8月20日:「Europa Universalis V」について追記
- 2025年7~8月:徐々に追記
- 2025年7月2日:初稿
- 今秋発売予定のEU5について
- EU5発売前後の予定
- 発売日やパッケージ・スペックなど
- 公式フォーラムでのスペック関連Q&A
- 今後のビデオ公開予定
- STORY VIDEOS
- FEATURE VIDEOS&DEV DIARIES
- Developer Diary #1 - Population and Living World | Paradox Interactive Forums:人口(pop)と生活世界
- Developer Diary #2 - Government, Politics and Estates | Paradox Interactive Forums
- Developer Diary #3 - Trade and Economics | Paradox Interactive Forums
- Developer Diary #4 - Discovery | Paradox Interactive Forums
- Developer Diary #5 - Religions & Cultures | Paradox Interactive Forums
- Development Diary #6 - Military and Warfare | Paradox Interactive Forums
- Development Diary #7 - Diplomacy | Paradox Interactive Forums
- EU5ベータプレイなど
- バニラでのEU4初心者向けまとめ
- 初心者のための(バニラ)オスマンプレイ
今秋発売予定のEU5について
バニラでのEU4初心者向けまとめ
そもそも世にテキスト主体のEU4解説サイトというのもあまりなく、むしろ動画が主体なのは最近の流れですが、「初心者向けの解説」と言いながらDLC前提だったり、動画をまるまる一本見ないとダメ(しかも肝心の細かい操作はスキップ)だとか「どういう視聴者/読者を想定して作って/書いてるんだろう」という疑問だらけになる解説が多いので自分なりにまとめてみました。
対象バージョンは1.37です。
- 2024年9月18日リリース:Hotfix 1.37.4
- 2024年4月30日リリース:Europa Universalis IV – Steamニュースハブ(1.37メジャーアップデート)
※EU4は過去のメジャーバージョンアップで(UIはもちろん基本的なルールについても)相当変更が入っており、例えば1.20時代の情報でもかなりあてにならない時があります。十分ご注意ください。
※バージョン1.37(Inca)がリリースされたのは2024年4月30日(5月9日発売のDLC「Winds of Change」に伴う無料パッチ)なので、それ以前の記述は100%は信用できないものが多いです。ウソというわけではないが、少なくとも書かれた時期により現在のバージョンとまったく異なる内容すらある。
※上記1.37メジャーアップデートだけを見ても、つい最近変更されたんだなということが非常に多く書かれています。例えば「和平提案の最大受諾金を Shift キーを押しながらクリックしても、戦勝点のコスト合計が 100 を超えなくなりました。」非常に便利ですが、つい最近のバグ修正です。そもそもAAR:After Action Reportsで攻略対象としている国家(あるいは従属国家)や州の地形が入れ替わっていたりすることもままあります。また一時期存在したバグ(例えばオスマンで宗教を切り替えながら最速でイスラム諸国の関係改善を行うなど)を利用した攻略手順などを使用している攻略動画や、それを前提とした掲示板スレッドもかなり見かけます。オスマンでプレイすると「モグーリスタン」という国名を頻繁に目にしますが、あれは以前はチャガタイでした。
初心者のための(バニラ)オスマンプレイ
なぜオスマンなのか?オスマンは何と言ってもプレイのしやすさで言えば一番なのです。
「あんなバルカン半島のど真ん中でまわりに国家がいっぱいあるのにプレイしやすいとはどういうこと?」と思うかもしれませんが、国家としての体力が並外れて優れており、少々のミスも完全に吸収してくれるプレイのしやすさがあります。
EU4をプレイする上で、いずれにしろヨーロッパの土地勘を掴む必要があるため、どうせ右も左もわからない場合は「一番強い国」でプレイするのが望ましいと思います。後々わかってきますが、EU4でのオスマンは、圧倒的な軍事力、圧倒的な経済力、圧倒的な地の利を持っているまさに初心者プレイのために用意された国家だと言えます。その上、統治者も優秀で、オスマン最盛期を導いたスレイマン一世の登場イベントもかなりの確率で起こります。そしてやがて台頭してくるフランス、イギリス、スペインなどの強大なキリスト教国家群との戦いに敗れ散っていくのです。
※シミュレーションゲームのプレイ経験があれば「背後から攻められない端っこの国のほうが楽じゃないの?」だと思うでしょうが、このゲームでは基本的に攻めるにも「開戦事由」というものが必要で、初心者が選ぶオスマンでは、よほどの事態にならない限り勝手に攻めてきたりはしません。
また宗教や文化の違いによりキリスト教国家から恐れられ、爪弾きにされ、忌み嫌われたオスマン帝国の悲哀を知り、ヨーロッパの歴史と文化を知るためにも最適な国家だと思います。バルカン半島から北に進出しようものなら、圧倒的なキリスト教圏国家の団結力に打ちのめされ、なかなか馴染んでくれずに反乱を繰り返す土地にうんざりし…、かといって南に進めば敵なしで単純な侵攻作業に疲れ…というこのゲームの奥深さを体感するのにも最適だと思います。いくら力で征服したところで、文化や宗教面の違いを認め、受け入れる努力をしないと世界帝国は実現しないのです。
ただし(初心者オスマンで)ウルバン砲が来るイベント大前提にしてたり(※バニラだとコンスタンティノープル要塞に防御-10%のイベントが起きるだけで砲兵は来ないはず)、イベントでビザンツ帝国に開戦事由が勝手につく前提で書いてたり(※今のバニラではミッションツリーの陸軍扶養限界100%到達で隣接州に25年間請求権付与。同85%でアナトリア全域の恒久的な請求権付与)と、いやそれ「上級者のDLC最大活用プレイを初心者にドヤりたいだけじゃん」という解説だったり、古すぎて今のバージョンと全然逆の話ししてたりする動画だらけだったので、思わず自分でまとめようと思いました。あと動画によく出てくる「イェニチェリ」「エヤレト」「おべっかを使う」等ももちろんDLC要素です。※ミッションツリーもまったく異なる。クリミア云々も朝貢国システムとDLCによるミッションツリーが必要で、バニラではほぼ関係がありません。まあ北方面をポーランド=リトアニア同君連合に占領されるよりは精神的に良いかもしれませんが。
※もう少しぶっちゃければ、「俺はオスマンなんていうシロート国家は最近やってないけど、初心者はオスマンから入るだろうから久しぶりにオスマンで無双かましてみるか」、あるいは「”初心者向け”という条件をつければオスマンプレイして公開しても許される」という動画なわけです。まあプレイ時間数千時間級の常時鉄人モードな熟練プレイヤーにしてみれば、オスマンなんてチートプレイくらい超簡単な国家なわけです。
一応公平を期すために書いておくと、この傾向は日本のみならず例えば米国掲示板Redditなどでも同様で、今もプレイを続けていてコミュニティに参加し続けているような人はほぼほぼDLC全部買いな人のため、新規プレイヤーが「セールなので始めたいがどのパッケージを買えばよいか?」と質問すると「全部買え(Ultimate Bundle)」または「サブスクリプションもあるぞ(日本円だと1070円/月~)」と答える傾向にあります。これは洋の東西を問わず、いわゆるパラドゲーに共通する傾向ですね。
しかも飛んできてレスする割には、現在のスターターパックに何が含まれているのか?や最近バニラに組み入れされたDLC(「Rights of Man」、「Art of War」、「Digital Extreme Upgrade」、「Common Sense」の各DLCがバニラ統合されたのは2024年10月のパッチ1.37.5)すらよく把握していません(細かい点で言えば、パラドゲーは日本向けでいうと数年前から値下げではなく2段階ほど値上げをしており、同じ値引き率でも旧来の販売価格より高くなっている)。まあ10年前からDLCを全部買ってきた人たちなので、正直そのあたりには興味がないのです。もちろんそれは構わないのですが、なぜ最近の情報に疎いにも関わらず寄って集って回答するのかがよくわかりません。
さて以下ではとりあえずバニラ本体だけや、あるいはスターターパックを買ったような初心者に向けて、「ゲーム開始直後にいったい何をするべきなのか?」というところから話を始めようかと思います。正直言ってバニラでも十分楽しいゲームだと思います。またいきなり全部入りを買っても出来ることが多すぎて混乱し、ゲーム習熟にさらに時間がかかりかねません。
※例えばEU4では、ある面においてはミッションツリーを大きく拡張してきた歴史があるようで、それはまたプレイヤーにいろいろな国家でのプレイを下支えする要素であったようです。しかし次作EU5ではミッションの役割を大きく変えると予告されており、ちょうど今議論が沸騰しています(”ゲームを一本道化し単調にする傾向がある”ため初心者向けのチュートリアル的な位置づけにするらしい)。なのでEU5のためにEU4をちょっとプレイしておこうなんて考えている人にとっては、今更EU4フルDLCをマスターしても意味がない可能性がある=ゲームがけっこう変わる可能性が高いので、バニラだけの習熟でも充分だろうということです。
もちろんDLCを否定するわけではなく、それぞれプレイする上で楽しみの幅を広げる魅力的なDLCになっています。しかし初心者が(10年以上前の作品を今さら)全部買うなんてのは矛盾していると気づいてほしいものです。まずバニラをプレイしてみて、その上で各DLCを吟味すると自分に必要かどうかがわかるようになると思います。※バニラ単体だと最近は9割引で700円と十分なお買い得感があります。
※よく叩かれているDLC商法も否定するつもりは無く、むしろ開発者を確保し続けゲーム寿命を伸ばすのには最適かもしれないとは思います。しかし(EU5を始めとする)次作はどれも苦労する羽目になるとは思います。結局10年かけて蓄積してきたDLC全部込みのフル機能前作(EU4+ALLDLC、あるいはMod込み)が”最大最強のライバル”として立ちはだかることになるし、必ず前作と比較して否定されるでしょうが(~~は前作のほうが良い)、10年間もDLCで延命してきた以上それは避けられません。それは同じパラド販売のCities Skylines IIでも起こったことです。
AIでのEU4習熟
そこで色々疑問が湧いてくると思いますが、現在はAI(生成AI)が非常に発達しており、「陸軍扶養限界とは何か?」とか「領土管理限界とは何か?」「各階級から領土を取り上げるとどうなるのか?メリデメリ(メリットデメリット)は?どんな影響が考えられるか?」「商人は資金回収と交易力送出のどちらが良いか?」「オスマンプレイだが商人をどの交易ノードに配置するのが良いか?」などと質問すると、ものすごく丁寧かつ具体的に理路整然と教えてくれます。わかったことを再度「~ということか?」と確認すると、「その通りです!」みたいに褒めてくれる場合もあったりして、ゲームの習熟がスムーズに行くかと思います。
※もっと具体的に「商人4人でどこどこの地方に進出しているがどこの交易ノードに置いたらよいか」と聞いても的確に提案してくれます。基本的には50%以上を占有できている上流(矢印が流れてくるノード)の交易ノードで”送出”し、それでも余ればできるだけ高い占有率の下流(矢印が出ていく方向)ノードで”回収”するのが基本とされる。
延々と数時間もある動画のどこに答えがあるかなんて探す必要もなく、(このサイトを含めて)求める答えが載っているかもわからないサイトを次々と調べる必要もなく、掲示板で尋ねてぶっきらぼうで上から目線の回答にイライラすることもなく(と言いつつそもそも日本語コミュニティってあるんだろうか?)、AIがスパッと回答してくれます。英語ソースの情報も日本語で噛み砕いて丁寧に説明してくれますのでノンストレスですが、単語の翻訳違いだけ注意しましょう。何か知らない用語を使ってきたら「EU4日本語Mod(”EU4日本語版”でも通じる)ではどう表現しているか?」と確認しましょう。
※あと油断すると、時々パラドックス社の別ゲーである「Stellaris」「Victoria」の情報を平気で回答したりするため、「自分の画面と違うな」「なんか違うぞ」と思ったらすかさず「それはEU4バニラ最新版(1.37)の情報か?」と確認しましょう。どうも現状のAIはパラド公式フォーラム(XenForoクラウド?)のスレッドや、スレッドの中のレス発言者などを個別に認識できないようです(全部をスレッド主の発言と認識している)。AIが「公式に発言しています」とか言うので「どこで?」と聞くと、それは普通に別ゲースレッドのしかも一般プレイヤー発言だったりします。なので少し怪しいと思ったら「それはEU4バニラ最新版(1.37)の情報か?(※繰り返し)」「(EU4日本語WikiではなくEU4 公式)Wikiなどで確認できるか?」と確認するようにしましょう。定型文(辞書)登録しておいても良いかもしれません。ただしEU4公式WikiもミッションツリーもDLC前提のツリー(Ottoman missions – Europa Universalis 4 Wiki)なので、DLCのなしのツリー(Rûm missions – Europa Universalis 4 Wiki)を参照する必要があります。
UI配置:国家ウィンドウ
つまりAIの発達した現在においては、一番わかりづらいのが具体的な情報の表示位置だったり、UIの操作手順だと思われます。ただしこれらは既存の情報だと説明不足だったりする。「眼の前にあるんだからわかるでしょ」という話で、確かにいちいち説明するのはめんどくさい。

一応最低限書いておくと、画面左上の大きな国旗アイコンを押すと開くのが国家ウィンドウの前回開いていたタブ。その左下が「生産インターフェース」(AIはこれを”マクロビルダー”と呼ぶ)、右下が国家ウィンドウ(ホバーすると”政府改革”と表示される)の政府タブが開きます。
なおこの国家ウィンドウは少し変わった挙動をし、政府改革ボタンでクリックすると「政府」タブが開くのですがタブは毎回政府タブに固定です。しかし大きなアイコンをクリックすると前回開いてたタブが開きます。
時々生産インターフェースを開いて軍事タブを開いてと交互に確認する必要があったりしますが、そのときには上の大きなアイコンもしくは「F1」キーを押すと前回開いていた国家ウィンドウタブが開きます。またF1を押してからF2を押すと軍事タブ、F1→F3は従属国タブが、F1→F4を押すと階級タブがそれぞれ開きます。
まとめると以下のとおりです。かなり細かい機能が詰め込まれているため、疑問に思ったりゲームプレイが進んだときに随時見るようにしてください。
UI配置:概要(アウトライン)
画面右端に表示される概要(アウトライン)ウィンドウはなかなか良くできているなと感じますね。
概要ウィンドウは、画面右端の「≡」的なアイコンで開閉できます。また表示する項目は、「+」アイコンでカスタマイズ可能です。※ちなみに右上端の+-はシミュレーション速度変更です。

世界中を対象とした広いマップで、「現在どこで何が行われて進行度はどんなものか?」という情報がひとまとめに集中表示(リアルタイム更新)されており、この概要ウィンドウだけで大抵の状況把握が済みます。表示項目のカスタマイズも「+」アイコンから可能です。
兵の募集状況、船の建造状況、包囲戦の状況、建造物開発状況、陸軍ユニットの一覧、海軍ユニット(船)の一覧、各階級の忠誠心と影響力と領土などが一目瞭然です。また該当項目をクリックすると、マップを現地に移動することも出来ます。※ただし起動(ロード?)するごとに表示順がばらばらになって入れ替わってしまい、並び順が統一されてないのが謎ですが。
画面下の右側
また登場回数が少なく少し分かりづらいのが、キリスト教カトリック系国家でのみ登場する画面右下の「ローマ教皇」ボタンと、その横の「神聖ローマ帝国」ボタンです。AIはこれらを何故か頑なに国家ウィンドウの宗教タブにあると言い張りますが、どうも違います(昔はあったのかも知れません)。
常設議会を設置した場合には、ここに議会ウィンドウを開くボタンが表示されます。
開始直後の外交・内政いろいろ
さて1444年でプレイ開始するわけですが(なぜか他の年代でのプレイはほぼ話に出ないし、”公式でも全年代でのバランス調整を放棄している”とプレイヤーに思われている)、まずやることは以下のものです。
- 大目標:
- とりあえずEU4というゲームを知るために、ヨーロッパ中欧方面とトルコ(アナトリア)・北アフリカ方面に攻め込んで痛い目に遭うところまでを学習範囲としましょう。
- とりあえず痛い目にあってみると「これはどうしたら良いんだ?」という疑問が湧いてきますが、そこから先はだいたいAIが教えてくれます。ただしさらっと嘘(過去情報)を教えてくるため「最新版のバニラで」と注釈をつけるのを忘れずに。
- プレイ期間(年代)は定めず、とりあえず戦争の開始と終了、兵隊の運用と回復(人的資源)、同盟とは?交易とは?といった辺りを学べば、次のプレイでの改良点や他国でのプレイでの基礎ができるかと思います。
- ※実はプレイ開始直後にもすでにランダム要素が始まっており、プレイヤーが操作できるようになった状態で国家関係が決まっている物もあり、長期的な視野では非常に困る致命的なものもあったりするのですが、さわりを知るための初心者プレイなのでそのあたりは気にしないでおきましょう。後々「あそことあそこが同盟組んでるのはまずい」というのがわかってきたりします。それがわかれば初回プレイはOKということにしましょう。
- あと大きいところではオスマンは言わずとしれたイスラム国家(スンニ派)であり、キリスト教圏の国家とは基本的に仲良くはなれないところがあります。結婚もしてくれませんし、怒らせるとキリスト教圏国家が大同団結して一斉に攻めてきます。基本的にアナトリア、北アフリカに伸ばすほうが初心者としては楽で、バルカン半島以北はちょっと手出ししてみてどんな反応を受けるかを知るためにあると思ったほうが良いでしょう。もちろんゲームがわかってきたならば、実力試しにウィーン包囲をしてみるのも良いでしょう。
- ※完全に蛇足ですが日本語化Modでいう「スンナ」とは”預言者ムハンマドの時代から積み重ねられた『慣行』(al-Sunnah スンナ)”を指し、一方の「スンニ」とはその”スンナ(慣行)に従う者たち”を表すアラビア語形容詞によります。もともと国際的には「Sunni Islam」(英語Wikipedia)が使われてきたため、日本のマスコミでは「スンニ」をよく使っているようです。このようなアラビア語での形容詞形は、イスラーム (Islām) → イスラーミー (Islāmī、「イスラム教の」「イスラム的な」「イスラム教徒の」)、クルアーン (Qur’ān、=聖典コーラン) → クルアーニー (Qur’ānī、「クルアーンの」「クルアーン的な」)など様々な用例がある。また他方のイスラム・シーア派(Shia Islam、英語Wikipedia)の「シーア(Shīʿa)」は、アラビア語で「党派」「追随者」を意味する普通名詞で、元々は「アリーの党派(Shīʿat ʿAlī)」の略称でした(形容詞形は「シーイー (Shīʿī)」)。シーア派は、預言者ムハンマドの父方のいとこであり養子(娘婿)でもあるアリー・ブン・アビー・ターリブ(日本語Wikipedia)こそが、血統的・霊的に預言者ムハンマドの正統な後継者であると主張しています(アリーとその血統を受け継ぐ子孫たちを「イマーム(Imam)」と呼び、どこまでを正統と認めるかで分派がある)。そもそもで言えばスンナ(Sunnaの語源である「سنة(ラテン語:sunnah)])とはイスラム以前のジャーヒリーヤ時代から存在する言葉であり、”確立された道、先祖や族長の定めた伝統・慣行など”を意味する言葉であったが、イスラーム登場後に預言者ムハンマドの慣行・宗教的規範を特に「Sunnah(省略形Sunna)」と呼ぶようになり、もともとの一般的な”地域的な慣行”的な意味合いは「url(ウルーフ)」(これもジャーヒリーヤ時代からの言葉で、より広範囲な地域社会での慣習や常識という似たような意味合いだが内容は時代性で変化する)という別の単語に移っていったのだという。しかしシーア派の人々も「スンナ(Sunnah)」は重要な規範であると信じており、遵守している。例えば1日5回のサラー(礼拝)、サウム(断食)、ハッジ(メッカ巡礼)、ハラール(豚肉やアルコールの禁止)や、食べ方・飲み方などのマナーは両派共通のスンナである。ただしシーア派の人々は預言者ムハンマドのスンナだけでなく、イマームのスンナも重要視している。
- 同盟相手探し:
- オスマンは特に最初のうちは同盟相手なんかいらないほど周りには攻めやすい小国があって、人的資源も豊富であっという間に軍隊も回復するため気の向くままに攻めることが可能ですが、そのうちヨーロッパ(中欧)やアフリカへと伸ばそうとすると、とたんに相手側の同盟関係に苦しめられることになります。東欧にはポーランド・リトアニアの巨大な同君連合(特殊な形態の同盟国)もあり手出しできません。
- 小国に攻めたつもりが知らない国家が参戦してきて、気づけば大艦隊が襲ってきて艦隊半壊状態になったり、あるいは陸軍があっという間に包囲されて潰されて涙目になります。またコンピューター(AI国家と呼んでおきます)は網羅的に弱点を探して隙があれば一点突破してでも後背地を狙ってきたりします。人間は逆にこれを塞ぐのが苦手なため、できる限り穴のない攻め方をする必要があります。この時にこちらもコンピューター操作の同盟国がいれば心強いのです。この同盟国を選ぶ際には、「攻略目標の国を攻める時に一緒に動いて欲しい相手」、もしくは「自分のミスをカバーして細かく動いてくれる相手」を選ぶとよいでしょう。※これも長期的には同盟相手が一番めんどい競合になったりするのですが、ここでは置いておきます。
- 上級プレイではいろいろ深謀遠慮の上で玄人好みな国家と同盟することが書かれていますが、「まずどんなものか知りたい」という初心者の場合は、とりあえず中欧方面向けに「ポーランド」か「ボヘミア」のどちらかと、アナトリア方面で初期に頼りにしたい「黒羊朝(こくようちょう)」あたりが良いかなと思います。マムルークというのが近くで大きくて怖いのですがまず組んでくれませんし、むしろ攻略目標(ライバル)の一つです。
- ※なお同盟相手と攻める相手国との第三国を含む「間」がある場合どうするんだと思うでしょうが、AI国家は「(第三国領内の)通行許可」を勝手に取りまくって進軍してきますし、通行許可はよほどの敵対国でない限りけっこうホイホイとくれるので心配は無用です。
- 逆に攻める相手とその同盟国の通行許可には少し気を配ったほうが良いかもしれません。メニューの「メッセージの設定」で、全国家を対象に「通行」で検索すると全部表示しないになっているはずですが、これをオン(慣れないうちはポップアップかつ時間停止)にしておくと、戦争が始まると突然かなり裏手を回ってでもこっちの裏手に出ようと開戦後に進軍ルートを順番に開拓している様子がわかります。
- 同盟枠があと1つ余っていますが、これは近くにある「ラマザン」が良いかと思われます。これは戦力を期待しての同盟相手というより将来の属国候補で、そのための同盟ということになります。これは後で説明します。とにかく特殊な同盟相手だと認識しておきましょう。
- なぜラザマンかというと他に属国になってくれる身近な国はないからです。試しに近隣国のカラマンやジャンダルの外交画面を開いてみると「属国化を提案する」が✗になっているのがわかります。ホバーするとその理由も書かれています。否定的要因に-1000とか-2000となっています。これは”相手国が中核州だと考えている州”をオスマンが現在持っているためです。これを覆すのはなかなか大変(戦争をして講和で消させたり)なので特に初心者のうちはやめておきましょう。こんな身近な小国で外交枠を取っていたら年月がいくらかかっても伸長できませんので、諦めて素直に戦争で併呑するほうが良いでしょう。
- あと注意点に、「ラグーザへの独立保障」というものがあり、(組んだ覚えがないけどもゲーム設定上そうなってる)これが後々引っかかるため必ず切っておきましょう。下手に強い相手と同盟を組まれると潰すに潰せず目の上のたんこぶになります。
- まとめると外交では、同盟相手は3国(うち1つは属国候補)、忘れずに独立保障を切るということになります。
- 長々と書きましたが、結局まとめると次のように整理できるかと思います
- 攻める相手:
- 〔バルカン半島〕:ビザンツ(アテネ)、イピロス、セルビア、アルバニア、ボスニア方面。
- 〔アナトリア〕:ジャンダル、カラマン。この2国はミッションのためにも必須。白羊朝(白羊朝は比較的オスマン評価が高めだがここを攻めないとミッションが進まない)
- マシュリク(アル・ジャジーラ、イラク・アラビー、バスラ):黒羊朝、ムシャーシャ
- マシュリク(アレッポ、シリア、パレスチナ):マムルーク(属国のシリア、ファドル含む)
- 〔アラビア・エジプト〕:マムルークほかエチオピア、アダル、イエメン、アデンなどなど。
- ※恐らく攻め入る頃には相当国家の併呑が行われていると思われるが、スタート時の国家名での目安
- 同盟相手:
- バルカン以北:「ポーランド」か「ボヘミア」のどちらか。たぶん1500年くらいまでは生き残る
- アナトリア:黒羊朝(ここは拡張できれば最後は同盟を切って攻めるかも。)、後々はシャンマルなどアラビア半島で評価の低くない国と。
- 最後に属国候補:ラマザンかドゥルカディル
- ※あまり遠いと戦争に誘っても遠隔地での戦争だから…と断られる
- 攻める相手:
- ライバル国家探し:
- EU4ではライバル設定をしないと様々なペナルティがあるため、仕方なくライバル設定する必要があります。逆にライバルに攻め入る時には戦後処理で有利になります。これは忙しいプレイ中に意識して変えるなんてのは難しいでしょうから最初は使い方を覚えるために1つだけは確実に攻める相手を選ぶようにしましょう。
- まずひとつ目は「マムルーク」で良いでしょう。あとは(初回はそこまで長期間プレイしないつもりなので)適当にイングランド、フランス、オーストリア、カスティーリャなどいわゆる大国を選んでおきましょう。というかオスマンでライバル指定できるのはほぼ「列強」だけで、次攻めるからと言って弱小国を指定することは出来ません。どうせキリスト教圏国家とは仲良くは出来ないので、そこから選ぶのが良いでしょう。
- ちなみにライバルとして選んだ相手は、逆に手のひらを返して同盟を組むときにはけっこう大変になるのと(その情報が様々なところに影響する。”同盟相手をライバル視している”など)、相手もライバルだと意識して(相手側にもわかるし、自国でも度の国がライバル指定しているのかは表示される)敵対心が強まって国家行動に影響を与えますので注意。
- ここもまとめるとライバルは、マムルークと後は適当に地理的に遠い列強からいくつか。
- できればですが、同盟相手が同盟してたりする相手国は選ばないようにしましょう。相手国(の同盟)とプレイヤー国家を天秤にかけて戦争時に出撃してくれなくなったりします。ですからポーランドかボヘミアと黒羊朝の国家外交画面を時折チェックしてどんな相手と同盟を組んでいるかは確認しておきましょう。そこをライバル指定すると危険だということです。
- なお「戦力投射(Power Projection)」という重要なパラメータがあり、これを上げると君主力に加点したり、要塞の防御力が上がったりするのですが、これは「ライバル」への対応により上昇します。具体的にはライバルに攻め込んだり、そこまでいかなくともライバルに「禁輸措置」をしたり、ライバルが戦争している国に「補助金を提供」(デフォルトの最低額で良い)すると増加します。戦力投射は、威信値や正統性への加点をはじめとして、25点以上で軍事点+1と州の要塞防御加算(x0.1)、50点以上で外交点+1、75点以上で統治点+1、100点で人的資源回復速度上昇などの優れた効果をもたらします。このためにもライバル指定と対応が必要になってきます。初心者の間は攻めるというのは厳しいかも知れませんので、禁輸措置や対戦相手国への補助金は忘れずに積極的に行っていきましょう。※ちなみに日本語Wikiではこの訳語について揉めた形跡があり、日本語訳”戦力投射”で質問すると怒られるようです(だから項目自体が英語項目になっている)。怖い世界です。
- 内政:
- 君主点:
- 君主のパラメーターは「統治力、外交力、軍事力」で構成されており、これがプレイヤーのあなたが取りうる選択肢に大きく影響を与えます。

- オスマンの場合は初期君主がかなりの強力な君主でありこれで困るようだと他の君主は大変なことになります。
- 君主点は「ナショナルフォーカス」という振り分け機能があり、その君主点の再振り分けが可能になっています。ここが落とし穴で、古い情報だと「とりあえず軍事力に振れ」と書いてあったりしますが、現在のバージョンでは圧倒的に統治力を使う機会が多いだろうためナショナルフォーカスは統治力に変更しておきます。
- ※なおナショナルフォーカスの再変更には20年のインターバルが必要。恐らく次に変更できるようになる頃にはだいたい触りがわかっている頃だろうという感じです。また「軍事技術を高めて戦いを有利に」などと書かれていますが、恐らく初心者プレイの20年程度は小国や下位国が相手なのでまず負けないし攻め込まれない。というか、初心者の勉強なので負けたら(まずったところが学習できたら)素直に戦争準備開始時点までリロードです。
- 君主のパラメーターは「統治力、外交力、軍事力」で構成されており、これがプレイヤーのあなたが取りうる選択肢に大きく影響を与えます。
- 顧問:
- 宮廷画面を開くと、統治・外交・軍事の3部門に1人づつ顧問を設定できる場所があります。この顧問は金は食うけど君主力に加算して補ってくれるし、その他の影響力も持っているので、予算と折り合いをつけてでもできる限り雇用(指定)しておいたほうが良いでしょう。オスマンは初期君主が非常に優秀で顧問なんかいらないくらいですが、そうは言っても初代が倒れたあともプレイは続くため、慣れる必要もあります。
- なお顧問は宮廷に常駐している3~4人ほどの中から選ぶのですが、そのうち君主力に+1してくれるのが一般に”レベル1の顧問”と呼ばれています。+2ならレベル2と上がっていくと月額給与も跳ね上がっていきます。ここは適当に以下のようなものを選んでおきましょう。もちろん3人雇う必要はなく、一番困っているところを補ってくれる顧問を選びましょう。ビザンツ(アテネ)、イピロスを潰してアナトリア半島に進軍する頃まではレベル1で十分です。
- 統治:「インフレ-0.10」あるいは、占領した土地を安定させるために「不穏度-2」を置きたい
- 外交:開戦事由をつけるための「諜報網の構築+」を選んでおく
- 軍事:人的資源補正+、規律+、陸軍士気+、兵員補充速度+などを入れておく
- 階級:
- これもめんどくさい要素の一つで、どの国家でも3種類(+α)の階級が存在し、それぞれ領土と権限と忠誠度を天秤にかけて、隙あらば反乱を起こしてくる要素です。オスマンでは呼称が特殊で、宗教関係者は「ウラマー」、貴族階級が「ユメラ」、市民は「商人組合」となっています。Wikiなどでは、最初に土地を取り上げて忠誠心を上げるなどと書かれていますがそれは長期的な視野に立った場合です。
- 初心者が完全に無視してよいのは色々並んでいる特権一覧の条件の4項目のうち、一番右の「最大絶対主義」です。これはゲーム内年代が1600年代後半から1700年代にかけて登場しますので、「初心者プレイ」では気にする必要は一切ありません。そこまでやるのはゲームに慣れた初心者を脱した段階でしょう。
- あと君主領を減らすなとも書かれていますが、これも20%後半くらいあればあまり気にする必要はありません。どっちにしろオスマンプレイだとどんどん領土拡張していくため、基本的に領土拡張分の一定数が次々と君主領に追加される形になるからです。
- これもまとめとしては、あくまで初心者プレイの一例ですが、ユメラで「領土管理限界+100」を選び、一番下の商人階級では「借款(借金)」を選ぶと良いかもしれません。
- ※この借款は低金利で有利なので「経済」タブで銀行より借りるよりお得(あっちは金利2%)です。これで君主領土は25%になってるはずですが、まあ大丈夫だろうと思います。どうせ反乱が起きればリロードですから気楽にやりましょう。金不足で動けないのは嫌ですし、オスマンはそのうち金が溢れるくらいになるので初期だけ借りておきましょう。なおこの借金は5口が1セットなので、1口返せるからと返してしまうと完済する前に必要になっても新たに借りることは出来ません(残口の延長だけ)。5口全額まとめて返せる余裕ができるまでは素直に借りておきましょう。
- あと階級の忠誠度が心配な場合は、「議会」の招集が時々(5年毎?)できるようになり、その議題を達成することで該当忠誠度の上昇(+10)が期待できます。念の為に議会招集前にセーブしておき、議会を開きそこに「基本税/基本生産/基本人的資源をXXにする(たいてい現状+2)」(あるいは工場/教会=モスクを建てるなど)という割と簡単な開発目標が示されるものがあるのでそれを選び、あとは期限までに開発して達成するだけでもけっこう忠誠度は伸びます。※万一満足の行く選択肢がなければリロード。時々、扶養限界以上の陸海軍を要求したり、他領地の占領(布教)などかなり無茶苦茶な要求をしてくることもある(そのままでは改宗不可能な改宗を要求してきたり)ので、必ずセーブロード。乱数が変わらない場合はどこかで開発度を1個あげるなど何らかの行動をすれば変化するはず。
- ※公式でも推奨している「君主力+1」は、直轄領が下がるため3階級でやると結構な下げ幅になるかと思います(というか-10×3で直轄領0になるはず)。オスマンの場合は初期君主に恵まれているためそれは必要ないでしょう(イングランドなど驚きの0-0-0ですのでそういうところでは必要でしょう)。一度になんでも覚えるというのはなかなか大変ですから、とりあえず戦争の仕方などを覚えてから階級特権について覚えていくようにしましょう。
- 君主点:
最初の戦争準備~終戦処理まで
恐らく戦争する気まんまんでプレイ始めたでしょうが、そうはいきません。その代わりに相手も「開戦事由」ができてようやく攻めてくるのです。※オスマンの場合、時々聖戦(十字軍派遣)を仕掛けられる場合がある
オスマンの周りを見渡すと、バルカン半島には東西にビザンツの残党がおり、そのビザンツの属国としてのアテネ、あとイピロスというのが見えます。とりあえずこれらが攻める相手です。
※この「バルカン」や「アナトニア」という地域名は、地理・世界史好きなら知っているかもしれませんがふつう大体の位置はわかっても具体的にEU4のマップでどこなのかはわからないかもしれません。EU4はマップモードが豊富で、画面右下のマップパネルでいろいろなマップに切り替えできます。このうち地理マップモードの「地方」や「地域」を見ると出てきます。よく使うマップモードは、右下のマップパネルの10ヶ所に登録できます。
それ以外にアルバニア(ベネツィアの独立保障)やベネツィアがいたり、エーゲ海にはジェノヴァやナクソス(ヴェネツィア従属国)、聖ヨハネ騎士団(ヴェネツィア独立保障)がいますが、手を出すとすかさずヴェネツィアが襲いかかってくるため最初は無視しましょう。※初心者でないなら早めに手を打つ選択肢もある
アナトリア方面は、これらバルカン半島の雑魚を掃除してから進出していきましょう。
軍備と海軍整理
オスマンのミッションに「帝国軍改革」というものがあり、陸軍扶養限界の85%以上を満たせばツリーを進めることが出来ます。初めは40なので34連隊以上募集をかければすぐに満たせます。これでジャンマル及びカラマン2カ国に対しての開戦理由がゲットできます。さらに同じくミッションに「扶養限界まで軍拡」というものもあり、こっちは100%をみたせば条件達成で陸軍士気+5%、陸軍維持費補正-5%をゲットできる上、すべての隣接州の請求権までゲットできます。初期の人的資源は不足しがちですので忘れずに100%を目指しましょう。恐らく1445年末頃には請求権ゲットできるはずです。
※ただしジャンマルの方はたいていマムルークと同盟を組むため注意が必要です。なにげなく宣戦布告するとマムルークの大軍団に蹂躙されかねません。対してカラマンの方は恐らくすぐには同盟相手は見つからないので攻めることが可能だと思われます。ただ初期に気をつけなければならないのが、同盟相手がホイホイと来てくれるわけではなく、国力差を勘案して油断すると褒美(州)をねだってきます。恐らく手のひらだと思うのですが、そのマークが付いている場合には褒美をよこすなら派兵してやるということです。この場合、講和処理で自動的に持っていかれます。例えばラマザンであればカイセリという州を中核州だと考えておりこれが持っていかれます。ラマザンはどうせ後から属国→併合してしまう運命なので渡しても構わないのですが、その他の同盟国に奪われると少し厄介ですので気をつけましょう。
※なお隣接州の請求権をゲットできてもカラマンなどには停戦期間が残っているため、初手はやはりビザンツ攻めになるかと思います。
海軍整理の方は、”戦闘に連れて行く船”とそうではない”輸送船”の2つに分けておきます。最初はガレー船7隻と輸送船12隻と、小型船3隻に分かれていますが、これをガレー+小型と輸送船に組み替えましょう。これをせずにふつうに海戦を行うとボコボコと輸送船がやられてしまいます。※輸送船は陸軍を輸送する船です(戦闘できなくはないが弱い)。
※この場合の組み換え手順としては、「22」と書かれている船団を全部マウスドラッグで指定し、開いたウィンドウ一番上の「ユニットの統合」を選び、続いて下段の右側の矢印が2つ逆方向に並んでいるアイコン「ユニットの新規作成」を押して編集画面に入ります。すると新たにウィンドウが開きますので、左側の上に並んでいるアイコンの右端、”輸送船”の下の「>>」をクリックすると先程書いた通りの2つに分けることが出来ます。
このときに注意なのは、指揮官/提督を指定している場合は、彼らは引き続き左側のユニットを率いるということです。右側の新規作成ユニット側には指揮官/提督はいなくなるので注意が必要です。特に海軍は港にいるときにしか提督の指定ができませんのでご注意ください。陸軍は自領地あるいは占領地なら指定/変更可能。
※なお小型船が入っている船団は、艦隊ミッションの「交易の保護」をすると収入を微増することが可能です(アレキサンドリア交易ノードで+0.13)。しかし初期の交易力では恐らく艦隊維持費の方がかさんでしまうため注意しましょう。また交易の保護を行うと海軍伝統の微増しますのでおすすめです。
開戦の予習
手始めにビザンツを右クリックして外交画面を開き、おもむろに「宣戦布告」をクリックしてみます。
※この宣戦布告画面の確認作業はとても大事です。開戦準備段階から何度も開いて、本当に準備万端なのかどうかを確認するようにしましょう。いま宣戦布告したらどんな同盟国が参戦してくるのか?その場合の侵攻ルートはどのあたりになるのか?その対策はどうするか?外交で敵は減らせないか?といった様々な対策を打ってから宣戦布告するようにしましょう。
すると大きな「宣戦布告」画面が表示され、開戦にあたっての条件などが細かく表示されます。これは非常に大事な情報ですのでじっくりと読みましょう。戦争はこの画面でほぼ成り行きが見えると言っても過言ではありません。この画面で勝利が確信できてから「確認」ボタンを押して開戦(宣戦布告)するようにしましょう。

一番上に「侵略的拡大」とデカデカと書かれています。開戦事由もなしになっています。要するに気分次第で大義もなく攻めるのは許さんぞ?という話です。この侵略的拡大は後々きちんとペナルティとして国内政治/外交の様々なところに響いてきます。
その代償として、「安定度-2」もされると書かれています。プレイしていくと痛感しますが、安定度-2というのは、最初期の初心者プレイヤーにはとてつもなく大きなペナルティです。ゲーム初期の安定度は恐らく1か2でしょうが、もしマイナスになろうもなら恐ろしい大ペナルティに発展します。
※この安定度が下がると、各地で反乱軍(農民軍や~僭称軍)が次々と乱立して国内は無茶苦茶に占領されまくります。一つ討伐したと思ったら次が勃発し…と反乱軍つぶしで数年かかったりします。反乱軍はあらかじめ予備行動できる場面以外では起きないに越したことはありません。
一定程度慣れると、余裕があるタイミングでダイアログが出た時には陸軍をその予定地(右側の「概略」ウィンドウに反乱予定地と兵数が表示されるので90%近くになったら待機)に移動させておきOKをクリックすると同時に反乱軍出現&討伐完了に持っていけるようになります(これで”最近の蜂起”がついて不穏度-90とかにできる)。戦間期にこういうガス抜き作業をやっておくと国内は沈静化出来ます。
その下に「敵側同盟国」と書かれており、敵側にアテネも参戦することがわかります(従属国アテネには選択権はない)。そして参戦総兵力がその下に書かれています。右側の総兵力は自軍側。この例では自軍側は空っぽですが、同盟を組んでいるとここに表示され援軍可能となっている同盟国に対してチェックを入れると援軍を呼べるようにもなります(戦争中にも参戦要請が出せる)。むしろ相手側援軍を抑える目的で裏から叩くために呼ぶことも有効かと思います。もし同盟国が参戦要請出せない場合は、「✕」にホバーして断る理由(遠隔地であるなど)も確認しておきましょう。※相手国は弱い同盟国・属国を狙うポリシーがあるため、開戦後すぐの疑似餌的な使い方もできる
この例では兵力差を見ればもちろん余裕で勝てるのですが、戦争は楽勝に見えても包囲戦で1年かかったりと甘く見ると痛い目に遭うこともあります。もっと楽に、確実に、ペナルティを最小限にして1000%勝てるところまで持っていってから開戦しないといけません。その1つ目が次で述べる開戦事由の創出です。
※なおここで注意なのが、DLC込みのEU4では1444年開始直後(数日~長くとも数ヶ月)辺りに特殊なイベントが発生し、オスマンはビザンツへの開戦事由を得ます。すると侵略ではなく一応の開戦事由ができ、いわば正々堂々と侵略できます。しかしバニラではどうもそのイベントが発生せず、独自で開戦事由を付ける必要があります。
開戦事由の創出
このゲームでは、それぞれの戦争に開戦事由(Casus Belli。よくCBなどと略されている)が必要です。それ無しに攻めこむと、上で書いたように手ひどいペナルティを食らうことになります。
それを創出(でっち上げ)するのが「請求権の獲得」になります。請求権というのは、要するに相手側の領土Xは本来俺のものだとでっち上げることでそれを宣戦布告の大義にするというものです。無茶苦茶ですが、それでもEU4の世界ではこれで一応紳士的な戦争をするようにはなります。
[諜報網構築] → [請求権捏造] → [宣戦布告]
まず相手国の外交画面を呼び出し、「諜報網を構築する」を選ぶとすぐに空いている外交官が1名派遣されて、数カ月にわたって常駐して工作活動を行い諜報網が構築されていきます。これが一定量(普通の相手だと20で捏造できる)貯まれば、外交画面から「請求権の捏造」の実行にチェックマークが入りいつでも宣戦布告できるようになります。
応用1:侵略的拡大と再征服
なおこの請求権獲得は「征服」という開戦理由であり、調子に乗って征服を続けていると、”侵略的拡大”というペナルティを受けます。※正確には侵攻ごとに少しずつ貯まる
これは自国側のパラメータではなく周辺国側で自国に対して持っているパラメータで、後述する「応用4:現状の外交関係を認識する」での外交-評価マップで確認できるものです。各国ごとに自国の侵略的な拡大を数値として持っており、一定以上蓄積すると「包囲網」が構築されたりします。こうなると弱小国を攻めるつもりが周囲一帯の国家を相手にして攻めなければならず非常に不利になります。
※また請求権獲得は、かなり計画的に行わないと諜報網構築に時間がかかりすぎて非効率(長期間貴重な外交枠を使ってしまう)。
この「侵略的拡大」をあまり貯めないための開戦理由が「再征服」です。これは”一度奪われた中核州を取り戻す”目的で行う戦争であり、属国が中核州を持っている場合等に非常に有効な開戦理由となります。通常の征服が侵略的拡大100%評価のところ、再征服ならその州に限って25%評価になります。(つまり請求権構築の手間もなく、侵略的拡大ペナも少なくなるという一石二鳥)。
このいわば埋没した再征服国家を探すのはある程度慣れれば簡単になりますが、最初はどの州を誰が持っていたかなど把握できないため、これから攻めようとする国家の州を一つずつクリックしては、人口統計の下にある「中核州と請求権」の欄を見てみましょう。※要するに今から攻める国の”次に攻めたいところ”の請求権(中核州)を持っている国家を探し出します。すると(グレーの国旗で)既に滅んだけど”中核州の記憶”のようなものが残っているものがあります。
※オスマンプレイなら、既に首都にしているコンスタンティーニーイ州をクリックするとビザンツなどが残っているはず。
例えば下図はオスマンプレイでマムルーク領の州を見たときの図です。赤くモヤっと囲まれた範囲が旧シリアの中核州です。既にマムルーク属国だったシリアは併合されていますが、中核州の”記憶”が残っているのがわかります。これを残党のように独立させてやる代わりに、彼らが持っている請求権を「再征服権」として利用するということです。

こういう国は講和条件で独立国として開放させた後に同盟して属国化することで、その「再征服権」を宗主国であるプレイヤー国が入手できます(だいたいすぐに同盟できるので後は”関係を改善”等で190まで持っていけば属国化可能で即座に再征服権ゲット)。オスマンを攻める側で言うとビザンツ、モレア(ビザンツ属国)、シリア(マムルーク属国)などがこれにあたります。
※特に文化ごとの一次国家(Primary Nation)の再征服権は消えることがなく非常に強力です。ブルガリア文化のブルガリア、シリア文化のシリア、イラク文化のイラク、チュニス文化のチュニスなどがこれにあたるそうで、他の文化にもそれぞれ存在します。その他のプライマリーではない国家の場合は、50年あるいは150年(同じ文化グループ国家支配の場合)で消滅します。
※中核州情報欄には、一次国家の場合には例えば「ブルガリアはブルガリアの代表的な国家です。~~を中核州として失うことはありません」等と書かれており、一次国家以外の場合は「xxxx年にこの州は彼らの手中から滑り落ち、彼らの中核州ではなくなります云々」と書かれています。この情報は非常に重要だということを覚えておくとよいでしょう。こうした細かい情報をきちんと記録しているのがEuropa Universalisならではのリアルさを感じさせる部分でしょう。なんの脈略もなく反乱が起きても「なんだこれ」となるだけですが、その地域の残党が残っているんだというイメージは非常に納得感があります。それを数値主体な世界規模シミュレーションゲームで実現するところが憎いですね。
もちろん一度自国中核州化したあとに外交画面から従属国作成で属国化した場合でも、同様に再征服権が獲得できます。利用する際には、マムルークとかの大国だと何度かの戦争が必要ですから、その1回目の講和で上記スクショの赤いもやっとした州のいずれか1つ(例えばアンターキヤー州・ハラブ州・アッ=ラッカ州のいずれか)でも良いので忘れずに必ず押さえて領有します。それを戦後に外交画面の一番下から属国作成すると、赤いもやもや範囲の州が中核州となり、次の戦争の講和画面で戦勝点の消費を押さえて一気に領有できるようになると言う手順です。
しかしこの場合、過剰拡大ペナも自国で払った上で中核化コストを自分で払った後に開放するため二度手間になります。それよりも講和条件時に独立→同盟→属国→再征服の方がだいぶ楽だ(過剰拡大ペナも軽減できる上に侵略的拡大ペナが減少する)ということがわかるでしょう。特に大きな国(オスマンやマムルークなど)を占領していく場合に、手っ取り早く力を削っていける(しかも侵略的拡大を食らいにくい)のが強制的な独立国化で、その次が属国の譲渡、さらに中核州からの属国作成(からの次回で再征服)になるかと思います。これらを組み合わせて効率的に少ない戦争回数で占領していきましょう。
講和をするときにはとりあえずセーブして(これから攻めたい国との境界付近の)従属国を作成してみたり、過去セーブデータなどに巻き戻しながら中核州情報を確認していくと発見があるはずです。言うまでもないことですが、属国の独立欲求管理が必要でかつ属国内で反乱も起こるため注意は必要です。手放しで楽して攻められる手段というわけではありません。
応用2:過剰拡大と属国餌付け
戦争がどんどん進むようになると、恐らく次に困るのが「過剰拡大」でしょう。戦争で勝ったら「全部俺のもの」とやっていくと、戦争のたびに過剰拡大が膨大な量になり、その戦後処理で1年以上を費やす羽目になります。おまけにあちこちで不穏度が上昇して反乱が勃発するしで溜まったものではありません。
そこで活用したいのが属国です。上の応用例で創出した属国などを次の戦争で活用し、戦争で得た土地はまず属国の領土としてしまい、戦線が先になって伸びすぎたら併合してしまう方が結果的に総コストが安く上がるのではないかというのがこの考え方で、EU4プレイヤーの間では相当古くからあるかなりポピュラーな手法のようです。
例えばオスマン初期に白羊朝を攻めた講和時に、占領した土地をラマザンに移しているところです。この占領州譲渡は、講和画面ではなく通常の州画面から行います。※厳密にはこの時点では属国ではないが属国OKフラグは立っている

こうして占領地譲渡を行ってから講和画面でその州をクリックすると、占領譲渡した州については自国ではなく属国に渡ります(もちろん同盟国にも譲渡可能)。こうして自国の過剰拡大を抑えるのです。もちろん中核化作業なども全部属国が担当することになります。いざとなれば属国後10年経てば併合できますので、育ちきったら折を見て併合してしまうのもありでしょうし、そのまま遊軍としてこき使うのもありでしょう。
※ただし肝心の属国側が「それを望まない」とか抜かして(失礼)受け取らないことがありますので、戦勝点が100になった時点で(講和画面に入る前に)「必ずセーブ」をするようにしましょう。占領譲渡したはいいものの受け取り手がなく(譲渡しちゃってるので自領土にはできない)泣く泣く敵国に戻すハメになりかねません。講和画面にはどれだけ時間をかけても惜しくないと思うくらい重要ですから、開戦前以上にセーブロードが必須です。
ただし「過剰拡大」が押さえられたからと言って併合してしまえば、けっきょく「領土管理限界」の壁で苦しむことになります。とはいえ自領もある程度増えないと相対的な力の差で属国の独立欲求は上昇しますので、現在の過剰拡大値や今後戦争を進める方向なども検討して譲渡州を決めていきましょう。※属国の独立欲求は、宗主国との相対的な総開発度差や軍事力差(その他外交的要因など)などをベースに上昇しますし、このあたりは権勢アイデアグループなどを取っているかどうかも影響してきます。
宣戦布告
そうすれば念の為に先程の宣戦布告画面を呼び出し、想定参加国や兵力に変動がないかを再確認します。相手側が同盟関係を強化している場合もあります。
別の攻略時ですが、これが初期としてはまあまあ手を打てた宣戦布告画面です。

開戦事由もちゃんとあり開戦ペナルティは一切なしです。属国たちも当然参加です。戦力差は9倍あり、人的資源も圧倒的で長期戦も戦えるでしょう。ミスを侵さない限り楽勝も楽勝でしょう。※後の「応用1:個別講和」のときの開戦画面。属国のうちラマザン以外はアラビア半島の2国で裏側から攻め込み挟み込むことを期待。
また焦らずに旅団ごとに攻め込む州の想定も行っておきましょう。相手が何部隊ほど出てきて、それらはどのような進軍ルートを辿って自領地へと攻めてくるのか?その時に裏でカバーできる兵団も用意しておきましょう。
※今回のビザンツでも複数州あるため裏をかかれる可能性を頭に入れておきましょう。複数州がある場合、敵は最後のあがきで一時的に兵を募集して前線を離れて裏をかいくぐって進軍してくる場合があります(このあたりが結構冷めるところではある)。あるいは戦争中に敵方に反乱軍が登場し、その反乱軍が占領済の相手州やあるいはこちらの領土に攻め込んでくることもけっこうあります。油断しないように、最低限の兵力で、逃さず確実に抑え込みに行くようにしましょう。またビザンツは初期海軍が結構多いため、艦隊は出さずに港で待機しておきましょう。左右前領土を制圧すれば100%取れるはずです。
なお同盟軍は心強い味方ではあるものの、こっちが敵主力と戦っている間にわざわざ向こう側からこっちに回り込んだ上でこちらが狙っていた州を真っ先に奪った上で、こっちが中核化できない奥地だけ残すなどの行動も平気でやってきますので(まるでプレイヤーのようですがAI国家は結果が気に入らなければ普通に同盟を切ってきます)、油断のならない同盟国の場合にはまず自分で狙っていた州を占領開始したあとで「参戦を要請!」してやりましょう(一番先に取りついて占領まで残れば包囲兵力に関係なくこちらの占領となる)。開戦画面で呼べる同盟国は、だいたいあとからでも参戦要請できます。
想定通りなら、とりあえずセーブを行ってから自軍兵力をさりげなく敵領地隣接州へと移動させます。予算削減をしている場合は陸海軍の予算もフルに戻しておきましょう。配置が終わったら時間停止。将軍の設定も忘れずに(占領中州を除いて他国にいる場合は将軍設定できません)。請求権の捏造→成功しました!(少し時間を進めて停止)→宣戦布告!で戦争が始まります。
宣戦布告できたら即座に時間停止を行い、予定通りに進軍ルートを指示してから時間を進めます。いろいろポップアップが出たりしますが、慣れない間は焦らずにスペースで時間停止をして一つずつ確実に処理するようにしましょう。
初心者のうちは、最初は小手試しだと思って巻き戻し(リロード)前提で進めましょう。一度「戦争(侵攻作戦)のシミュレーション」を行ったあと、(例えば兵力不足を感じるなら事前に徴兵したり、傭兵を雇うなど)万全な対策を打ってから実践に移すでも良いでしょう。それこそシミュレーションゲームですから何度でも巻き戻しが可能です。
※ゲーム実況や動画公開をしている方ならともかく、個人でオフラインでプレイしている限り、何度巻き戻しても一切恥じることはありません。なにしろ悪名高い”彗星イベント”(どれを選んでも最悪な結果が確定)など平気でプレイヤー不利なイベントを起こすゲームなので、何も遠慮はいりません。むしろ戦争中に次々と不利なイベントが起こるようならそれはプレイヤーの戦争準備が万事周到だったという傍証になると思うくらいに、結構不利なイベント(君主が死んだり、跡継ぎが死んだり、正室が不倫したり、貴族が反乱したり)が連発する場合があります。「めんどくさ」と思ったらすぐ巻き戻して乱数表を変化させてイベントを回避しても良いでしょう。「楽しくプレイできなければゲームじゃない(個人的主観)」ですから遠慮なくやりましょう。
戦争の経過
野戦や包囲戦で勝つたびにリアルタイムに「戦勝点」というものが溜まっていきます。恐らくオスマンプレイの場合、イケイケドンドンで戦争を有利に進められますから、減ることもなく勝手にずんずん溜まっていくでしょう。
これが(20%、30%、40%など)一定量溜まったら、とりあえず時間停止を押して画面下右側にある盾状のアイコンを「右クリック」して終戦処理(講和条件)のシミュレーションを行います。
通常は領土割譲が目的ですから、欲しい相手方の州をクリックして赤色から緑色に変えていくと「その時点の要求で必要な戦勝点」がリアルタイムに計算され、戦勝点が足りているか、不足しているかがわかります。
この時に戦争後の互いの領土がどう変わるかをイメージして、できるだけ価値の高い(商業地・商業都市・世界的貿易港や、交易州だったり開発度が高かったり)州を取り込み、なおかつ相手方を不便な土地へと押し込めるようにクリックしていきましょう。
これを何度かやるとわかりますが、一定数の州を持つ相手(たとえば対マムルーク)の戦争では、一度の戦争ですべてを占領して割譲させるのは無理だとわかってきます。いくつかの州をクリックすると「戦勝点100点を越える要求はできない」云々という表示が出て、それ以上州がクリックできなくなります。するとそこ(合計95~99か100)までが今回の戦争での目標範囲(目標戦勝点)ということになります。
※一度講和すると10年間の停戦期間が発生し、互いに攻め込むことができなくなります。3回攻めて全部取れたとしても2回20年の停戦期間を含みますから、30年近くをかけてようやく全部攻め取るということになります。当然こんなまどろっこしいことはやってられませんので、同盟など外交を駆使してあの手この手で参戦し、参戦させて攻めていくことになります。
後はその目標戦勝点になるまで戦争を続けていきます。敵が1州しか持っていない場合には、包囲戦で勝利すると一気に100%になります。
※いつまでも100%にならない場合は、参加同盟国の領土がまったく占領できてなかったり、あるいは盲点ですが船団が残ってたりしても戦勝点は進みません。参戦した同盟国がいる場合、その領土や所持兵力もすべてが戦勝点対象となり(要するに最初の宣戦布告画面で計算されていた総兵力)、多く残っているとなかなか伸びなくなります。※占領している時間経過で徐々に伸びるが年単位で時間が溶けていく
・幸いオスマンには強力な船団がありますから、戦闘海域に出しておけばそうした「漏れ」も無くせます。相手側の港を含む州を攻める時には海域に待機(港封鎖)させておいて一気に敵海軍をたたき潰したり、もし敵同盟側に強力な海軍(ヴェネツィアやマムルークなど)が出てくる場合にはあえて自海軍は港に待機させておいたり(船団には”戦争時は港に避難”指示があったりするし、また港にいる船はその州が占領されない限り安全)。このあたりも慣れが必要です。酷い話ですが同盟軍にまず削らせておいて、ある程度減ってから自軍が出ていくという戦い方も十分有効です(ただし対等な立場の同盟軍だと戦勝点分配上不利になったりする)。あるいは自同盟軍の出動(さすがに突然宣戦布告するので少し遅れる)を待って一緒になって叩くというのももちろんありです。同盟軍といえども明日はどうなるかわかりませんしお互い様です。ただし属国についてはある程度手ひどい負け方をしないように気を使う必要がありますが。
・またゲーム的には領土を要求しない「ライバルに恥をかかせる」という開戦事由もあり、その場合は領土割譲要求は出せません。徹底的に叩いて満足したら賠償金をふんだくって帰りましょう。
オマケ:輸送艦での陸軍移動の仕方
若干わかりづらいのが海軍の輸送艦を使った陸軍移動の仕方だと思われます。自動輸送の場合は良いのですが、オスマンなどのような複数海に輸送艦を所有して移動する場合、どの艦隊を使うのかが問題になります。この時、EU4のシステム自体は「できるだけ大部隊を輸送できる艦隊」を割り当てようとして、地中海での移動にも関わらずホルムズ海峡にいる艦隊をアサインしようとします。そうすると(スエズ開通前は)糞真面目にアフリカ西岸を回ってでも割り当てようとしだしますが、さすがこれはムダすぎます。というか輸送艦隊が沈没するでしょう。※艦隊アクションで「自動輸送を禁止する」という設定もあります
これを指定の艦隊に割り当てるのが、やや癖のある操作になっています。
- まず輸送に割り当てたい艦隊(輸送艦を含む艦隊)を輸送したい陸軍近くの沿岸州港に移動させる
- 輸送したい陸軍もその沿岸州へと移動させておく
- 両者そろったら、陸軍のウィンドウを開いて右肩にある「乗船」アイコンをクリックする
※これで割当が行われる - 続いて輸送艦側を輸送したい沿岸州へと移動させる
※すると陸軍も一緒に移動する。輸送艦隊に輸送陸軍情報がくっつく形になる - 輸送先に着いたら、輸送艦隊の右肩にくっついている陸軍を選択し、移動したい沿岸州を指定すると陸軍が勝手に下船して沿岸州へと移動する
※なお輸送してきた輸送艦隊は海上に残ったりするため、油断せず港に入れたりすること
なお移動するのはだいたい戦争中であるため、無防備な輸送艦隊だけをゆうちょうに移動させてると、どこからともなく現れた敵艦隊の餌食になったりする可能性が非常に高いです。できればですが、できるだけ同じ海域での(最短距離)輸送にとどめ、同時に自国艦隊本体をその海域に待機させておくと安全に輸送できるでしょう(もちろん艦隊本体に輸送艦を入れてしまっても良いが、やはり本格的な海戦になると不安が残る)。また戦争時にこの操作を全部やるのは大変なので、輸送・上陸が必要な場合には、事前に沿岸州へと陸海軍ともに移動し、乗船割当までは行っておくようにしましょう。
※なお海戦について、同じ規模の艦隊を用意しているのにボロ負けする場合には、次の点を注意しましょう。1.まず輸送艦を分離しておくこと。2.次に戦争が始まったからと行って即座に出さず、敵艦隊の動きを十分観察する(大型艦や小型艦・輸送艦の割合はどれくらいか、どこの沿岸州を閉鎖しようとするか)。3.勝てる見込みがあるなら、必ず提督を割り当てたあと敵が閉鎖している海域へと出動する。4.一度海戦を行ったら必ず消耗を確認し、90を割っているような艦があれば必ず近くの港へ入港して消耗を100に戻すこと。輸送艦は規模が大きくなれば海域閉鎖も可能ですが、相手側の艦隊が出てくれば餌食になりかねませんので無理はしないようにしましょう。
また海峡を渡る必要がある場合には、開戦前にできるだけ移動しておき、「海峡閉鎖されて陸軍が移動できない!」ということがないように移動準備しておきましょう。ダーダネルス=ボスフォラス海峡、ジブラルタル海峡、ホルムズ海峡、バブ・エル・マンデブ海峡などが要注意です。またAI国家は、この海峡を巧みに操って鬼ごっこを仕掛けてきますので、艦隊に余裕ができた頃には、必ずこれらの海峡を抑えて同盟軍を含めて陸軍移動に支障が出ないようにしましょう。またアフリカやホルムズ海峡付近に進出できた場合には、この海峡付近から抑えて要塞を建築することで、鬼ごっこを塞ぐのに有利になります。
終戦
望み通りの領土割譲ができるまで戦勝点が溜まった場合には、割譲要求の他に、さらにダメ元で金銭要求欄の「+」上で”Shift+左クリック”してみます(可能最大値要求)。もしかすると(要求する領土割譲に加えて)金銭がふんだくれるかもしれません。こうやって領土割譲+余剰戦勝点分は金銭で埋めるというのが戦争での毎回の行動になります。金銭をゼロに戻すには「-」の上で”Shift+右クリック”。
それ以外でも、下記のような条件と組み合わせることも可能です。
- 相手の中核州を別の国家に引き渡す(放棄・返還)
- 従属国の開放、国家の開放
- 何らかの条約を切る(同盟関係・ライバル関係など)
- それ以外の個別条件(個別請求権放棄・交易力の移譲強要・属国化)をつける
ぐちゃぐちゃになってわけがわからなくなった場合は、一度「白紙に戻す」して再度条件を指定していきましょう。なお「和平案の自動作成」はたいていロクな内容にならないのでおすすめしません。最適解なんでしょうが、人間的には先にこっちの港湾州を抑えたいとか、交易力のある州を抑えたいとか、相手領土を分断させたいとか、もしくは交易力低くていいからできるだけ多くの州を抑えたいとか局面により色々作戦がありますが、コンピューターの自動作成和平案はそういうのは一切考慮してくれません。
応用1:個別講和
自分から仕掛けた戦争で、なおかつ相手側からいっぱい同盟軍が来ている場合(従属国ではなく同盟国に限る)は、それらの付いてきた国と個別に講和して撤退してもらうことも可能です。これにより向こうの戦力を大幅に削ることが可能です。※戦勝点も再計算され変動する
講和画面の右側に相手国のシンボルがズラッと並びますが、この1番目が対戦相手で、2番目以降が呼び出された同盟国です。戦勝点がある程度(20~50など相手国との関係性や戦闘結果などによる)進んだ時点で、これらを選択してから講和を試してみましょう。これは金銭を要求してもいいですし、あるいはきつい状況(例えばキリスト教圏が大挙して来ている場合など)なら無条件講和でも構わないでしょう。
例えば↓の画面では相手側は同盟軍が参戦しており、戦勝点88%とかなり進んだ状態です。攻めているのはシルヴァーンという弱小国で、引きずり出したのがアジャム(後のペルシア)です。

ここで下側の相手側同盟軍(アジャム)をクリックしたのが下の画面です。確かこの場面ではアジャムの抵抗が予想外にめんどくさくて(裏に回り込まれた)先に個別講和を選んだんだと思います。

すると戦勝点も切り替わり、細かく見るとぶんどれる領土も(並びが)変わっているのがわかります。
※これは宣戦布告時に相手側同盟軍にチェックを入れて州をぶんどれるように設定していたためですが、そうしていない場合でも倍の戦勝点を支払ってぶんどるか、あるいは金銭講和で(あるいは無条件講和でも)相手を減らすことが可能です。
あるいは、最初からこちらの同盟軍が目標で、あえてその同盟先弱小国を攻めることで本当の目的国を引きずり出してきて領土を奪うという戦争の仕方も可能です。たとえばヴェネツィアを相手にすると大量に強敵同盟軍を引き連れてくることが多いのですが、そのヴェネツィアの同盟先の(かつ同盟国の少ない)弱小国を見つけておいて、その弱小国に宣戦布告することでヴェネツィア「だけ」を引きずり出すということも可能といえば可能です。ヴェネツィア領土を奪うには倍の戦勝点が必要ですが、それでもかなり楽になる。
そうやって敵を減らした後に、本来の敵との講和条件に臨むわけです。
とにかく邪魔なところからチマチマ個別講和をしかけて削れる戦力は削っていきます。そうして本当に相手したい国だけを残して完全に近い勝利を目指しましょう。
こうして様々な手管を通じて領土拡大を進めていけるのが本作EU4の魅力のひとつだと言えるでしょう。
応用2:様々な講和条件(中級以上を目指して)
州をぶんどるだけが戦争ではありません。「戦争で州を勝ち取らずにどうするんだ?」と思うでしょうが、初心者はそれで良いのですが、ある程度戦争に慣れてくると「いかに効率的に領土拡大を行うか?」という面を重視せざるを得なくなってきます。
事前準備を進め、戦争を有利に進め、講和条件では相手の州を全部ぶんどってを繰り返していると、「侵略的拡大」のペナルティを受け、列強などから目をつけられ、あまりに酷いと「包囲網」が構築されてしまいます。これは長期的に見ればかなりまずい状況です。
また全部領土化すると中核化するのに君主点(特に統治力)を膨大に消費し、不穏度の上昇と反乱軍勃発に怯えながらステート化・再コア化を行う必要が出てきます。これではあまり効率的とは言えません。
ではどうするのかと言うと、使える手段を全部使うということです。よけいな占領政策で時間と貴重な君主点を消費せず、一度属国化し、その属国に領土の管理をやらせつつ戦争に駆り出してこき使うというのが比較的効率の良い手段です。属国化から10年経てば併合も可能です(もちろんペナルティというか他の属国への悪影響がある)。
※ただし併合には時間と、ある程度の外交点を継続的に消費し、他の属国への大きな影響も出ます。また併合過程中には戦争に参加しなかったり、敵国から狙われたり、敵国から独立支援を受けることもあり、独立欲求が高まれば併合が中止されたりといった様々なペナルティは存在します。なんでもかんでも一度属国化して後でガチャンと併合すればいいというものでもなく、外交的に安定している時期に行う必要があります。もちろん属国のままにしておく選択肢も十分存在します。
また属国化した属国がその隣接州に請求権を持っていることがままあり、その請求権を使ってさらに戦争を進めるということも可能です。
※つまりある国を占領して属国化目的で講和するときには、「中核州の放棄」をせず、「属国要求」を出した上で「(あれば)自国へのすべての請求権の放棄」を指定すれば良い。すると属国の独立欲求を抑えられ、なおかつ属国が持っていた第三国への請求権を活用して次の戦争をすることができるでしょう。もし「中核州の放棄」をしてしまうと、その国が第三国に持っている請求権まで放棄してしまいかねません。この請求権管理は重要で、戦争を始める前には自国の請求権を用意するのはもちろん、攻めようとする国の同盟関係やそれぞれが持っている請求権の関係をしっかり確認するようにしましょう。
その他講和条件の中には、中核州の放棄(再征服権を奪う)、その国がいままで併合してきた隣接州の現存元国家への(州ごとに)返還であったり、従属国の開放、国家ごと開放(過去に併合・併呑した国家を占領州から独立させる)、条約破棄(同盟・ライバル)、敗北の容認・軍事通行権強制・請求権放棄・交易力譲渡などがあります。今後のあなたの戦略や周辺諸国との関係性などを考え、とりうる最大限にうまく組み合わせて講和を成功させましょう。
※「国家ごと開放」はどんなメリットが?と思うかも知れませんが、”併呑されていたのを独立させた恩義”(この補正値が100くらいある)を感じて比較的友好な状態で独立するため、すかさず同盟を結び、通行権などを与えながら「関係を改善」して190まで持っていけば属国化可能です。さらに併呑された国は概ね中核化元領土を持っていることが多く、これを再利用すれば再征服という低コストな領土拡大が可能になります。※上の「開戦事由の創出」で説明した”再征服”。
全部領土化して中核化してだと膨大な君主力と領土管理限界と時間コストが必要で、さらに侵略拡大ペナルティも受けますが、「属国化+再征服」ならそれらを抑えて一石三鳥くらいで領土拡大が出来ます。周囲の国を併呑して大きくなった国は比較的これで削りやすいと言えます。もちろん自国領土と仮想敵国との位置関係などを十分考慮して選ぶようにしましょう。
応用2-1:「国家ごと開放」の実例
小さい国なら丸ごと属国化も可能ですが、20州など広めの領土を持つ国家の場合にはいきなり属国化もできません。こういう場合には国家ごと開放した後に自国の属国化を目指すのも手です。
例えば下記は、同盟国ボヘミアと共に邪魔なハンガリーに怒りの鉄槌を食らわせた講和画面です。

これを試しに領土を分割して首都ペストも押さえて…とほしいままに領土要求をした画面が下記。小さくて見えないかもですが、「侵略的拡大は最大103.1」もあります。かなり危ない数値ですね。

この時点のハンガリーは30州弱もある大国のため、頑張ったところでこれだけしか押さえられず、なおかつ侵略的拡大の効果により、今後北側では同盟を組むことも困難となり、ほぼ単独で侵攻を進めることになります。下手をするとボヘミアからも同盟を切られてしまいかねません。
ところがこれを仮に2つの独立国に分割した上で、余りの戦勝点で1州だけを取得した場合は、「侵略的拡大は最大9.7」に収まっています(これは再征服ではなく通常の征服戦争)。その割にしっかりハンガリーの勢力は削ぐことが出来ました。※それ以外に同盟国ボヘミアの南下を塞ぎ、対ヴェネツィア向けの前線基地も確保するという狙い

自国で占領するケースに比べるとどうでしょうか。
※ただし注意点としては、オスマンプレイでのこれら2国は宗教が異なり婚姻できませんので、関係を改善したからと言って直ちに属国化することは難しいです。ですからこのケースでは主に「侵略的拡大」を回避するメリットに留まります。もちろん独立保障をしている同盟国として動いてはくれるでしょうが、これが宗教の壁です。
オスマンの場合には、主に南進東進(イスラム教スンニ派が多数)した場合にこの手法が使えないかを積極的に検討すればよいかと思います。例えばマムルークやアジャム(ペルシア)は、あなたが攻め入る頃には多数の国家を併呑しているはずですから、「主権国家として独立→属国化→再征服」をうまく活用して行くようにしましょう。属国化+再征服ならば領土限界も圧迫せず侵略的拡大の評価値も25%に収まります。ただし便利だからと属国開放をやりすぎると外交関係上限を圧迫してしまいかねませんのでご注意ください。
応用3:単独講和
あと意外に分かりづらいのが、「同盟軍に呼ばれて参戦した場合の終戦処理(単独講和)」です。実は呼び出した同盟軍が終戦処理に入る前に単独講和が可能です。呼び出されていったのに突然戦争が終わってしまって、何ももらえずスゴスゴ帰ってませんか?実は同盟軍に呼び出される戦争ほどオトクなものはありません。外交下準備が一切不要ですし、めんどくさくなったら(あるいは望みの州が取れたら)途中で単独講和すら出来てしまうからです。※ただし同様に停戦もつきますのでご注意ください。
ある程度(戦勝点60~80)進んだら、とりあえずセーブしましょう。これは同盟軍がどのタイミングで終戦するかわからないためです。
そしてそのタイミングで講和画面を呼び出し、試しに自分の欲しい州などをカチカチとクリックしてみて要求がどこまで通るかを確認します。呼ばれた時点での想定通りならそこで単独講和しても構いません。もちろんお金もきっちりふんだくっておきましょう。できれば最後の戦勝点99まで粘ったほうがいいのですが、何度もリロードするのがめんどくさい場合は自分の欲しい州を押さえられたらさっさと和睦して撤退するのもありでしょう。長期出兵は戦争疲弊まで喰らいますし。
※また戦況によっては州をぶんどるのが難しい局面もあるかと思います。しかし絶好の機会ですので、相手の海軍を削っておいたり(陸軍が人的資源で復旧できるのに対して海軍は再度建造する必要がある)、お金をふんだくったり、あわよくば条約関係に口出したりしましょう。
ただし呼び出した同盟国からは「単独講和」をしたことでペナルティというか悪感情(-30~-35とか)が付いてしまいます。最悪相手国の欲しかった(戦争目的だった)州を完璧に奪ってしまうと、いきなり同盟を切られることもあります(怒らせないように一応脇の方や、戦略的に重要な州に絞り込んで押さえる)。怒らせてもいい相手なのか、もしくは長期視点でそこまで欲しい州なのかをちゃんと考えたうえで単独講和しましょう。
※相手国の外交画面からハートマークの右の数字にマウスカーソルを合わせると細かい評価式が表示されますので、そこで確認しておきます。相手との関係で同盟を続けたいならば「関係を改善」しておきましょう。
応用4:現状の外交関係を認識する
初心者の段階だと「自国と相手国の関係性」だけに注目しがちですが、現実世界でもEU4の世界でも、国際関係というのは”多対多”の関係性で成立しダイナミックに動いています。それを理解し、ある程度認識しておかないと「あれ?なんでこいつ参戦要求に応じないんだ?」とか「この同盟国、気づいたら相手側に入ってやがる」てなことになりかねません。「同盟を組んだから最後まで安心」というわけでは決してないのです。※なお基本ルールとして、両者と同盟を結んでいる国家は防衛戦争側に回る。
これを知るには主に2つの手段があります。
- まずは「評価」マップ:外交-評判マップモードにしてカチカチといろいろな国をクリックすると、その国に対して(全世界の)周辺国家がどのように評価しているかがグラフィカルに表示されます。ある程度拡張した後にこれを確認してみると、周辺国はあなたの国家に対して「侵略的拡大をしている」と判断し微妙に黄色から赤に近づいたりしているはずです。また他国をクリックしてみるとその国に対する外交的評価を知ることも出来ます。いわば「外交マップ」の詳細版とも言えるかと思います。同盟相手と第三国に注目してみると、2国間で妙に仲が良かったりすることがあるため、兆候を知ることが出来たりします。例えばこれ

はオスマンプレイで主にバルカン半島から中欧方面に侵略的拡大を続けたときのオスマンに対する評価を表示させたものです。赤は「激怒」、オレンジで「敵意」、薄オレンジ~黄色で「中立」を示します。マムルークは最初から歴史的な対立国家なので仕方ないにしろ、主に北方向でけっこうな赤表示になっています。この時は確か包囲網を結成されていた時期です。北の緑色は基本属国ですが、独立させたものは緑色になっています。当然ながら北を中心に嫌われまくっており、もうこうなると外交関係の構築すら難しいでしょう。 - 国家ウィンドウの「外交タブ」:外交タブ自体は非常によく使うタブだと思いますが、これを通常の”外交アクション”タブから、”評価”タブに切り替えるとこうなります。

デフォルトでは全国家がズラッと並びますが、隣接国、敵国、フレンド(同盟国)などに絞り込めます。左列は当該国から見たその国(この場合オスマン)への評価で、右列はその国(オスマン)から見た当該国の評価です。初期に同盟を組んでいたボヘミアなんかはこちらからは+42と未練が残っていますが、相手国からは-114と結構な嫌われ具合だということです。この落差を知るのが大切です。EU4では外交関係は200~-200までで表され、-200というのは最下限状態でありもうここまで嫌われると外交関係などあったものではありません。これはオスマンプレイのオスマン外交画面から見た数値ですが、敵国はおろか第三国の外交関係も全部見ることが出来ます。
同盟相手からしょっちゅう結婚を提案してくるのはこのためです。あなたとの関係が重要だと認識していれば、評価値の維持を目的として一番手軽な婚姻関係で維持しようとしているのです。また婚姻関係を築くと、世界交代するか婚姻相手が死亡するまで互いに攻め込めなくなります。「こいつは将来攻め込むかも」という国家とは、あまり気軽に婚姻しないように気をつけましょう。※同盟関係ならば同盟破棄すれば停戦5年後に攻め込める
2つの画面の使い分けとしては、評価マップは全体的な傾向の把握、評価タブは細かく外交交渉を使う場面で参照すると良いでしょう。
毎回確認する必要はありませんが、ゲーム開始直後当初や、大きな戦争を準備し始める前や、大きな戦争が終わった後、気になる国家など他国間で戦争が行われた際には都度確認するようにしましょう。
※なお外交タブの最後のタブは”外交フィードバック”タブです。ここでは信頼度と好感度が表示されます。ゲーム開始直後は大半の国家が信頼度50、好感度0ですが、例えばオスマンに対するマムルークやビザンツなどは信頼度15、好感度0で始まります。同盟を破棄したり、開戦事由なく宣戦布告したりすると当然下がります。同盟国を戦争に駆り出しながら十分な戦勝点分配を行わなかったり、また細かいところではイベントでの選択肢や、外交アクションなどでも変化し、「関係の改善」を数年かけて行うことで信頼度を(わずかに)上昇させることも出来ます。
戦後処理(中核化)
満足できる戦果を上げて目的の領土割譲などができれば、終戦しましょう。するとダイアログが出て戦争は終了します。ここでも一時停止をします。戦後処理としてやるべきことがたくさんあります。
- 割譲させた州の中核化:奪い取って放置ではいけません。
- とりあえず「中核化」することで確実に自分の領土としましょう。

中核化が完了すると「ステート化」(複数州での管理)というものが可能になり、するとさらに2回目の「中核化」が可能になります。この2回目の中核化は一瞬で終わります。この都合2回の中核化フェーズで君主力のうち統治力が必要になります。例えばこの画面では9州もぶんどったのですが、その代償としてここで「コスト」と書かれている統治力が必要(+再中核化でも統治力が必要)になるということです。
※「中核化(徐々に進行する)」 → 「ステート化」 → 「中核化(一瞬で終わる)」
- とりあえず「中核化」することで確実に自分の領土としましょう。
- 不穏度の確認:
- 占領したての州は不満が爆発寸前で反乱軍が湧きやすいため、必ず自軍を一定期間(再中核化が終わるくらいまで)駐留して不穏度を抑え込みましょう。※軍隊には兵数により抑え込める不穏度というものが表示されており、駐留期間内は一時的に抑え込むことが可能です。

※この1万人の軍隊の場合は「不穏度-2.50」と表示されている。連隊数(人数)により変化し、最大値で-5.00。 - 中核化が終わって軍隊が駐留していてもあちこちで不穏度が10%を越えるようなら、最後のダメ押しで自治率を上げるのもありです(ワンクリックで自治率は25%上昇し、不穏度は-10変動する)。

「+」を押すことで自治率が25%上昇する代わりに不穏度は下がります。自治率を上げることでその州からの収入は激減しますが、反乱軍を起こされる可能性があって軍隊を動かせなくなるよりはマシでしょう。
※ただし全領土平均自治率を下げていかないとどこかで破綻しますので、(その文化の領土における率が高ければ”受容文化”に入れたり、あるいは宣教師を送って”改宗”したり)ちゃんと不穏度を下げて自治率を上げてから次の戦争へと移るようにしていきましょう。文化とは文化マップモードにすることで表示されるものです。
・バルカン半島付近だけならまだ勢いでなんとかなりますが、これがアナトリアへと広がっていくと(上記短期的な手法では)自治率100%近い州ばかりになり苦境に陥ります。オスマンはとにかく人的資源が圧倒的で、戦争で消耗しても即復活するので、どんどん侵攻できてしまい、右へ左へと停戦していない国家に次々と順番にケンカをふっかけてしまいがち。
・オスマンであれば、国家自体はトルコ文化ですが、バルカン半島の大半はギリシャ文化で、さらに北に行けばブルガリやセルビア、ルーマニア文化があります。そしてアナトリア半島を東や南へ進むとアルメニア・クルド・シリア・ベドウィン・エジプトなどの諸文化地域を組み入れていくことになります。文化受容数には限りがありますので、自国で重要な位置を占める地域でかつ独立気質の高い文化は受容することも考慮しましょう。オスマンだと特にクルド、アルメニアなどは結構反乱気質が高いと感じるかと思います(抑えても抑えても反乱軍が成長してくる)。※非受容文化州では税収+人的資源が-33%され不穏度が+2されるペナルティがあり、さらに異教徒州(スンニ派に対するシーア派、カトリックに対するプロテスタント)では不穏度+2(イスラム教とキリスト教など大宗教の相違で+3)も加わる。実際にはこれに過剰拡大や戦争疲弊、安定度、自治度、異教寛容度などが加味され変動する。
・あるいは軍隊配置に余裕があるなら反乱軍出現率を80~90%になるまで放置しておき、その発生予定ポイントに陸軍を配置しておいて潰す(つまりはガス抜き)のもありです。一時的に不温度が-90くらいに落ち着きます。ただしガス抜きして下がったからといって「じゃあ自治率下げるか」というのは危険です。
- 占領したての州は不満が爆発寸前で反乱軍が湧きやすいため、必ず自軍を一定期間(再中核化が終わるくらいまで)駐留して不穏度を抑え込みましょう。※軍隊には兵数により抑え込める不穏度というものが表示されており、駐留期間内は一時的に抑え込むことが可能です。
- (残っている場合)相手側領土の監視:
- 相手に残存州がある場合は、相手領土側も怠りなく見ておきましょう。もしかすると相手側領土内で反乱軍が発生し、それがこちら側になだれ込んでくる場合もあります(これはEU4では非常によくある)。反乱軍は自領土、周辺国領土に関係なく動き回って占領しまくるので他国の反乱軍にも注意が必要です。
- 戦争疲弊・過剰拡大・安定度なども確認
- これらの数値も非常に大事です。中核化指示が終わったらこちらもチェックしておきましょう。

- これらの数値も非常に大事です。中核化指示が終わったらこちらもチェックしておきましょう。
- 戦争疲弊:
- 戦争疲弊は上がるのか下がるのか。下がるとしてもどの程度の期間かかるのかを頭に入れておきましょう。もし国内の不満を押さえるために急遽下げたければ「軽減」をクリックします。外交力75を消費することで戦争疲弊を軽減できます。
- 安定度:
- 次に安定度が超重要です。宣戦布告時にちゃんと開戦事由をつけていれば下がりませんが、強引に攻め込んだ場合にはここがマイナスになっていたりします。そうなるとかなり広範囲に深刻な影響を与えますので(代表的には不穏度を上げる効果)、もし安定度を上げれるのであれば「増加」をクリックすると統治力を数百消費して上げることができます。イベントで突然下がったりしますので、常に2以上を目指すようにしましょう。「彗星」イベントなど、こちらにまったく落ち度がないのにどれを選んでも安定度が下がるイベントもある。
- 領土管理限界:
- 領土管理限界とは現在の国家の能力で占領・統治できる州の数に比例した値だと思えばよいでしょう。これを越えると各所に負担が出てきますので、あまりに多くの州を入手した場合などは、この管理限界を増やす事も考えましょう。※2ページ目末に「領土管理限界はどうやって増やすのか」を追記しました
- ※国家ウィンドウの政府タブを開いてもう一度赤い「政府改革」画面に切り替えて右上側の「+」の付いたアイコンを押すと”政府改革進捗度”を消費して増やすことが出来ます。ただしこの政府改革進捗度は、その下にある政府改革レベルの上昇にも使うための値であり、領土拡大だけに使っていると改革レベルが上がりませんので注意が必要です。
※各階級にも「領土管理限界+100」というのが一つずつありますので、あまりに限界がきつくて政府改革値も貯まらない時にはそれを使うのもありです。3階級ともいれると一気に300増やせます。確か王室領が下がるはずなのでひとつずつ計画的に入れましょう。
- ※国家ウィンドウの政府タブを開いてもう一度赤い「政府改革」画面に切り替えて右上側の「+」の付いたアイコンを押すと”政府改革進捗度”を消費して増やすことが出来ます。ただしこの政府改革進捗度は、その下にある政府改革レベルの上昇にも使うための値であり、領土拡大だけに使っていると改革レベルが上がりませんので注意が必要です。
- 領土管理限界とは現在の国家の能力で占領・統治できる州の数に比例した値だと思えばよいでしょう。これを越えると各所に負担が出てきますので、あまりに多くの州を入手した場合などは、この管理限界を増やす事も考えましょう。※2ページ目末に「領土管理限界はどうやって増やすのか」を追記しました
- 過剰拡大:
- 要するに自国領土化(中核化)できていない占領地が大量にある状態を示しています。これを下げるには「管理」を押して「中核化」を行う(統治力消費)必要があります。その中核化が進むことで過剰拡大を下げることが出来ます。戦争で領土拡大をすると(基本的には)中核化作業が入るので、それを半年~1年かけて処理という形になります。
あるいはめんどくさければ従属国として独立させるのもありといえばありですが、それもまた”属国ごとの独立欲求”管理という別の管理作業が発生してきます。
- 要するに自国領土化(中核化)できていない占領地が大量にある状態を示しています。これを下げるには「管理」を押して「中核化」を行う(統治力消費)必要があります。その中核化が進むことで過剰拡大を下げることが出来ます。戦争で領土拡大をすると(基本的には)中核化作業が入るので、それを半年~1年かけて処理という形になります。
- 反乱軍の兆候:
- %は「次の蜂起までの進行度」です。これが80~90%になると書かれている州・規模で反乱軍が発生するため、陸軍を移動させて討伐するなどの具体的な対処が必要です。
- 通常はそこまで上がらないように「制御せよ!」をクリックして対処しておくと良いでしょう。
- 「弾圧」:30%以上なら軍事力を消費して「弾圧」できる。弾圧すると進捗度(%)を30ポイント下げることが出来ます。ただし根本解決にはならず、時間経過でどんどん伸びてきます。
不温度がある限り伸び続けるため、モグラたたきの要領で削る必要がありますが、大量の州を一気に獲得した場合には追いつかなくなります。そんな時は受容文化に入れたり、長期的には改宗を行うなどして自国に馴化させていきましょう。 - 「安定度を高める」:これは上の画面にある「安定度の増加」ボタンと一緒の働きをします。対象の州別に動くような位置にありますが、あくまで全体の安定度を下げるだけです。
- 「要求を受け入れる」:せっかく占領した土地が、その左枠に書いてある内容で独立してしまいます。威信も下がりますのでこれは絶対に避けましょう。
- 「弾圧」:30%以上なら軍事力を消費して「弾圧」できる。弾圧すると進捗度(%)を30ポイント下げることが出来ます。ただし根本解決にはならず、時間経過でどんどん伸びてきます。
- あるいは反乱軍に対処できる余裕がある場合は、あえて反乱軍を発生させてガス抜きするのもありです。90%になったら発生予定地点に対処可能な兵数を置いて発生に備えましょう。
- 戦争疲弊:
こうした戦後処理を進めながら、次に攻める相手関係の調査をしたり、あるいは外交で敵を減らしたり仲間を増やしたりといった作業を並行していきます。こうして次の侵略戦争の準備を行っていくのが、このゲームのルーチンワークということになります。
次のページでは、「属国化」や「国家アイデア」、「バニラでの探検」について述べます。