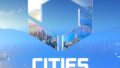属国化
はじめの外交のところでラマザンを攻めずに同盟を組みましたが、適当な時期から「関係行動-関係を改善」しておきましょう。
属国(従属国)とは、「その国の総開発度が100以下」で、「軍事同盟を組んでいて」、かつ「外交関係が190以上ある」国に対して属国要求が出せます。
属国化提案に”✔”が付いているのにクリックできない場合は、その”✔”をホバーしてみましょう。ならない原因がずらずらと記されています(属国化可能な場合は、同盟を組む前から「彼らはきっと受諾するでしょう!」と書かれている)。もし外交関係だけが足りないのであれば、ダメ押しで
- 同盟を組む:+100
- 独立を保証する:+15 ※相手の戦争には必ず出陣する
- 結婚:+25
- 軍事通行権を提供する:+10
- ライバルを侮辱する:+25
- 贈り物を送る:+0~25 ※必要金額は相手国との関係による
- 借款を返す: ※相手に借款がありなおかつこちらに支払いを許可するときのみ
- 補助金を与える:+0~15
- 〔列強限定〕国家に影響を与える:+25 ※ただし1国家あたり10年に1回
- 〔列強限定〕対外債務を引き受ける:+10~200 ※あいてに借金がある時のみ
すれば上がるので活用しましょう。これで190になればすぐ属国要求が出せます。属国にならない言い訳と対策。相手によっては属国になるのを拒否するケースが多々あります。
- 軍事力の比較:~+20 ※彼我双方の軍事力(海軍含む)の比較
- 外交評判:0~+10 ※外交評判+につき+3。小数点以下切り捨て
- 王族間の婚姻:+10 ※カトリックは婚姻不可能だし君主制国家に限定される
- 政府ランクの違い:0~+10 ※政府ランクが高いほどよい
- 外交態度:~+10 ※同盟すれば変化する。
- 信頼度:~+10 ※「おべっか(要DLC)」で上げておき「好感度を信頼度に変換」することもできる
- 諜報アイデアの7番目「脅迫」:(属国化の受諾)+15 ※固定値で上昇
- 中核州を領有している:我が国の領土に相手の中核州がある
- 経済基盤:相対的に大きすぎても不安を感じて属国化を拒否する
※ただし以前に戦争で争っていたり、あるいは歴史的な対立国家だとそうは行きません。そもそも好感情報で-1000とかされていて同盟すら出来ないことが大半です。また特にギリシア以北のキリスト教圏だと宗教が異なるのも大きな壁となります(カトリックは異教徒とは結婚できない)。
ある程度見方がわかってから周辺の国をカチカチクリックして調べると(あるいは外交-評判マップモード)、最初からオスマンに対して悪感情を持っている国家が多数あることに気づくかと思います。そうした意味で属国化しやすいのがラマザンということになります(その隣のドゥルカディルでも良いが油断すると伸びすぎて開発度が100を越してしまう)。ある程度大きくなれば向こうから同盟要求が来ますし(これは参戦希望で来る罠のことも多い)、マムルーク以外のアラビア半島諸国なんかも属国化しやすいでしょう。ただし彼らもマムルークと同盟して一度でも戦うと面倒ですのでご注意ください。
属国は、戦争は(侵攻側/防御側関係なく)必ず同行しますし、毎年収入の半分を送金してくれます。
※一番いいのは領土管理限界などを圧迫しないことです。めんどくさい時は、自分の外交画面の一番下にある「自国の州の一部から従属国を作成」をクリックして属国化するのもありでしょう。できれば中心地ではなく「あまり攻めないけど攻めて来られたら困る」位置関係などから選ぶとよいでしょう。いわば砦代わりのようなものです。万が一戦争勃発時には(その時の自軍配置によっては)自軍よりも早く出動してくれたりもします。
なお「属国化完了したからこいつは一生裏切らねえ」とは限りませんので、常に属国タブを見て独立欲求の数値を確認し、もし高ければ関係を改善したりしましょう。たいていは戦争で一緒に行動することで勝手に信頼値が上がっていくかと思いますが。※なお独立欲求を下げる行動で一番効率が高いのは開発度上昇です。属国なら建造物を経てたり、あるいはいわゆるDEVポチが可能ですから、どれか余り気味な君主力で開発してあげましょう。
ただし属国は戦争の際にも敵から狙われやすい傾向にあるようですので、「戦争が起きた時はどう守るか」というのも少し考慮に入れておきましょう。前線だけに気を取られていると、後背地にある属国領が狙われることもままあります。
国家アイデアについて
国家アイデアって必要(大事)なの?と思うでしょうが、はっきりいってとても必要で大事です。内政から外交・軍事まで様々な場面で少しずつ強化をしてくれます。これがあるとないとではまったくプレイのしやすさが違ってきますし、下で述べる「探検」などではこの国家アイデアがないと始めることすら出来ません。
しかしこの国家アイデア画面が、非常に分かりづらいUIだと思います。
画面上部にバルーンのお知らせが出て「アイデアが有効になりました」「アイデアグループが有効になりました」などと出てきてクリックするものの一体どこでなにをすればよいのかがよくわかりません。
国家アイデアでプレイヤーが行うことは2段階あります
- まず「技術」画面で各君主力を消費して[統治技術]のレベルを上げる
※外交/軍事技術ではアイデアグループ開放はできません。これが君主力のナショナルフォーカスを統治力にする理由です。現在のバージョンでは圧倒的に統治力が不足する作りになっています。 - (統治技術がレベル5/7/10/14…になれば)「アイデア」画面から解除された青いボタンをクリックして開放するアイデアグループを選択する
※過去バージョンでは最初のアイデアグループ開放にだけ統治力が必要で、その後は各君主力で開放できたらしい。つまり統治力依存が少なかったが、現在はとにかく統治力が酷使される構造。 - 「アイデア」画面で1つずつアイデアを進めていく
※君主力が溜まって各アイデアのバーが伸び切ればクリックできるようになる - 一定程度進んだら次のアイデアグループが解除される
※あくまで開放される(見れる)だけであって、上述した通り、実際にアイデアグループを有効化するには統治技術をレベル5/7/10/14…にする必要がある。ここが非常にわかりづらくなっている。
という流れで進んでいきます。
※君主点があまってるからといって惰性でカチカチやってしまうと、肝心のアイデアグループに投資できなかったりして、また君主点が貯まる頃には国家アイデアのことは忘れてしまってまた消費して…と成りかねませんので、まさにご利用は計画的にということになります。
要するに統治力を消費して「統治技術を次の段階に進める」と、「アイデアグループがアンロック」され、アンロックしたアイデアグループ内の個別アイデアの段階を進めるために統治/外交/軍事の各君主点が必要になるということです。
具体的に手順を見ていきましょう。
1.「技術」画面
この画面で統治/外交/軍事技術の段階を進めることができる。しかしアイデアグループをアンロックできるのは統治技術のみになっている。アイデアグループのアンロックは、統治技術がそれぞれレベル5/7/10/14…になったタイミングです。

この画面例では、統治技術が9、外交技術が8、軍事技術が10ということを表しています。そして一番上の「統治技術(10)」がうっすら青くなっており(下の緑色バーも伸び切っている)、クリックすることで統治力を消費して現在のレベル9からレベル10に上げることが出来ます。青いボタンの中にアイデアグループのアイコンがある通り、統治技術をレベル10にすれば3つ目のアイデアグループがアンロックされます。
他の外交/軍事技術は青くなっていないため(君主点が溜まっていないため)現在は上げることが出来ません。各君主点の下に緑色のバーが伸びていますが、これが目標値に対する現在の君主点ということになります。
また各大きなボタンや、その右側に並んでいるアイコンにホバーすると、どの技術要素がどのレベルでどこまでアンロックされるのかが表示されます。
※蛇足ですが、この「各技術のレベルアップに必要な君主点」は様々な計算式で計算されます。大きな要素が、1.”全世界の平均的なレベル”とどれくらい乖離しているか(先行していればペナルティ、遅れていれば必要値減算)、2.広まっている”「制度」を受容しているか”否かの2つが大きな要素です。
・特に後者がわかりづらいかと思いますが、制度とは「ルネサンス」「植民地主義」「活版印刷」などがそれです。プレイし続けているとどこかの段階で「~はルネサンスを伝えてきました」などと表示されます。そして自国でも「オスマンでルネサンスが受容可能です」などと表示されます(けっこうなお金が必要)。必ず受容しましょう。この受容有無で必要君主点が数百は変動しますのでとても大事です。
・マップモードを「制度」に切り替えると、ルネサンスであれば”ダ・ヴィンチの顔”アイコンがイタリア半島のどこかに付いて、そこを中心にどの制度がどの国のどの州まで何%浸透しているか?ということがグラフィカルに表示されます。これが自国領土まで一定程度浸透して来ると「(自国での)制度の受容」が可能になります。確か自国総開発度に対する受容した州の開発度合計が10%を越えたとかそんな計算式だったかと思います。オスマンの場合は、1.イタリアあるいはカスティーリャの方面(要するに地中海沿岸)に領土を伸ばしておく(制度伝播上は内陸州より沿岸地域州の方が有利)、2.制度発生地に近い領土の開発度を地道に上げる(とりわけ首都の開発度もガンガンあげておく。ちなみに建造物ではなく、いわゆるDEVポチと書かれている作業)、という2つの手段が考えられます。要するに開発して発展してる土地(首都も含む)には新制度が受容しやすいということです。
2.「アイデア」画面
「アイデアグループが開放されました」という時に見るのがこの画面です。

この例では、「外交アイデア」「経済アイデア」の2つのアイデアが解放済(選択済)で進行中であり、さらにもう一つのアイデアグループ枠も開放されている状態を示します。※ホントの初心者の頃に取ったスクショなので進行がぐちゃぐちゃです。
1つ目の「外交アイデアグループ」では、その1段階目が緑色の後背が微妙に光ったようになっておりこれはすでにそのアイデア段階が君主点を消費して有効にできることを示します。その下の緑色のバーも伸び切っています。
この様になっていれば、その小さいアイコンをクリックすることで(外交アイデアなのでこの場合は外交力を消費することで)アイデア段階を有効化できるということになります。※1段階目を有効化すると、2段階目が赤く光り、バーも(現在の残り君主点に応じて)変動する。
右側の「経済アイデアグループ」の場合は、2段階目が赤く光っており、まだ有効化できないことを示しています。下のバーも伸びきっていません。
このアイデアグループ内の個別アイデア7つをすべて有効化すると、✗の右に「ランプ」アイコンが付いて完走(アイデアグループ内完了)したことを示します。
政策と決断
こうしてアイデアグループを開放していくと、その組み合わせにより「政策と決断」で無料の政策というものが実行可能になります。いわば複数アイデアコンプリートのご褒美です。
これがなかなか強力なものがあるので、これも合わせて自国のアイデアをどの組み合わせで進めていくのかについてじっくり考えることが必要でしょう。
注意点
まとめると、とにかく「統治力」をたくさん消費しないと(個別のアイデア取得以前に)アイデアグループ開放すら出来ないということです。統治技術を上げずに軍事技術だけ上げていても、アイデアは一つも開けられない。
まず国家アイデアを進めるためには統治力を消費した上でアイデアグループを開放する必要があり、さらに統治アイデアを進めるのにも統治力を必要とする構造になっています(外交・軍事アイデアグループの進行はそれぞれの君主点)。また統治力は、その他にも安定度を上げたり、占領した州を中核化(再中核化)するのにも統治力が必要なため、特にオスマンのように軍事力に物を言わせてどんどん攻め込んでいくスタイルの国家だと圧倒的に統治力が不足し続ける構造になっているということです。
これがナショナルフォーカスを統治にするのをおすすめする理由です。
※過去のバージョンでは、最初のアイデアグループ開放だけは統治技術開放が必要で、その後は統治/外交/軍事技術を対応する君主点で進めることで対応するアイデアグループがアンロックされる作りになっていたようで、そのためにも軍事にフォーカスすることが推奨されていたようですが、バージョン1.3頃に改修が入った結果、とにかく統治力を大量に消費するゲームに変わったようです。
・もちろん軍事技術が一切要らないというわけではないですが、「大砲」が開放されるのは確かレベル7であり、大砲部隊があったとしても(特にバニラの場合は手動砲撃も出来ず)包囲戦が劇的に変わるかと言えばバニラではやや早くなるかな程度(DLCで砲撃OKなら一撃10~20%くらいいくが1包囲戦につき1回限り)なので、バニラならそこまで優先するべきかどうかは不明です。他国家より遅れるのは問題だとしても、初心者オスマンプレイで他国に先駆けて軍事技術を優先する意味は、私は感じません。
・戦争中、包囲戦発生時にいちいち部隊を組み直して大砲部隊を組み入れるか?とか大砲所持部隊で包囲するか?といえばそんな面倒なことをしているよりさっさと身近な部隊で包囲したほうが早いし(戦場での小部隊はコンピューター国家の大部隊に狙われ各個撃破されがち)、中欧~西欧のぐちゃぐちゃした戦線では兵種(兵科)よりとりあえず連隊数勝負になり勝ちで、実際コンピューターも敵とあたる際には(所属国に関係なく)とにかく数をかき集めて渾身の力であたってきます。数十年単位で長期的に見れば、当然最新兵科のほうが好成績を残すでしょうが、1回の戦争の1戦闘場面において圧倒的に戦果を変えるものではなく、第一義的には数が勝負(兵科よりむしろ陸軍指揮値)。
・私個人としては、初心者のオスマンプレイを前提として考えれば(中盤までは圧倒的な軍事力を誇っており、大国を相手する場合は戦術より外交戦になる)、それよりも統治・外交のアイデアグループで国家運営を楽にするほうが重要だと思います。なお「弱小国」でプレイするときには軍事技術レベル(を含めた軍事力)は非常に重要で、これが周辺国より劣っていれば攻め込まれたりします。あなたが初心者を脱した暁には各自で様々なプレイスタイルを考えられるようになるでしょうから、その時に自分のプレイに必要な技術・アイデアを考えるようにしましょう。
お金と人的資源
初期プレイで困るのはお金と人的資源じゃないかと思います。金がなければ動くに動けず、赤字になれば勝手に銀行借金されさらに2%の金利がかかってきて「貧すれば鈍する」状態に陥っていきます。
また人的資源がなければ募兵することも出来ず、戦場で損耗した兵の補充すらままならなくなります。
そこで初期にこれら「お金(ダカット)」と「人的資源」を確保する手段をいくつか書いておきますので、すべてを実施するのではなく、各自の戦略に合わせて選択すると良いでしょう。
お金(ダカット)の稼ぎ方
ここで地道に稼ぐ手段を書いていきますが、国家と進行度により作戦は変わってくるため注意が必要です。
- 交易保護&海賊狩り
- オスマンには小型船が3隻あります。これを艦隊ミッションから「交易の保護(アレキサンドリア)」を指定すると少しだけ交易収入を増やす効果が出るはずです。しかし戦争時には港に避難させておかないと敵艦隊の餌食になるため注意しましょう。※敵は必ずといっていいほど少数艦隊や少数連隊を狙ってきます。そのようにハードコーディングしているという事ですから、戦争前には港に(面倒でも手動で)入れるようにしましょう。「1隻ならいいじゃん」ということじゃなくて、無駄に相手の海軍伝統や海軍指揮を上げて、戦勝値を献上するだけです。
- なおオスマンの場合は、最初からコンスタンティノープル交易ノードで比較的高い交易力を持っているため交易保護では効果があり逆に海賊狩りでは効果が薄くなります。そのため海賊狩りをやるならアレキサンドリア(エジプト)で行うと良いでしょう。
- これとは別に艦隊ミッション「海賊狩り」というのもあります。海賊狩りは、海賊や私掠船と不意に戦闘にある可能性がありますので注意が必要です。ただし海戦で勝利すればさらに海軍伝統が伸びます。こちらの場合も戦争時には(面倒でも手動で)避難させておくとよいでしょう。
- 税収増加
- 税収を増やす効果のあるものがあちこちに散らばっており、それらを実行することで税収増が見込めます。
- 例えばオスマンだと特殊な”ズィンミー”と言う階級(イスラームではないユダヤ教徒やキリスト教徒など)があるのですが、彼らの特権に「ズィンミー税の増税」というものがあります。これは州の宗教がイスラム教以外の州に対して税金をかけるもので、初期オスマンの場合それが(ほぼバルカン半島側に)20州もあるため、恐らくですが0.5ダカット程度は増やす効果があります。ただしオスマンでは「ズィンミー自治の保障」という特権がゲーム開始時についているため、(自治率+8.5のペナルティが付くため)人的資源がやや低下しています。ただしこの「ズィンミー自治の保障」特権を外すとズィンミーの忠誠度が20%も下がりますので注意しましょう。
- これ以外にも宮廷の統治顧問に「国家の税補正+10%」という人物が出ることがあります。彼を雇うと初期費用は16ダカット程度、毎月1ダカットのコストが発生しますが、彼を雇ってから経済画面を見ると、課税が15%になっているのがわかります(ゲーム開始直後は5%)。内訳を見ると、聖職者5%+(顧問名)10%となっており、かなりの効果があることがわかります。ただし初期費用+毎月のコストも発生するため、最初期だとギリギリコスト割れするんじゃないかと思います。これには顧問費用を抑える効果のある統治アイデア(-25%)、革新アイデア(-25%)、外交アイデア(-20%)などのほか、ウラマー階級特権の「聖職者顧問団」(統治顧問コスト-15%、安定度コスト+10%)などを組み合わせるなどすれば改善する余地があります。※階級特権ではウラマーが統治顧問コスト、ユメラが軍事顧問コスト、商人が外交顧問コストについて、それぞれ削減効果を持つものがある
上の方で”商人階級では「借款(借金)」を選ぶと良い”などと書いていますが、これには「重商主義を1.0喪失し、インフレを0.5獲得する」というデメリットもあります。一度借金に頼るとずっと頼り続ける傾向になってしまい、それだけでインフレに長期間悩まされることにもなりかねません。
あくまで初心者のオスマンだから(とりあえずお金がなければ身動きも取れない)ということで借款を例示していますが、長期間プレイすることを考えればできれば借金をなくしインフレを抑制することが大事ということも徐々にわかってくるかと思います。私も「GSGでインフレって何?」って最初思ってました。
中盤以降になれば、領土も広くなって交易ノードごとの交易力を高めるなどしていくことで収入も伸び楽になってくるでしょう。そうなれば、交易会社州化したり、あるいは交易ノードごとの開発度を上げていくなどすればさらに高収入が入るようになるかと思います。
人的資源
人的資源とは、要するに兵隊を雇用したり、戦闘で損耗した兵隊を補充するための人資源を指し、陸軍の人的資源と海軍の水兵(人的資源)に分かれています。沿岸に位置する州では「水兵」という項目に数値がありますが、内陸州では存在しません。※いわば予備役兵的な存在が州単位で集計され、国でまとめて振り分けられる
特に初期には開発度も低いため、この人的資源に困ることになります。陸軍を徴兵しようとしても人的資源が尽きて徴兵できず、また戦争をすれば補充できずに見る見るうちに連隊の兵士数が減少していきます。
オスマンの初期状態だと、画面左上の2番目に人的資源が表示されています。州画面を開くと詳細が表示されます。※州ごとの「基本人的資源」の250倍したものが基本値。3なら750、4なら1000
この「人的資源」を増やすための施策を考えてみます。
- 貴族階級(オスマンではユメラ)の特権
- ユメラの特権に「徴募兵の増加」というものがあります。これは(初期オスマンの場合はユメラが36%の地権を持っているため)人的資源を+18.1%を増やす効果があります。これを付与すると、例えば首都であるエディルネ(基本人的資源は初期状態で3)の州情報を見ると、人的資源の欄に「885」となっており、そこにマウスホバーすると「基本750、中核州+75%、陸地州+25%、徴募兵の増加+18.1%」と書かれており、結果885名になったことがわかります。※ただし36%の地権により国家の税補正を-3.6%するデメリットがあります
- ちなみにその下のゲリボルの州画面を見ると、さっきのズィンミーの特権と合わせて「809」となっています。マウスホバーすると「基本750、中核州+75%、陸地州+25%、徴募兵の増加+18.1%、自治率によりさらに-8.5%」と書かれています。これが2つのズィンミー特権のメリット(税収増)とデメリット(自治率増加による人的資源減)になります。
- さらに海峡を挟んだその下のビガの州画面を見ると、ちょうど首都のエディルネと同じ数値になっていることがわかります。これはエディルネが首都でズィンミー特権が無効化しているのと、ビガの州宗教がイスラム教であることで(同じくズィンミー特権がない)ちょうど数値が釣り合っていることを示します。他の週もクリックして州宗教などと合わせて人的資源の補正値を確認してみましょう。
- オスマンのデシジョン
- 「決断と政策」タブに国家の決断がいくつか並んでおり、その中に「デヴシルメ制度の拡大」というものがあります。バルカン半島のキリスト教徒を強制徴兵するもので、軍事力を100使いますが、国家全体の人的資源補正値を+10%増加させます。これをクリックして再度州画面の人的資源を確認してみましょう。
- 首都エディルネでは、「960」となっており、マウスホバーすると「基本750、中核州+75%、陸地州+25%、デヴシルメ制度+10.0%、徴募兵の増加+18.1%」となっています。ちなみにゲリボルでも確認すると「878」内訳が「基本750、中核州+75%、陸地州+25%、デヴシルメ制度+10.0%、徴募兵の増加+18.1%」となっていることがわかります。
それぞれデメリットも存在するため、それを認識した上でどういう選択をするかはあなた次第ということになります。どんな政策や特権、アイデアや政府改革にもメリットデメリットが存在し、それらを組み合わせることであなたの取りたい戦略を下支えするものとなります。「唯一絶対正しくて、どの国家でもどんな局面でもこれだけでいい」なんてのはなく、国家や局面ごとに自分に必要なものを選択していく必要があるということです。
それぞれものすごく細かい変更を加える設定ですが、このゲームは基本的に長期間(年数)プレイするゲームであり、その毎月毎年のちょっとした数値の積み重ねがプレイ中盤や終盤にはとても大きな変化となっている可能性があります。ゲームプレイに慣れてきたあとは、そういった細かい数値にこだわって何度もプレイし直すことでより理解が深まり、プレイの幅が広まると考えます。
バニラでの探検
EU4の魅力の一つとしてポルトガル・カスティーリャ(スペイン)でのアフリカ・新大陸での「探検」要素があります。※もちろん他国でも不可能ではないが、史実反映的にも圧倒的にこの2国家が有利
これもDLCのない状態だとけっこう詰まる要素なので書いておきます。
まずいろいろ書かれている文章を見ると「探検家を見つけたら後は小型船に乗せて”探検ミッション”から選ぶだけ」と書かれていますが、それはDLC「El Dorado」で追加・改良されたものであって、バニラではDLC実装以前の操作が必要になります。2015年2月発売のDLCで既に記憶がないのか、公式フォーラムでも「できないのはおかしい」などといってたりします。
私も最初に詰まった点ですので詳しく書いておきます。
バニラでの探検~入植作業
探検に必要なものは「探検家」「入植者」「小型船3隻以上の艦隊」になります。
- [探検家]:「探検」アイデアグループで探検家をアンロックすると、F1で開く国家ウィンドウの「軍事」タブに将軍(提督)の一人として登場します(望遠鏡マークのあるのが探検家。あるいはそのタブの下に並んでいるボタンのうち「探検家を募集」で将軍などと同様に募集する)。そして探検家は艦隊の提督として乗船させ手動で海域や沿岸部を「未入植地」として発見させます(覆い隠している”雲”が晴れてクリックできるようになる)。
- [入植者]:発見した未入植地をクリックして、(入植者を)「送る」を選ぶと自動で派遣されるのが入植者です。入植家はアンロックすると画面上部にある商人や外交官の並びにこっそり追加されます。入植者はちょうど宣教師と同じ扱いだと思えば良いでしょう(年齢などの情報もなく死んだりもしない模様だが派遣すると名前が出る)。
結局手順としては下記になります。
- 「探検アイデアグループ」の1番目で「探検家」をアンロックする
※必ず(「拡張」アイデアなどではなく)「探検」アイデアグループを1番目に取ること。この探検グループの1番目の「新世界の探索」により探検家の募集が可能になる
※「入植家」は2番目でアンロックされる。また3番目の「植民範囲拡大」も取らないと届かない可能性もある - 小型船3隻以上の艦隊を組む(大型船でも良いらしい)
※できれば途中で沈没するリスクも考えて5隻程度がいいかも - その艦隊の提督欄をクリックして「探検家を募集」する
※探検家と言いつつ”探検家属性”を持つ艦隊提督なわけです
※「原住民政策の決定」というアラートが出てきてクリックすると「安定度と拡張」タブが開く。右側の「拡張」の下にアイコンが3ツ並んでおり、その中から原住民政策を決定する。急ぐ場合は右端(結構頻繁に原住民暴動が起きる)、急がない場合は左端(反乱ゼロ)、中間くらいなら中央のアイコンを選んでおく。現地に連隊を派遣できるなら右でも良いが、派遣できない場合には中央か左端でもいいかと思われる。 - その艦隊を雲で隠れている「未知領域」へと右クリックでの手作業指定で順番に移動させる
※とんでもない航路を辿ろうとするので、ガーッと大きく指定しないでちまちま一歩ずつ近づけていきましょう。結構最短距離ではなく海流や風に沿った動きをするのでかなり横道にそれ、消耗も激しい。DLC「「El Dorado(エルドラド)」があれば、ここは”艦隊ミッションにある探検先を選ぶだけ”になります。要するに現代人なら歴史で習った新大陸発見や、喜望峰を見つけるルートです。 - そうすると艦隊が動いたラインに沿って未知領域の陸地を「発見」することがある
※ここまでで探検家の役目は終わり - (若干時間差があって)未植民州をクリックして州画面を開くと特有の未植民州画面が開く
- その未植民州に対して「入植家」を派遣する
※「未植民州画面」の「送る」で派遣できる - するとだいたい一ヶ月に多くても100人未満の移住者がちょっとずつ移住を始める
※数十人程度として、ボーナスがない頃の1ヶ所目は入植完了までにだいたい2年近くかかることになる - 移住者が1000人を超えたら通常の州へと変わり入植完了
※中核化、ステート化、再中核化が必要。新大陸の場合、(同一交易地域内で)5州開拓するとそれらが「植民地(属国)」として独立する。国家ウィンドウの属国タブに表示される。
要するに「探検家」を派遣して未知領域を発見すると、その未植民州に対して入植できるようになるので、「入植家」を派遣して時間をかけて1000人入植成功すれば州化できるという流れになります。
「探検家」はともかく、「入植家」は一人が1年以上未植民州に張り付いて入植することになるので大変効率が悪いのですが、こういう仕組みです。つまりアイデアなどで「入植家」を多く抱えられる国家が、並行して入植作業を進められるため非常に有利になってくることになります。
国家アイデア
「とりあえずポルトガルかカスティーリャで”探検”をやってみたい」という場合は、迷わずアイデアは「探検」+「拡張」だろうと思います。すぐに入植家が2人体制になって並行して入植を進めることができるようになります。3番目を取るならば(積極的な属国化前提として)属国管理が楽になる「権勢」アイデアが良いかと思います。
※そもそもゲーム内で探検家(提督)を雇用しようとすると「新世界の探索」のアイデアが必要だと書かれているのですが、これは「探検」アイデアの1つ目のことを指しています。つまり通常通り進めるのであれば、アイデアは「探検」→「拡張」という手順になるかと思います。
「探検をとりあえず体験したいけどどっちか?」と聞かれたらやりやすいのはポルトガルだろうと書いておきます。カスティーリャ(スペイン)は一見国土が大きく見えますが全体的に開発度が低く人的資源に苦労しますし、内乱イベントがかなりの確率で起こりますのでおちおち侵攻できません。またイザベル・ウェディング(アラゴンとの同君連合化)を希望するなら、内乱より先にイザベル登場イベントが起きてしまえば(内乱で後継者が登場する)恐らく巻き戻しになるかと思いますので、正直めんどくさい国です。※順序的には、内乱(終わってなくても必ず先に内乱勃発させてから)→イザベル登場して後継指名→ウェディングで同君連合が望ましい
いっぽうのポルトガルも、そもそもゲームスタート時には「摂政評議会」状態にあり、1447年まで開戦はできません。また初期の同盟相手(フランス・イングランド・ブルターニュ・ブルゴーニュ)によってはフランス本土での戦争へ頻繁に駆り出されますので、自国より北とは同盟はあまり組まないほうが良いでしょうし、かつ北アフリカ(マグリブ)への進出も(探検・入植が並行作業でできる程度に)ほどほどにしたほうが良いかと思います。ただしカスティーリャ(スペイン)の動向には十分注意して戦争にならないように全力を尽くしましょう(具体的にはグラナダを1州でも抑えるとミッションが進行せず良いらしい)。またゲーム内数十年後にはなりますが、喜望峰をまわってアラビア半島まで出ると恐らくマムルークが絡んできますので、それに備えて置くことも必要です。アラビア・中東で戦争してるつもりが、地続きですから普通に遊軍あるいはマムルーク本隊がセウタ経由でポルトガル本国首都まで攻め込んできます。
※探検ではなくヨーロッパで覇権を唱えたいんだという場合にはガラッと戦略が変わるかと思います。ポルトガル・カスティーリャのいずれでも、相手との関係をどうするかが大問題です。ポルトガルとしてはイングランドとは歴史的友好国なので仲良くできるかと思いますが、フランス本土での戦争にしょっちゅう呼び出される羽目になります。またカスティーリャの場合は内乱を経てイザベル・ウェンディングを成功させるまでが(20~30年近く?)けっこうイベントに縛られるプレイになるかと思います。いずれの場合も中級以上ということになると思いますので、探検目的以外で両国を選ぶメリットは薄いかも知れません。何度かプレイしているとわかりますが、統一できた後のフランスは圧倒的に強いですし、イギリスも国内統一に苦しみますが統一後は強国になります。かといってその2国がプレイしやすいかというと話はまた別で、オスマンに比べれば初期は圧倒的にきつく感じるでしょう。初期オスマンはそれくらい強国です。
「探検中」の注意点
特に手動での探検活動中はかなり勢いよく艦隊が損耗し、0になるまでに港に戻れなければ沈んで船を失います。特に新大陸側はかなり慎重に探検させるようにしましょう。(突然大回りに動くこともあるため)目安として60を切ったら素直にその回は元の港へと戻りましょう。
「入植中」の注意点
探検家で発見した未入植地は「植民者」で植民していくのですが、この入植中に現地住民が暴動を起こしたとかなんとか言って、包囲戦のような状態になります。現地住民が1000人くらいだと数年落ちないのですが、これが2000人とかになると下手するとせっかくの移住者がが全滅して(入植者も逃げ帰り)入植のやり直しになります。数年かけて入植を進めるためこうなると入植効率がとても悪くなります。
そこでこうなることを予想して、入植家を派遣する段階になったら陸上部隊10k人程度の部隊を輸送船でその未開拓州に運んでおきましょう(発見後は、制限はあるが陸上部隊が移動・上陸できる)。そうすると暴動が起きた途端に鎮圧でき入植が順調に進むようになります。※あくまで一般論ですが、仮に原住民が5000人だとすれば、5000人の兵を置いておけば十分だと思います
※この時に「安定度と拡張」タブにある「原住民政策」により、原住民の反乱可能性を無くしたり、半減させたり出来ます(ただし融和政策だとその分入植時間がかかる)。
※ただし隣接州に原住民国家が存在していたり、あるいは別の大国が進出している場合には、いざというときに備えて多めの軍隊を動かすか、あるいは並行して原住民国家との外交についても考慮するようにしましょう。自分の領地の間は良いのですが、いざ植民地として独立してしまうと(5つ目の入植完了直後に)「トルデシリャス条約」が発効して自動的に独立して植民地化(属国)します。こうなると宗主国であるあなたは植民地国家の戦争には途中参戦できず、指をくわえて見ていることだけしか出来ません。こうならないように、隣接地にヤバそうな国があるなら早めに請求権を確保して植民地として独立する前に自領土化してしまい、植民地成立時にその州を割譲(寄贈)してしまいましょう。入植時期にもよるかと思いますが、比較的北アメリカ(特に現在の合衆国東部)は原住民国家が乱立しているイメージです。
あと忘れがちなのが交易ノードとその流れで、カリブ交易ノード(ミシシッピ川及びリオ・グランデ植民地)までならセビリアに送出できますが、それより北(アメリカ東部及びルイジアナ植民地のチェサピーク湾ノード)になるとセビリアには送出できませんので他に優先するメリットはないかと思います。いくら頑張ったところで後から来るイングランドやフランスのために頑張っているようなものです。もちろんボルドーやイギリス海峡まで領土化すれば話は別ですが、それらの陸上も抑えてかつ植民地も取ってとなると、かなりの上級プレイヤーということになるかと思います。またいくら「トルデシリャス条約」で抑えたとしてもプロテスタント国家には効き目はありませんので、平気で入植してくる可能性があります。それを考えてもブラジル以南を確実に抑えに行って序盤の利益確保を行った後は、東を目指しましょう。ポルトガルのミッションもそのようなミッション配置になっているかと思います。
※1.37ポルトガルミッションツリーだと、南アフリカ地方のいずれか”発見”→ソファラ/ケリマネ/モザンビーク(コモロ諸島忘れずに)のすべて”領有”(喜望峰地域全領有で前ニ者請求権獲得)→アフリカの角沿岸部いずれか”発見”→ゴア”発見”→マラヤ地方”領有”(東インド洋のココス諸島でもOK)→華南/日本の”発見”となっている。なお領有は入植開始の時点で判定される。アフリカ南端は恐らく未進出なので良いとして、アラビア半島やインドにはその頃にはかなり大きな国家が誕生しており同盟関係も入り組んでいるはずなので一筋縄ではいかない。
いずれにしろポルトガル・カスティーリャ(スペイン)のいずれも、相手が初期の植民地競争でのライバルになりますので、同盟相手とはいえうかうかしてると取りこぼします。ポルトガルならばやはり史実通りブラジル~コロンビア方面、やや欲張ってカリブ方面に進出すると良いかも知れません。そしてその後は喜望峰を回ってアラビア半島・インド・マラッカ方面に進出でしょうか。史実どおりに1543年頃に日本に到達するのはけっこう厳しいかも知れません。
バニラでの新大陸経営
入植地を5つ獲得すると、「植民地」として勝手に独立します。そしてその後は属国の1形態である植民地国家が勝手に伸長してくれるようになります。もちろん金銭や兵力など母国からの援助があるとより進度が高まります。
結局バニラと「El Dorado(エルドラド)」DLCでの違いは、探検家での未入植値発見のプロセス(手作業か、探検ミッションでの自動化か)であってその後は基本的に同じということです。
征服者による未入植地発見
また探検家による探索では沿岸部しか発見できないのですが、その後内陸部の未入植地を探す際には「征服者(将軍)」を使います。
ある程度の規模(10k以上)の部隊を作り(あるいは本国から輸送し)、その「指揮者」に征服者属性を持つ将軍を設定すると、この内陸調査が可能になります。
※たびたび原住民による襲撃を受けるため、できれば大規模部隊のほうが安心できる
あとはその征服者を手動で隣接地へと移動させていくと、(探検船では沿岸部しか発見できないが)内陸部で未入植地を発見できる。この入植地は中核化済州の隣接地なら入植手続きが取れるが、放って置くと植民地国家が勝手に入植を始めたりする。
つまり”探検家による探索作業”や”征服者の探索作業”が、DLCにより選択/自動になるということでもあります。
DLC「El Dorado(エルドラド)」での探検および植民地経営
バニラだけじゃなくDLCがあれば探検は何が変わるのか。
DLC「El Dorado(エルドラド)」があると変わることの1点目は、探索が楽になることです。
- 探検家をアンロックすると提督に探検家を指定するところまではバニラと同じですが、その後は艦隊メニューのミッションから探検ルートを選択するだけでよくなります。後は探索が終わって帰港すれば報告してくれるので、続いて探索に出かけさせましょう。
- なお探索は、~~海(海) → ~~海(海岸)という手順で進みます。「海岸線は見つかるけど入植地は発見しない」という場合は、これの「(海)」しかできてなくて「(海岸)」の探索がまだということです(小さい島で”未知領域”となっているのも海岸探索で発見できる)。例えばカリブ海なら、カリブ海探索を行わせた後にカリブ海沿岸調査を行うことで入植可能な未入植州が発見できます。そうなれば植民者を派遣して植民州へと変えましょう。
- その後は、新大陸なら上で書いた「バニラでの新大陸経営」と同じです。またアフリカ大陸であれば交易商人州化するか、あるいは中核化しステート化再コア化を行い領土化するという手順になります。基本的には象牙海岸やコンゴは交易商人州に、また喜望峰から先は(アラビア半島やインドを経て)マラッカへと進出していく拠点として整備することになるかと思います。
- なお旧大陸と新大陸を横断して領有する時に問題になるのは、艦隊だと思います(陸軍の方は募兵すればすぐ集まる)。しかし旧大陸側から艦隊を移動させると、恐らく喜望峰を回れずに沈没すると思います。そのためコンゴあたりと喜望峰を越したあたりで補給港が必要になるかと思います。1回程度なら(候補国家と関係改善して港湾利用許可を得ることで)移動できるかもしれませんが、インドを超えるには恐らくアフリカ東岸~インド洋向けの艦隊が必要になるかと思います。ミッションでも喜望峰地域全領有でアフリカ南東部の請求権を獲得するため、つながってきます。1ヶ所も領有もせずいきなり中核州を得るのは無理で、かつ上陸作戦はかなり不利になるため、素直にミッションを進めて喜望峰あたりを領有したうえで戦線を進めるほうが良いでしょう。
2点目は、交易会社州にしたり、あるいは新大陸側では他国に先駆けて植民地化すると「トルデシリャス条約」対象エリアとして優先権のようなものが入手できるという点です。
- 「交易会社」は、通常の中核州とは違い交易会社が支配する州のような存在で、交易の利益だけが本国に金銭で送られる仕組み。過剰拡大の対象外で、文化・宗教不一致のペナルティもない。その上けっこうな交易力となり、生産品にも10%のボーナスが乗る。※ただし対象地域は、アフリカ、インド、東南アジア、中国などとなっている。またDLC「Dharma」があると、交易会社関連が更に強化される。
- いっぽうの「トルデシリャス条約」とは、要するにカトリック教国では、「新大陸の植民地ごと」に先に5州を開拓した国家に優先権が与えられ、その後にカトリック教国が入植するとペナルティを受けてしまうという制度(植民地の領域は、地理-植民地と交易地域マップで確認できる)。具体的には対象と認められた植民地地域に対して、5州植民地化の一番乗り国家にその対象地域に対する請求権が付与される。Wiki情報だと「人口増加-20、教皇影響度-10、教皇領・ボーナスを受けている国からの評価-50」というけっこうなペナルティになるらしい。
※ただし非キリスト教圏国やプロテスタント教圏国(イギリスやオランダなど)の場合は、この教皇の発行する「トルデシリャス条約」対象外なためノーペナルティで入植されてしまう。またこの5州はあくまで入植者で開拓した入植地だけが対象であり、原住民国家の州を戦争で占領したりして入手した州はカウント対象外になる。
変態メモ
EU4の面白さの一つに、歴史上のIfを再現する「変態」というイベント(実際は「国家の決断」で実行)があることもその一つだと思われます。例えばペルシア国家を樹立したり、スペイン王国を樹立したり、グレートブリテンを樹立したりといった、元からある国家形態から国名もミッションも構成を入れ替えることです。
しかしなかなか微妙な条件をかいくぐってやる必要があったりとなかなか大変です。ここではその変態をやってみた経験談を書き記しておきます。
変態の基本情報は「データ/変態 – EU4 Wiki」です。完結かつ網羅的にまとめられています。先人のご苦労に頭を下げるしかありません。
ただしこれを初心者が読み解くとなると並大抵の知識量じゃ足りません。そのプレイ経験をメモしたものだと思ってください。基本テキストは上記Wikiです。
ムガル帝国(ティムールから)
簡単なところから行きましょう。ティムールで開始してムガル帝国に変態します。
ムガルに変態すると、「文化同化」というムガルしか持っていない特徴を持つことが出来ます。この文化同化とは、該当文化州を中核化して100%同化するとその文化の特徴を自国の要素としてマスターするというものです。例えば、イラン文化を100%同化させれば(占領すれば)顧問コスト-10%が。またインド北部ヒンドゥスタン文化ではコア化コスト-10%、中央インド文化では陸軍損耗-10%と、結構強力な同化ボーナスが入手できます。
※ここでいう同化とは、その文化を持っている州のすべてを中核化することを言います。中核化するごとに、政府ウィンドウの政府タブの下にあるところに「イラン:何%」などと記載されていきます。これが100%に達するとボーナス効果が発動します。なお文化同化では属国の領域は含まないため、邪魔な属国は併合する必要があります。
ということで変態のやり方。
ティムールは内部に属国を4つも抱えており、まずは内政が大変です。属国たちのご機嫌伺いをしつつ、積極的な侵攻も求められます(属国安定には領土拡大が一番の良薬)。常道では、とりあえず西方のアジャムを攻めて国内を安定させ、その後ムガル条件を得るために東方インド北西部を攻める必要があります。
ここでムガル変態の条件をおさらいしておきましょう ※Wikiから引用して追記
- ムスリムグループである
- これはティムールからの場合は考える必要はありません。
- デリー/Delhiをコア州(中核州)として領有する
- ラホール(Lahore)、ドアバ(Doaba)、中央ドアブ(Central Doab)の何れかをコア州として領有する
必要な州は書かれている通りで、ラホール州とはインド北西部にあるラホール交易ノードの中心都市です。ドアバ州はその北東隣接州です。中央ドアブ州は少し(4州)東に行ったデリーの南東にある州で、ゲーム開始時はジャウンプルが所持している州です。つまりデリー州に加えて3つのうちいずれかを領有するのが条件で、要するにティムールで開始してインド北西部を押さえればムガル変態条件を満たすということです。
- ※AIに聞くと、アフガニスタンとスィースターンの外交併合も条件だみたいに言ってきますが必要ありません。まあアフガニスタンはまだ残してもいいとしてスィースターンは意味がないので併合したほうが良いかと思いますが。あと北のトランスオクシアナと沿岸ファールスは辺境伯指定して侵攻作戦に使い倒すのが良いでしょう。
そしてムガル変態については、「各国戦略/ティムール – EU4 Wiki」に詳しく書かれています。なかでも「各国戦略/ティムール#インド北西部の攻略に向けて – EU4 Wiki」とわざわざ一項をもうけて解説してくれているのですが、これはそのままだと初心者には難しい内容ですので、ここを補足します。
これを噛み砕くと、ムガル変態するための条件(諸州)を得たうえで、インド北部を占領するのに元から存在するデリーを利用するのが非常に有効なため、ゲーム開始初期に起こる「デリー属国シルヒンドによる対デリー独立戦争」に相乗りしたうえで乗っ取ってしまおうという戦略なのです。
実際、初心者がえっちらおっちらとアジャムを攻め終わってインドに目を向ける頃には、すでにデリーは(独立戦争を終え)大国化しており、おまけにインド地方は大国同士で同盟を組みまくる傾向もあって簡単に手出しできないことがよくあります。※恐らくシルヒンドという国家自体見たことないという人が多いでしょう。
その手出しできる最も良い絶好のタイミングが、シルヒンド独立戦争時だということになります。独立戦争が終わってしまえばデリーは強国になってますし、ましてや同盟まで組まれたら手出しが難しくなってしまうため、独立戦争という相手にとっては国難の時期を狙うということです。
1444年のゲーム開始直後からインドに注目しておきます。Wikiによれば、初期デリーの運命は次の3つです。
- 属国シルヒンドに独立戦争を起こされてデリーは負ける
- この場合がややこしくて、デリーを強制統合したシルヒンドは変態して「デリー」を名乗り始めます。これを「偽デリー(国IDはSIR)」と呼び、こうなると利用価値はなくなってしまいます(初期画面で外交マップに切り替えてデリーとシルヒンドをクリックすると所持している中核州の違いがわかる)。
- 二番手の策として、この独立戦争に乗っかっても条件は満たす。しかし若干食べ残し感が残る。
- デリーがカシミールのマーガラ州を再征服した後にシルヒンドに独立戦争を起こされて負ける
※この独立戦争に途中で割り込んで乗っ取ってついでにシルヒンドも併合するのが狙い
※デリーにしてみれば、開幕カシミールを併合した途端に属国に独立戦争を起こされたと思ったら、そこに変な国(ティムール)が割り込んできて首都を占領され、ついでに強制属国化を命じられて自分の中核州権を利用して拡大・占領されるとう話。 - 稀にデリーがシルヒンド独立戦争を押さえて勝者となる(国ID:DLHと中核州は元のまま)
※これでも中核州的には意味はなくないが、間違いなく同盟を組んでいるため(ムガル条件獲得ですら)インド全土数カ国を巻き込んだ激しい戦争となる。恐らくムガル化は2番に比べ数十年遅れることになる。
このうち私が手順的に一番良いと思ったのが2番です。
まずデリーが対カシミール戦争をやり(この間シルヒンドは独立戦争できない)、マーガラ州をデリーが抑える。直後にシルヒンドが独立戦争を開始しますが、このマーガラ州はティムール属国であるアフガニスタンに隣接しているため請求権が捏造できます。ですからデリーがマーガラ州を占領したらすぐさま請求権捏造を開始します。諜報網が20になれば捏造できますので、独立戦争中であるデリーに対してマーガラ州の請求権を捏造したうえで宣戦布告します。請求権がないまま宣戦すると安定度-1のペナルティが付きますのであったほうが良いでしょう。
※このときまでに首都デリー州がシルヒンドに押さえられていたらリセマラ(データ巻き戻しかゲーム再開始。けっこう結果がころころ変わるため、独立戦争開始直後のセーブデータロードで良いと思われる)となります。シルヒンドの独立戦争は首都デリー州を抑えるのが条件なので、そのまま進めても恐らく独立戦争が成立してしまいます。つまり上記2で負けた状態になる。
(カシミール攻めがあって)独立戦争が遅れて我々が首都デリーを抑えることが出来ると、講和でデリーを強制属国化した直後にシルヒンド独立戦争に巻き込まれてニコイチでオトクな感じでデリー属国化に加えてシルヒンドも占領することが可能です。
まとめると、ムガル変態に向けた理想的な初期ダッシュ手順は下記になります。
- デリーがカシミールに再征服戦争を開始(講和でマーガラ州はデリーのものになる)
- マーガラ州(デリー)に対してティムールが請求権捏造開始
- シルヒンドがデリーに対して独立戦争開始
- (請求権が捏造できていればその請求権で。できてなければペナルティ覚悟で)ティムールがデリーに対して宣戦布告。当然必要な連隊をアフガン国境に事前待機させておく
- (シルヒンドより先に)まっさきに首都デリー州を抑え、残りもできる限り押さえて、「デリーの強制属国化」を指定して講和 ※これはマスト。シルヒンド軍より包囲開始が遅れたら負け
※デリー州さえ押さえていれば独立戦争は成立せずシルヒンド軍は固まるはず。「他国との戦争で占領中」となりシルヒンドには再占領されないため、デリー+属国軍さえいなくなっていればデリーに居座る必要はない。なお講和でデリーを直接併合してしまうと属国化(広大な請求権)の意味がなくなり侵略的拡大も被ってしまう。
※なおシルヒンド独立戦争は恐らく失敗まで5年以上継続するため、デリー強制属国化の条件さえ満たせればすぐ講和して良い。ヘタに長引かせると戦争疲弊がとんでもないことになる。 - 講和(デリーの強制属国化)が終わると同時に、独立戦争中のシルヒンドに対する属国デリーの戦争にティムールは自動参戦する
- シルヒンドをティムールに全併合して完了 ※これはマストではないが最低でも上記(中央ドアブ州を除いた)ラホール州・ドアバ州の2州いずれかを抑えてないと変態条件を満たさず全く意味がない
- 10年たったらデリーを外交併合して変態条件達成
※外交での属国併合には属国化から10年経過が必要。その間にアジャム・黒羊朝・ムシャーシャ・ホルムスを攻めたり、アラビア海やインド洋で必要な海軍を整備する。1年くらい前から属国デリーの関係改善を忘れずに
これでムガル変態条件を満たすことが出来ます。これが、先達プレイヤーが初期の請求権などを冷静に判断し構築されたムガル変態の流れであり、見事というほかありません。
あとは外交併合化までの10年間をインド北部も含めて他国侵攻に使い(ティムールミッションはムガル変態したら消えるのでできる限り消化する)、10年たった時点で外交的併合でデリーを併合してしまうことでムガル変態条件を確保できます(ムハル変態は「国家の決断」に登場する)。
やってみるとすごくシビアなタイミングですが、これをもし偽デリーに対して力技で全併合なんてことをやると、同盟軍が膨れ上がりインド全土を巻き込んだ戦争だけで数年以上かかってしまうでしょう。また侵略的拡大(AE)が溜まり、下手すると包囲網構築まで行ってしまいかねません。こうなると30年間は攻められなくなります。それを起こさせずに序盤にムガル変態条件を速攻で抑えるのが上記手順になるということです。深いゲームですね。
ペルシア(ティムールから)
同じくティムールでペルシア樹立を目指します。
参考)各国戦略/ペルシア – EU4 Wiki
参考)各国戦略/ティムール – EU4 Wiki 「初動」の特に後半、文化転向の辺り。
同じくWikiから条件を引用します
- 主要文化がイラングループであるか、アゼルバイジャン/Azerbaijaniであるか、白羊朝である
- ハマダン/Hamadan、イスファハン/Isfahan、ヤズド/Yazd、ゴム/Qom、ガズヴィーン/Qazvinをコア州として領有する
- アーモル/Amolかシーラーズ/Shiraz、タブリーズ/Tabrizかケルマーン/Kermanかマシュハド/Mashhadをコア州として領有する
このティムール→ペルシア変態で難しいのが「主要文化」です。ティムールはゲーム開始時はウズベクというなかなかに辺境な文化になっているため(ホラーサーン文化36%、ペルシア文化18%、ウズベク文化7%)、ペルシア文化を50.1%以上にする必要があります。
※文化には「文化グループ」とその下位の「文化」が存在しているためわかりづらいが、ここでいう文化条件は、マップモードを文化マップに変更した後に「ペルシア」をクリックすると濃い緑色になる州が対象(エメラルドグリーン色のホラーサーン文化はここでは含まない)。
これを実現するために
- アジャムを攻めてペルシア文化州を取り入れる
- 属国ファールスを外交併合してペルシア文化を取り入れる
※1454年以後。恐らく一瞬で併合できるはず
することでペルシア文化比率を50%以上にし、このタイミングを逃さず主要文化に指定します。これでほぼ条件を満たせます。州を中核化する以外に、該当州の開発度を増やしてもペルシア文化比率さえ調整できればなんでもOKです。
ただそのタイミングがアジャムを攻めた直後くらいしかないということです。その他周辺国を攻めるほどペルシア文化の比率は下がっていき(あっという間に数%に落ちる)、どんどん主要文化変更が難しくなっていきます。
※文化面だけに着目すれば、アジャム(パッチ1.23追加国)で開始してヤズド州を取るほうが早そうに見えるが、プレイヤー的には結構なハイスキルが要求される(恐らくティムール国内の独立戦争中に便乗するとかになる)。なおEU4には「文化転向」という手段もありますが、けっこうな時間がかかる(宣教師改宗よりはるかに長い)ため現実的ではありません。
FAQ形式のメモ
どうも「領土管理限界」のワードで飛んでくる方が多いようなので自分用の整理も兼ねてまとめてみました。
領土管理限界はどうやって増やすのか
領土管理限界を増やすにはいくつか方法はありますが限られています。
- 基礎値:200
- 政府ランクの上昇:王国で+200、帝国で+200
※1444年オスマンの場合は王国スタートなので+200された状態
※国家ランク上昇条件:公国→王国は開発度300以上。王国→帝国は開発度1000以上。ただしオスマンなやカスティーリャなどはイベントやミッションで昇格するものがある - 統治技術の上昇:レベル8,12、16、20、24、28でそれぞれ+50
- アイデア:
- 統治-統治アイデア完走で領土管理限界への補正+20% ※統治アイデアの全アイデアを取得する
- 複数アイデアグループ完走ボーナス
- インフラ+貴族:領土管理限界への補正+10%
- 政府改革進捗度を消費して+20(1つあげるごとに次に領土管理限界をあげるのに必要な政府改革進捗度は+20%上昇していく)
- 各階級特権で+100。×3で300
- オスマン:固有のTier1政府改革「オスマン政府」で+150
- Tier10政府改革「朕は国家なり」で+250
- その他ミッションやイベントなど
これらにより、例えば1444年スタートのオスマンだと550になっています(基礎値200+政府ランク(王国)200+オスマン政府改革150)。
領土管理限界値の確認
なお領土管理限界は、次の箇所で確認できます。
- 国家全体:安定度と拡張タブ:「領土管理限界」に現在値/最大値で表示されている
- 州ごと:州ウィンドウ右側についているタブをクリックして建設ウィンドウを引き出すと、天秤アイコンの横に表示されている。
※首都ステートは-100%。1444年のゲーム開始時点のオスマンだと、削減要素がないため(首都ステートを除いて)各州の領土管理コスト=開発度となっている
領土管理限界超過時のペナルティ
統治コストと呼ばれるものは、自分の領土内の各州の開発度の合計に様々な補正値が加わったものです。これが領土管理限界を超えると様々なペナルティが発生します。
- 安定度コスト補正+
- 顧問コスト+
- 関係改善-
- 侵略的拡大の影響+
- 統治効率-
これらの実際の数値は、領土管理限界の超過程度により増減します。オスマンの場合、領土管理限界の初期値が大きいため油断してしまい、ふと気づくと超過してしまっていたりすることが多いため(「過剰拡大が酷い!」というアラートが出る)、意識してある程度計画的に増やしていくようにしましょう。
緊急的には、政府改革進捗度を消費して増やすか、あるいは階級特権を3種つければ合計300まで確保できます。しかし後者は王領のパーセントを下げるため、次は「王領が少ない!」というアラートに悩まされることになりかねません。
領土管理コストとステート収入・人的資源との関係
1444年のオスマンで首都右上のステート:シリストラ(トルシュ州、シリストレ州、ティルノヴォ州)を例に上げると次のように変化する
- 中核化した州をテリトリーのままにする:領土管理限界値としては-75%なので2.25+1.00+1.50=4.75、ステート収入は0.45ダカット
※ただし生産(0.08→0.01)と人的資源(375→75)が激減する - ステート化:領土管理限界値4.50+2.00+3.00=9.50、ステート収入は-0.04ダカット
- ステート化+中核化(フルコア):領土管理限界値4.50+2.00+3.00=9.50、ステート収入は0.19ダカット
※ゲーム初期状態
領土管理限界の節約方法
逆に領土管理限界をできるだけ消費しない節約方法もあります。※国全体ではなく州/ステート単位
- 州の管理方法
- 中核化州(フルコア化):中核化の上でステート化することで、州ごとに開発度1あたり25%に圧縮
- テリトリー州(非コア化):自治度に比例して州ごとに-75%
- 交易会社州:州を交易会社管理にすることで州ごとに-50%(テリトリー中核州で-75%、交易会社州で+25%)
- ※けっきょく交易会社州にすれば領土管理限界的にも収入面でも美味しいが、人的資源などでは劣るという話。このゲームで交易会社を持とうというレベルの国家だといきなり宣戦布告なんてのは恐らくないため、領土管理限界がきつくなってきたら交易会社州にするのが良い(あるいは下の建造物を建てていく)ということになる。さらにDLC「Dharma」があると、この交易会社投資として交易会社州専用の建造物などがあり効果を拡大できる。
- 建造物
- 裁判所:州ごとに1つ建設可能で-25% ※統治技術レベル8
- 役所:裁判所のアップグレード。州ごとに1つ建設可能で-50% ※統治技術レベル22
- 州議会議事堂:ステートごとに1つ建設可能で、領土管理コスト-15%、州の領土管理コスト上昇-10、ステート全体の領土管理コスト-20% ※統治技術レベル12
外交官を増やす方法
外交アクションを実行するための外交官を増やす方法。
- 基礎値:2人
- 政府ランクの上昇:王国で+1、帝国で+1
- アイデア
- 統治-拡張アイデア:5番目「外交官の追加雇用」+1
- 外交-外交アイデア:1番目「大饗」+1、4番目「温和な外交官」+1
- 外交-諜報アイデア:4番目「諜報員の養成」+1
- 軍事-貴族アイデア:5番目「国際貴族」+1
- 複数アイデアグループ完走ボーナス
- 革新+諜報:+1人 ※2つ以上で出てくるアイデアを太字強調
- 経済+諜報:+1人
- 統治+外交:+1人
- インフラ+権勢:+1人
- 外交+貴族:+1人
- 外交+防衛:+1人
- 諜報+攻勢:+1人
- 政府改革:
- 特定国家でのTier4政府改革「国家と宗教」の「勢力均衡の維持」で+1
- 特定(君主制)国家でのTier2政府改革「?」で+1 ※らしい
- 特定の地位で+1 (神聖ローマ皇帝、将軍、教皇庁の支配者) ※らしい
- 特定ミッション
外交関係を増やす方法
同盟や属国が増えると外交関係枠を圧迫し、月ごとに増えるはずの外交力が減少することにもなりかねません。
この外交関係を増やす方法をまとめます。※外交官の人数ではなく、どれだけの国と(同盟や属国、軍事通行権など)関係できるかという外交関係です。
- 基礎値:4
- アイデア
- 外交-外交アイデア:3番目「緩衝国」で+1
- 外交-権勢アイデア:4番目「内閣」で+1
- 外交-権勢アイデア+攻勢アイデアの完走ボーナス「外国での徴兵の中心地」で+1
- 複数アイデアグループ完走ボーナス
- 経済+権勢:+1 ※2つ以上で出てくるアイデアを太字強調
- 人文+権勢:+1
- 統治+外交:+1
- 外交+傭兵:+2
- 外交+防衛:+1
- 権勢+先住民:+1
- 権勢+攻勢:+1
- 貴族階級の特権「強力な公爵領」:+2
- フランス:固有の貴族特権「フランスの強大な公国」:+3
- 特定国家:Tier1政府改革「強大な公国」:+2
※ブングルト王国 (Burgundian Kingdom)/カルマル同盟(Kalmar Union)/統一カルマル王国/評議会制度/リヴォニア騎士団 - その他:+1
※神聖ローマ皇帝、君主制、共和国、神権政治政府改革「聖職者委員会」、先住民部族政府改革「氏族評議会」 - ※逆に減らすもの
- 貿易同盟:-1
- 明の天界帝国:-1
- 先住民部族:-1
商人を増やす方法
外交官や外交関係とは異なり、商人はある程度時間をかければ順調に増やすことが可能です。
※もちろん商人もアイデアで増えますが、上で見たように外交官や外交関係を増やすのはけっこう大変なため、商人目的でアイデアを取るのはかなり贅沢な使い方だと思います(また自国で全部占領していくとすぐに領土管理限界や過剰拡大などがオーバーするため新規獲得州は同盟国や属国に食わせて行くほうが効率が良いが、そうするとすぐに外交関係がオーバーする)。そのため、商人は下記の交易会社で取る方が良いでしょう。
それは交易会社州を作り、その交易ノードでの交易力が51%を超える(50%超ではない)と、商人が1人増え、その商人はどこの交易ノードにでも配置可能になります。
まず交易会社州を作ると、「属国」タブに交易会社としてリストされます。この画面で最後から2列目の「ボーナス」欄の商人アイコンのツールチップを表示させると、”今そのノードで自国の交易力が何%か”がわかります。これを(該当ノード内で開発度をあげたり交易会社州を増やすことで)51%以上にすると、その時点で(確か翌月初)商人が一人増えます。最初商人アイコンは白黒で描かれていますが、51%を越えて商人が増えると商人アイコンがカラフルになります。

※このイメージでは、12個ある交易会社(交易ノード別会社)のうち、8州が商人有効化、4州が未達成状態ということです。
この商人追加ボーナスは交易ノード毎に判定されるため、自国の首都のあるノード以外(同大陸除く)にどんどん拡張していくことで、どんどん増やすことが可能です。
※交易会社州にできるかどうかは占領した州画面を開くとわかります。州画面右側、州の自治率の下あたりに、アイコンが3つ並んでおり左端が「+」の州ならば交易会社州化可能であり、その位置に「+」アイコンがなければ(アイコンが2つしかなければ)交易会社州化は不可能となります。
ちなみにこの交易会社州化するのにいちいち全ての州の+アイコンをクリックする必要はなく、交易ノードごとに配下の州の一括指定が可能です。州画面の一番下に「交易ノード名」のボタンが有りそれをクリックすると交易ノード画面が開きますが、その交易ノード画面の左上隅の「+」アイコンを押せば交易ノード内の全ての州に対して交易会社州化することが可能です。
包囲網対策
オスマンで調子に乗ってガンガン侵略していると、包囲網が形成されてどんな小さな国を攻めようとしても「包囲網」参加国がずらずらと顔を並べて圧迫され戦争できなくなることがあるかと思います。これは「侵略的拡大」というものが周囲の国家に影響を与え、これが減少するまではなかなか(年単位で)包囲網を解いてはくれなくなります。※放置してさらに貯めると懲罰的戦争を起こされるそうです。
この「侵略的拡大」は講和画面でも表示されるため、できるだけ直接領土化を避け、同盟軍に与えたり、あるいは一気に併呑出来ない場合には同盟関係の破棄や従属国の開放だけに留めることで抑えることが出来ます。しかしそれでも侵略的拡大は貯まるもので、戦争処理が上手になればなるほど気づけば周囲が真っ赤っ赤に激怒しているケースもよく出てくるかと思います。
包囲網を解散してもらうには、本当なら外交手段を使って一国ずつ「関係を改善」したり、(相手が列強以外なら)「国家に影響を与え」たり、「贈り物(金銭)を送」ったりすることで少しずつ解消していくのですが、それこそ数年~10年は関係改善で終わってしまったりします。ましてやヨーロッパ方面のHRE(神聖ローマ帝国)小国が一気に包囲網加盟したりすれば、十か国以上にまんべんなくそういう外交的解消をする必要があり、(マクロビルダーで自動的に関係改善出来ないバニラだと)とてもやってられません。
この包囲網を崩すのに一番楽な方法は、「募兵しまくる」ことです。
「陸軍扶養限界なんか知ったこっちゃねえ!」という勢いで、仮に管理限界が100だとしても200くらい募兵しまくれば、戦争することなく小国から徐々に包囲網を抜けていってくれます(目安として相手包囲網の総陸軍を遥かに凌駕する規模の陸軍を持つ)。募兵した兵が出現し始めると、一気に包囲網から抜けていくのがわかるかと思います。最終手段として知っておくと良いかも知れません・
ただし、管理限界を越えた軍隊維持費がとんでもないことになり、自国すら借金まみれで下手すれば破産してしまいかねません。そうならないように、基本的には侵略的拡大を計画的に押さえて進軍したり、あるいは外交的併合を使いながら進めるようにしましょう。
※「外交的併合」とは、関係改善して仲良くなって、同盟を組んだり独立保障したり婚姻したりで関係を深め、属国にするという手順です。属国化して10年経てば外交的併合も可能です(ただし外交併合ペナルティ=10年間外交評判-3なども発生する)。あるいは軍事技術のレベルアップに頑張るというのもひとつの手です。未検証ですがAI国家はこちらの軍事技術レベルと総兵数(陸軍)を見て勝てると踏めば戦争をしかけてくるそうです。包囲網もそれに近い考え方だと言えます。
なお「傭兵でもいんじゃね?」と思うでしょうが、包囲網を解くためだけなら傭兵でも可能(同様にカウントされる)らしいです。しかし実際には扶養限界を超過していても陸軍のほうが維持コストが低くなるらしいので、すぐに戦争予定ならともかく数年間戦争予定がないなら素直に募兵したほうが良いでしょう。超過ペナルティは、AIによれば「(軍維持費) × (1 + 0.5 × ((現在兵数 – 扶養限界) ÷ 扶養限界))」で最大2倍に達するのだそうです(しかも傭兵は初期費用も高め)。検証したこともないので詳細不明ですが。
「支配的な宗教」とは
「支配的な宗教」とは、要するに宗教別に州ごとの開発度を合算した合計値でシェアを算出したものです。例えば、正教会の州が2つあり総開発度が30で、スンニ派の州が5つあり総開発度が10だった場合、「支配的な宗教」は正教になります。※この条件はシェア50%を超える必要もなく、宗教別総開発度で最大であれば何%でも構わないはずです。
つまり、この「支配的な宗教」は、国家ウィンドウ宗教タブの宗教統一度のツールチップに表示される「州から」の数値とはズレてきます。この数値は、右下メニュー「台帳」の35ページ目左上に円グラフ形式で表示されます。

※これは1444年開始直後のオスマンでの分布。グラフ上はスンナ派(州48.7%)と正教会(州48.7%)が均衡していますが、開発度で見るとスンナ派51.2%、正教会45.9%となっています。つまり州宗教でみると同じ州数ですが、州の開発度の総合値でスンナ派がオスマンでの支配的な宗教となっています。
例えばDLC「Cradle of Civilization」では、追加される交易ノードごとに選択実行できるアクション5種があるのですが、あの「宗教の伝播」では様々な条件の中に「支配的な宗教」というのがあり、これがこの支配的な宗教を指しています。
参考)貿易 – Europa Universalis 4 Wiki、Cradle of Civilization – Europa Universalis 4 Wiki
宣教師を消費することもなく次々と自動的に改宗を進めてくれるので大変便利なのですが、このアクションが使いたければ、国教州の総開発度を高く維持する必要がある(あるいは単純に宣教師を派遣して国教州を増やすでも良い)ということです。
※通常は宣教師を一人一人派遣して改宗する必要がありますが、この「宗教の伝播」を使うと、その交易ノード内州の改宗を自動的に実行してくれます。通常交易会社州にすると(交易会社に属している-20%+テリトリー-2%が付いて)事実上改宗できなくなるのですが、このアクションを使うことで交易会社州のまま改宗作業も行えます。その場合には総開発度での国教シェアに常時気を配る必要があるということです。
様々な条件:「宗教の伝播」が解禁、ムスリム宗教グループ or ゾロアスター教 or ”ダルマ宗教のグループ or ミッション「メッカの玄関」達成”、支配的な宗教、交易会社州を持っていてかつ51%以上交易力で商人を所持している。