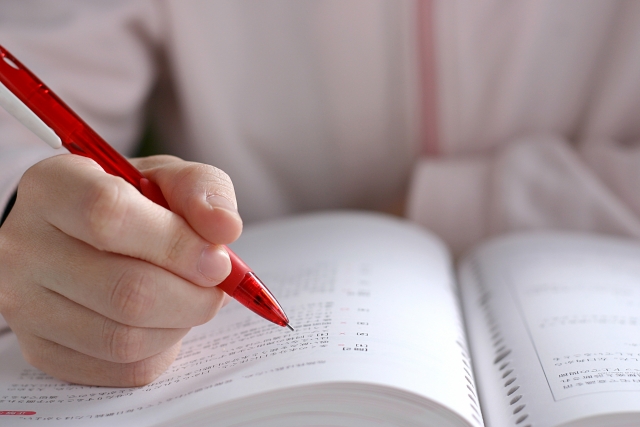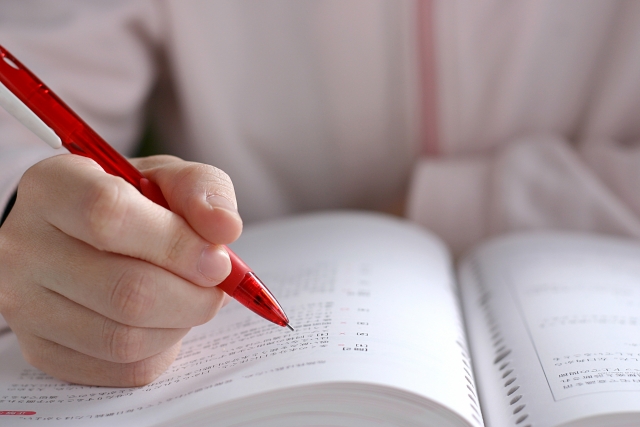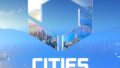元テニスプレイヤー、現在はタレント・スポーツ解説者として活躍する松岡修造さんがファミリーヒストリーに登場していました。
元プロテニス選手・松岡修造さんは、阪急電鉄・宝塚歌劇団・東宝などを創業した伝説の実業家・小林一三をルーツに持つ日本屈指の“華麗なる一族”。勝負師として一代で成り上がり船会社を興した高祖父、その名は松岡修造。祖母・フサ子は長男を亡くした悲しみを乗り越え、三人の娘をタカラジェンヌに。そして実は父・功はテニスの名選手だったが、修造とは違う道を歩むことに…。それぞれの夢に人生をかけてきた家族の物語。
(NHKファミリーヒストリーより)
松岡修造さんは、気さくな人柄ながら、言わずと知れた名家の血を引く方です。
字面だけ追えば、曽祖父は阪急創始者の小林一三。祖父、父、兄はその阪急系統企業の経営者。高祖父もまた立志伝中の人物。さらに母は元タカラジェンヌで、母の姉や妹、従妹も元タカラジェンヌ。妻は元アナウンサー、果ては自分の娘もタカラジェンヌ。親類を見渡しても有名経営者や政治家がズラリ。言葉を飾る必要がない”超”のつく名家、まさに華麗なる一族だと言えます。
曽祖父は小林一三。
阪急電鉄、宝塚歌劇団、東宝などを立ち上げた立志伝中の伝説の実業家です。「鉄道会社が自ら不動産事業や小売事業(百貨店、スーパーマーケット)などを通して鉄道需要を創出する」という現代につながる経営手法を確立した人物として高名で、これは日本の私鉄経営モデルの祖として後に東急など他の私鉄やJRが倣うところとなった。その他住宅ローンなどの創始者でもある。
昭和32年(1957年)正月、NHKで放送された対談番組に、松下幸之助氏とともに出演していました。当時84歳。年齢にも関わらず時代の変革を確信していました。
この小林一三から見ていきましょう。
父方:松岡家
祖父・松岡辰郎は小林一三の次男ですから、父方松岡家は小林家でもあります。
小林小平治維明 ── 小林甚八(丹澤) ── 小林一三 ── 松岡辰郎 ── 松岡功 ── 松岡修造
※小林甚八は丹澤家からの入り婿、松岡辰郎は小林一三の次男で松岡家に入り婿。
曽祖父:小林一三
小林一三は山梨県韮崎の出身。甲州街道沿いには商家が立ち並んでいたといい、その中でも随一の豪商だったのが布屋本家(ぬのやほんけ)。この布屋が小林一三の実家です。生糸などを売って財を成した大店(おおだな)でした。通称「布七」。むかし諏訪や高遠の大名ですら、借金をしていたため頭が上がらなかったという。
※小林一三の著書「楳泉亭由来記」によれば、
小林安右衛門維熙(元禄11没) ── 五良左衛門維景(正徳5没) ── 小右衛門維修(寛保2没) ── 七左衛門維邦(安永9没) ── 庄右衛門維時(寛政11没) ── 七左衛門維周(天保12没)
と続いており、 最後の維周の三男が(松岡修造氏の5代前)小平治維明となっている。
江戸時代末、布屋に生まれたのが松岡修造さんの5代前の祖先、小平治維明(こへいじこれあき)です。梅泉の号を持つ俳句を好む趣味人で、三男で分家主人として悠々自適に暮らしていたといいます。しかし慶応2年(1866年)に40代なかばで病死。一族は小平治の娘・幾久野(きくの)に、明治2年(1869年)夫・丹澤甚八を迎え、跡を継がせます。
※小林一三の著書によれば、小平治維明は長女幾久野(16歳)、次女松代(14歳)を残して慶応2年(1866年)に亡くなったという。そして残された2人の姉妹が本家に引き取られたとする。ただし維明の長兄(七左衛門維周の長男)の維清も亡くなったため、七左衛門維周の四男・維百が本家を継ぎ、この維百の本家にて養われたとしている。幾久野は明治3年(1870年)に長女を生み、その後明治6年(1873年)に一三を生んだ。
※丹澤家は中巨摩郡竜王村で煙草を生業とする素封家。なお丹澤家と小林家は代々婚姻を重ねており、七左衛門維清の妻・芳子や、七左衛門維百の妻・房子は丹澤家の出である。両者は叔母・姪の関係に当たる。さらに丹澤甚八も房子の甥にあたり、さらにその甥である富次も七郎維親の息子・林太郎に嫁いだ。この間だけで4代婚姻関係にある。
明治6年(1873年)1月3日に生まれた長男が小林一三。ところが母・幾久野は、一三を生んで約半年後、8月22日に22歳で亡くなります。さらに父・甚八は養子縁組を解かれ、実家へと戻ります。一三は本家へと引き取られます。※一三著書によれば引き取られたのは長女である姉・竹代と2人。なお父・甚八はこれも甲州の素封家である田辺家へと再婿入し、そこで田邊七六(衆議院議員7回当選)、田邊宗英(後楽園スタヂアム社長)、田邊加多丸(第一勧業銀行理事、第2代東宝社長)らを生んだ。ややこしいので系図で整理してみましょう。
小林七左衛門維周─┬七左衛門維清──女児一人 │ ├源六維賢(保坂家へ養子) │ │(別家) ├維明─┬─幾久野 ┌姉・竹代 │ │ ├────┴小林一三 │ │ │ │ │ 丹澤甚八(小林甚八→田邊七兵衛堅一) │ │ │ │ │ ├────┬田邊七六 田邊七兵衛栄七─│───│─たつ ├田邊宗英 │ │ └田邊加多丸 │ └─松代 │ └七左衛門維百───七郎維親───娘
まだ家庭を持たない若い頃から、独りで床の中で、お母さんというものの恋しさを想像して、我知らず「お母さん」と大きな声で叫んだことが度々あったことを記憶している。私は、私を育ててくれたおばアさんに対してもその御恩は忘れられないけれど、私を生みっぱなしで死んだ亡きお母さんぐらい、この世の中に恋しい慕わしい人はないのである。
「楳泉亭由来記」(大乗茶道記 – 国立国会図書館デジタルコレクション)
※番組中の引用が少し違っていたので原文から引用しました。なお「おばアさん(おばアん)」というのは、育ての親である維百の妻(つまり一三の大叔母)のこと。一三と姉は、維百のことを「おじいやん」、その妻のことを「おばアん」と呼んでいたという。著書では「維百の長男は妻を娶り、長女が生れる、この長女は私より四つか、五つか年下で、私を「兄やん、兄やん」と呼んで居ったから私は実の兄と思って居たのである。(略)やや長じて、彼女が頗る美人で、しかも雄々しくお姫様のように威張って、私を居候々々と呼び「祖母(※維百の妻)は私の祖母だ、兄やんのおばあアんじゃないよ」といわれるようになって、私は村一番のお金持ちで、この大きな家の実の子ではない、居候だと自覚したのはいくつの年頃であったか記憶はないが、このお姫様を私もまけぬ気の悪童であったから、いじめかえすと、そのお父さん(※維百の息子)が黙って私の耳を強く引張って憎々しく睨みつける、その眼の恐ろしさは今でも忘れることの出来ないイヤな思い出である。イヤなことだけが記憶にのこって、可愛がられて育ったことは覚えて居ない。」と記述している。実の大叔父(父の弟)・大叔母を「おじいやん」「おばアん」と呼ぶのと合わせて、どんな境遇だったかは推して知るべしである。この維百の孫娘(長男の長女)はおそらく青地氏に嫁いだ「りん」ではないかと思われるが、著書では記載なし。
幼い一三は、寂しさを忘れるためか勉学に勤しみます。小学高等科卒業後は成器舎に入って当時としては進歩的教育を受けた。
明治21年(1888年)一三は15歳で上京し、慶應義塾に入塾します。当時は(創設者)福沢諭吉も健在で(当時53歳)塾生たちに独立自尊の精神を説いていました。
慶應義塾には当時の小林一三をうかがい知ることのできるものが残っています。塾の寮生たちで作る冊子「寮窓之燈(寮の窓のともしび)」の主筆(編集長)を務めていました。文学にハマり、小説を新聞に連載したともいいます。弱冠17歳で山梨の新聞に小説「練絲痕(れんしこん)」を連載していました。実際に起きた外国人教師殺人事件を題材にしたミステリー仕立ての物語でした。一三は小説家になることを夢みていたのです。
※モデルにした殺人事件は当時未解決だったことから、真に迫る筆致のこの小説は警察関係者から真相を知る人物ではないかと疑われた。学校からも呼び出しを受け、塾監局で警察の尋問を受けたという。嫌になった一三は途中で連載を止めてしまう。”練絲”とは生糸の膠質(セリシン)を除去して、特有の光沢と手触りを出した絹糸のこと。なお一三自身は44年後の昭和9年(1934年)にこの小説を読み直して「一読して拙(ま)づいのに驚いた。こんなものを書いて、それで小説志願者であったかという過去を顧みると、何と無茶であったかと、苦笑せざるを得ないのである」と振り返っている。
明治26年(1893年)、慶應義塾を卒業した一三は三井銀行に入行。しかし小説家になる夢を諦めきれず仕事に身が入らない日々が続きました。
※当初は都新聞へ入るつもりだったが諸事情で断念し、高橋義雄(箒庵)の推薦を受けていやいや入ったという。当時の三井は合名会社に組織変更したところで、総長は三井高保、専務理事が中上川彦次郎、理事が西邑虎四郎、益田孝(鈍翁)、斎藤専蔵であった。はじめ東京本店秘書課勤務、同年9月大阪支店勤務。当時支店長は高橋義雄。
そんな一三に運命の出会いが訪れます。大阪天満出身で芸者をしていた「丹羽こう」に一目ぼれ。一三と同じく早くに両親を亡くした「こう」は、優しくて気丈な女性でした。明治33年(1900年)、一三とこうは結婚。一三が26歳、こうは17歳でした。
※実際には一三は一度結婚しているが、それ以前から付き合っていた「丹羽こう」の話を聞いた新妻がわずか数日で実家に戻ってしまったため、二度目の結婚だという。その「丹羽こう」の実父は大阪の豪商”炭彦”こと炭屋彦五郎で、若死してしまったため丹羽市蔵の養女となっていた。丹羽市蔵は俳諧の宗匠をしており、自宅を一水庵と名付けていた。婚儀はその一水庵の二階で行い、結婚後は大阪高麗橋一丁目にあった三井銀行の社宅で新生活を営んだ。
長男・富佐雄、長女・とめに続き、明治37年(1904年)に次男・辰郎(たつろう)が誕生。これが松岡修造氏の祖父です。一三が当時を振り返った文章が残されています。
この簡素な親子5人の生活は、誠に潔白な純情そのものであった。到底忘れることの出来ない思い出である
「逸翁自叙伝」
親の愛に飢えて育った一三が、ようやく手にした家族の幸せでした。
※なお三井銀行時代14年間の一三は、最初こそ本店秘書課だったが、のち高橋義雄の大阪支店を経て、辞めるときには閑職の本店検査係主任だった。
当時三井銀行内で辣腕を振るっていた池田斉彬(のち日銀総裁、大蔵大臣)は三井銀行時代の一三を評して「小林君は、三井銀行に行ったとき調査係というところにおり、私は余り懇意ではなかったが、評判はよくなかった。文学物ばかり書いているというので、その時分から文学青年だったね。だから『小説家のような男だね』と皆が言ったものです。したがって銀行家としては余り持てなかった。これはずっと後の話だが、私は小林君に『あなたがもし三井銀行におったら、支店長にならずに辞めさせられたでしょうね』と言ったことがある。」
明治40年(1907年)、一念発起した一三は銀行を辞め、大阪の鉄道会社「阪鶴鉄道」に入社しました
※岩下清周の推薦により監査役として入社。阪鶴鉄道は現在のJR西日本の福知山線。しかし明治39年(1906年)3月31日に施行された鉄道国有法により、明治40年(1907年)8月1日に国有化された。一三の阪鶴鉄道での最初の仕事は、清算事務及び役員社員の退職慰労金の決定への参加であった。つまり一三は、会社整理をするために入ったということになる。ただし小林を引き入れた側の目的としては、後の阪急電鉄(箕面有馬電気軌道株式会社)の設立を睨んでいたのである。
ある日、一三は手つかずになったままの計画書を目にします。それは大阪梅田と箕面市(みのおし)、宝塚市、西宮市を結ぶ路線計画でした。
その沿線は当時人影もまばらな田園地帯。鉄道を引いても到底採算がとれないと放置されていたのです。しかし一三には何か惹かれるものがありました。田園地帯を歩き回って電車が走る姿を想像しました。その電車に乗っているのはどんな人たちだろう。そして「人がいないなら、人が住む場所もみずから作ればいい」と思いつきます。
※実際には抜かりなく計算をして設立へと動いている。「有名な逸話であるが、ひそかに池田から大阪までの計画路線を二度も徒歩で往復した。地元の人は『この鉄道会社はそのうちつぶれるだろう』と馬鹿にしていた。会社の信用がないから本来値上がりすべき沿線の地代が一向に上がらない。小林の試算では、その好条件で住宅地として適当な土地を安く買う。仮に1坪1円で50万坪買うとすれば、開業後1坪につき2円50銭利益があるとして、毎半期5万坪売れば12万5000円は利益が出る。田舎電車だから、最初からこういう副業を試みれば、運賃収入が上がらなくても経営ができるのではないか。」
明治43年(1910年)、一三は周囲があきれる中、人生をかけた挑戦に打って出ます。5億円以上の負債を背負う覚悟で箕面有馬電気軌道、後の阪急電鉄を開業します。しかしそれは壮大な事業の始まりにすぎませんでした。
沿線の田園地帯を丸ごと買い取り分譲地として売り出したのです。一三が思い描いていたのは、沿線に家族団らんの地をつくることでした。当時、大気汚染に苦しんでいた大阪市民に向けてパンフレットを作り、自ら考えた言葉で訴えました。
美しき水の都は昔の夢と消えて、空暗き煙の都に住む不幸なる我が大阪市民諸君よ!田園趣味に富める楽しき郊外生活を思うの念や切なるべし
一三の発想力はとどまるところを知りません。分譲住宅の購入希望者には10年間の月賦で完済できる日本初の住宅ローンを始めます。更に終着駅の箕面には箕面動物園、宝塚には温泉施設「宝塚温泉パラダイス」を建設。都会で働く人々が郊外で安らかに暮らし、家族で行楽にも出かけられるように。一三の発想の源には、常に自らが欲してやまなかった家族の幸せがありました。
「やってみないと分からない」。そのチャレンジ精神で一三の夢はどんどん広がります。大正3年(1914年)、鉄道沿線の温泉施設で家族みんなで楽しめる少女たちの舞台を始めます(宝塚少女歌劇)。これが後の宝塚歌劇団です。少女たちの舞台は東京にも進出。やがて、東の宝塚「東宝」となって日本の映画界をけん引していきます。
昭和4年(1929年)には日本初の駅直結型デパート阪急百貨店を開業。一三は、庶民には敷居の高かったデパートも家族で楽しめる空間に変えました。食堂では25銭のライスカレーが家族連れに大人気となります。お金のない客の間では、5銭のライスに据え置きのソースをかける「ソーライス」が流行。反対する従業員もいましたが一三は歓迎しました。「今はお金がないかもしれない。でも将来家族が出来たとき、彼らは子どもを連れて戻って来る。」
不遇だった少年時代と家族の愛への渇望。それが一三を大実業家へと導いたのです。
ここで松岡修造さんはある疑問を口にします。
何で僕の名前は「三(さん)」じゃなかったんだろうって、もう何度も今見てて思いました。一三の「三」。僕は「造る」なんです。何で「三(さん)」じゃないの?って。いや「三」持ってこいよ!って。
※この話はすぐあとで回収されます。
祖父:松岡辰郎(たつろう)
小林一三の次男・辰郎は、昭和5年(1930年)お見合いをした女性に一目ぼれしました。女性の名は 松岡節子(まつおかさだこ)。聞けば祖父を亡くしたばかりで縁談が急がれたのだといいます。
節子の祖父は、大阪の実業界で一代で成り上がったという「松岡修造」でした。
※テニスの松岡さんと同姓同名。番組に倣い、以後この人物を「初代」とします。
松岡修造(初代) ── 松岡潤吉 ── 節子(夫:小林辰郎) ── 松岡功 ── 松岡修造
※潤吉も馬場家からの入り婿。辰郎は松岡汽船創業者の子である松岡潤吉の松岡家に養子入りし、その子が東宝名誉会長・松岡功氏。さらにその息子が東宝東和取締役会長で第15代東宝代表取締役社長の松岡宏泰氏。テニスの松岡修造さんはその松岡宏泰氏の実弟にあたります。
高祖父:松岡修造(初代)
高祖父の松岡修造氏もまた立志伝中の人物です。
修造さんと同じ名前を持つ初代・松岡修造とは一体どんな人物だったのか。古い戸籍に記された松岡家の住所は、宝塚市のすぐ隣の有馬郡生瀬村(なまぜむら)。生瀬町の淨橋寺(じょうきょうじ)に松岡家ゆかりのものが残されていました。
家系図によれば、はじめて松岡姓を名乗ったのは、およそ250年前の当主・松岡忠蔵(ちゅうぞう)。その三代後に松岡修造(初代)がいます。これが松岡修造さんの高祖父にあたる初代・修造。
松岡修造(初代)は、幕末安政6年(1859年)、生瀬村の松岡家の次男として生まれました。有馬郡の「立志人物伝」によると、「幼くして非常に賢く優秀。天性の優れた商才がある」。明治14年(1881年)、22歳の時に大阪に出た初代・修造。どんな夢を描いたのか。
大阪市内における有数の実業家の一覧を記した明治27年(1894年)の「大阪新繁昌記」によれば、大阪堂島濱通でお米の取引を営んでいたといいます。仲買や卸売を営む米穀商だったといいます。
江戸時代に諸藩の蔵屋敷が置かれていた大阪・堂島では、大規模な米の取り引きが行われていました。初代・修造はその米を大量に仕入れて売る仲買人になり、米相場で勝負していたのです。当時、米の価格は毎月のように乱高下を繰り返していましたが、初代・修造は持ち前の頭脳と勘の良さで財を成していきます。
そして大正11年(1922年)、63歳になっていた初代・修造は人生最後の大勝負に出ます。船会社を創業したのです。資産を整理し3隻の中古船を購入。大金がかかる畑違いの事業に乗り出しました。
初代・修造は浮き沈みの激しい海運業界でも勝負強さを発揮します。創業直後、ロシアの沿海州やシベリアからの木材輸入量が急増。その市場にいち早く割って入ったのです。当時の海運雑誌には「沿海州材に対する松岡汽船の進出、松岡汽船の割り込みが完全にその功を奏し、市場にセンセーションを起こしている」と書かれています。
曽祖父:松岡潤吉(じゅんきち)
初代・修造の死後松岡汽船を継いだのは松岡潤吉。初代・松岡修造の娘・千恵の婿養子として入った人物です。
※旧姓は馬場、前名は敬三。兵庫県武庫郡精道村(現芦屋市)出身。馬場三右衛門の弟として生まれた。
※松岡潤吉は、大和田紡績、松岡汽船各社長、北海道松岡牧場主、阪神急行電鉄監査役、東洋鋼板、北海道炭礦汽船、東宝各取締役、日本海運協会顧問、日本体育協会評議員、神戸日伯協会理事、大阪駐在ポーランド国名誉領事などを歴任した。ほか、加島信託取締役、大日本人造肥料監査役を務めている。さらに昭和7年(1932年)には兵庫県多額納税者として貴族院議員に互選され昭和14年(1939年)まで在任。昭和17年(1942年)の補欠選挙でも当選し、昭和22年(1947年)の貴族院廃止まで在任し貴族会の研究会に所属した。
この潤吉、事業を成長させていくかたわらで、あることに熱中していました。実業団スポーツの運営です。当時のスポーツ年鑑にも「テニス国内ランキング2位佐藤俵太郎 松岡汽船所属」と載っています。佐藤俵太郎は後年、日本のプロテニス選手第1号となったほどの実力者でした。
Hyotaro Sato – Wikipedia ※なぜか英語版Wikipediaにしか記事がない。ウィンブルドン選手権にも2回出場。
潤吉が「実業団スポーツ」に異常なほど気合いを入れていることはマスコミの間でも有名でした。
野球・庭球といえば出費を惜しまぬ球狂(たまぐるい)・松岡社長。鋭意野球部の充費を計り、グラウンドを新設。毎日、社長自らユニフォーム姿となり、練習を督励し、或いは合宿に選手と寝食を共にする
スポーツ選手を熱く応援する姿は誰かに似ています。
祖父・松岡辰郎
昭和5年(1930年)、松岡潤吉の長女・節子(さだこ)に小林一三の次男・辰郎が一目ぼれし、結婚。以後、辰郎は松岡姓を名乗ります。
4年後、次男・功(いさお)が誕生しました。修造の父です。
昭和16年(1941年)太平洋戦争が勃発します。松岡汽船など民間の船も輸送船として徴用されました。武力を持たない船はアメリカ軍の標的となり、船は多くの船員と共に犠牲になっていきます。
民間の戦没船の記録。ここに松岡汽船の記述が見つかりました。松岡の「松」の字を取って名付けられた「松安丸(しょうあんまる)」はサイパン島近海で空襲によって撃沈。トラック諸島に停泊していた「松丹丸(しょうたんまる)」爆弾が積み荷のダイナマイトに引火して沈没。グアムに向けて航行中の「松運丸(しょううんまる)」は300機以上の空襲を受け撃沈。
戦時下の松岡汽船を率いていたのは修造の祖父・辰郎。次々飛び込んでくる悲報になすすべもありませんでした。そして終戦。松岡汽船は14隻の船と237名の船員を失います。残ったのはたった3隻でした。
サイパン島の沖合、水深10メートルの浅い海底で撮影した写真。「松安丸(しょうあんまる)」が映っています。空襲を受けてサイパン島の沖合に沈んだ松岡汽船「松安丸」。トラック諸島沿岸水深50メートルに眠る「松丹丸」。グアムの近くロタ島の海底に横たわる「松運丸」。勝負師、初代・修造が人生をかけた夢の跡が、水中写真家・戸村裕行さんにより撮影された映像が流れました。太平洋の海底で永い眠りについています。
父・松岡功
昭和9年(1934年)、兵庫県芦屋市で松岡辰郎の次男として生まれました。
父・功は、小林一三が創業した映画会社東宝の元社長(第11代)。経営者として30年にわたり敏腕を振るい、映画界の発展に人生をささげてきました。実はかつて功はテニスの名選手でした。しかし志半ばで実業界へ。一方、息子・修造はテニスを貫きました。全く違う道を選んだ親子の物語です。
父・功は、中学生の時、部活動でテニスを始めます。180センチを超える恵まれた体格と抜群のセンスで学生テニス界の注目を集めるようになりました。
※甲南大入学当時に「高校テニス三羽烏」の一人に数えられており、設立3年目の新設大学の広告塔として期待されていた。全日本学生選手権でシングルス・ダブルスで合計3回の優勝を記録。大学4年次の昭和31年(1956年)デビスカップ日本代表。
昭和30年(1955年)、功は大学選手権で優勝(シングルス)。翌年には国別対抗戦デビスカップの日本代表にも選ばれました。将来のテニス界を引っ張っていく逸材だと期待を一身に集めていました。
しかし功は、大学卒業を前に進路について悩みます。このままテニスを続けるべきかどうか。実業団で働きながらテニスを続け世界で戦ってみたい。しかし果たしてどこまでやれるのか。迷った功は、父・辰郎に相談します。その時のやり取りが書き残されていました。
功「まだ若いので5年やりたい。その後は考える。」
辰郎「それなら今止めなさい。仕事とテニスは両立しない。一生テニスをやり続ける覚悟があるなら別だが」(父母を忘れさせない教育法)
※番組で触れていない部分もあったため引用する。これは功氏へのインタビュー内容で、その父は松岡辰郎氏。
「当時、神戸の芦屋に住んでいましたが、(※父・辰郎氏は)週二日は必ず家で家族と食事を共にしていましたね。といっても、小学生の頃は、戦中、戦後の混乱期で、マイホーム主義といっても、現在のそれとは、かなりかけ離れていました。食べるのに精一杯、校内暴力とか不良なんて時代ではないんです。念のためにいえば終戦は小学校5年のときです。(略)兄(※松岡通夫、松岡汽船代表取締役社長)の影響で中学2年から本格的にテニスを始めました。私の通っていた甲南中学はスポーツの盛んなところで、中でもテニスは活発。すぐれた選手を多数送り出していました。それからすっかり熱中してしまい、大学までテニスばかりでした。そして全日本学生選手権も何度か取りました。将来この道でメシを食おうかと思いましてね。もっとも、あの頃は、今と違いプロはまだなく、せいぜいセミ・プロ止まりです。で、先輩のツテで倉レ(※現クラレ、旧倉敷レイヨン株式会社)を受けたんです。テニスでですよ。できることなたテニスをやり続けたいと思い、一応父に話しましたら、反対されましてね。私は「まだ若いので5年やりたい。その後は考える」といいましたら、「それなら今止めなさい」とピシャリといわれました。「仕事とテニスは両立しない。一生テニスをやり続ける覚悟があるなら別だが……」というんです。要するに、人間、二またかけたり三またかけたりすると、どれも中途半端になるということなんでしょうね。一つのことに目標を定めたら、それに全力投入しなさい、というわけです。父親はやがて東宝の社長になりまして、私も東宝に入ったのですが、俗にいう帝王学などというものは、まったく受けていません。(略)私は、自分でいうのも変ですが、比較的経済面では恵まれていた方だと思います。それでも、父親は口ぐせのようにいっていましたね。「すねかじりのうちはぜいたくはするな。ぜいたくしたかったら、自分で稼いでからしろ」と。※この書籍は61人の経営者・文筆家・教授・スポーツ選手などにインタビューしたもの。ビートたけし、松田聖子なども登場する。CBSソニーのミス・セブンティーン九州大会で優勝したが厳格な父親に初めて頬を打たれ、挙句の果てには勝手にCBSに電話され断られた経緯などが記されている。
経営者として実業界で闘っていた辰郎。功に厳しい言葉を突きつけました。
覚悟を問われた功。きっぱりとラケットを置くことを決断しました。
長男の宏泰さんはその覚悟を証言しています。「うちには父のトロフィーとは賞状とかラケットはまったく置いていなかったんですよ。やっぱり悲しいけれども中途半端はいかんと。だから仕事に集中するんだということで、ふんぎりをつけたんじゃないですかと思います。」
昭和32年(1957年)、功は東宝に入社。大阪の劇場に配属されます。新たな道を歩み始めました。
そして4年後、たまたま呼ばれた食事の席で出会ったのがタカラジェンヌの山本静子でした。
母方:山本家
続いて母方を見ていきましょう。
松岡修造さんの母・静子(しずこ)は、かつて宝塚歌劇団(雪組)の男役スター「千波 静(ちなみ しずか)」として活躍していました。
実は静子の姉・淳子(千波淳)と妹・正子(千波薫)も元タカラジェンヌです。華やかな舞台に3人の娘を送り出した母方・山本家。その裏には悲劇を乗り越えてきた家族の物語がありました。
※松岡修造さんの長女・稀惺かずと(きしょう かずと)さんも宝塚歌劇団星組男役。
山本家のルーツを求め訪ねたのは静岡市内の本籍地。明治期の戸籍に記されていた旧小河内村(こごうちむら)です。
※現在の静岡市清水区で、かつての小島村の一部。1889年(明治22年)に町村制が施行された際に、小島村、小島町、立花村、但沼村、小河内村、宍原村が合併して小島村が発足。その後1961年(昭和36年)に清水市に編入され、2003年(平成15年)には清水市が静岡市と合併したことで、旧小河内村域は静岡市の一部となった。
曽祖父:山本愛太郎(あいたろう)
山本家は江戸時代から地域の農家のまとめ役「名主(なぬし)」を務める家柄でした。
小河内村は農地が少なく生活は楽ではなかったといいます。山林、養蚕、紙漉きなど営んで暮らしてきたといいます。妻・たき。
祖父:山本喜之輔(きのすけ)
明治42年(1909年)、山本家の次男として生まれたのが祖父・喜之輔(きのすけ)。テニスの松岡修造さんの祖父です。
利発な少年だった喜之輔は農業以外の道へ進もうと学問に励みます。大正11年(1922年)喜之輔は県下有数の難関校である静岡工業学校(現、静岡県立科学技術高校)に合格。電気科で最新の技術を学びました。
卒業後、喜之輔は静岡市内の工場で働き始めます。穏やかな人柄で、周りには自然と人が集まってくる好青年でした。
間もなく喜之輔は隣村出身の女性と恋仲になります。片平フサ子さん。喜之輔の8歳年下で笑顔がすてきな女性でした。後の修造の祖母です。フサ子の生まれ育った地元では、今も一族自慢の娘だったと言い伝えられています。フサ子は静岡市内で幼稚園の先生をしていました。優しくて子ども好きのフサ子には縁談が次々と舞い込みました。
松岡修造さんのいとこで、叔母にあたる正子さん(千波薫)の娘の田中里依さん(千波ゆう)は親子二代のタカラジェンヌです。宝塚歌劇団を退団。その後は女優として活躍中。
祖母のフサ子が乙女のように語ってくれた恋物語を覚えています。「いいなづけがいて、ほんとは他の人と結婚することになっていたけれどおじいちゃん(山本喜之輔)のことがどうしても好きで一緒になりたくてっていう話を、すごくあの何か声をひそめながら言ってたんでだいぶ自分の中で秘密の話だったのではないでしょうか。」
昭和10年(1935年)、2人は親の反対を押し切って結婚。駆け落ち同然で上京し、喜之輔は品川の町工場で働き始めます。
長女・淳子(あつこ、昭和10年生まれ)に続いて、昭和13年(1938年)に生まれたのが静子(しずこ)。修造の母です。更に2年後、夫婦にとって初めての男の子、悌弘(よしひろ)が誕生しました。
「家族を幸せにしたい」。喜之輔は 大きな決断をしました。自分の会社を立ち上げたのです。航空機の部品となる電気絶縁体を作る工場でした。※山本喜之輔興亜合成工業所(荏原区上神明町)
しかし太平洋戦争が始まり一家の暮らしは暗転します。
昭和20年(1945年)5月、品川に激しい空襲があり、喜之輔は家も工場も失いました。そして終戦。さらに終戦から3ヶ月後の11月、突然の悲劇に見舞われます。
その日、喜之輔は疎開していた静岡で屋根の修理に取りかかっていました。はしごを登ってきたのはわんぱく盛りの長男・悌弘。喜之輔は「危ないから下りなさい!」と叫びます。次の瞬間悌弘は転落。翌日あっけなく亡くなりました。僅か5歳でした。
深い悲しみに暮れる一家を何とか支えたのはフサ子でした。自らの悲しみは押し殺し、残された家族に愛情の全てを注ぐと決意しました。得意のピアノを弾き娘たちと歌ったり踊ったり笑顔を絶やさない毎日を送ろうと努めます。娘たちが丈夫な体になるようにバレエ教室にも通わせました。
そしてフサ子自身は料理教室に通い、栄養満点のおいしい食事を家族に振る舞いました。
やがて喜之輔も工場を再建(興津精器工業株式会社、東京都品川区中延)。さまざまなプラスチック製品を開発し事業を軌道に乗せていきました。三女、四女も生まれ以前にも増してにぎやかな家庭になります。フサ子のひたむきな愛情が、絶望のふちから家族を救ったのです。
松岡修造さんは語ります。「一度も怒らず、いつも笑顔。どんな時も前向きっていう。だからテニスも ウィンブルドンも含めて一番苦しい時に僕必ず空を見て、苦しくなったら「おばあちゃん」って。そうすると前向きになれましたね。
母:静子
こうと決めたらやり抜く芯の強さを受け継ぎました。
昭和31年(1956年)静子は高校を中退し宝塚音楽学校を受験。見事合格を果たします。

※後列中央の和服姿が母・静子、中段左が祖父・山本喜之輔、右手が祖母・フサ子。四姉妹については紹介がなかったが、恐らく後列左手の袴姿が長女、後列右と手前右は三女・四女のどちらかではないかと思われるが不明
翌昭和32年(1957年)、千波 静として初舞台。以降、男役として人気を集めていきました。
昭和36年(1961年)静子は同僚から誘われた食事の席で一人の男性と出会います。話を聞いて驚きました。その男性は宝塚歌劇団の創設者小林一三の孫だというのです。名前は松岡功。
後に修造の両親となる二人の出会いでした。
※「創業者一族なんだから宝塚入りできて当然じゃーん」と勘違いしそうですが、山本静子さんは宝塚44期生で入団4年後に松岡功氏と出会っているので完全に個人が評価されてのことです。ちなみに姉の千波淳さんは42期生(昭和30年)、妹の千波薫さんは48期生(昭和35年)。
高校を中退して宝塚歌劇団を目指し夢を実現した静子。その芯の強さに功は惹かれます。
二人は結婚。昭和39年(1964年)長女・敏子(としこ)が、2年後、長男・宏泰が生まれます。そしてその翌年、昭和42年(1967年)に生まれたのが松岡修造さん。
松岡修造さん
船会社を起こした4代前の高祖父にあやかって名付けられました。姉の辻敏子さんによると、幼い頃の修造は、やんちゃ坊主というかおとなしい子ではなかったそうです。自分で作った歌を歌ったりして、一人で楽しそうにしていたといいます。
修造は小学2年生の時母と姉が通うテニス教室で初めてラケットを手にします。父がテニス選手だったことは知らぬまま、その面白さにのめり込んでいきました。
しかし決して才能豊かではなくいつも褒められるのは一緒にテニスを始めた兄・宏泰でした。
※ちなみに、松岡修造さんの実兄・松岡宏泰さんも元テニスプレイヤー。慶應義塾大学時代には慶應義塾體育會庭球部で主将を務め、全日本大学選手権などに出場しました。テニス専門誌などにもしばしば登場するほどの名選手だったといいます。現、東宝社長(第15代、2025年現在)。ほか東宝東和株式会社取締役会長(元第4代社長)、関西テレビ放送株式会社非常勤取締役、公益財団法人川喜多記念映画文化財団評議員。
番組では、松岡修造さんの友人・甘露寺重房氏が登場し、「(宏泰さんは)生まれ持っているものがもともとあった。宏泰さんの方がボールに対する感覚だとか、技術的なことも含めて、器用さという意味では宏泰さんの方が器用だった。(松岡)修造はどちらかと言えばそういうものを持っていない」。
松岡修造さん自身も、「兄のほうがよっぽど(テニスの)素質があった」「もしテニスを続けていたなら、間違いなく名を遺したと思う」と認めている。なお甘露寺重房氏も元テニスプレイヤーで、堂上公家の本物の「名家」で旧華族・甘露寺伯爵家の血を引く方(小一条内大臣・藤原高藤を祖とする)。松岡修造さんとは幼稚園の頃からの幼馴染。親の都合でカリフォルニア州に移住してテニスの道に進み、ボブ・ブレットに指導を受けた。一時松岡修造さんとダブルスを組んでもいる。
※つまり、父・功氏、兄・宏泰氏とそろってテニスプレイヤーな訳です(ついでに言えば父の兄・松岡通夫氏も)。しかも日本でもかなり上位に進んでいたものの、けっきょく父、兄はテニスの道を断念して経営者となっている。
修造は中学でもテニスに没頭します。しかしミスを繰り返す姿を見て父・功は言います。「お前はテニスに向いてない」。
更に高校1年生の時、父から厳しい言葉を突きつけられました。「このままダラダラ続けるくらいならもうやめた方がいい」。それはかつて功自身もその父・松岡辰郎から伝えられたメッセージでした。「中途半端ならやめろ。やるからには全てをかけろ。」
覚悟を問われた修造は高校1年の終わりに思い切った決断をします。昭和59年(1984年)、通っていた慶應義塾高校を自主退学し、福岡にあるテニスの強豪柳川高校に編入したのです。
「俺はテニスという夢に人生をかける。」
修造はその年(二年次)のインターハイで、シングルス・ダブルス・団体戦の全てを制覇。三冠を達成します。
※このときに映った新聞には「父に”並んだ”」と書かれています。しかも実兄の宏泰さんも慶應義塾3年で同じインターハイに出場しており、第三戦で敗退。その対戦相手である甲南大学田中智選手を、弟の松岡修造さんが破ったという展開。
1年後、テニス界の名伯楽ボブ・ブレットに見いだされ アメリカへ。プロテニス選手への道を歩み始めました。
※ボブ・ブレット(Bob Brett、1953-2021)はオーストラリア出身のテニスコーチ。イタリアのサンレモにテニスアカデミーを設立し、日本テニス連盟のコーチも務めた。教え子にはアンドレイ・メドベデフ(1999年全仏オープン決勝)、世界ランキング4位のニコラス・キーファー、マリオ・アンチッチなど。修造チャレンジトップジュニアキャンプで指導し、錦織圭を含むほとんどの日本人選手の育成に貢献したという。
当時の日本人男子の世界ランキングは最高でも300位以下。父・功は変わらず厳しい言葉を送ります。「どうせやるからには、世界ランキングで50位くらいには入ってほしい。」
※父・功はあくまで厳しく、プロ転向に際し一切の援助は行わないと条件を付けられていたため、自分でマネージメント会社と契約し、1年300万円の活動資金を得た。世界ランキング100位に入ったのは昭和63年(1988年)。
プロ生活は世界中を転戦する過酷な日々でした。そんな中で修造を支えてくれたものがあります。それは母方の祖母フサ子の心がこもった手料理でした。
松岡修造さん「僕はこう海外から帰ってくるとおばあちゃんちに行って、おばあちゃんのおみそ汁を飲むっていうのが一つのルーティーンになってて、それはもう昔から自分の中におばあちゃんのおみそ汁が世界一だと思ってたし愛情があった。」
平成4年(1992年)、修造はATPソウルオープンでツアー初優勝。日本の男子選手として初のATPツアーシングルス優勝を達成。同年6月のクイーンズ・クラブ選手権でも番狂わせの活躍を見せ、ランキングは当時歴代最高の46位まで上がりました。
そして平成7年(1995年)松岡修造さんは初めてウィンブルドンのコートに立ちます。日本人男子(1933年の佐藤次郎以来)62年ぶりのべスト8。客席には東宝の会長として多忙を極める父・功の姿がありました。※センターコートは平成8年(1996年)のミヒャエル・シュティヒ戦
相手は当時世界最強のピート・サンプラス。修造は第1セットを先取しました。しかしその後サンプラスが2セットを連取し逆転。第4セットに入っても修造は4ゲームを立て続けに落とし、窮地に立たされます。
思わず両親のもとへ歩み寄りました。

松岡修造さん「こうやってうちの母と父がいてコーチがいて。わざわざ僕はあえてそこを通って『かなわないわ』って言った時に、うちの母は『これからよ』って言ったわけですよ『頑張りなさいよ』って。うちの父は無言でじっとコートの中心を見つめていました。」
「やるからには、全てをかけろ」
その後、修造は意地で2ゲームを取り返します。世界最強を相手に全力で戦い抜きました。試合後敗れた修造について問われた父・功は、ひと言「やはりサンプラスはうまいですね」と答えています。最後まで厳しく冷静な父でした。
兄の宏泰さん「見ていてほんとに差があるということは分かったと。だけど誇らしかったんじゃないですかね。やっぱり自分の子供が一生懸命やって、やめろ やめろって言ったのに世界1位と戦ってるのを見た時は、きっとうれしかったんだと思います。」

松岡修造さん「何でテニスだったんだろうって、僕はよく思うことあるんですよ。なぜ世界だったんだろうって。何かこう1つの道がファーッて開いてく感じなんですよ。やっぱり柳川へ行くこととかアメリカへ行くこととか人との出会いって。僕がつかんでったのかもしれないですけど道がちゃんと出来てった。そこには自分のヒストリーっていう、一族のこの道をつくってってくれてるっていうのは、間違いなく今日見て感じました。」
現役中は度重なる怪我に苦しめられた松岡修造さん。それでも、引退する最後の最後まで自分の全てをかけて戦い抜きました。
引退後はスポーツキャスターとして活躍する一方、錦織圭さんや西岡良仁さんなど世界に羽ばたく後進を育ててきました。受け継いできた思いをテニス界にとどまらず伝えています。
修造さんの曽祖父・小林一三はこんな言葉を残しています。
誰にも夢がある。それはたとえ小さくとも、その夢がふくらみ、花を咲かせ、立派に実のるのを見るのは楽しい。
(宝塚漫筆)
修造さんに厳しい言葉を送り続けた父・功さん。かつてインタビュー記事でこう語っていました。
しばらく前までは、「松岡修造は松岡功の息子だ」と言われていたんですけど、最近は「松岡功は松岡修造の父だ」と言われるようになってしまいましてね。
ついでに言うと小林一三ですら、「小林一三は松岡修造の曽祖父だ」に変わった。(Decide 平成元年(1988年)12月号)
※もう少し長く引用すると、
『「最近、親子の立場が逆転しかけていましてね。ちょっとピンチなんですよ」とぼやくのは、東宝社長の松岡功さんだ。『しばらく前までは、松岡修造は松岡功の息子だと言われていたんだけど、最近は、松岡功は松岡修造の父だと言われるようになってしまいましてね」と。つまりこれまで、父親の松岡功氏を軸に親子関係を見ていた人たちが、最近は、息子の修造氏を軸に話すようになった、というのである。ついでに言うと、阪急コンチェルンを一代で築き上げた小林一三翁ですら、以前は「松岡修造は小林一三翁の曾孫だ」という言われ方から、「小林一三翁は松岡修造の曽祖父だ」に変わった。「松岡修造」とは、言うまでもなくソウル・オリンピックにも出場したプロテニスプレイヤーの松岡修造さんである。松岡功・東宝社長の次男である。(略)父親の松岡功さんも甲南大時代にデビスカップ代表に選ばれた名プレーヤーだが、もちろん、プロ入りするまでには至らなかった。その夢?を、息子が実現してくれたわけだ。当初、「勝手に慶応を辞めちゃうんだから。あんなもの、勘当ですよ」とつっぱっていた松岡氏だったが、「ツアーからツアーで、ちゃんと生活できているんだろうか」という言葉もそのうち出るなど微妙に心境の変化を見せ始め、今年あたり、「どうせやるからには、世界ランキングで50位ぐらいには入って欲しいな」と、積極的に応援する方向に変わってきた。88年夏に、ATPランキングで100位以内にはいった修造さんは、その後も急ピッチにランキングを上げ、念願の50位にも、手が届くところまできた。ベストテン入りも決して夢ではない。もちろん、日本人のテニスプレーヤーとしては、初の快挙である。』
などと書かれている。
※当時、長男の宏泰さんは慶応大学テニス部キャプテンで、翌年に卒業して海外留学へと進むと書かれている。番組引用文後半の「小林一三ですら」は功氏の言葉ではなく恐らくインタビュアー(記者)の文章である。また「世界ランキングで50位」の発言の意図も番組とは少し違っているように感じる。
※本当に蛇足ながら書いておくと、「こういうトップエリートは金に恵まれてるんだから成功して当たり前だ」などというのは我々一般人はつい思いがちです。「帝王教育も受けてるんだし出発点がまったく違う」なんてのもよく聞かれる言葉です。自分の努力を棚上げにしてそう思いたいのです。もちろん我々庶民に比べれば経済面で苦労はないか、あるいは圧倒的に少なく、学生時代までの教育面が優れているのはいうまでもありません。それはご本人たちも認めるでしょう。※実際に偏差値的な学力面で有利になったのかは別にして。また家庭環境という意味では、庶民と異なるものも多分にあるかと思います。
しかしその後は独立独歩の精神で自ら独り立ちしている人が大半だということがわかります。相当の決断を幼少期から求められ、だからこそ成功しているのだとも言えます。例えば父・功氏はデビスカップ代表に選ばれ、スポーツで企業を受けて(要するに実業団希望)までいながら、その父・松岡辰郎氏に相談後はきっぱりテニスの夢は諦め(ラケットやトロフィー賞状まで処分して)、企業人としての努力を積み重ね、重圧をはねのけて経営者となったのです。その覚悟ができるかどうか、努力を積み重ねられるかどうか?は人それぞれ、あくまで個人的なものだろうと思います。
それは松岡修造さんが努力で勝ち得た結果でも言えるかと思います。テニスの才能はむしろ兄・宏泰さんの方が秀でていたし、親からは何度も「素質がない辞めろ」と言われていた。にも関わらず、夢にすべてをかけた。その努力の熱量が違ったということだろうと思います。番組ではボブ・ブレット氏に見出され…としていましたが、実際にはブレット氏は松岡修造氏には練習試合後に「明日アメリカへ帰ります。さようなら」としか言わなかったというのは有名な話で、誘いの言葉や少なくともアドバイスなりをもらえると期待していた修造氏は落ち込んだといいます。そこから食らいついていけるかどうか、それはそこに全てをかけられるか?という覚悟なんだろうと思います。それが「やるからには、全てをかけろ」「一生テニスをやり続ける覚悟があるか」という言葉に集約されているのだと思います。スポーツであれ仕事であれ、何事もすべてをかけないと成功は難しいということだろうと思います。
皮肉な見方をすれば、この番組自体がいわゆるジョブズ式メソッド(人生には無駄なことなどなく振り返ればすべてが現在の自分に繋がっている)に沿って先祖を紹介するものと見ることもでき、紹介する先祖の選択からエピソードの取捨選択もそういう図式で選ばれているため、番組を見ればまるで過去から現在が計算されていたかのように感じるのが当然なのです。しかも成功者の経歴がバックグラウンドにあるのですから、説得力は段違いです。実際、福山雅治氏も「まるで物語の結末が最初から決まっていたかのようだ」と感想を語っていますし、松岡修造氏も「僕がつかんでったのかもしれないですけど道がちゃんと出来てった。(略)一族のこの道をつくってってくれてるっていうのは、間違いなく今日見て感じました」と同様の言葉を語っています。
ただしそれはあくまで本人が覚悟し努力した結果であって、その源を先祖に求めてみたに過ぎないのです。そういう意味では、私が偶然の繰り返しに驚いたのは、記事を書いている中では鶴田真由さんの回でした。